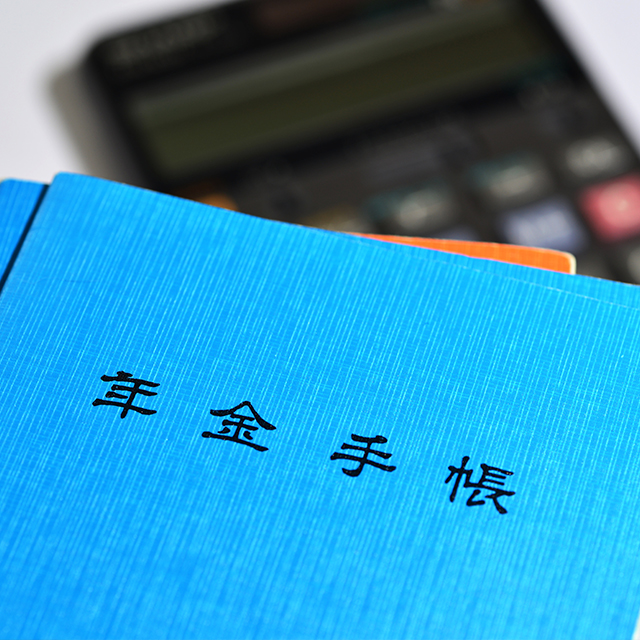医学部の学費は?
国公立・私立大学の違いと内訳、必要なお金の備え方や支援制度を紹介
子どもが大学の医学部へ進学を希望していたら、どのくらい学費がかかるのか気になる保護者も多いのではないでしょうか。
医学部の学費は、理系のなかでも特に高いイメージがあります。しかし、どれほどの費用が必要なのか、費用の内訳はどうなっているのか、具体的に知っている人は少ないかもしれません。
本記事では、国公立大学・私立大学ごとに医学部でかかる学費やその内訳を解説します。さらに、学費の負担を抑える支援制度や、学費を準備する方法をあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
※本記事は、2024年3月現在の内容です。

大学の医学部に進学したら学費はどれくらい?内訳は?
大学の医学部に進学したら学費はどのくらいかかるのか、国立大学・公立大学・私立大学ごとに、それぞれの平均額を確認しましょう。
通常、大学の学費は授業料をさしますが、ここでは入学金を含めた大学の初年度納入金を学費として紹介します。
国立大学医学部の学費の相場
国立大学の学費は、文部科学省により「標準額」として金額が定められています。2024年時点、国立大学の入学金は282,000円、授業料は535,800円で、初年度納入金は学部にかかわらず817,800円です(※)。
標準額の上限20%以内であれば大学の判断で学費を増額できるため、必ず標準額どおりになるわけではありませんが、国立大学への進学は標準額をベースに考えてよいでしょう。
ただし、一般的な学部が4年制であるのに対して、医学部は6年制のため、通常の大学より学費や生活費の支払いが2年分多く必要です。
(※)出典:e-Govポータル「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」
公立大学医学部の学費の相場
公立大学は、地方自治体が税金を出資して運営する大学です。学費は大学ごとに異なりますが、授業料はおおむね国立大学の標準額に準じた金額となっています。
ただし、入学金は地域内と地域外で異なるケースが多く、地域内から進学する場合は地域外に比べて入学金が低額である傾向です。
2023年度の公立大学の平均学費は、入学金が地域内224,066円・地域外374,371円、授業料が536,191円でした(※)。つまり、初年度納入金は地域内で約76万円、地域外で約91万円となります。
ただし、入学金は125,000円から564,000円、授業料は322,300円から696,000円と大学や学部で金額に開きがあります。
特に、医学部は入学金が高い傾向です。例えば、福島県立医科大学の入学金は地域内282,000円・地域外564,000円ですが、医学部は846,000円と設定されています。
(※)出典:文部科学省「2023年度 学生納付金調査結果(大学昼間部)」
私立大学医学部の学費の相場
2023年時点で医学部のある私立大学は31校です。国立大学42校、公立大学8校と比べても、私立大学は医学部進学の重要な選択肢であるとわかります(※1)。
2023年度の私立大学の医学部の平均学費は、入学金1,360,098円、授業料2,656,053円です。国公立大学にはない施設設備費1,063,284円を追加した初年度納入金は5,079,434円となり、入学時だけで学費は500万円を超えます(※2)。
ほかにも実験実習費などが別途必要になり、結果として初年度納入金は平均約705万円に達します。
また、自主運営の私立大学は大学ごとの学費差が生じやすく、進学先によっても学費は異なるでしょう。
(※1)出典:文部科学省「医学部を置く大学一覧(令和5年度)」
(※2)出典:文部科学省「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
私立大学医学部の学費はなぜ高い?
国公立大学の医学部にかかる学費は6年で約350万円~400万円、私立大学は6年で約2,000万円~5,000万円とされています。国公立大学に比べて、私立大学の医学部はなぜここまで学費が高いのか、推測される理由を解説します。
臨床実験の設備や指導する人材にお金がかかる
私立大学医学部の学費が高い理由の一つは、国公立大学とは違い、国や自治体からの補助金(私学助成金)が少ないことが考えられます。
医学部には臨床実験を行なう医療設備などを整えるためにお金がかかりますが、私立大学はその資金のほとんどを学費で賄わなければなりません。
ほかにも、優れた医師を育てる指導者の確保にも高額の費用が伴います。
学生数の制限があるため学費を減らしにくい
適切な教育環境を保つ目的から、私立大学は文部科学省から入学定員(学生数)制限の通達を受けており、学生数を容易には増やせません。
文部科学省からの通達を守らず学生数を増やすと、私学助成金の減額もしくは不交付のペナルティが課され、運営の負担が大きくなるためです。
学生数を増やせば一人あたりの学費負担は減らせる可能性があります。しかし、それにより私学助成金を減額されては運営が立ち行かなくなる恐れがあり、私立大学は学費を減らしにくいものと考えられます。
医学部の学費を支援する制度
国公立大学と私立大学で学費差はありますが、6年間の学校生活を必要とする医学部はほかの学部に進学するよりも、学費にかかる負担が大きい事実には変わりません。
そこで、医学部の学費にかかる負担を軽減できる支援制度を紹介します。
※制度に関する記載は2024年3月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

奨学金制度
奨学金制度には給付型と貸与型があります。進学する学生の大学生の約半数がなんらかの奨学金を利用しており、学費の支援制度として広く定着しています(※)。
ただし、奨学金は進学する子ども自身がお金を借りる制度です。給付型は返済不要ですが、貸与型は将来子どもに返済の負担がかかる可能性もあるため、十分に検討のうえ利用しましょう。
多くの人が利用する日本学生支援機構の奨学金制度には、給付型、貸与型(無利子と有利子)の3種類があります。受験前の場合は高校を通じて、医学部へ入学後の場合は大学の奨学金窓口を通じて申し込みます。
日本学生支援機構以外にも地方自治体や民間団体、製薬会社などの企業が実施する奨学金制度があります。医学部進学者のみを対象とする奨学金もあり、支援内容もさまざまです。
このような奨学金の多くに「卒業後は一定期間、特定地域や特定分野の医療に従事する」や「条件を満たせば返済を不要とする」など、団体ごとに異なる条件が定められています。
(※)出典:日本学生支援機構「令和2年度 学生生活調査」
高等教育の修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度は「大学無償化」とも称される制度で、98%の大学、短期大学をはじめ、高等専門学校は100%、専門学校は79%を対象としています(※)。
(※)出典:文科省「高等教育の修学支援新制度について」
利用要件は以下のとおりです。
- 世帯収入(住民税非課税世帯、それに準じた世帯が対象)
- 学ぶ意欲(学校の成績よりもやる気を重視する)
要件に該当すれば、入学金・授業料の減免や返済不要の給付型奨学金を受けられます。世帯年収に応じて、それぞれの支援額が段階的に分かれます。
入学金・授業料の減免 上限額(年額)
| 国公立大学 | 私立大学 | ||
|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 |
| 約28万円 | 約54万円 | 約26万円 | 約70万円 |
給付型奨学金の給付額 上限額(年額)
| 国公立大学 | 私立大学 | ||
|---|---|---|---|
| 自宅生 | 下宿生 | 自宅生 | 下宿生 |
| 約35万円 | 約80万円 | 約46万円 | 約91万円 |
なお、2024年4月からは制度が拡充されています。
さらに、理⼯農系を対象に、私⽴大学などの⽂系との授業料差額を支援する内容も加わりました。
大学独自の学費軽減制度
医学部のある大学には、奨学金制度、特待生制度など、独自の学費軽減制度を設けているところも多くあります。
例えば、埼玉医科大学の「埼玉医科大学医学部特別奨学金」は、入学時350万円、2年次以降年300万円(総額1,850万円)を貸与されます。また、貸与期間の1.5倍(6年の場合は9年)指定機関で医師として働くと、奨学金の返済が不要となります。
制度のなかには入学前に申し込みが必要な場合もあるため、早めにリサーチしておくことが大切です。
医学部の学費を準備する方法
ほかの学部よりもお金のかかる医学部進学に向けて、効率よく学費を準備する方法を紹介します。
教育ローン
教育ローンには、国の教育ローン(教育一般貸付)と、民間の金融機関による教育ローンがあります。
教育ローンの種類
| 種類 | 実施機関 | 特徴 |
|---|---|---|
| 国の教育ローン (教育一般貸付) |
日本政策金融公庫 | 世帯年収の要件を満たした家庭が対象で、1人あたり原則として350万円までを融資する。低所得世帯には金利の優遇制度がある。 |
| 民間の教育ローン | 銀行や信用金庫など民間の金融機関 | 金融機関により適用条件は異なる。融資限度額は大きいが金利もやや高め。最短即日の融資に対応する商品もある。 |
国の教育ローンは、民間の教育ローンに比べて返済の負担は抑えられますが、申し込みから融資までに2~3ヵ月かかります。利用条件やお金が必要なタイミングにあわせて適切なローンを選びましょう。
学資保険
学資保険は子どもの教育資金を計画的に用意するための貯蓄型保険です。保険商品により異なりますが、保険料を満期まで払い込むと、払い込んだ保険料を上回る金額を受け取れます。
まとまった資金をいきなり用意するのは大変ですが、学資保険なら長期にわたって一定の保険料を積み立てるうちに学費を用意できます。
毎月の家計への負担を抑えながら、教育資金を用意できるでしょう。
また、多くの学資保険では、契約者である保護者に万一のことがあれば、以降は保険料の払い込みが免除されるなどの保障も受けられます。
学資保険を検討するなら「明治安田生命つみたて学資」がおすすめ
学資保険とは、一般的に子どもが幼少期のころから将来の学費に備えて加入する貯蓄型保険です。
「明治安田生命つみたて学資」は、大学進学時と在学中に教育資金3回と満期保険金1回、計4回に分けてお金を受け取れる学資保険です。初年度納入金など、入学当初の負担が特に大きい医学部進学への備えになるでしょう。
また、契約者に万一のことがあれば、将来の教育費や満期保険金はそのまま、保険料の払込みが免除される保障も備えています。
出生予定日の140日前からお申込みいただけるため、積立期間を長く確保できる分、毎月の保険料負担を抑えられます。ただし、被保険者(お子さま)のご契約年齢の範囲は満6歳までとなっている点にはご注意ください。
契約者の万一の際に備えながら、学費を着実に用意できる「明治安田生命つみたて学資」をぜひご検討ください。
※明治安田生命つみたて学資をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
大学の医学部の学費は、6年制であるうえに、実験・実習も多いため、さまざまな学部のなかでも特に高額な傾向です。
ただし、国公立大学と私立大学で学費は大きく異なり、初年度納入金を比較すると国公立が約80万円~90万円、私立が約400万円~700万円となっています。
国公立大学・私立大学いずれも、医学部進学にはまとまったお金が必要となるため、早めに準備をはじめることが大切です。
学費の用意が難しい場合は、教育ローンや奨学金制度など、学費の負担軽減になる方法を検討しましょう。
募Ⅱ2400806ダイマ推