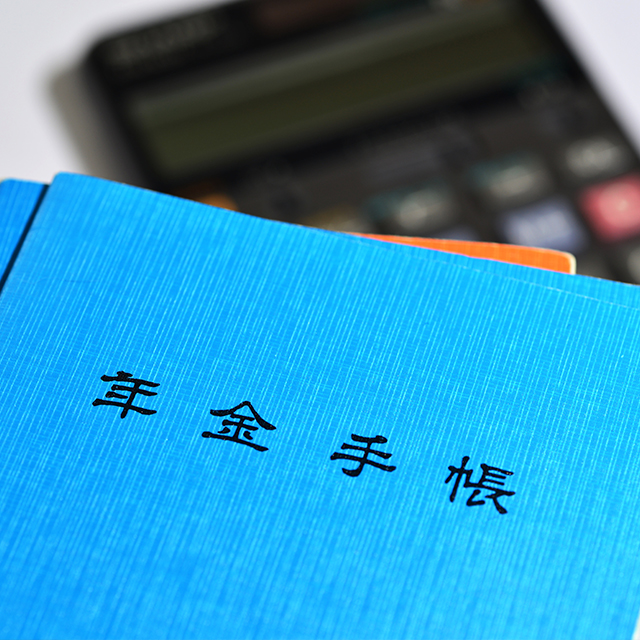小学生の習い事にはいくらかかる?
費用の平均や負担を抑えるコツなどを解説
子どもに習い事をさせたいと考えている人も多いのではないでしょうか。また、子どもから習い事をしたいと言われているケースもあるでしょう。
本記事では、実際に小学生はどのような習い事をしているのか、習い事にかかる費用はいくらなのか解説します。教育資金の貯め方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※本記事は、2024年1月現在の内容です。

小学生はどのような習い事をしている?
厚生労働省による第9回21世紀出生児縦断調査(令和元年)によると、平成22年出生児が小学3年生の時点で習い事等をしていた割合は87.7%でした。
小学校低学年(1~3年生)の間は、学年が高くなるほど習い事をしている割合は増えています。
習い事等をしている割合
| 習い事等をしている | 習い事等をしていない | 不詳 | |
|---|---|---|---|
| 小学1年生(第7回調査) | 76.8% | 23.0% | 0.2% |
| 小学2年生(第8回調査) | 84.7% | 15.0% | 0.3% |
| 小学3年生(第9回調査) | 87.7% | 12.1% | 0.2% |
参考:厚生労働省「第9回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)(令和元年)」
習い事の種類で多いのは、男児は水泳・サッカー・学習塾、女児は音楽(ピアノなど)・水泳・通信教育です。女児と比べると男児は運動系が人気であることがわかります。
小学3年生の習い事等の種類ランキング1~5位
| 男児 | 女児 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 水泳 | 40.0% | 音楽(ピアノなど) | 39.6% |
| 2位 | サッカー | 21.1% | 水泳 | 34.2% |
| 3位 | 学習塾 | 20.4% | 通信教育 | 22.0% |
| 4位 | 通信教育 | 19.0% | 習字(硬筆を含む) | 21.9% |
| 5位 | 英会話(他の外国語を含む) | 16.4% | 英会話(他の外国語を含む) | 21.0% |
小学生の習い事にかかる費用
第9回21世紀出生児縦断調査(令和元年)によれば、平成22年出生児が小学3年生のときにしていた習い事の費用は、1ヵ月平均1.4万円(男児1.3万円、女児1.4万円)でした。
21大都市部(※)はやや高く、そのほかの市や郡部はやや低いことから、都市部のほうが習い事にかかる費用は高めであることがわかります。
※東京都特別区部及び札幌,仙台,さいたま,千葉,横浜,川崎,相模原,新潟,静岡,浜松,名古屋,京都,大阪,堺,神戸,岡山,広島,北九州,福岡,熊本の各市
小学3年生の習い事等にかかる月額費用
| 全体 | 男児 | 女児 | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1.4万円 | 1.3万円 | 1.4万円 |
| 21大都市部 | 1.6万円 | 1.6万円 | 1.6万円 |
| そのほかの市 | 1.3万円 | 1.2万円 | 1.3万円 |
| 郡部 | 1.1万円 | 1.0万円 | 1.1万円 |
参考:厚生労働省「第9回21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)(令和元年)」
習い事等の月額費用の分布(全国)は以下をご覧ください。
習い事等の月額費用(全国)
| 全体 | 男児 | 女児 | |
|---|---|---|---|
| 5千円未満 | 11.8% | 13.4% | 10.0% |
| 5千円以上1万円未満 | 28.8% | 29.4% | 28.2% |
| 1万円以上2万円未満 | 37.8% | 36.5% | 39.1% |
| 2万円以上3万円未満 | 13.4% | 12.9% | 14.0% |
| 3万円以上 | 8.0% | 7.6% | 8.4% |
| 不詳 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
習い事の費用を抑えるコツ
習い事でかかるのは、授業料やレッスン料だけではありません。運動系の習い事なら体操着やシューズ、音楽系なら楽器、場所によっては交通費もかかります。
費用面の負担が大きいときは、以下のコツを実践してみてはいかがでしょうか。
- 自治体の助成金制度を利用する
- 兄弟・姉妹割引のある習い事を選ぶ
- 自治体主催の習い事に参加する
それぞれ詳しく見ていきましょう。

自治体の助成金制度を利用する
自治体によっては、習い事の助成金制度を実施しています。助成金額や受給条件は制度によって異なるため、お住まいの自治体で実施されている場合は詳細を確認しておきましょう。
助成金制度は、基本的に返還不要です。ただし、所得制限が設けられていたり、生活保護受給世帯などに対象が制限されていたりする場合があり、必ずしも利用できるわけではありません。
※制度に関する記載は2024年1月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
兄弟・姉妹割引のある習い事を選ぶ
兄弟・姉妹割引を実施している習い事もあります。兄弟・姉妹をふたり以上同時に通わせると、授業料やレッスン料、発表会代が割り引かれることや、入会金が無料になるなど、内容はさまざまです。
どのくらい割引されるかは、教室やスクールによって異なります。また、割引が適用されない場合でも、兄弟・姉妹で一緒に送り迎えができる点は忙しい親にとって嬉しいポイントです。
通わせたい習い事に兄弟・姉妹割引があるか確認し、割引があるなら積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
自治体主催の習い事に参加する
自治体が主催している習い事なら、民間の習い事よりも費用が少なく済む傾向にあります。ただし、人気が高く、抽選制となっていたり、申込期限が設けられていたりするケースもあるため注意が必要です。
お住まいの地域に子どもが参加できる習い事がないか、調べてみてはいかがでしょうか。公民館などの地域の施設や、自治体役場などに直接問い合わせてみてください。
子どもの教育資金を準備する方法
習い事以外にも、子どもの教育費には多額の費用がかかります。受験や進学の際など突然の出費に困らないためにも、教育費は計画的に備えておきましょう。
教育資金を準備する主な方法は、以下のとおりです。
- 児童手当を貯めておく
- 財形貯蓄を活用する
- 新NISAを利用する
- 学資保険を利用する
それぞれの方法を見ていきましょう。
児童手当を貯めておく
中学校卒業までの児童を養育している人が受給できる児童手当を貯めておくことで、子どもの教育費に備えることができます。
児童手当の支給額は、3歳未満は月々15,000円、3歳から15歳の誕生日後の最初の3月31日までは月々10,000円です。第3子以降は小学校修了前まで15,000円で、その後は月々10,000円になります(※)。
誕生月や出生順によって異なりますが、児童手当の受給総額は子ども1人あたり約200万円です。月々かかる習い事の費用に使ったり、大学や専門学校の学費に充てたりできるでしょう。
※扶養親族の人数によって所得制限が定められています。
参考:子ども家庭庁「児童手当制度のご案内」
財形貯蓄を活用する
財形貯蓄制度とは、勤労者の給与から天引きして積み立てる貯蓄制度です。
財形貯蓄制度には、勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)、勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)、勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)の3種類があります。
子どもの教育資金のために利用するなら、使途自由の一般財形貯蓄を利用してみてはいかがでしょうか。貯蓄額は給与から天引きされるため、着実に貯蓄できます。
新NISAを利用する
通常、投資で得た分配金や譲渡益には20.315%の税金が課せられます。しかし、NISA制度を利用すれば、投資で得た利益が非課税になり、手元により多くの利益を残せます。
なお、以前のNISA制度の非課税保有期間は、一般NISAでは5年間、つみたてNISAでは20年間でした。しかし、2024年1月からはじまった新NISA制度では非課税保有期間が恒久化され、長期的な投資も可能です。
また、以前のNISA制度の年間投資枠は、一般NISAでは120万円、つみたてNISAでは40万円でしたが、新NISAでは年間最大360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)まで投資が可能になりました。(別途、投資枠の合計に上限設定あり)
ただし、預貯金とは違い、元本が保証された制度ではないため注意しましょう。
※制度に関する記載は2024年1月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
学資保険を利用する
学資保険とは、子どもの教育費に備えるための貯蓄型保険です。子どもの入学や進学にあわせて教育資金・満期保険金が受け取れます。
大学入学時・在学中に教育資金を受け取れるものや、大学入学時に満期保険金を受け取れるものなど、保険会社やプランによってさまざまです。
また、保険料払込免除の規定がある場合、契約者に万一のことがあった際、保険料の払込みが免除され、以降も予定どおりの教育資金・満期保険金を受け取れます。
「明治安田生命つみたて学資」で計画的に教育費を準備しよう
「明治安田生命つみたて学資」は、お子さまの進学にあわせて計画的に教育資金を準備できる学資保険です。
受取率(※1)は加入時一括払いの場合、最大で129.2%(保険契約の型:Ⅰ型/ご契約者:25歳 男性/被保険者(お子さま):0歳/21歳満期/基準保険金額:70万円/一括払込は10歳払込満了(新年掛)/保険料率:2025年11月1日現在)です。
費用がかさむ大学などの時期にあわせて年に1回、合計4回教育資金・満期保険金を受け取れます。また、保険料の払込みは長くても15歳で終了するため、学習塾などの課外学習費が重なる高校生の時期は負担がありません。
ご契約者さまが万一の際は、以降の保険料の払込みが免除され、保障内容はそのまま継続されます。ぜひ「明治安田生命つみたて学資」で、お子さまの教育費に備えてみてはいかがでしょうか(※2)。
※1 受取率とは、払込保険料の累計額に対する満期までの受取総額の割合をいいます。また、受取率はご契約内容によって異なります。
※2 明治安田生命つみたて学資をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
小学3年生の約9割が放課後活動の一つとして、何らかの習い事を行なっています。
習い事にかかる費用は、小学3年生の場合で1ヵ月平均1.4万円です。兄弟・姉妹割引や自治体主催の習い事を活用して、出費の負担を抑えられるかもしれません。
子どもの教育費は習い事だけではありません。高校や大学、大学院の学費や、部活動などにも多くの費用がかかります。
必要な教育費を用意するためにも、児童手当や財形貯蓄、新NISA、学資保険などを活用し、計画的に備えておきましょう。
募Ⅱ2500973ダイマ推