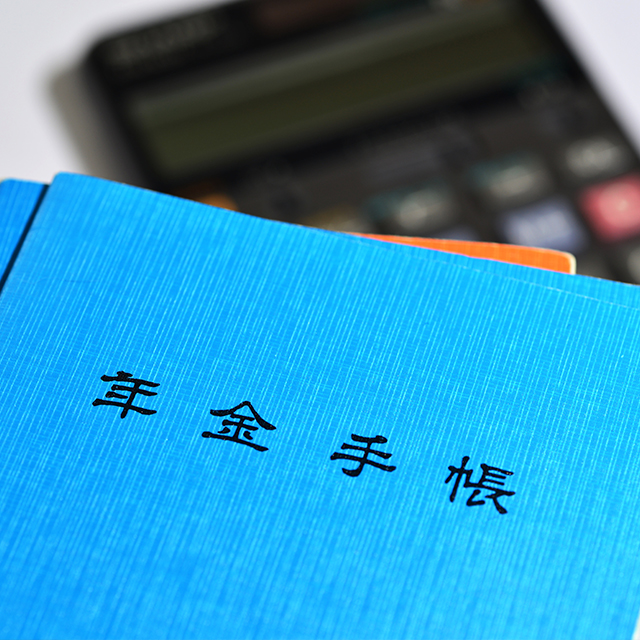退職金の相場を企業規模や勤続年数別に解説!
老後資金の準備方法も紹介
退職金制度のある企業に勤めていると、退職金がいくらもらえるのか気になることもあるのではないでしょうか。退職金制度のある企業は、退職金規定が定められているため、一度自社の退職金規定を確認してみましょう。
この記事では、企業規模や勤続年数別の退職金相場を紹介します。退職金を考える際にぜひ参考にしてください。
また、退職金の相場は年々減少しています。退職金だけでは老後資金を十分に準備できないケースも想定されるでしょう。今すぐ始められる老後資金の準備方法についても紹介します。ぜひ参考にして、経済的な不安を解消しておきましょう。

大企業の退職金の相場
中央労働委員会の2021年のデータによると、大卒で定年退職まで勤務した場合の平均退職金は約2,230万円、高卒で定年退職まで勤務した場合は約2,018万円でした。
| 大卒で定年退職まで勤務 | 高卒で定年退職まで勤務 |
|---|---|
| 約2,230万円 | 約2,018万円 |
出典:中央労働委員会「令和3年賃金事情等総合調査(確報)」をもとに作成
なお、このデータは資本金5億円以上かつ労働者1,000人以上の企業を対象に実施されています。大企業の退職金相場として参考にしてください。
中小企業の退職金の相場
東京産業労働局の2022年度のデータによると、中小企業に定年退職まで勤務した場合のモデル退職金(※)は、大卒で約1,092万円、高卒で約994万円でした。大企業と比べると半分程度の水準です。
| 大卒で定年退職まで勤務 | 高卒で定年退職まで勤務 |
|---|---|
| 約1,092万円 | 約994万円 |
出典:東京都労働産業局「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」をもとに作成
※モデル退職金:学校を卒業してすぐ入社した人が普通の能力と成績で勤務した場合の退職金水準)
勤続年数別の退職金の相場
定年まで同じ企業で勤務するとは限りません。ライフスタイルの変化やキャリアプランにあわせて、転職をする人も多くいます。また、勤務先の都合で早期退職を求められるケースもあります。勤続年数ごとの退職金相場も確認しておきましょう。
会社都合で退職したケースの退職金について、大企業・中小企業で比較します。

【大企業】勤続年数別の退職金相場
大学卒業後すぐに大企業に入社し、標準的に昇進した人の勤続年数別の退職金相場は以下のとおりです。
| 勤続年数 | 自己都合での退職 | 会社都合での退職 |
|---|---|---|
| 10年 | 約180万円 | 約310万円 |
| 15年 | 約387万円 | 約578万円 |
| 20年 | 約727万円 | 約953万円 |
| 25年 | 約1,143万円 | 約1,394万円 |
| 30年 | 約1,707万円 | 約1,915万円 |
※大学卒、事務・技術労働者、総合職相当
参照:中央労働委員会「令和3年賃金事情等総合調査(確報)」
退職金の計算のベースとなる基本給が増えるため、勤続年数が増えるごとに退職金も増えます。たとえば、勤続年数10年と20年では年数は2倍ですが、退職金は約3倍になります。
【中小企業】勤続年数別の退職金相場
大学卒業後すぐに中小企業に入社し、標準的に昇進した人の勤続年数別の退職金相場は以下のとおりです。
| 勤続年数 | 自己都合での退職 | 会社都合での退職 |
|---|---|---|
| 10年 | 約112万円 | 約150万円 |
| 15年 | 約213万円 | 約266万円 |
| 20年 | 約343万円 | 約415万円 |
| 25年 | 約491万円 | 約578万円 |
| 30年 | 約654万円 | 約754万円 |
参照:東京都労働産業局「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」
中小企業も大企業と同様、勤続年数が増えるごとに退職金の増加幅が増えます。
退職金の給付相場は年々減少傾向に
退職金の給付相場は減少傾向にあります。定年退職まで勤務した場合の平均退職金の推移は、以下をご覧ください。
なお、大卒・高卒ともに管理・事務・技術関連の職種に就いている場合の金額です。
| 調査年 | 大卒入社の平均退職金 | 高卒入社の平均退職金 |
|---|---|---|
| 2003年 | 約2,499万円 | 約2,161万円 |
| 2008年 | 約2,323万円 | 約2,062万円 |
| 2013年 | 約1,941万円 | 約1,673万円 |
| 2018年 | 約1,788万円 | 約1,396万円 |
2003年から2018年の15年間で、大卒入社の退職金相場は約710万円以上、高卒入社の相場は約760万円以上も減少しました。物価が上昇していることと考えあわせると、退職金の価値は額面以上に減っているといえます。
今後は、退職金だけで老後資金すべてを準備するのは、より難しくなると考えられます。老後の不安を軽減するためにも、退職金だけに頼るのではなく、退職金以外の方法も併用して老後資金の準備をすることが必要です。
老後に備えて資金を準備する方法
退職金は今後も下がる可能性があります。退職金以外で老後資金に備えることも検討しておきましょう。主な方法としては、次のものが挙げられます。
- iDeCo
- 新NISA
- 貯蓄型保険
退職金制度のない企業に勤めている人や、自営業の人もぜひ参考にして、老後資金の準備を始めてください。
iDeCo
iDeCoは、掛金を拠出して運用し、原則として60歳以降に掛金と運用益の合計額を老齢給付金として受け取る制度です。早くからはじめることで掛金が増え、受け取れる給付金も増やしやすくなります。
iDeCoは税法上の優遇がある点も特徴です。掛金は全額所得控除の対象になるため、所得税と住民税の負担軽減につながります。
また、運用益が非課税で、受け取る際も「公的年金等控除」もしくは「退職所得控除」の対象となるため、税金の負担が軽減できる分、受け取れる金額が多くなります。
ただし、iDeCoは貯蓄ではなく運用するという点に注意が必要です。運用成果によっては、掛金の合計額よりも給付金が少なくなるリスクがあります。
新NISA
NISAは、投資で得た運用益が非課税になる税制優遇制度です。
本来、株式や投資信託を運用すると、利益に対して約20%の税金が課せられます。しかし、NISAの枠内で運用する場合は、利益は非課税となるため、そのまま受け取ることが可能です。
2024年からは新NISA制度がはじまります。新NISA制度では「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの運用枠があります。「つみたて投資枠」では年間120万円、「成長投資枠」では年間240万円の投資が可能です。
非課税限度額は全体で1,800万円あり、最大1,800万円の資金を元に非課税で運用していけます。新NISAはこつこつ貯めることに適しているため、老後資金を備える手段としても活用できるでしょう。
ただし、運用には損失のリスクもあります。複数の株式や投資信託などに資産を分散し、リスクを抑えた運用を心がけましょう。
※制度に関する記載は2023年6月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
貯蓄型保険
貯蓄型保険は、保障を得ながら貯蓄もできる保険のことです。保険料の一部が積み立てられ、満期時には満期保険金、解約時には解約返戻金を受け取れます。
なお、解約返戻金は多くの場合、払い込んだ保険料を下回るため、解約時には注意が必要です。契約してから短期間で解約すると、解約返戻金を受け取れない場合もあります。
老後資金を準備するだけでなく、万一に備えたいという人におすすめの方法です。
退職金だけでは不安!
「明治安田生命じぶんの積立」で準備をはじめよう
「明治安田生命じぶんの積立」は、月々5,000円から積み立てられる貯蓄型保険です。保険料の払込みが5年間(保険期間は10年)と短めなため、気軽にはじめられます。
また、加入時の告知も不要で、健康に不安のある人や持病のある人もお申込みいただけます。いつ解約しても100%以上の受取率(※)なので、受け取れる金額が払い込んだ保険料を下回ることがありません。
満期保険金は幅広い用途で利用できるため、老後資金を積み立てる方法としてもおすすめです。
※受取率とは、払込保険料の累計額に対する満期までの受取総額の割合をいいます。
※保険商品をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
どの程度の退職金を受け取れるのか理解しておくと、老後資金計画が立てやすくなります。勤務先の退職金規定も確認し、概算しておきましょう。
ただし、退職金は減少傾向にある点に注意が必要です。また、物価の上昇が続けば、お金の価値そのものが減少していきます。
税金の負担を軽減しながら運用できるiDeCoや新NISAや、貯蓄しつつ保障も得られる貯蓄型保険なども活用し、老後資金を計画的に準備しましょう。
募Ⅱ2300939ダイマ推