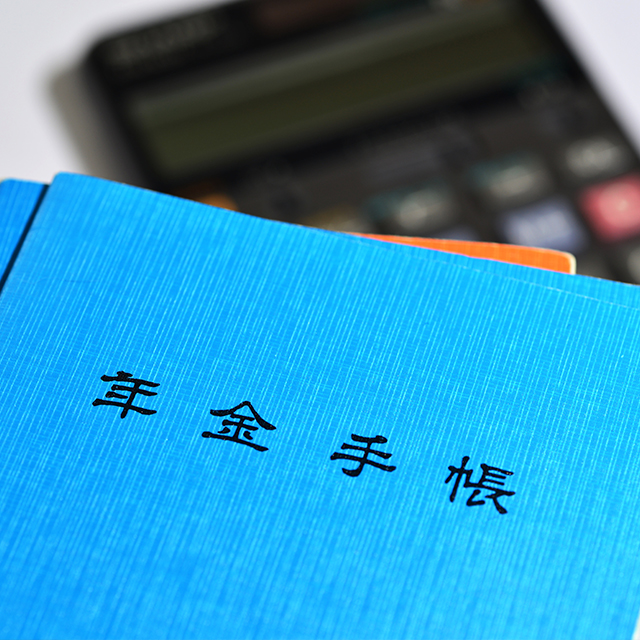学資保険でかかる税金について分かりやすく解説!
控除や申告方法も紹介
子どもの教育資金を準備するため、学資保険の加入を検討する人も多いのではないでしょうか。
子どもが小さいうちから保険料を払い込んでいれば、進学のタイミングでまとまった金額を用意できます。
ただし、学資保険で受け取れる教育資金や満期保険金も課税対象です。税金が思わぬ負担になるケースもあるため、加入前に知っておく必要があります。
この記事では、学資保険にかかる税金に関してや税金がかかる場合の計算方法を解説します。学資保険は、受取時にかかる税金も知ったうえで加入することが大切です。
※税法上の取扱いについては2023年6月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更の伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。

学資保険に課せられる税金とは
学資保険で受け取れる教育資金や満期保険金は、所得税・住民税・贈与税・相続税のいずれかが課せられます。
どの税金が課せられるかは、保険料を払い込む人(契約者)と保険金を受け取る人が同じか異なるかで決まります。
所得税
学資保険の保険料を払い込む人と、教育資金を受け取る人が同一人物の場合、所得税の課税対象になります。
学資保険では、契約者と受取人を同じ人に設定して契約するケースが一般的です。そのため多くの場合、学資保険の教育資金や満期保険金を受け取る際は、所得税が課せられます。
所得税の税率は1年間の総所得金額によって異なります。受取時の総所得金額が多いほど、税金の負担も増加します。
住民税
学資保険の契約者と受取人が同一人物の場合、所得税とあわせて住民税の課税対象になります。
住民税には、所得割と均等割があります。所得割は所得金額に応じて増減し、1年間の総所得金額の10%が課せられます。均等割は一定の所得がある人に一定額が課せられ、税額は5,000円です。
2023年度までは東日本大震災の影響から各都道府県の防災費用を確保するため、一律500円加算されています。
贈与税
学資保険の契約者と受取人が異なる場合は、贈与税の課税対象になります。たとえば、親が保険料を払い込んで子どもが教育資金や満期保険金を受け取るケースや、父親が保険料を払い込んで母親が教育資金を受け取るケースなどです。
ただし、学資保険では契約者と受取人を同一にした契約を結ぶ場合が多く、贈与税が課税されるケースは少ないでしょう。
相続税
学資保険は契約者が万一の際、保険料の払込みが免除され、教育資金や満期保険金を受け取れるものもあります。
この場合、教育資金や満期保険金は相続財産として扱われるため、相続税の課税対象です。
契約者に万一のことがあり、保険料を払い込んでいない人が教育資金や満期保険金を受け取る権利を得るため、このような扱いになります。
学資保険で税金が課せられるケース
学資保険に所得税・住民税が課せられる場合、教育資金を一括で受け取るか、年金形式で受け取るかで税金の計算方法が異なります。
また、契約者と受取人が異なる場合に課せられる贈与税や相続税も、税率や控除額が違うため、ケースごとに分けて解説します。
教育資金を一括受取にする場合
学資保険の契約者自身が、教育資金や満期保険金を一括で受け取る場合は税法上、一時所得に該当し、所得税と住民税の課税対象です。
この場合、まず課税対象となる一時所得の金額を求めます。
【一時所得の金額を求める計算式】
一時所得の金額=教育資金・満期保険金―(払込保険料総額―剰余金)―特別控除額50万円
払込保険料総額は、教育資金や満期保険金を受け取るまでに払い込んだ保険料の総額です。
剰余金は、保険会社の運用結果に余剰があった際、契約者へ分配される配当金で、配当がない保険もあります。
たとえば、月々15,000円の保険料を15年間払い込み(払込保険料総額270万円)、300万円を一括受取(配当なし)する学資保険の場合を考えてみましょう。
300万円-270万円-50万円=-20万円
受け取った教育資金や満期保険金から払込保険料総額と特別控除を差し引くと、マイナスになるため、課税対象となる一時所得金額は0円です。そのため、税金はかかりません。
また、課税対象となる金額は、一時所得金額の2分の1です。
課税対象となる一時所得を求めたのち、給与所得や事業所得などほかの所得とあわせて、所得税・住民税を計算します。
教育資金を年金形式にして受け取る場合
教育資金や満期保険金を年金形式で学資保険の契約者自身が毎年受け取る場合は、税法上、雑所得に分類されます。
年金形式で受け取る場合も、所得税と住民税の課税対象です。
【雑所得の金額を求める計算式】
雑所得の金額=その年に受け取った金額―受け取った金額に対応した払込保険料総額
雑所得には、一時所得にあった特別控除はありません。上の計算式にて算出した雑所得に、給与所得や事業所得などほかの所得とあわせて、所得税・住民税を計算します。
ただし、一定の要件を満たす会社員などの給与所得者は、雑所得の金額が20万円以下であれば申告は不要です。
保険料を払い込んだ人と受取人が違う人の場合
学資保険の契約者と受取人が異なる場合は、贈与税または相続税が課せられます。
贈与税
贈与税の課税対象になるのは、契約者である親が保険料を払込み、子どもが教育資金や満期保険金を受け取るようなケースです。
【贈与税の計算式】
贈与税=(受け取った保険金―基礎控除110万円)×贈与税率―控除額
贈与税率は契約者・受取人の関係によって、一般税率と特別税率に分けられ、税率と控除額が異なります。
【贈与税の一般税率】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
【贈与税の特別税率】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
特別税率は、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与で、贈与を受けた人の年齢が18歳以上の場合に適用されます。
一般税率を適用するのは、特別税率が適用されない場合です。たとえば、夫婦間や親から子どもへの贈与で、子が未成年の場合は特別税率が適用されます。
契約者ではない人が教育資金を一括で300万円受け取った場合、課税対象は基礎控除110万円を差し引いた190万円です。一般税率・特別税率ともに税率は10%で、19万円を税金として支払います。
300万円-基礎控除110万円=190万円
190万円×10%=19万円(控除額なし)
相続税
相続税が課せられるのは、契約者が万一の際に、保険料の払込みが免除されて教育資金や満期保険金を受け取るケースです。
相続税の場合は、教育資金や満期保険金の受取時ではなく、相続が発生した時点で課せられます。
また、相続税は相続財産すべての価額を合計し、基礎控除額を差し引いた残りに課税されます。学資保険で受け取れる教育資金にかかる相続税だけを、個別に計算できません。
教育資金が相続税の対象となる場合は、その他の預貯金や不動産、有価証券などの相続財産と合算して相続税を求めます。
【相続税の計算手順】
1,相続する財産の価額を合計する
2,債務や葬儀費用、非課税財産を差し引いて遺産額を算出する
3,遺産額に相続開始前3年以内の贈与財産を加算する
4,法定相続人の人数に応じた基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出する
5,課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したと仮定して税額を計算する
法定相続人とは民法で定められた相続人であり、配偶者は必ず相続人になります。次いで子ども、父母・祖父母、兄弟姉妹が基本的な順位です。
そして、法定相続分とは民法で定められた、法定相続人の相続割合です。実際に相続で受け取る金額とは異なるケースもあります。
【相続税の基礎控除額の計算式】
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が配偶者と子ども1人の2人だった場合、基礎控除額は4,200万円です。
学資保険で受け取る教育資金を含む相続財産から債務や葬儀費用、非課税財産を差し引き、3年以内の贈与財産を加算しても4,200万円までなら相続税は課税されません。4,200万円を超えた部分に対して、相続税が課税されます。
基礎控除を差し引いた課税遺産総額が0円でない場合、法定相続分どおりに分けたものとして相続税を求めます。
例えば法定相続人が配偶者と子ども1人の場合、法定相続分はそれぞれ2分の1です。按分した金額に対して次の税率をかけて相続税を求めます。
| 受取金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁「相続税の税率」
また、相続税の税額には、配偶者控除や未成年者控除も存在します。
【相続税の税額から控除されるものの例】
| 配偶者の税額軽減(配偶者控除) | 実際に受け取った遺産額が1億6,000万円まで、または法定相続分相当額までなら相続税はかからない |
|---|---|
| 未成年者控除 | 18歳未満の相続人は10歳に達するまでの年数1年につき10万円控除 |
| 障害者控除 | 相続人が障がい者の場合は85歳に達するまでの年数1年につき10万円控除(特別障害者の場合は20万円控除) |
税額からの控除を差し引いた金額を、相続税として納めます。
学資保険の保険料も生命保険料控除の対象
学資保険は教育資金や満期保険金を受け取る際、税金がかかる場合もあるとわかりました。
しかし、学資保険で払い込んだ保険料は保険料控除の対象です。払い込んだ金額を控除に含めれば、税金の負担を軽減できる可能性があります。
保険料控除の概要や申告方法を解説します。
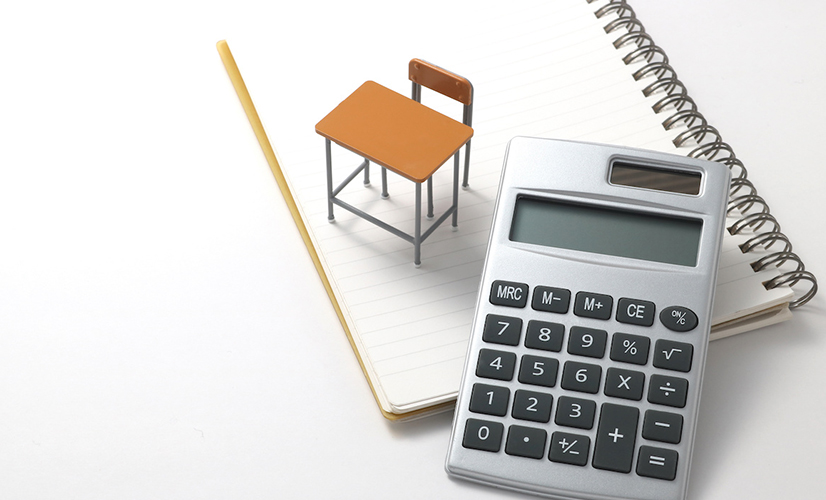
生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、1年間に払い込んだ生命保険料を所得から一定額差し引ける所得控除です。所得控除を受けると、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
生命保険料控除は2011年12月31日以前に締結した保険(旧契約)と、2012年1月11日以降に締結した保険(新契約)とに分けられ、控除額の上限が異なります。
2012年1月11日以降に締結した保険(新契約)では最高4万円、2011年12月31日以前に締結した保険(旧契約)では最高5万円が生命保険料控除の対象です※。
【年間の払込保険料と控除額(旧契約:2011年12月31日以前に締結)】
| 年間の払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料等×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 払込保険料等×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
出典:国税庁「保険と税」
【年間の払込保険料と控除額(新契約:2012年1月11日以降に締結)】
| 年間の払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 払込保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
出典:国税庁「保険と税」
※生命保険料控除の控除額は、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合計して最高12万円までです。
生命保険料控除の申告方法
生命保険料控除は申告しなければ控除されません。税金の負担を抑えるため、控除できる保険料を払い込んでいる場合は、忘れずに申告しましょう。
申告方法には、年末調整と確定申告が存在します。
年末調整で申告
会社員などの給与所得者の場合、生命保険料控除は勤め先で年末調整を受ける際に申告します。
勤め先で配布される申告書には、保険会社の名称や保険の種類、契約者・受取人の名前、払い込んだ保険料などを記入しましょう。
払込金額を証明する書類を添えて勤め先に提出すると、年末調整で払い込んだ生命保険料控除が受けられます。
払込金額を証明する書類は、保険会社から送付される生命保険料控除証明書を使用します。生命保険料控除証明書は多くの場合、毎年10月ごろに届く傾向にあります。最近はインターネット上で発行する場合もあるため、保険会社のホームページなどで確認しましょう。
確定申告で申告
一年の途中で退職した人や給与所得がない個人事業主など、年末調整を受けない人は確定申告の際に生命保険料控除を申告しましょう。
確定申告書の生命保険料控除の欄に必要事項を記入し、払込金額を証明する書類を添えて税務署へ提出します。
証明書類は年末調整を受ける場合と同じく、保険会社から発行される生命保険料控除証明書を使用します。
学資保険なら「明治安田生命つみたて学資」
「明治安田生命つみたて学資」は、家計の状況やライフプランにあわせて、保険料の払込期間を選べる学資保険です。
払込期間はお子さまが10歳になるまで・15歳になるまで・加入時に一括払込から選択できます。
大学進学でかかる費用に備えられるよう、教育資金や満期保険金は4回に分けて受け取れます。
充実した受取率(※)を実現しているほか、契約者に万一の際は払込みが免除されて内容は継続するため、安心して教育資金を備えられます。
教育資金の準備方法として、ぜひご検討ください。
※受取率とは、払込保険料の累計額に対する満期までの受取総額の割合をいいます。
※保険商品をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
学資保険で受け取れる教育資金や満期保険金も課税対象です。かかる税金の種類は状況によって異なりますが、多くの場合は保険料を払い込む契約者自身が教育資金を受け取るため、所得税・住民税が課せられます。
契約者と受取人が同一である場合、受取った教育資金から払い込んだ保険料を差し引いて税金を計算するため、税金を払わずに済むケースも多いでしょう。
しかし、契約者以外の人が教育資金を受け取る場合、贈与税または相続税が課せられ、税金を支払わなければならない可能性があります。
学資保険の契約時は税金がかかる可能性を考慮して、契約内容を決めましょう。
募Ⅱ2301003ダイマ推