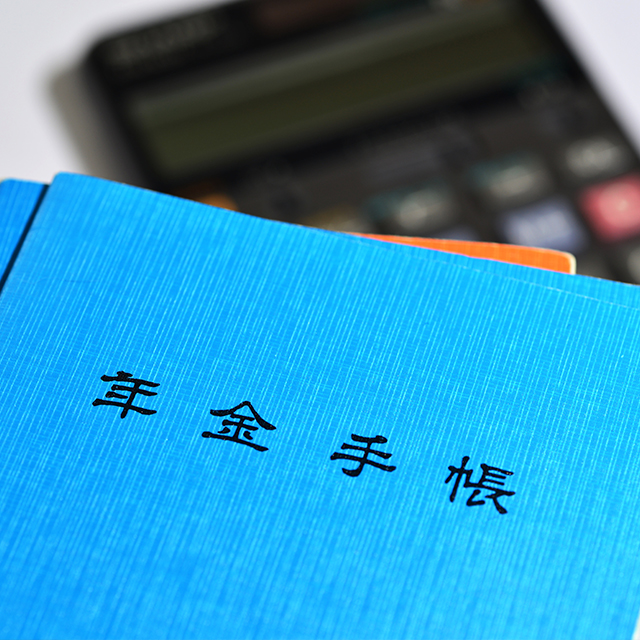子どもの教育費は幼稚園から
大学卒業までいくらかかる?
準備する方法についても解説
妊娠中や子育て中の人のなかには、子どもの教育費がいくらかかるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
本記事では、子どもが幼稚園(保育園)〜大学卒業までにかかる教育費を公立・私立に分けて解説します。
また、子どもの教育費のために活用できる国の制度や、教育費を準備するための具体的な方法も紹介します。妊娠中や子育て中の人は、ぜひ参考にしてください。
※本記事は、2023年10月現在の内容です。

子どもの教育費は公立か私立かで大きな差が生まれる
子どもにかかる教育費は、公立と私立で大きく異なります。幼稚園〜大学まですべて国公立に通った場合とすべて私立に通った場合の差は、約1,500万円です(※)。いずれにしても、子どもが幼稚園~大学まで通うには大きな金額の教育費がかかります。
※文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」と日本学生支援機構「令和2年度学生生活調査結果」をもとに算出
また、入学のタイミングではまとまった費用が必要です。さらに、下宿が必要な場合は毎月の家賃や生活費の負担も大きくなるでしょう。
子どもが幼いうちからどのように備えるのかをよく話し合い、計画的に教育費の準備を進める必要があります。
子どもの教育費は平均でいくらかかる?
子どもの教育費にいくらかかるのかが気になる人向けに、文部科学省と日本学生支援機構の調査結果をもとに、幼稚園〜大学までの教育費の平均を国公立と私立に分けて紹介します。
幼稚園の教育費平均
文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」によると、公立幼稚園と私立幼稚園の教育費平均は、それぞれ以下のとおりでした。
| 区分 | 教育費(3年間合計) |
|---|---|
| 公立幼稚園 | 495,378円 |
| 私立幼稚園 | 926,727円 |
| 公立と私立の差額 | 431,349円 |
※文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」をもとに作成
公立幼稚園と私立幼稚園の教育費を比べてみると、3年間で約43万円の差が生じる計算です。
文部科学省によると、「令和3年度子供の学習費調査」のデータでは全体の12.8%が公立幼稚園、87.2%が私立幼稚園に通っています。従って、幼稚園の教育費を考える際は私立幼稚園に通うと仮定して計算すると良いでしょう。
小学校の教育費平均
同調査によると、公立小学校と私立小学校にかかる教育費の平均は、それぞれ以下のとおりでした。
| 区分 | 教育費(6年間合計) |
|---|---|
| 公立小学校 | 2,115,396円 |
| 私立小学校 | 10,001,694円 |
| 公立と私立の差額 | 7,886,298円 |
※文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」をもとに作成
文部科学省によれば、私立小学校は、公立小学校と比べて教育費が年間約131万円多くなっています。6年間合計では、公立と私立で約789万円と大きな差が生じる計算です。
私立小学校のうち、学校教育費の大きな割合を占めているのが「授業料」です(※1)。また、学校外活動費をみると、公立・私立ともに自宅学習や学習塾、家庭教師などにかかる「補助学習費」の支出が多くなっています(※2)。
なお、文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、小学校に通う全生徒のうち公立小学校に通っているのは98.7%であり、私立に通っている生徒は1.3%と少数です。
※1 学校教育費は、学校納付金や授業料など、学校教育のために各家庭が支出した全経費を指します。
※2 学校外活動費は、自宅学習や学習塾・家庭教師、体験活動や習い事などの経費です。
中学校の教育費平均
同調査によると、公立中学校と私立中学校にかかる教育費の平均は、それぞれ以下のとおりでした。
| 区分 | 教育費(3年間合計) |
|---|---|
| 公立小学校 | 1,616,397円 |
| 私立小学校 | 4,309,059円 |
| 公立と私立の差額 | 2,692,662円 |
※文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」をもとに作成
私立中学校の教育費は、公立中学校と比べて年間約90万円多くなっています。3年間にかかる教育費の公立・私立の差額は、約270万円です。
学校教育費をみてみると、私立中学校は「授業料」「通学関係費」「学校納付金等」「入学金等」の割合が高く、特に授業料は4割以上と高い割合を占めています。
一方、学校外活動費をみると、「補助学習費」にかかる支出は私立中学校よりも公立中学校のほうが多い結果です。
高校の教育費平均
次に、公立高校(全日制)と私立高校(全日制)の教育費平均を比較しましょう。
| 区分 | 教育費(3年間合計) |
|---|---|
| 公立高校(全日制) | 1,538,913円 |
| 私立高校(全日制) | 3,163,332円 |
| 公立と私立の差額 | 1,624,419円 |
※文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」をもとに作成
公立高校(全日制)と私立高校(全日制)では、教育費に年間約54万円の差が生じています。私立高校(全日制)の年間教育費は、公立高校(全日制)の約2倍です。3年間の合計でみると、約162万円の差があります。
私立高校(全日制)の学校教育費の内訳をみると、「授業料」と「学校納付金等」の割合が高く、その二つをあわせて5割以上を占める結果です。
大学の教育費平均
日本学生支援機構の「令和2年度学生生活調査結果」によると、国公立大学(昼間部)と私立大学(昼間部)の教育費平均は、それぞれ以下のとおりでした。
| 区分 | 教育費(4年間合計) |
|---|---|
| 国立大学(昼間部) | 2,368,000円 |
| 公立大学(昼間部) | 2,420,000円 |
| 私立大学(昼間部) | 5,242,800円 |
| 国公立と私立の差額 | 2,848,800円(※1) |
※1 国立大学(昼間部)と公立大学(昼間部)の平均と私立大学の差額を計算しています。
※日本学生支援機構「令和2年度学生生活調査結果」をもとに作成
年間でみると、私立大学は国立大学・公立大学の2倍以上の教育費がかかっています。4年間合計の差額は、約285万円です。
幼稚園~大学卒業までを合計すると、すべて公立の場合で約816万円、すべて私立の場合は約2,364万円の教育費がかかる計算です。
子どもの教育費の支援を受けられる制度
子どもの教育費は、公立・私立のどちらに通っても大きな金額となります。子どもの教育費について、国から支援を受けられる制度を知っておきましょう。
ここでは、以下4つの支援制度を紹介します。
- 高等学校等就学支援金制度
- 高校生等奨学給付金
- 特別支援教育就学奨励費
- 大学等奨学金
※制度に関する記載は2023年10月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

高等学校等就学支援金制度
「高等学校等就学支援金制度」とは、授業料に充てるための就学支援金が支給される制度です。
国公・私立を問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(年収約910万円未満の世帯)の生徒が対象となります(※)。
※「年収約910万円未満」は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。
公立高校の場合、支給限度額は以下のとおりです。
| 区分 | 支給限度額(定額授業料の場合) |
|---|---|
| 公立高校(全日制) | 月額9,900円 |
| 公立高校(定時制) | 月額2,700円 |
| 公立高校(通信制) | 月額520円 |
※文部科学省「高等学校等就学支援金制度 支給期間・支給限度額一覧」をもとに作成
私立高校では、全日制・定時制・通信制ともに月額9,900円が支給限度額であり、世帯所得や通う学校種により加算支給される場合があります。
ただし、公立・私立ともに、単位ごとに授業料が設定される課程に在学する場合は支給額が異なるため、ご注意ください。
なお、高等学校等就学支援金制度の手続きは、学校等を通じて行ないます。
高校生等奨学給付金
高校生等奨学給付金は、就学支援金とは別に、低所得世帯に対して授業料以外の教育費を支援する制度です(※1)。以下の世帯が対象となります。
※1 授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、強化外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費、通信費等です。
- 生活保護世帯
- 年収約270万円未満の住民税所得割が非課税の世帯(家計が急変して非課税相当になった世帯も含む)
給付額は、世帯の状況や国公立・私立で異なります。
| 世帯状況 | 給付額(年額) | |
|---|---|---|
| 国公立 | 私立 | |
| 生活保護世帯(全日制等・通信制) | 32,300円 | 52,600円 |
| 非課税世帯(全日制等) 第1子 |
117,100円 | 137,600円 |
| 非課税世帯(全日制等) 第2子以降(※2) |
143,700円 | 152,000円 |
| 非課税世帯(通信制・専攻科) | 50,500円 | 52,100円 |
※2 15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合
※文部科学省「令和5年度 高校生等奨学給付金リーフレット」をもとに作成
家計の急変によって非課税相当になった場合は、申込月によって給付額が異なります。
なお、高校生等奨学給付金を受けるには、学校またはお住まいの都道府県への申込み手続きが必要です。
特別支援教育就学奨励費
特別支援教育就学奨励費とは、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級等への就学に必要な学用品費、給食費、通学費などの一部を国や自治体が補助する制度です。
以下の児童・生徒が対象となります。
- 特別支援学校、特別支援学級、国立大学法人の付属支援学校・付属小学校・付属中学校に通っている
- 小学校または中学校に在学し、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に当てはまる障害がある
支給額は各自治体で異なるので、お住まいの自治体のホームページなどで確認しましょう。
大学等奨学金
大学等奨学金は、意欲と能力のある学生等が経済的理由により進学等を断念することがないよう学生を支援する制度です。独立行政法人日本学生支援機構が運営しています。
大学等奨学金には、「給付型」と「貸与型」があります。返済が不要な給付型は、貸与型と比べて世帯年収等の条件が厳しく設定されているのが特徴です。また、貸与型には第一種奨学金(無利子)と第二種奨学金(有利子)があります。貸与額は、以下のとおりです。
| 区分 | 第一種奨学金(無利子)(月額) | 第二種奨学金(有利子)(月額) | |
|---|---|---|---|
| 自宅通学 | 自宅外通学 | ||
| 国公立大学 | 20,000円、30,000円、45,000円 | 20,000円、30,000円、40,000円、51,000円 | 20,000~120,000円(10,000円刻み) |
| 私立大学 | 20,000円、30,000円、40,000円、54,000円 | 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、64,000円 | |
※独立行政法人日本学生支援機構「奨学金 支給・貸与月額について知りたい」をもとに作成
なお、大学等奨学金は、学力基準や家計基準を満たした場合に利用できます。
子どもの教育費を準備する方法
教育費は、子どもが幼いうちから計画的に準備することが大切です。ここでは、子どもの教育費を準備する方法として、以下4つを紹介します。
- 児童手当を貯める
- 財形貯蓄制度
- つみたてNISA
- 学資保険
児童手当を貯める
児童手当を貯めれば、高校および大学の教育費の一部に充てられます。
児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している人を対象に毎月一定額が支給される制度です。すべて貯めると、約200万円になります。
| 児童 | 支給額(1人あたり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
ただし、児童手当制度には所得制限限度額・所得上限限度額が設定されているため、受給できない人もいます。
財形貯蓄制度
財形貯蓄制度は、事業主が従業員に代わって賃金から天引き預金する方法により貯蓄を行なう制度です。設定した金額が自動的に天引きされるので、計画的にお金を貯められます。
また、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄では、その利子等について税法上の優遇措置が受けられるのも特徴です。
| 財形貯蓄の種類 | 目的 | 税法上の優遇措置 |
|---|---|---|
| 一般財形貯蓄 | 自由 | なし |
| 財形年金貯蓄 | 年金として受け取る (満60歳以上) |
財形住宅と合算して550万円まで利子が非課税になる |
| 財形住宅貯蓄 | 住宅の取得・増改築の費用に充てる | 財形年金と合算して550万円まで利子が非課税になる |
なお、財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄に加入できるのは、契約時に55歳未満の人です。また、財形貯蓄制度を利用するには、お勤め先で制度が導入されている必要があります。
※税法上の取扱いについては2023年10月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。
つみたてNISA
つみたてNISAは、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。毎年40万円を上限に一定の投資信託を購入でき、最長20年間、800万円まで分配金と利益が非課税になります。
手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、一定の基準を満たす投資信託だけが対象であり、投資初心者でも取り組みやすいのが特徴です。また、金融庁でもNISAの活用事例として子どもの教育費を挙げています。
なお、2024年1月には「新しいNISA」が導入され、一般NISAとつみたてNISAが一本化される予定です。新しいNISAでは、非課税保有期間が無期限となり、年間投資枠や非課税保有限度額が拡大します。
※税法上の取扱いについては2023年10月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。
学資保険
学資保険は、子どもの教育費に備えるための貯蓄型保険です。毎月保険料を払い込み、入学や進学のタイミングで教育資金を受け取れます。
学資保険を活用すれば、払込保険料総額より大きな教育資金を受け取ることもできる場合があります。
教育資金は、大学入学以降に受け取るのが一般的です。ただし、高校、中学など受け取るタイミングを自由に選べる学資保険もあります。
お子さまの教育費に備えるなら「明治安田生命つみたて学資」がおすすめ
「明治安田生命つみたて学資」は、充実した受取率で計画的に教育費を準備できる学資保険です。費用がかさむ大学などの時期にあわせて、教育資金をお受け取りいただけます。保険料を一括でお払い込みいただいた場合の受取率(※1)は、最大129.2%(ご契約の一例(※2)です)。
また、ご契約者様に万一のことがあった場合、保険料の払込みが免除されます。払込みが免除されたあとも、保障内容はそのまま継続するので安心です。
さらに、ご加入者さまは、看護師や保健師などの専門家による妊娠やお子さまのケガや病気などへのアドバイスを24時間無料で受けられます。お子さまの出生予定日の140日前からお申込みできるので、ぜひご検討ください。
※1 受取率とは、払込保険料の累計額に対する満期までの受取総額の割合をいいます。受取率はご契約内容によって異なります。
※2 保険契約の型:I型/ご契約者:25歳 男性/被保険者(お子さま):0歳/21歳満期/基準保険金額:70万円/一括払込(10歳払込満了(新年掛))/保険料率:2025年11月1日現在※明治安田生命つみたて学資をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
子どもの教育費は、公立と私立のどちらに通うかで大きな差が生まれます。
すべて公立の場合で約816万円、すべて私立の場合は約2,364万円と、いずれにしても負担は小さくありません。利用できる国の支援制度を把握し、活用しましょう。
お子さまの教育費を貯めるなら、進学のタイミングで学資金を受け取れる学資保険がおすすめです。計画的に教育費をご準備したい人は、ぜひご検討ください。
募Ⅱ2500979ダイマ推