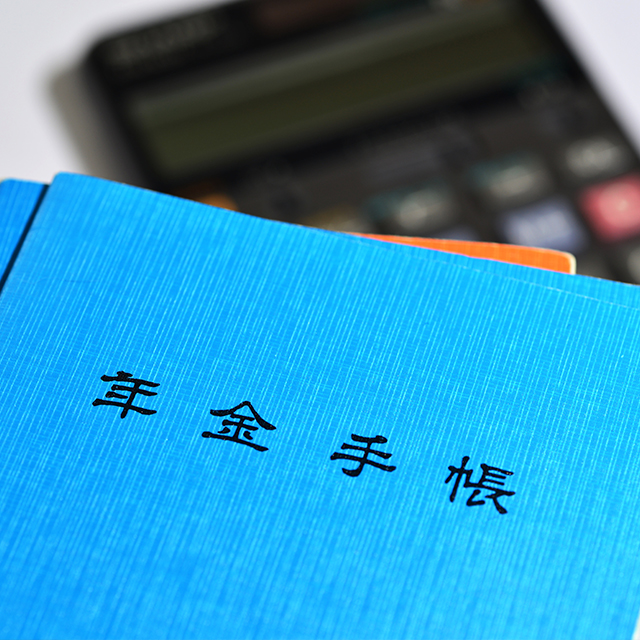大学の学費はどのくらい高い?
平均額や国公立と私立の違い、奨学金制度などを解説
文部科学省の「令和5年度学校基本調査」によると、2023年度の大学進学率が57.7%と過去最高を更新し、現代では大学進学を選択する子どもが増えています。
教育費のなかでも特に高いとされる大学の学費にどれくらい備えておけばいいのか、悩む人もいるでしょう。
家計にも大きな負担となるため、大学進学時に困らないように、学費の目安を把握して少しでも早くから準備することが大切です。
そこで、国公立と私立、学部などによる違いにも注目しながら、大学の学費の平均額を解説します。
あわせて、国からの補助や奨学金など、負担を軽減する手段や効率よく学費を準備する方法を紹介するのでぜひ参考にしてください。
※本記事は、2024年3月現在の内容です。

大学の学費の平均額はどれくらい?
高いイメージが先行しがちな大学の学費ですが、実際には国立・公立・私立の種別ごとに金額の開きがあります。
また、授業料は毎年ほぼ一定ですが、初年度納入金は入学金が含まれるため、在学中でもっとも高い学費の支払いとなり、学費の高さを知る目安になります。
上記を踏まえて、国立・公立・私立の種別ごとの初年度納入金を、大学の学費の平均額として紹介します。
国立大学の学費
国立大学の入学金と授業料は、文部科学省の省令により、「標準額」として金額を定められています。
国立大学の学費(2024年度標準額)
| 項目 | 標準額 |
|---|---|
| 入学金 | 282,000円 |
| 授業料 | 535,800円 |
| 合計(初年度納入金) | 817,800円 |
出典:e-Govポータル「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」
大学側は、標準額の上限20%以内であれば、入学金と授業料の増額が可能です。そのため、大学ごとに学費の違いが出る可能性はありますが、国立大学の学費に大きな差はありません。
公立大学の学費
公立大学は大学や学部によって学費が異なります。
さらに、市区町村など地方自治体が税金を出資して運営されるため、その自治体に税金を納める地域内入学者に対して入学金を優遇する大学が多く、地域内・地域外で初年度納入金額が変わる場合もあります。
文部科学省が公表している、2023年度公立大学の初年度納入金の平均額は次のとおりです。
公立大学の学費(2023年度 大学昼間部)
| 項目 | 地域区分 | 費用 |
|---|---|---|
| 入学金 | 地域内 | 224,066円 |
| 地域外 | 374,371円 | |
| 授業料 | 地域内・外共通 | 536,191円 |
| 合計(初年度納入金) | 地域内 | 760,257円 |
| 地域外 | 910,562円 |
出典:文部科学省「2023年度 学生納付金調査結果(大学昼間部)」
ただし、入学金は地域のほか、医学部や看護学部など学部によっても異なる場合もあります。また、初年度納入金の平均額は国立大学と大きな差がなくても、実際の初年度納入金は大学や学部ごとに開きがある点に注意が必要です。
文部科学省の「2023年度 学生納付金調査結果(大学昼間部)」のデータでは、公立大学の入学金は125,000円から564,000円、授業料は322,300円から696,000円の開きがあり、進学先によってかかる学費に差が出る可能性があります。
私立大学の学費
2022年5月時点の大学数は、国立大学が86校、公立大学が100校で、私立大学は622校と群を抜いて多く、7割以上は私立大に進学する状況です。国公立大学だけではなく、私立大学の学費の動向も押さえておきましょう。
国公立大学とは違い、私立大学は学校設備の維持や拡充にかかる費用を自己負担しなければならないため、入学金と授業料のほかに「施設設備費」を学生から集めます。
私立大学の学費(2023年度)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 入学金 | 959,205円 |
| 授業料 | 240,806円 |
| 施設設備費 | 165,271円 |
| 合計(初年度納入金) | 1,365,281円 |
出典:文部科学省「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
私立大学の初年度納入金の平均額は、国公立大学より45万から55万円ほど高いです。
しかし、私立大学は国立大学のように標準額がなく、公立大学のように自治体による運営ではないため、大学や学部によって学費の設定が異なります。
以下で詳しく解説します。
学部によっても異なる私立大学の学費
私立大学は、大学や学部によって学費の差がありますが、学部による学費の違いには一定の傾向が見られます。
そこで、私立大学の学費を学部の系統別から紹介します。
私立大学の学費(2023年度)
| 学部系統 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 合計(初年度納入金) |
|---|---|---|---|---|
| 文系 | 223,867円 | 827,135円 | 143,838円 | 1,194,841円 |
| 理系 | 234,756円 | 1,162,738円 | 132,956円 | 1,530,451円 |
| 医歯系 | 1,077,425円 | 2,863,713円 | 880,566円 | 4,821,704円 |
| その他 | 251,164円 | 977,635円 | 231,743円 | 1,460,542円 |
| 全平均 | 240,806円 | 959,205円 | 165,271円 | 1,365,281円 |
出典:文部科学省「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
上記のとおり、私立大学では文系より理系の学費が高く、また医歯系の学費は突出して高い傾向があります。
理系は実験や実習が多い分、文系よりも学費が高くなる傾向にあると考えられます。さらに、医学部や歯学部などは実習が多いため、初年度納入金だけで500万円近くの金額になります。
学費以外に大学でかかる費用
大学では、学費(入学金と授業料)以外にもさまざまな費用がかかります。
- 生活費
- その他
それぞれ詳しく解説します。

生活費
大学に進学すると、大学に通学するための交通費や、下宿であれば家賃や食費、光熱費など、日常の生活費の負担も大きくなります。
日本学生支援機構の調査によると、自宅から通う大学生(自宅生)の生活費は1ヵ月あたり約3万2,000円、アパートなどに下宿する大学生(下宿生)の生活費は1ヵ月あたり約9万2,000円です(※)。また下宿の場合、敷金や礼金、家電の購入などの初期費用も必要になるでしょう。
(※)日本学生支援機構「令和2年度学生生活調査結果」のデータをもとに試算
下宿生の生活費は住まいの家賃によって変わるとはいえ、自宅生の3倍近い生活費がかかる可能性を考慮して、教育資金を備えることが重要です。
その他
大学の授業に使う教科書は、授業料などの学費には含まれず、別途購入しなければなりません。またレポート作成に欠かせないパソコン購入も、大学生にとって大きな買い物の一つです。
ほかにも、部活やサークルなどの活動費にお金がかかる学生もいるでしょう。
大学の学費はいつ納付する?
大学の学費(入学金と授業料)の納付期限は、通常、合格発表から1~2週間と設定されている場合が多いです。合格発表のタイミングで学費の納付期限が決まります。
3月上旬から下旬に合格発表シーズンを迎える国公立大学に対して、私立大学は試験も合格発表も2月です。
そのため、国公立大学を受験予定でも、いわゆる「滑り止め」として、先に納付期限を迎える私立大学に学費を納めなければならない可能性もあります。
また、推薦入試は、一般入試より試験や合格発表が早いため、9月ごろに学費を支払う場合もあります。
在学中の学費は、春(4~5月)と秋(10~11月)の2回に分けて納付する大学が一般的です。多くは銀行振込ですが、口座振替のみとする大学もあるため、口座残高にも注意しましょう。
大学の学費にかかる負担を軽減する制度
大学の学費は支払いの通知から納付期限までが短い場合も多いため、余裕を持った準備が大切です。準備が難しい、負担が大きいと感じたら、国が実施する制度の利用を検討しましょう。
※制度に関する記載は2024年3月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
奨学金制度
奨学金は、大学に進学する学生本人に給付または貸与される制度です。
日本学生支援機構の調査によると、大学生の約半数が奨学金を利用していますが、返済義務が子どもに課せられるため、申し込む前に家族でよく話し合いましょう。
日本学生支援機構による奨学金制度と、その他の奨学金制度に分けて詳しく紹介します。
日本学生支援機構による奨学金制度
大学の学費を準備する手段として広く知られている支援制度が、日本学生支援機構の奨学金です。大学生の約3割が利用しており、現在は返済不要の給付型奨学金、将来の返済が必要な貸与型奨学金(有利子・無利子)があります。
その他の奨学金制度
日本学生支援機構のほかに、地方自治体や民間団体などが実施する奨学金制度もあります。なかには独自の奨学金制度を設ける大学もあります。
給付と貸与の違い、進学先の学部、居住地、卒業後の進路などさまざまな違いがあるため、検討する際は申込条件をよく確認しましょう。
高等教育の修学支援新制度
高等教育の就学支援新制度は「大学無償化」とも呼ばれる制度です。
98%の大学・短期大学を含む高等教育で学びたい学生を対象に、経済的に支援する制度で、授業料などの減免と給付型奨学金の受給、二つの支援を受けられます。
支援対象は次の要件を満たす学生です。
- 世帯収入や資産の要件を満たす(子どもの数や年齢など家族構成によって変わる)
- やる気や学ぶ意欲がある(学校の成績だけで決まらない)
自宅以外から通う私立大学生の場合、返済不要の給付型奨学金は最高約91万円です。支援上限額は世帯年収に応じて3段階に分かれます。
給付型奨学金は高校3年生の4月から高校を通じて日本学生支援機構へ申込みます。ただし、学校ごとに締切日が異なるため事前に確認しましょう。
また、大学の授業料減免は入学時に大学へそれぞれ申込みます。入学後のお申込みも可能です。
2024年からは高等教育の修学支援新制度を拡充
高等教育の就学支援新制度は、2024年4月から制度が拡充されています。これまでの支援対象は、世帯年収約270万円まで、約300万円まで、約380万円までの3段階で設定され、支援上限額が分かれていました。
しかし、拡充後は以下のように支援対象が広がります。
- 扶養する子どもが3人以上いる多子世帯は、世帯年収約600万円までが支援対象になる
- 理工系・農学系学部の私立大学の学生に対して、文系との授業料の差額を支援する
多子世帯への支援額は、全額支援の4分の1(授業料等免除と給付型奨学金)です。
※制度に関する記載は2024年3月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
大学の学費を準備する方法
大学の学費にはまとまったお金が必要です。家計に影響しないように、できるだけ早くから準備することが大切です。しかし、どうやって準備すればいいのか、不安に感じる人も多いでしょう。
以下で大学の学費を効率よく準備するポイントを紹介します。
児童手当を貯めておく
児童手当は、子どもが中学校を卒業するまで(15歳の誕生日後最初の3月31日)、国や自治体から支給される手当です。
| 児童の年齢 | 支給額(ひとりあたり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
例えば、第1子の児童手当を全額貯蓄すると「15,000円×3年+10,000円×12年=198万円」になります。約200万円の貯蓄があれば、大学の初年度納入金に充てられるでしょう。
ただし、一定以上の所得になると所得制限により月額5,000円へ減額、さらに所得上限額を超えると支給がなくなります。なお、所得制限は世帯年収ではなく児童を養育している人の所得が基準である点に注意しましょう。
学資保険で備える
学資保険は、子どもの教育費の準備を目的とした貯蓄型保険です。保険料を払い込み、子どもの入学や進学のタイミングにあわせて、教育資金・満期保険金を受け取れます。
保険ならではの保障もあります。多くの学資保険は、契約者に万一のことがあると、以降は保険料の払込みを免除され、その後も保険料の払込みがあったものとして教育資金・満期保険金を受け取れます。
学資保険の種類によっては、払い込んだ保険料以上の教育資金・満期保険金を受け取れる場合もあります。
教育ローンを利用する
教育ローンには、日本政策金融公庫が運営する「国の教育ローン(教育一般貸付)」と民間の金融機関による教育ローンがあります。
- 国の教育ローン:入学金や授業料、受験費用、教材費などさまざまな資金に使える
- 民間の教育ローン:金融機関や商品によって使い道や申込条件などが異なる
国の教育ローンは、融資限度額が350万円までと限定されていますが、自宅外通学の場合の住居費用などに使えることや、固定金利のため毎月の返済額が一律であることが特徴です。
NISA制度を利用する
NISA制度(少額投資非課税制度)は、株式の配当金や投資信託の分配金、売却益が非課税になる制度です。通常20.315%かかる税金が非課税となるため、効率的な資産形成に向いています。
2024年1月からは非課税投資枠が拡大され、非課税期間が無期限となり、年間投資枠や非課税保有限度額が拡大しております。
ただし、投資には預貯金のような元本保証がないため、仕組みやリスクに対する正しい理解が求められます。
※税務上の取扱いについては2024年4月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。
大学の学費を学資保険で準備するなら「明治安田生命つみたて学資」がおすすめ
大学の学費を学資保険で準備するなら「明治安田生命つみたて学資」がおすすめです。教育資金3回と満期保険金1回、計4回に分けてお金を受け取れる学資保険で、費用がかさむ大学などの時期にあわせてお金を準備できます。
保険料の払込みは長くても15歳までで終わるため、教育費がかかりやすい高校から大学の時期に保険料の払込みによる負担がかかりません。
ご契約時のお子さまの年齢が2歳以下の場合は、保険料払込期間を10歳までとするご契約も可能です。
また、教育資金と満期保険金の受取率(※1)は、ご加入時保険料一括払いの場合で最大129.2%(ご契約の一例(※2))で、大学の学費にもしっかり備えられます。
(※1)受取率とは、払込保険料の累計額に対する満期までの受取総額の割合をいいます。また、受取率はご契約内容によって異なります。
(※2)保険契約の型:Ⅰ型/ご契約者:25歳 男性/被保険者(お子さま):0歳/21歳満期/基準保険金額: 70万円/一括払込は10歳払込満了(新年掛)/保険料率:2025年11月1日現在
まとめ
大学の学費は、国公立・私立の種別、学部などによって異なります。国公立大学はほぼ同じくらいの金額ですが、私立大学は初年度納入金が平均130万円を超える場合があります。
大学の高い学費に備えるには、早くから準備をはじめることが重要です。
教育ローンやNISA制度などさまざまな方法がありますが、ローン返済の負担や元本を下回るリスクを考えたうえで慎重に利用しなければなりません。
安心できる保障を備えながら、着実に学費を貯めたいなら、「明治安田生命つみたて学資」をぜひご検討ください。
※明治安田生命つみたて学資をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
募Ⅱ2500974ダイマ推