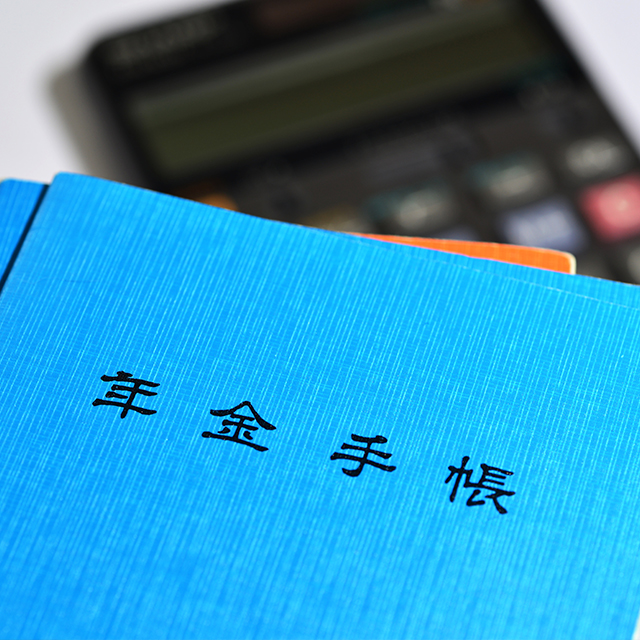大学費用がないときはどうする?
今すぐできる対処法と計画的に準備する方法を解説
大学の学費は、教育費のなかでも特に家計への負担が大きい費用です。「将来子どもが希望した大学の学費を払えるのか」と不安を感じている人や、「大学の学費を払えなくなった」と困っている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、大学費用がないときの対処法と学費の目安を紹介します。また、学費が払えないときのリスクや、学費に困らないための対策もあわせて解説します。
※本記事は、2024年1月現在の内容です。

大学費用がないときの対処法
日々の家計のやりくりに精一杯で、学費を計画的に用意できていない家庭もあるでしょう。大学の在学中に、経済的事情の変化などで学費の支払いが難しくなる場合もあります。
大学費用が払えないときは、以下の対処法を検討しましょう。
- 大学に延納や分納を相談する
- 奨学金制度を利用する
- 国の教育ローン(教育一般貸付)を利用する
- 民間の教育ローンを利用する
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度を利用する
大学に延納や分納を相談する
学費の支払いが期日までに難しいと分かったら、なるべく早く大学に相談しましょう。やむを得ない事情がある場合は、延納や分納の対応をとってくれる可能性があります。
- 延納:納入期日を延期する方法
- 分納:複数回に分けて納める方法
延納・分納を希望する場合、大学が定めた期日までに申請する必要があります。大学によって必要な書類や手続き方法などが異なるので、担当課に相談したり、ホームページなどで確認したりしましょう。
また、一定の要件を満たす場合に学費を減免する制度を設けている大学もあります。
奨学金制度を利用する
学費の納入期日が差し迫っていない場合は、奨学金の利用を検討しましょう。日本学生支援機構によると、大学生(昼間部)の49.6%が奨学金を受給しています。
奨学金制度とは、経済的な理由で進学が難しい学生に学費の給付や貸与を行なう制度です。日本学生支援機構が運営する奨学金制度や学内奨学金、自治体が行なう奨学金制度などがあります。
日本学生支援機構の奨学金制度には、給付型(返済不要)と貸与型(返済必要)があり、貸与型はさらに無利子の「第一種奨学金」と有利子の「第二種奨学金」に分けられます。
学費の支払いが難しくなった場合、在学中でも申込みが可能です。必要な書類を作成し、大学が定める期限までに提出しましょう。なお、奨学金制度は、日本学生支援機構のホームページで検索できます。
国の教育ローン(教育一般貸付)を利用する
国の教育ローン(教育一般貸付)とは、政策金融機関の一つである「日本政策金融公庫」が扱う公的な教育ローンです。
350万円(一定の要件を満たす場合は450万円)を上限に、教育に関連する費用を借入れできます。学校納付金だけでなく、さまざまな資金に利用可能です。
- 学校納付金
- 受験費用
- 在学に必要な住居費用
- 教材・パソコン購入費
- 学生の国民年金保険料など
金利は固定型で年2.25%と低めに設定されており、一定の要件を満たす人はさらに年0.4%引き下げられます。
ただし、世帯年収が上限額を超える場合は利用できません。上限額は扶養人数によって異なり、子ども1人の場合は790万円(所得600万円)、2人の場合は890万円(所得690万円)と決まっています。
なお、子どもが2人以下の場合は、一定の要件を満たせば上限額が990万円(790万円)に緩和されます。
また、申込みから審査完了まで10日前後、融資金が振り込まれるまでにさらに10日前後の日数を要する点にも注意が必要です。必要な時期の2~3ヵ月前が申込みの目安となっているため、利用を希望する人は早めに手続きをしましょう。
民間の教育ローンを利用する
民間の金融機関が提供している教育ローンを利用する方法もあります。民間の教育ローンは、各金融機関の申込条件を満たせば申込みが可能です。
使い道は、学校納付金に限られたり、教材代や住居費などにも対応していたりする場合があります。金融機関によって異なりますが、国の教育ローンより高額な借入れが可能です。
また、いつでも申込みができ、金融機関によっては最短即日融資に対応しています。
金利は、国の教育ローンと比べると高い傾向がありますが、使い道が自由なカードローンやフリーローンと比べると低めです。
利用する際は、金融機関所定の審査に通過する必要があります。また、最低年収・最低勤続年数が設けられている場合があるため、申込条件をよく確認しましょう。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度を利用する
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度とは、20歳未満の児童を扶養している母子家庭や父子家庭を対象とした貸付制度です。
高校や大学の教育資金のほか、就職のための資金や医療を受けるために必要な資金、生活資金、結婚資金など、さまざまな資金を借入れできます。
大学の授業料や書籍代などは「修学資金」、就学に必要な被服等は「就学支度資金」が利用できます。大きな特徴は、無利子で借入れできる点です。
| 資金の種類 | 利率 | 限度額 | 返済期間 |
|---|---|---|---|
| 修学資金 | 無利子 | 大学(私立・自宅外通学の場合):月額146,000円(貸付期間は就学期間中) | 20年以内 |
| 就学支度資金 | 無利子 | 国公立大学・短大・大学院等(自宅外通学):420,000円 私立大学・短大等(自宅外通学):590,000円 |
就学:20年以内 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度を利用したい人は、なるべく早めにお住まいの地方公共団体の福祉担当窓口に問い合わせましょう。貸付まで数ヵ月かかる場合もあるため、学費の納入期日が迫っている場面には向いていません。
※制度に関する記載は2024年1月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
大学費用はいくらかかる?
「大学へ通うために、実際どのくらいお金がかかるの?」と気になっている人もいるのではないでしょうか。
国公立・私立大学の在学にかかる費用の目安は、以下のとおりです。

| 区分 | 国公立大学 | 私立大学 |
|---|---|---|
| 入学料 | 282,000円 | 245,951円 |
| 授業料(4年間で算出) | 2,143,200円 | 3,723,772円 |
| 施設設備費(4年間で算出) | - | 720,744円 |
| 合計 | 2,425,200円 | 4,690,467円 |
※文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」、「私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」をもとに作成
国立大学の入学料・授業料は、文部科学省により標準額が示されており、その120%を限度に各大学が決定する仕組みです。
公立大学の多くは、授業料を国立大学の標準額と同水準に設定しています。一方、入学料は入学者や保護者の住所によって差がつくケースもあります。
私立大学の学費は、学部によっても大きく異なりますが、国公立大学と比べて高い傾向があります。上記の目安は4年間で算出していますが、6年制の学部ではさらに高額な学費が必要です。
大学費用がないときに知っておくべき注意点
大学の学費が払えないと、どのような影響があるのでしょうか。大学費用がないときに知っておくべき注意点を解説します。
- 学費が払えないと除籍になる場合がある
- 進路の幅が狭まる可能性がある
- 奨学金や教育ローンを滞納すると信用情報に影響する
学費が払えないと除籍になることもある
納入期日までに学費が払えなかった場合、学生本人や保証人に督促が行なわれます。督促を受けてもなお納入しない場合、除籍(学籍を失うこと)になる場合もあるため注意が必要です。
大学によっては復籍できますが、決められた期限までに学費と復籍手数料を払わなくてはならない場合があります。大学によって対応が異なるので、学則を確認しておきましょう。
進路の幅が狭まる可能性がある
学費を納入期日まで払えず除籍や自主退学となった場合、就職活動に影響を与える場合があります。
最終学歴が「高校卒業」となるため、「大学卒業」が条件となっている企業には応募できません。また、すでに内定をもらっていた場合も、内定取り消しになる可能性があります。
奨学金や教育ローンを滞納すると信用情報に影響する
奨学金や教育ローンを長期間滞納すると、信用情報機関に延滞情報が一定期間登録されます。
信用情報とは、クレジットカードやローンの契約内容や利用状況に関する情報です。クレジットカードやローンに申し込むと、審査で信用情報に問題がないかチェックされます。
延滞情報が登録されていると、クレジットカードやローンの契約が一般的に難しくなります。期日に遅れないよう、計画的に返済しましょう。
大学費用に困らないために事前にできる対策
大学の学費は人生のなかでも大きな支出であり、すぐに用意できるものではありません。大学費用が払えない事態を避けるために準備しておく主な方法を解説します。
- 児童手当を貯蓄する
- 新NISAを利用する
- 学資保険で備えておく
児童手当を貯蓄する
児童手当とは、中学校卒業までの児童を養育している人が受給できる手当です。
3歳未満は月額15,000円、3歳から15歳の誕生日後の最初の3月31日までは月額10,000円を受け取れます(第3子以降は小学校修了前まで月額15,000円)。
誕生月によって異なりますが、受け取れる児童手当の総額は約200万円です。すべて使わずに貯蓄しておけば、学費の一部に充てることができます。
※制度に関する記載は2024年1月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
新NISAを利用する
新NISAとは、2024年1月からはじまった制度で、少額・長期・分散投資をサポートする非課税制度です。
投資で得た分配金や譲渡益には、通常20.315%の税金がかかります。しかし、新NISAでは、年間360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)を上限に一定の投資信託等を購入でき、そこから得た譲渡益や分配金が非課税になります。
ただし、投資信託等は元本の保証がない金融商品です。預貯金とは異なるため、仕組みやリスクを正しく理解しましょう。
※税法上の取扱いについては2024年1月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更の伴い取扱いが変わる場合があります。
学資保険で備えておく
学資保険とは、子どもの教育費に備えるための貯蓄型保険です。子どもの入学や進学にあわせて、教育資金・満期保険金等が受け取れます。
大学入学時・在学中に教育資金を受け取れるものや、大学入学時に満期保険金を受け取れるものなど、保険会社やプランによってさまざまです。
また、保険ならではの保障がある点も学資保険の特徴です。契約者である親などに万一のことがあった場合、保険料の払込みが免除され、以降も予定どおりの教育資金・満期保険金等を受け取れます。
学資保険で備えるなら「明治安田生命つみたて学資」
学資保険で備えたいと考えている人には、「明治安田生命つみたて学資」がおすすめです。
「明治安田生命つみたて学資」は、大学にかかる費用を計画的に準備できる学資保険です。保険料の払込みは最長15歳までに終了し、特に費用がかさむ大学の時期等に計4回、教育資金・満期保険金を受け取れます。
ご契約者様に万一のことがあったときは保険料の払込みが免除され、保障内容はそのまま継続します。
また、お受取金額は家計の状況やお子さまの進路に応じて設定できます。大学の学費を計画的に準備したい人は、ぜひご検討ください。
※明治安田生命つみたて学資をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
大学の学費が期日までに払えなかった場合、督促が行なわれます。督促を受けてもなお払わない場合、除籍となる可能性があります。
学費の支払いが難しいなら、まずは大学に延納や分納ができないかを相談しましょう。また、奨学金制度や教育ローンを利用する方法もあります。
子どもの進路によっても異なりますが、大学は教育費のなかでも特に高額な費用がかかる時期です。学費に困らないためにも、児童手当や学資保険などで早い時期から計画的に準備しましょう。
募Ⅱ2302375ダイマ推