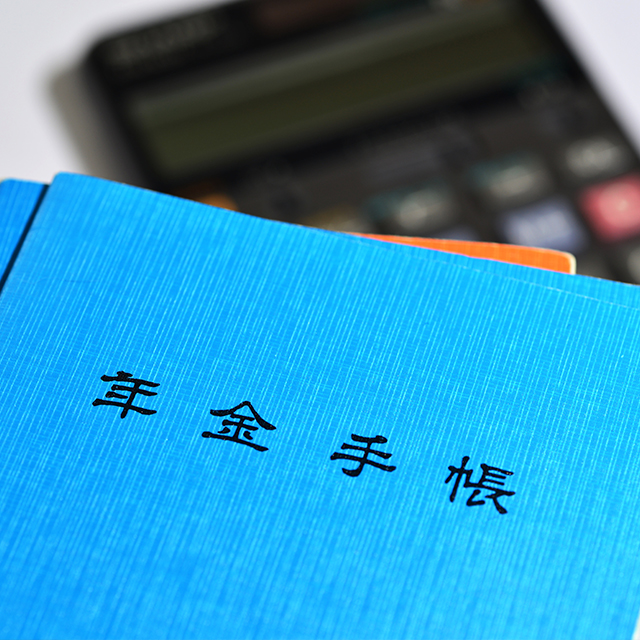児童手当の支給金額は
いくら?受け取り条件や所得
制限、使途などについて詳しく解説
子育てには多くのお金がかかるため、児童手当の金額がいくらなのか気になる人もいるのではないでしょうか。
子どもの年齢や人数に応じて受け取れる児童手当は、家計の支出を助ける存在です。
本記事では、児童手当で受け取れる金額や受け取るための条件、所得制限を解説します。児童手当の申請方法も説明するので、お子さまのいる人はぜひ参考にしてください。
※本記事は、2023年10月現在の内容です。
※児童手当に関する記載は2023年10月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

児童手当で受け取れる金額
児童手当で受け取れる金額は、養育している子どもの年齢によって異なります。以下の表は、受け取れる金額を子どもの年齢別にまとめたものです。
| 子どもの年齢 | 受け取れる金額(1人あたりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
なお、児童手当で受け取れる金額に地域差はなく、どこの自治体でも変わりません。
児童手当を受け取る条件
児童手当を受け取るために必要な条件は以下のとおりです。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日まで)の子どもを養育している
- 子どもが日本国内に在住している
- 養育者の所得が所得上限限度額未満である
子どもが日本国内に住んでいることが条件ですが、留学のために日本国外で住んでいて、一定要件を満たす場合は受け取れます。
両親の居住地は問われませんが、両親が離婚協議中などで別居している場合は、子どもを養育している人が優先的に受け取れます。
また、両親が海外に住んでいる場合、日本国内で子どもを養育している人を指定すれば、指定された人が受け取れます。
死別や何らかの事情により両親が子どもを養育していない場合は、子どもを養育する未成年後見人や里親、入所施設の設置者が児童手当を受け取ります。
なお、未成年後見人とは親権者を亡くした子どもの代理人として、子どもの監護養育や財産管理、契約などを行なう人です。
児童手当の所得制限限度額
子どもを養育する人の所得が一定額を超えると、児童手当の減額や支給対象外になる所得制限があります。児童手当の所得制限には所得制限限度額と所得上限限度額があり、各限度額は扶養親族の人数で変化します。
なお、児童手当の受給者が施設の設置者や里親の場合は、所得制限が適用されません。
各限度額は以下のとおりです。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (収入の目安) |
所得上限限度額 (収入の目安) |
|---|---|---|
| 0人 (前年末に子どもが産まれていない場合 等) |
622万円(833.3万円) | 858万円(1,071万円) |
| 1人 (子ども1人の場合 等) |
660万円(875.6万円) | 896万円(1,124万円) |
| 2人 (子ども1人と年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円(917.8万円) | 934万円(1,162万円) |
| 3人 (子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円(960万円) | 972万円(1,200万円) |
| 4人 (子ども3人と年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円(1,002万円) | 1,010万円(1,238万円) |
| 5人 (子ども4人と年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812万円(1,040万円) | 1,048万円(1,276万円) |
子どもを養育する人の所得が所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合、特例により子ども1人当たり月額一律5,000円の児童手当を受け取れます。
所得上限限度額以上の場合は、児童手当を受け取れません。法改正により2022年10月支給分から(6~9月)特例の対象から外れました。
児童手当における所得額の計算方法
児童手当での所得額は以下の方法で計算します。
児童手当での所得額=所得額の合計-控除額の合計-8万円
所得額は以下の所得を合計して算出します。
- 総所得(給与所得や事業所得、利子所得などの合計額)
- 退職所得(総合課税)
- 山林所得
- 土地等にかかる事業所得等
- 長期譲渡所得
- 短期譲渡所得
- 先物取引にかかる雑所得
- 条例適用利子等
- 条例適用配当等
控除額は以下の控除額を合計して算出します。
- 雑損控除額
- 医療費控除額
- 小規模企業共済等掛金控除額
- 障害者控除27万円(特別40万円)
- ひとり親控除35万円
- 寡婦控除27万円
- 勤労学生控除27万円
算出した金額から児童手当での所得額を求め、所得制限限度額や所得上限限度額を下回るか確認しましょう。
受給者の所得額が所得制限限度額を超える場合
受給者の所得自体は増えていなくても、所得制限や所得上限の限度額以上になるケースも存在します。例えば、以下のようなケースです。
- 控除できる金額が減った
- 配偶者の年収が103万円を超えた
- 独立や死別などで扶養親族が減った
所得から差し引く控除額が少なくなれば所得額は多くなり、結果的に限度額以上となる場合もあります。
また、限度額は扶養親族等の数でも変化します。扶養親族等に含まれる人数が減れば、所得が増えていなくても限度額以上になる場合があるでしょう。
年収103万円を超える配偶者は配偶者控除の対象にならないため、扶養親族等に含みません。子どもが独立し、同一生計でなくなった場合も扶養親族からは外れます。扶養していた親や兄弟などの親族が独立した場合も同様です。
なお、所得が所得上限限度額以上になり、児童手当を受け取れなくなっても再度下回れば受給できます。再び受給できる状態になった場合は、あらためて認定請求書の提出が必要です。
所得制限の撤廃も検討されている
2023年時点で、児童手当の所得制限は撤廃が検討されています。現在、所得制限のために児童手当を受け取れていない、あるいは所得制限にかかりそうな人は注目すべき事柄です。
ほかにも対象となる子どもを高校生まで拡大し、第3子以降の支給額を増額することなどが、少子化対策の強化案として検討事項に挙がっています。
児童手当の申請方法
児童手当の申請は住んでいる市区町村へ、認定請求書を提出して行ないます。
里帰り出産により子どもを産んだ地域で出生届を出すと、児童手当の認定に別途手続きが必要です。申請に時間や手間がかかる可能性もあるため、出生届の提出は基本的に居住する市区町村で行ないましょう。
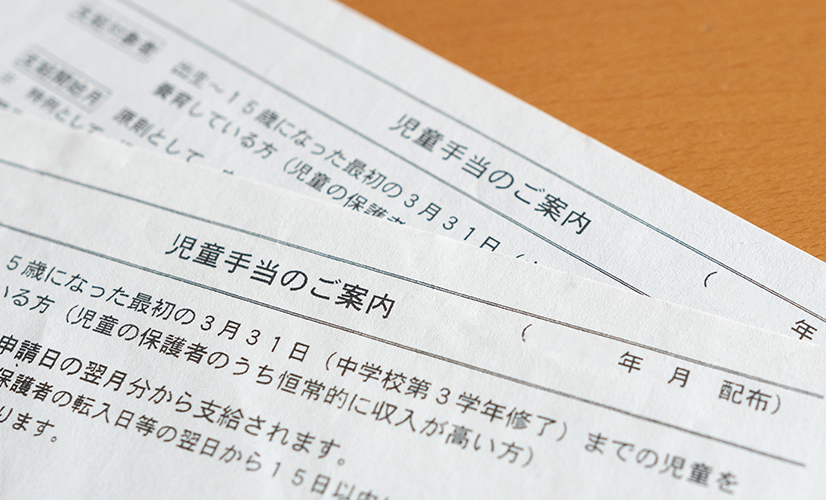
例外として、受給者が公務員の場合は、居住地ではなく勤務先で申請を行なうので注意が必要です。
なお、児童手当を継続して毎年受け取るために必要だった「現況届」の提出は、2022年度より原則不要になりました。ただし、市区町村から提出を求められた場合は、現況届の提出が必要です。
認定請求書や現況届は窓口で提出するほかに、郵送や電子申請も可能です。
郵送の場合は住んでいる市区町村の該当窓口へ、認定請求書と添付書類を送付します。請求日は消印ではなく、書類到着日となるので注意しましょう。
電子申請の場合は、マイナポータルからマイナンバーカードを使って行ないます。パソコン端末とICカードリーダライタ、または電子申請に対応したスマートフォン端末が必要です。
はじめて児童手当の申請をする場合
はじめて児童手当の申請をする場合、住んでいる市区町村へ児童手当の認定請求書を提出します。申請が遅れると、児童手当を受け取れない月が発生する場合もあるため、出生日の翌日から15日以内に行ないましょう。
申請の際は認定請求書のほかに、以下の書類が必要です。
- 窓口で手続きする人の本人確認書類
- 申請者名義の金融機関の通帳など
- 申請者と配偶者のマイナンバーが確認できる資料
- 申請者の健康保険証の写し(被扶養者や公務員の場合)
子どもが産まれたときに提出する出生届を、住んでいる市区町村ではないところで提出すると、児童手当の申請がスムーズに進みません。出生届は児童手当の申請と同じ、住んでいる市区町村へ提出しましょう。
継続して児童手当を受け取る場合
継続して児童手当を受け取る場合、以前は毎年6月に現況届の提出が必要でした。
2022年度より原則不要となりましたが、市区町村の判断で提出を求められる場合があります。
現況届の提出を求められた人は、以下の添付書類とともに市区町村へ提出しましょう。
- 健康保険証の写し(請求者が会社員などの場合)
- 前住所地の市区町村長が発行する前年分の児童手当用所得証明書(その年の1月1日に現住所で住民登録がなかった場合)
現況届の提出が必要な場合、6月30日までに提出しないと児童手当の受け取りが遅くなる場合があるので注意しましょう。
申請後に転居したら児童手当の申請はどうする?
児童手当を申請したあとに転居した場合は、転居先の市区町村で手続きが必要です。
転出日の翌日から15日以内に、転居先の市区町村であらためて児童手当を申請します。申請時に必要な書類は、はじめて申請する場合と同じです。
受け取った児童手当の使途は?
多くの場合、児童手当は子どもの教育費や生活費に使用されています。また、子どもだけのために使うとは限定せず、家庭の日常生活費に使うケースも少なくありません。
なお、子どもの将来のための貯蓄や保険料の払込みに利用する場合も多く、子どもの将来への備えとしても活用されていることが分かります。
「明治安田生命つみたて学資」は教育費の準備におすすめ
「明治安田生命つみたて学資」は、子どもの成長にあわせて教育資金を受け取れる学資保険です。
受取率(※1)は保険料を一括払いした場合で最大129.2%(ご契約の一例(※2))と充実しており、進学時に必要な教育資金を着実に準備できます。
保険料の払込みは10歳まで(※3)・15歳まで・一括払いが選べ、最長でも教育費がかさみやすい高校進学までに終了します。
また、ご契約者様に万一のことがあった場合、保険料の払込みは免除されて保障は継続します。
※1 受取率とは、払込保険料の累計額に対する満期までの受取総額の割合をいいます。また、受取率はご契約内容によって異なります。
※2 保険契約の型:I型/ご契約者:25歳 男性/被保険者(お子さま):0歳/21歳満期/基準保険金額:70万円/一括払込(10歳払込満了(新年掛))/保険料率:2025年11月1日現在※3 ご契約時のお子さまの年齢が2歳以下の場合、保険料払込期間を10歳とすることもできます。
※明治安田生命つみたて学資をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
児童手当の金額は、子どもの年齢で決まります。3歳未満は月額一律15,000円、3歳以上は月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)、中学生は月額一律10,000円です。
ただし、所得制限があるため、養育者の所得が一定額を超えると受け取れる金額が変化します。
所得が所得制限限度額以上だと特例給付で子ども1人につき月額一律5,000円となり、所得上限限度額以上だと受け取れません。
15歳未満の子どもを養育し、その子どもが日本国内に在住していて、養育者の所得が所得上限限度額未満であることが、児童手当を受け取るための条件です。
募Ⅱ2500978ダイマ推