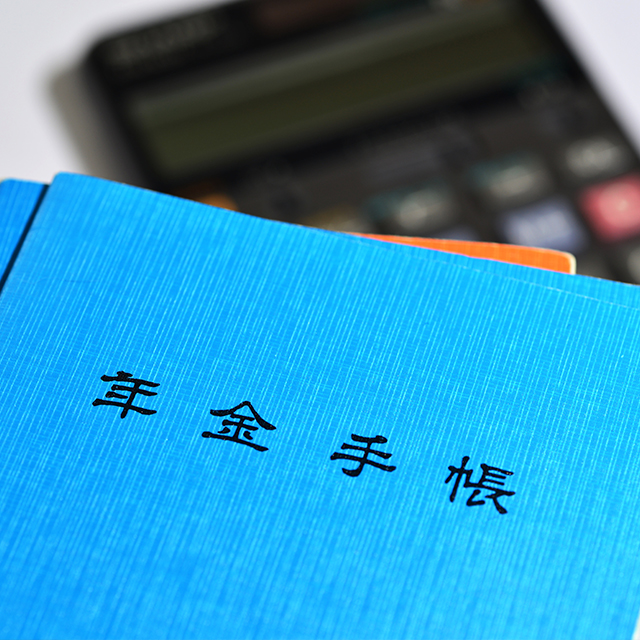高校授業料無償化とは?
高等学校等就学支援金制度の仕組みや申請方法、注意点を解説
高校授業料無償化がはじまり、高校へ通う子どもがいる家庭の助けとなっています。
私立高校への支援も拡充され、私立高校へ通っている場合も授業料の負担が実質無料となるケースがあります。
本記事では、高校授業料無償化の概要や所得要件、申請方法を解説します。制度を受ける際の注意点も取り上げるため、高校へ通う子どもがいる人は、ぜひ参考にしてください。
※本記事は、2023年11月現在の内容です。

高校授業料無償化(高等学校等就学支援金制度)とは?
高校授業料無償化の正式名称は「高等学校等就学支援金制度」です。
所得などの要件を満たして認定を受けると、高等学校等就学支援金が支給され、授業料の負担を軽減できます。
対象者は日本国内に在住し、高等学校に在学する人です。
国公立高校では、授業料相当額が支給され、授業料の負担は実質無償です。
私立高校では、保護者等の所得に応じて支給額が変わります。支給額と実際にかかる授業料の差額は、各家庭で負担します。
※制度に関する記載は2023年11月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
高校授業料無償化の所得要件
高等学校等就学支援金制度には所得要件があり、保護者等の所得が一定以上の場合は受給対象外となります。
具体的には、以下の計算式から算出した金額が30万4,200円未満の世帯の生徒が受給対象となります。
保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%−市町村民税の調整控除額
課税所得とは、給与等の収入から所得控除を差し引いた金額を指します。世帯年収にすると約910万円未満が受給対象の目安です。
高校授業料無償化の支給上限額
高等学校等就学支援金の支給上限額は、国公立高校と私立高校で異なります。私立高校に関しては、世帯収入によって支給上限額が異なります。
以下では、国公立高校と私立高校に分けて、高等学校等就学支援金の支給上限額を解説します。
国公立高校の支給額
国公立高校の支給限度額は、全日制・定時制・通信制によって異なります。
| 月額 | |
|---|---|
| 公立高校・国立高校全日制 | 9,900円 |
| 公立高校定時制 | 2,700円 |
| 公立高校通信制 | 520円 |
※国立高校の定時制・通信制は存在しない
出典:文部科学省「支給期間・支給限度額一覧(令和2年4月以降)」
なお、単位制の場合は、学校の種類によって支給額が異なります。
私立高校の支給額
以下の計算式で算出された金額が、15万4,500円以下の場合は最大39万6,000円、15万4,500円以上30万4,200円以下の場合は11万8,800円が支給されます。
保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%−市町村民税の調整控除額
世帯年収の目安は以下のとおりです。
<両親共働きの場合>
| 子の人数 | 11万8,800円(月額9,900円)の支給 | 39万6,000円(月額3万3,000円)の支給 |
|---|---|---|
| 子ふたり(高校生・中学生以下) | 〜約1,030万円 | 〜約660万円 |
| 子ふたり(高校生・高校生) | 〜約1,070万円 | 〜約720万円 |
| 子ふたり(大学生・高校生) | 〜約1,090万円 | 〜約740万円 |
<両親のうち一方が働いている場合>
| 子の人数 | 11万8,800円(月額9,900円)の支給 | 39万6,000円(月額3万3,000円)の支給 |
|---|---|---|
| 子ふたり(高校生・高校生) | 〜約950万円 | 〜約640万円 |
| 子ふたり(大学生・高校生) | 〜約960万円 | 〜約650万円 |
※支給額は、私立高校(全日制)の場合。
※子について、中学生以下は15歳以下、高校生は16~18歳、大学生は19~22歳の場合。
※給与所得以外の収入はないものとし、両親共働きの場合、両親の収入は同額として計算した場合。
ただし、年収はあくまでも目安です。各種控除を差し引いた結果次第では、紹介した年収以内でも支給対象にならない、または年収を超えていても支給対象になるケースもあるので注意しましょう。
高校授業料無償化の申請方法
高等学校等就学支援金制度は、所得要件を満たしていても、申請しなければ支給されません。申請は原則オンラインであり、新入生と在学生では手続きの時期や内容が異なります。
以下、新入生と在学生に分けて、申請方法を解説します。
新入生の場合
新入生の場合、申請に必要なID・パスワードが4月ごろに学校から配布され、案内が届きます。案内に従って専用のオンライン申請システムから、申請を進めましょう。
オンライン申請システムで配布されたID・パスワードを使ってログインすると、支給希望の意向確認があります。
意向確認後、生徒情報の内容を確認し、保護者の氏名や生年月日、収入状況を登録します。収入状況は原則、親権者全員分の登録が必要です。
マイナンバーカードを持っている場合、審査に必要な課税情報などはマイナンバーカードの読み取りで取得できます。マイナンバー情報を、学校などへ提出する必要はありません。
マイナンバーカードを持っていない場合は、都道府県で課税情報などを確認するため、個人番号を入力します。
登録内容から都道府県で審査後、結果が通知され、対象世帯は申請月から支給がはじまります。
在学生の場合
在学生の場合、毎年7月ごろに世帯の所得情報が更新され、学校から案内が届きます。新入生の場合と同様、案内に従って収入状況を届け出ましょう。
入学時に配布されたID・パスワードを使ってオンライン申請システムにログインし、支給継続の意向を登録します。
登録済みの生徒や保護者の情報を確認し、保護者に変更がある場合は内容を登録します。
マイナンバーカードを持っている場合、課税情報などはマイナンバーカードの読み取りで取得できます。
マイナンバーカードを持っていない場合は、都道府県で課税情報などを確認するため、個人番号を入力します。ただし、過去に提出済みの場合は、再提出は不要です。
なお、申請を忘れると7月以降に支援金が支給されません。忘れずに申請しましょう。また、過去にマイナンバーを提出していると、一部手続きを省略できる場合があります。
登録内容から都道府県で審査後、結果が通知され、対象世帯へ申請月から支給がはじまります。
高校授業料の支援金を受ける際の注意点
高校授業料の支援金を受ける場合、以下の3点に注意しましょう。
- 制度対象は公立・私立高校の授業料のみ
- 所得制限の要件を満たしていても申請が必要
- 支援金は学校の設置者が受け取る
以下で詳しく解説します。

制度対象は公立・私立高校の授業料のみ
高等学校等就学支援金制度で支給される支援金は、月々の授業料以外で必要な教科書代や教材費などには使えません。
授業料以外の教育費は、高校生等奨学給付金などで支援しています。また、都道府県ごとに独自の支援制度を設けている場合もあるため、必要に応じて居住地の自治体に確認しましょう。
所得制限の要件を満たしていても申請が必要
所得要件を満たす家庭であっても、入学時の申請や毎年の届け出を忘れていると、支援を受けられません。
高等学校等就学支援金制度は、自動的に支給される制度ではないため注意しましょう。
また、収入に関して虚偽の申請をすると、刑罰を受ける場合があります。申請時の収入状況は正しく登録しましょう。
支援金は学校の設置者が受け取る
高等学校等就学支援金制度の支援金は、高校へ通う生徒自身や生徒の保護者ではなく、都道府県や学校法人など学校の設置者が受け取ります。
支援金を受け取ってから、学校へ授業料を支払う手続きは発生しません。私立高校で授業料に差額がある場合は、差額分のみを支払います。
「明治安田生命つみたて学資」は大学の費用に備えられます
「明治安田生命つみたて学資」は、子どもの教育資金を計画的に準備できます。
保険料の払込みは一括払いのほか、子どもが10歳まで・15歳までを選択でき、早めの払込みも可能です。子どもが大学等へ進学するタイミングにあわせて、まとまったお金を受け取れます。
受取率(※1)は保険料を一括払いした場合で最高129.2%(ご契約の一例(※2))となっており、契約者に万一のことがあった際は、保険料の払込みが免除されて保障が継続します。
子どもの将来に必要な教育資金へ着実に備えられる学資保険です。
※明治安田生命つみたて学資をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
※1 受取率とは、払込保険料の累計額に対する満期までの受取総額の割合をいいます。また、受取率はご契約内容によって異なります。※2 保険契約の型:I型/ご契約者:25歳 男性/被保険者(お子さま):0歳/21歳満期/基準保険金額:70万円/一括払込(10歳払込満了(新年掛))/保険料率:2025年11月1日現在
まとめ
高校授業料無償化の正式名称は「高等学校等就学支援金制度」といい、国公立高校の授業料の負担を実質無償化できる制度です。
支給には所得要件がありますが、要件を満たす世帯は案内に従って申請すると、授業料相当額を学校側が受取ります。家庭で負担する授業料が、国公立高校の場合で実質0円となり、高校へ通う子どもがいる家庭にとって大きな助けとなるでしょう。
なお、私立高校へ通う場合は所得に応じて支給額が変化し、差額分の授業料は各家庭が負担します。
家庭の負担を軽減するため、高校へ通う子どもがいる場合は、忘れずに申請しましょう。
募Ⅱ2500980ダイマ推