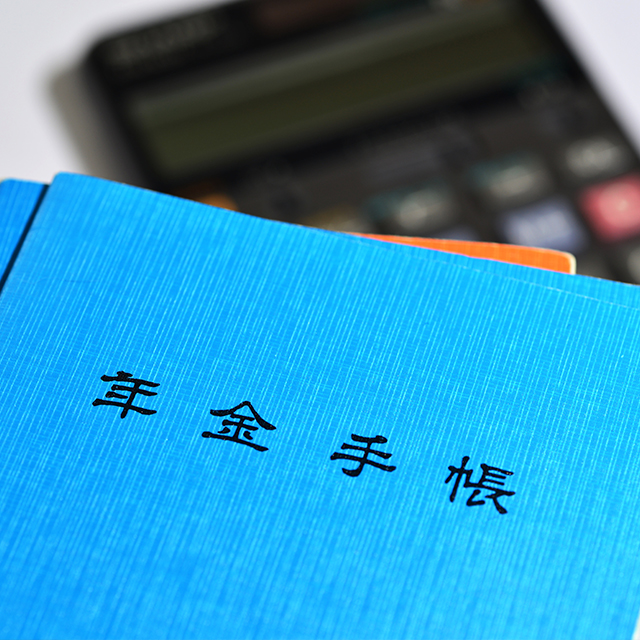満期保険金とは?
受け取れる保険の種類や
税金について解説
満期保険金は、保険期間が満了を迎えたときに保険会社から受け取れる保険金です。
主に養老保険や学資保険など、保険期間が定められている貯蓄型保険で満期保険金が受け取れます。
この記事では、満期保険金の特徴や解約時に受け取れる解約返戻金との違いなどを解説します。満期保険金を受け取った際にかかる税金も説明するので、参考にしてください。

満期保険金は保険期間が満了したときに
受け取れる保険金
満期保険金は、保険期間が満了した際に受け取れる保険金です。保険商品により満期保険金が受け取れるものと受け取れないものがあります。
基本的に、満期保険金を受け取れるのは、保険期間が定められている貯蓄性のある保険です。掛け捨て型の保険や保険期間の定めがない終身保険には満期保険金がありません。
保険の「満期」の定義
保険の「満期」の定義は、契約時に定めた保険期間が満了を迎えることです。ただし、掛け捨て型保険と貯蓄型保険では「満期」の際に行なわれることが異なります。満期保険金を理解するためにも、掛け捨て型保険と貯蓄型保険の満期時はどのように異なるのか確認しましょう。
掛け捨て型保険の満期時は、保険契約を更新するか検討することが必要です。主に、保障の期間が終了することを意味し、満了後も保障を継続する場合、更新が必要となります。満期を迎えても満期保険金は受け取れず、更新する際の年齢や保険料率で計算されるため、同じ保障内容で更新する場合、保険料が上がるのが一般的です。
一方で、養老保険や学資保険のような貯蓄型保険の「満期」も保険期間が満了することは同じですが、貯蓄型保険の満期時には、満期保険金を受け取ることができます。
解約返戻金との違い
保険で受け取れるお金には、「満期保険金」のほかに「解約返戻金」もあります。違いがわからない方もいるのではないでしょうか。満期保険金と解約返戻金の違いを説明します。
- 解約返戻金:保険を途中で解約した際に払い戻されるお金
- 満期保険金:保険が満期を迎えた際に受け取れるお金
解約返戻金は、保険を途中解約した際に払い戻されるお金をさします。払い込んだ保険料の一部が積み立てられ、解約した際にその一部が返ってくる仕組みです。
保険料の全額が積み立てられるわけではなく、一部は保険金などの支払いや、契約の締結、維持に必要な経費などに充てられます。そのため、解約返戻金の金額は払い込んだ保険料よりも少なくなるのが一般的です。
一方、満期を迎えた際に受け取れる満期保険金は、払い込んだ保険料より多い金額を受け取れる場合もあります。
満期保険金と解約返戻金は、どちらも貯蓄性のある保険などで受け取れます。ただし、保険期間の定めのない保険では、満期保険金は受け取れません。
そのため、終身保険のように満期のない保険の場合、解約返戻金は受け取れる保険商品もありますが、満期保険金はありません。
満期保険金が受け取れる保険は?
先に述べたとおり、満期保険金が受け取れるのは保険期間の定めのある貯蓄型保険です。満期保険金が受け取れる主な保険を以下で紹介します。
- 養老保険
- 学資保険
- 生存給付金付定期保険
それぞれ特徴をみていきましょう。
養老保険
養老保険は、万一のときにも満期時にも保険金が受け取れる保険です。被保険者が亡くなった場合に死亡保険金、満期時に生存している場合に満期保険金が受け取れます。なお、死亡保険金と満期保険金は同額です。
死亡時の保障に加えて、満期時の楽しみもあるのが養老保険の特徴です。老後資金や教育資金などの貯蓄をしたい方で、万一にも備えたい方に適しています。ただし、死亡保障のみの定期保険と比べて、一般的に同じ保障内容であれば、保険料は高めに設定されています。
学資保険
学資保険は、子どもの教育費に備えるための保険です。原則として親が契約者、子どもが被保険者として契約し、子どもの入学や進学のタイミングにあわせて、教育資金や満期保険金が受け取れます。
学資保険の特徴は、保険料の払込み免除があることです。契約者である親に万一のことがあった場合、その後の保険料を払い込む必要がなく、教育資金や満期保険金は予定どおり受け取ることができます。
例えば、教育資金を銀行預金で貯めていた場合、親に万一のことがあっても、それ以上積み立てることはできませんが、学資保険なら保険料の払込みが免除され、保障内容はそのまま継続されるため安心です。
生存給付金付定期保険
生存給付金付定期保険とは、死亡すると死亡保険金が支払われる定期保険に、一定期間ごとに生存していれば受け取れる生存給付金が付いた保険です。
生存給付金があるため、掛け捨て型の定期保険と比べて、一般的に同じ保障内容であれば、保険料は高く設定されています。一定期間ごとに生存給付金、満期を迎えると満期生存給付金が支払われます。生存給付金を受け取れるタイミングは保険商品により異なりますが、2年ごとや3年ごとに受け取れるものが多いです。また、保険商品によっては、生存給付金を受け取らずに据え置けば、所定の利率で計算された利息がつきます。
満期保険金には税金がかかる
満期保険金を受け取ると、税金がかかる点も知っておきましょう。かかる税金の種類は、保険料を負担する人と受取人が誰であるかにより異なります。
以下2つのケースにわけて解説します。
- 所得税と住民税が発生するケース
- 贈与税が発生するケース
※解約返戻金を受け取る場合も、税金がかかることがあります。
※税金制度に関する記載は2022年11月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

所得税と住民税が発生するケース
保険料の負担者と保険金受取人が同一人物の場合は、所得税・住民税がかかります。かかる税金の計算方法は、満期保険金の受取方法で異なります。
一般的に、満期保険金を一時金として受け取った場合、所得の種類は「一時所得」、年金形式で受け取った場合は「雑所得」です。
一般的に満期保険金を一時金で受け取った場合、以下の計算式で一時所得を算出します。
一時所得の金額=満期保険金―払い込んだ保険料―特別控除(最高50万円)
一時所得の金額をさらに1/2にした金額が、所得税・住民税の課税の対象です。計算式からわかるとおり、最高50万円の特別控除があるため、満期保険金から払い込んだ保険料を差し引いた金額が50万円以下の場合は税金がかかりません。
なお、同じ年に他の一時所得が発生している場合は合算して計算する必要があります。
5年以内に満期になる一時払養老保険や、5年を超える場合でも契約から5年以内に解約した養老保険など「金融類似商品」にあたる場合は、20.315%の源泉分離課税となります。
ただし、払い込んだ保険料よりも受け取る満期保険金額が下回る場合は、非課税となります。
贈与税が発生するケース
一方、保険料の負担者と保険金受取人が異なる場合は、贈与税の対象です。
満期保険金から基礎控除額を差し引いた金額に対して、贈与税が課税されます。基礎控除額が110万円あるため、受け取った満期保険金が110万円以下の場合は非課税です。
ただし、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計から110万円を差し引いた金額に対して課税されます。そのため、同じ年に受けた贈与財産が満期保険金のほかにもある場合は、合計して計算しなければなりません。ほかの贈与財産と満期保険金が合計で110万円を超えていれば税金がかかるため、注意してください。
満期前に解約すると
どうなる?
満期前に保険を解約すると、満期保険金は受け取れません。また、満期前に解約した場合、以下の点にも注意が必要です。
- 払い込んだ保険料を下回る可能性が高い
- 保障がなくなる
以下で詳しく解説します。
払い込んだ保険料を下回る可能性が高い
満期前に解約すると、保険商品によっては解約返戻金が受け取れます。しかし、解約返戻金は払い込んだ保険料の一部が払い戻される仕組みであるため、多くの場合払い込んだ保険料を下回ります。
特に、保険を契約後短期間で解約した場合、解約返戻金がまったくない、あってもごくわずかな金額になるため、注意してください。
保障がなくなる
保険を途中で解約すると、保障がなくなります。保障が必要であれば新たに保険へのお申込みが必要ですが、その時点の年齢などで保険料が決まるため、同じ保障内容の場合、保険料は高くなるのが一般的です。健康状態などによっては、保険にお申込みできない可能性もあります。
途中解約をなるべく避けるためにも、無理なく払い続けられる保険料に設定することが大切です。
明治安田生命じぶんの積立は
満期保険金がある積立保険
明治安田生命じぶんの積立は、幅広い資金に備えられる積立保険です。月々5,000円から積み立てでき、保険料のお払込みも5年間で終了するため、気軽に始められます。
さらに、10年間の保険期間を満了すると満期保険金が受け取れます。
まとめ
満期保険金とは、保険が満了した際に受け取れるお金のことです。養老保険や学資保険などの貯蓄性のある保険で満期保険金が受け取れます。
明治安田生命じぶんの積立なら、月々5,000円から積み立てでき、満期時に保険金をお受け取りいただけます。
いつ解約しても100%以上の受取率のため、安心して積み立てられます。ぜひ一度ご検討ください。
※保険商品をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
募Ⅱ2401917ダイマ推