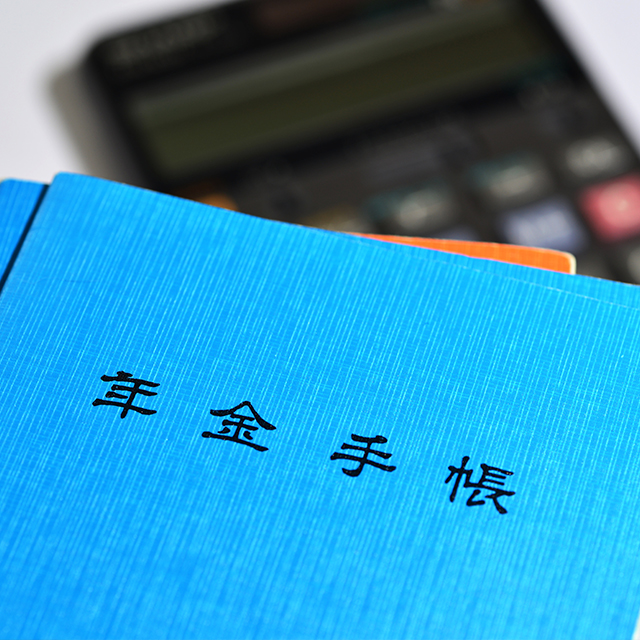中学校の学費はいくら?
公立と私立の違いやかかる費用の内訳、支援制度など紹介
小学校から中学校へ進学すると、これまでかからなかった支出が発生し、一般的に学費の負担が増えます。
入学金や授業料など学校教育にかかる費用以外にも、クラブ活動費や塾の費用など学校外の費用も増えます。中学校の学費の目安を知っておくと、計画的に教育資金を準備できるでしょう。
そこで、中学校でかかる学費を、公立と私立との違い、費用の内訳などを紹介します。さらに、学費の負担軽減になる支援制度や、学費を着実に準備する方法をあわせてお伝えします。
※本記事は、2024年3月現在の内容です。

中学校3年間の学費はいくら?内訳は?
文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」によると、中学校で必要な1年あたりの学費は公立で平均538,799円、私立で平均1,436,353円です(※)。
私立中学校は公立中学校の約2.7倍で、公立・私立間で学費に大きな差がみられます。特に入学金を含めた初年度の学費は、公立中学校が平均約53万円なのに対し、私立中学校は平均約181万円と高額です。
中学校の学費は「①学校教育費」、「②学校給食費」、「③学校外活動費」に分けて調査されています。そこで、公立中学校と私立中学校の違いに注目しながら学費の内訳と金額を詳しく紹介しましょう。
(※)出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
①学校教育費
学校教育費とは、学校で実施される教育に関連した費用です。具体的には、以下の費用が挙げられます。
- 授業料
- 教科書代
- 遠足・修学旅行費
- 教科外活動費
- 制服・通学用品費
- 通学費
- PTA会費 など
1年でかかる学校教育費は、公立で平均132,349円、私立で平均1,061,350円となっており、私立中学校は公立中学校の約8倍かかります(※)。
(※)出典:文部科学省「令和3年度全国学力・学習状況調査」
中学校で必要な学費のうち、学校教育費が占める割合は公立24.6%、私立73.9%です。授業料や教科書代が無料の公立中学校に比べると、私立中学校は学校教育費の割合が約3倍になります。
また、学校教育費に含まれる「教科外活動費」のほとんどはクラブ活動費で、年間平均30,000円ほどとされています。
②学校給食費
年間の学校給食費は公立で平均37,670円、私立で平均7,227円です(※)。
国公立・私立をあわせた全中学校での給食実施率は2021年時点で91.5%と、年々上昇を続けています。しかし、国からの補助を受けられない私立の給食実施率は11.6%です。
給食がない学校も多いため、カフェテリアの利用やお弁当持参などで、学校給食費には含まれないランチ代の負担が増す可能性があります。
(※)出典:文部科学省「令和3年度全国学力・学習状況調査」
③学校外活動費
学校外活動費は中学生が学校以外の活動で支出する費用です。学習塾へ通う費用や習い事の費用、パソコンや学習机など家庭学習のために支出する費用などが含まれます。
1年あたりの学校外活動費は、公立で平均368,780円、私立で平均367,776円です。
ただし、学年別にみると、公立中学校は1年生と3年生とで約30万円から約50万円へ増加する一方、私立中学校は学年ごとの変化はあまりみられません(※)。
公立中学校では、学年が上がるにつれて、高校受験に向けた学習塾や家庭教師などの利用が増えるため費用がかさむと考えられます。
私立中学校は中高一貫教育を取り入れている学校もあり、高校受験の必要がない環境が影響していると考えられます。
(※)出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
中学校の学費を支援する制度
公立・私立にかかわらず、中学校の学費は一般的に小学校よりも高額のため、学費の支払いを負担に感じる家庭も多いでしょう。そんなときには、国や自治体による支援制度を活用して学費の負担を抑える方法があります。
ここでは「就学援助制度」を中心に、中学校の学費を支援する制度を紹介します。
※制度に関する記載は2024年3月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
就学援助制度
就学援助制度とは、経済的に困窮している家庭に対して、学校生活に必要な諸費用の一部を国が支援する制度です。
就学援助費とも呼ばれ、受給要件は世帯の人数や所得に応じて決まります。例えば、9歳の子どもひとりと両親の場合、世帯あたりの所得は約315万円以下が目安です。
援助対象は、授業料や給食代、PTA会費、クラブ活動費など、学校教育費と学校給食費に該当する費用です。
就学援助制度の申請は毎年4~5月ごろで、学校または教務課や学務課など自治体の担当部署へ必要書類を提出します。
申込方法や申込時期を含め、制度の取扱いは自治体ごとに異なるため、詳しくはお住まいの自治体に問い合わせて確認しましょう。
就学援助制度は国公立の小・中学校の学費を支援するもので、2024年3月時点、私立中学校の学費には国による同等の支援はありません。
しかし、国によって支援制度の実証事業が進められており、今後は私立中学校の学費に対する支援が進むと期待されています。
地方自治体や民間団体による補助金制度
就学援助制度は国公立の小・中学校のみが対象ですが、地方自治体や民間団体では私立中学校の学費を支援する制度を設けているケースもあります。
- 神奈川県「私立学校生徒学費緊急支援補助金」
- 埼玉県「父母負担軽減事業補助金」
- 大阪府「大阪府私立高等学校等授業料減免制度」
- 東京都私学財団「私立中学校等授業料軽減助成金事業」
上記は一例ですが、いずれも私立中学校や中等教育学校(前期課程、いわゆる中高一貫校の中等部)を対象に含めた支援制度です。主に授業料の支援を目的としており、受給要件は制度により異なります。
利用できる支援制度がないか、詳しくはお住まいの自治体に確認してみましょう。
中学校の学費を準備する方法
子どものいる家庭では家計に占める学費の割合が大きく、小学校、中学校と進学するにつれて一般的に学費の負担は増えます。
また、中学校以降の進路によってはさらに学費がかさむ可能性は高く、早くからの備えが重要です。そこで、中学校をはじめとした、子どもの学費を準備する方法を紹介します。

学資保険や定期預金を活用する
中学校をはじめとした子どもの学費準備は、学資保険や定期預金がおすすめです。以下で主な特徴を紹介します。
| 方法 | 主な特徴 |
|---|---|
| 学資保険 |
|
| 定期預金 |
|
特に学資保険は、契約者の万一に備えつつ、払い込んだ保険料を上回る保険金を受け取れる商品もあり、安心して着実に学費の準備ができます。
学資保険の保険料は自動引落しやカード払いに、定期預金は自動引落しにしておくと、預貯金が苦手な人も学費を貯めやすいでしょう。
NISA(少額投資非課税制度)の併用を検討する
中学校から先の学費も見据えてまとまった資金を用意したいなら、株式や投資信託で資産運用をはじめる方法があります。
NISA(少額投資非課税制度)を活用すれば、配当金や売却益などの利益にかかる税金が非課税となるため、効率的に学費を用意できる可能性があります。
ただし、資産運用には元本保証がないため、仕組みやリスクを正しく理解し、学資保険や定期預金など安全性の高い方法との併用がおすすめです。
高校や大学進学に向けたお金の準備も必要
中学校の3年間はあっという間です。高校受験を想定したお金の準備も早めにはじめましょう。
高校受験にあたり必要となる検定料(受験料)と初年度納付金の平均額は次のとおりです。
| 検定料(受験料) | 入学金 | 授業料 | 施設設備費等 | |
|---|---|---|---|---|
| 公立高校 | 2,200円 | 5,650円 | 118,800円 | − |
| 私立高校 | 15,000~30,000円 | 164,196円 | 445,174円 | 149,510円 |
参考:文部科学省「令和4年度私立高等学校等初年度授業料等の調査結果について」
参考:東京都「都立高等学校、中等教育学校(後期課程)の授業料・入学料及び特別支援学校高等部の授業料について」
公立高校と私立高校を併願する場合、公立高校の合格発表までに私立高校の入学金を支払う必要があることが多く、ゆとりをもった準備が大切です。
高校卒業後に大学へ進学する場合には、さらに学費がかかります。大学の学費は国公立・私立による差が大きいため、子どもがどんな進路を選んでも問題ないように余裕をもって備えておきましょう。
大学の学費を学資保険で準備するなら「明治安田生命つみたて学資」がおすすめ
「明治安田生命つみたて学資」は、お子さまの大学進学等にあわせて、教育資金3回と満期保険金1回、計4回にわたってお金を受け取れる学資保険です。最大129.2%(※1)の受取率(※2)を実現できます。
また、保険料の支払いは、一括払いと月払いが選べるため、月払いを選択すれば保険料をコツコツ積み立てるうちに学費を準備できます。
中学校や高校の学費は家計から、特に高額になりやすい大学進学の学費は学資保険から、と効率よく教育資金を準備できます。
また、保護者であるご契約者に万一のことがあれば、保障はそのままで保険料の払込みが免除されます。保険ならではの保障と将来の学費の準備を両立したいなら、「明治安田生命つみたて学資」をご検討ください。
※1 保険契約の型:Ⅰ型/ご契約者:25歳 男性/被保険者(お子さま):0歳/21歳満期/基準保険金額: 70万円/一括払込は10歳払込満了(新年掛)/保険料率:2025年11月1日現在
※2 受取率とは、払込保険料の累計額に対する満期までの受取総額の割合をいいます。また、受取率はご契約内容によって異なります。
まとめ
中学校の学費は公立より私立が高い傾向です。しかし、学年が上がるにつれて公立中学校の学習塾代が私立を上回る、給食の提供がない私立中学校ではランチ代がかさむなど、公立と私立でお金のかけどころが異なる特徴もあります。
公立・私立のいずれにせよ、一般的に小学校よりも学費が高くなって家計の負担は大きくなります。しかし、中学校は高校や大学への通過点と考えて、できるだけ家計から学費を捻出しましょう。
また、家計が苦しいと感じたら、就学支援制度など学費の負担を抑えられる制度もあります。
中学校の学費を含む子どもの教育費にはまとまったお金が必要なため、できるだけ早くからコツコツと備えておくことが大切です。
「明治安田生命つみたて学資」は、お子さまの出生予定日の140日前からお申込みいただけ、2歳までのお申込なら保険料の払込みを10歳までとするご契約も可能です。高校卒業後の進学に備えて、計画的に学費の準備をしたい人に適しています。
※明治安田生命つみたて学資をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
募Ⅱ2500968ダイマ推