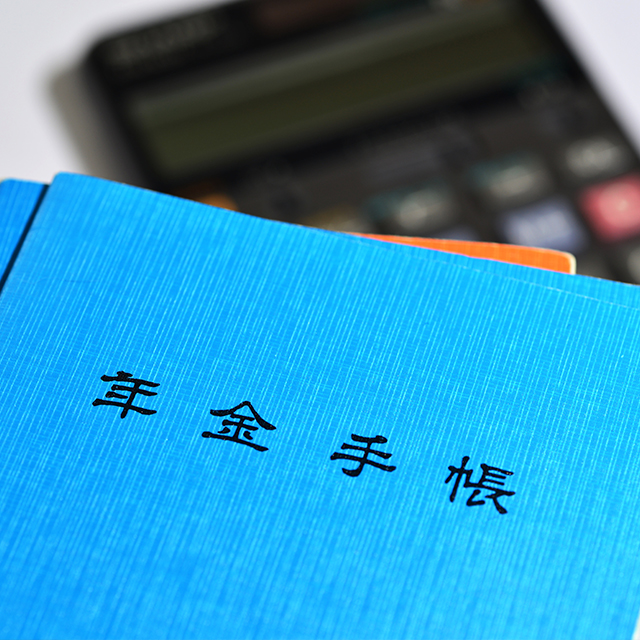お金が貯まらない人の特徴とは?
上手に貯めるポイントやおすすめの貯蓄方法も紹介!
将来に備えたいと思っているのになかなかお金が貯まらないと、悩みを抱える人は珍しくありません。
努力しているつもりなのに貯蓄できないなら、まずお金が貯まらない原因をはっきりさせて解消することからはじめましょう。さらに、お金を上手に貯める方法を知って、目的にあわせて使い分けるのもおすすめです。
本記事では、お金が貯まらない人の特徴、貯まりやすくなるポイントやおすすめの方法などを紹介します。
※本記事は、2023年10月現在の内容です。

預貯金額の平均は?
金融広報中央委員会が実施している「家計の金融行動に関する世論調査」を見ると、日本人の預貯金を含む金融資産保有額がわかります。
2022(令和4)年の二人以上世帯の預貯金を含む金融資産保有額は次のとおりです。
| 平均預貯金 | 金融資産(※)保有額 | ||
|---|---|---|---|
| 平均 | 中央値 | ||
| 20歳代 | 121万円 | 214万円 | 44万円 |
| 30歳代 | 246万円 | 526万円 | 200万円 |
| 40歳代 | 356万円 | 825万円 | 250万円 |
| 50歳代 | 508万円 | 1,253万円 | 350万円 |
| 60歳代 | 834万円 | 1,819万円 | 700万円 |
| 70歳代 | 814万円 | 1,905万円 | 800万円 |
※金融資産とは、普通預金や有価証券などの区分によらず、運用や将来への備えを目的に蓄えている資産
出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和4年)」
二人以上世帯の預貯金額の全国平均は、562万円でした。ただし、平均は極端に大きい、あるいは小さい数値の影響を受けやすい特徴がある点に注意が必要です。
金融資産保有額は、生活費などで日常的に出し入れする預貯金を除き、何らかの目的に備えて貯めている資産を示すため、預貯金以外の資産も含まれています。
金融資産保有額の全国平均は1,291万円、中央値は400万円となっています。
平均は総保有額を全世帯で割った値であるのに対し、中央値は数値を小さいものから順に並べたときに真ん中にくる値を示しています。よって、一般家庭の実情に近いデータと考えられるため、中央値を参考にするとよいでしょう。
中央値で見る金融資産保有額は、20歳代で44万円、30歳代で200万円です。年齢が上がっていくにつれて増えていることがわかります。
お金が貯まらない人の特徴
なかなかお金が貯まらない人には共通する特徴が見られます。どれも意識すればすぐに解消できるものばかりなので、もし当てはまる特徴があればすぐに行動に移しましょう。
収支の把握ができていない
貯蓄を成功させるには、まず収入と支出を把握することが重要です。当然ながら支出が収入に対して少なければ、お金を貯めることができます。収支を把握していなければ、支出が収入を上回らないように意識できないため、お金を貯めにくいでしょう。
特に支出は、現金だけではなく電子マネーやバーコード決済、クレジットカードの支払いなども含まれるためお金の流れをつかみにくく、正確に管理しきれていない人もいるかもしれません。
収支の管理が難しいと感じる場合は、家計簿をつけてお金の管理をするとよいでしょう。家計簿に関して詳しくは後述します。
各支出の予算を決めていない
毎月の支出の内訳は、住居費や食費、通信費、水道光熱費、被服費、娯楽費などさまざまです。毎月何にどれくらいのお金を使うか予算を決めておかなければ、計画的にお金を使うことができません。
無計画な支出は、お金が貯まらない原因の一つです。無駄な支出を減らすためにも、支出項目ごとに予算を決め、予算内におさまるように計画的にお金を使うといいでしょう。
お金を貯める目的や目標額が定まっていない
お金を貯める明確な目的や目標額が定まっていなければ、貯蓄に対するモチベーションの維持は難しいでしょう。目的や目標が具体化するほど、貯蓄への意欲は高まります。
旅行費用や趣味の買い物など、短期的な目的は達成感を得やすいためおすすめです。
ただし、ライフプランにあわせた長期的な目的・目標も大切です。結婚や出産、子どもの教育、マイホーム購入など、ライフステージの変化には大きな出費がつきものです。
長期的な目線で目標額を設定し、早めに貯蓄をはじめることも大切です。
余った分を貯めようと考えている
毎月の収入から生活費を出して余ったお金を貯蓄に回す、この考え方ではお金は貯まりにくくなる恐れがあります。
人は目の前の資源をあるだけ使い切ってしまう不合理な特性があるとされており、それは手元にあるお金についても同じです。
そのため、余ったお金を貯めようと考えていても、結果的にお金が残らないことになってしまいがちです。
ラテマネーが習慣化している
ラテマネーとは、ちょっとした金額だからと習慣的に続けている支出のことです。お金が貯まらない人は、ラテマネーが積もり積もって支出が膨らんでいる可能性も考えられます。
いつもと違う行動や決断をするよりも、人は習慣化した行動を無意識に選んでしまう習性があります。やめようと思っても、つい続けてしまうのがラテマネーの油断できないところです。
自分へのご褒美など明確な理由や目的がある場合を除き、「なんとなく」の習慣でラテマネーを支出しないようにしましょう。たとえ1日300円のラテマネーでも、1年(365日)続けると10万円を超える出費になります。
お金を上手に貯めるためのポイント
お金が貯められる人の多くは、貯蓄しやすい環境を整えています。それでは、お金を上手に貯めるために実践したいポイントを5つ紹介します。
家計簿をつける
お金を貯めるには家計の管理が欠かせません。利用して家計簿をつけ、収支を正しく把握してから貯蓄をはじめましょう。
家計簿をつけるとこれまで意識してこなかったお金の流れが見えるようになり、貯蓄の目標額も具体的に立てられます。
決済方法が多様化しているため、家計管理が煩雑になっていますが、クレジットカードや銀行口座、電子マネーなどと連携できるスマートフォンアプリもあります。
家計簿は継続がなにより重要です。そのため、便利なツールを活用する、食費や水道光熱費などの支出項目を細かくしすぎないなど、自分が無理なく続けやすいスタイルを選びましょう。
固定費の削減を検討する
毎日の支出は「変動費」と「固定費」の大きく二つに分類されます。
食費や消耗品費、水道光熱費など使い方によってかかる金額が変わる出費が変動費、住居費や通信費、サブスクリプション代、保険料など、毎月ほぼ同じ金額の出費が固定費です。
節約しようと考えると毎日の変動費をできるだけ切り詰めようと考えがちですが、注目すべきは固定費です。固定費は一度減らしてしまえば、節約を意識しなくても、継続して長く支出を抑えられます。
たとえば毎月1万円の固定費を減らして貯蓄すれば1年間で12万円、10年で120万円と、継続するとまとまった預貯金額になります。
先取りで貯蓄する
お金を貯める習慣を身につけるのは大変です。そこでおすすめの方法が、収入から先取りして貯蓄するお金をあらかじめ差し引いておく方法です。
残ったお金の範囲内で毎月の生活費をやりくりするうちに、着実にお金を貯めながら、家計管理する習慣が身につきます。
先取りでの貯蓄を長く続けられるように、毎月の貯蓄額は無理のない金額にしておくことが大切です。たとえば月々1万円からスタートして、生活に余裕があるなら翌月から増額するなど、家計にあわせて調整しながら金額を設定していくといいでしょう。
先取りで貯蓄する方法には、給与の振込口座から預貯金用口座への自動振替サービス、給与天引きの社内預金制度や財形貯蓄制度の活用などがあります。
ストレスをためない
お金を貯めようとすると、無駄なお金を使わないように我慢する機会が増えます。これまで経験のない我慢が続いてストレスを感じると、貯蓄に疲れてしまい、お金が貯まらなくなる原因になる可能性もあります。
ストレスをためないように、自分にあったストレス解消法を取り入れるのがおすすめです。
たとえば、家族旅行などの短期目標で達成感を味わう、目標達成ごとに自分へのご褒美を用意する、自由に使えるおこづかいを設定する、週2回のラテマネーを許すなど、やる気につながる方法をみつけましょう。
収入を増やす努力をする
預貯金を貯めたいなら、支出を減らす工夫とともに、収入を増やす努力も大切です。
給料アップにつながる資格を取得する、キャリアアップをめざして転職する、副業をはじめる、専業主婦から復職するなど、ご自身の状況に応じてチャレンジしてみましょう。
また、生命保険やiDeCo(イデコ)などで所得控除を受ける方法もあります。所得控除を受けると課税所得が軽減されるため、所得税の負担が少なくなった分、給与の金額は変わらなくても手取りを増やせます。
お金が貯まらない人におすすめの貯蓄方法
思うように貯蓄が進まない、もっと上手にお金を貯めたいと悩んでいるなら、お金を貯めるのに適した方法を積極的に活用しましょう。

積立定期預金
会社勤めの人なら、給与の振込口座から自動振替で貯蓄できる積立定期預金がおすすめです。預金保険制度の対象で元本保証のある定期預金で、毎月決まった日に指定した金額を積み立てられます。先取り貯蓄できるので、続けるうちに自然とお金が貯まります。
積立金額は、銀行ごとに異なりますが、月々1,000円以上1円単位など細かな設定に対応しています。
ただし、1ヵ月以上10年以内など、あらかじめ決めた契約期間は原則としてお金を引き出せないため、無理のない金額を積み立てましょう。
財形貯蓄
財形貯蓄は給与天引きで利用できる方法で、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類あります。給与が振り込まれた時点で貯蓄が完了しているため、貯蓄の習慣化に向いています。
| 一般財形貯蓄 | 財形年金貯蓄 | 財形住宅貯蓄 | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 自由 | 退職後の年金 | マイホーム取得や工事費75万円超のリフォームなどの増改築 |
| 申込時年齢 | 制限なし | 満55歳未満 | 満55歳未満 |
| 積立期間 | 3年以上 | 5年以上 | 5年以上 |
| 引出し | 預入れから1年を経過すると全額または一部引出せる。 | 原則として60歳以降に5年以上の年金として受け取る。 積立期間5年未満の引出しは5年をさかのぼって課税対象となる。 |
目的どおりの場合、5年以内でも引出せる。 目的以外の引出しは5年をさかのぼって課税対象となる。 |
| ポイント | 預入限度額はない。 自由度が高い。 税法上の優遇措置は受けられず、利子などは源泉分離課税の対象となる。 |
1人1契約のみ。 財形住宅貯蓄と合計で元利合計550万円までの利子などが非課税となる。 |
1人1契約のみ。 財形年金貯蓄と合計で元利合計550万円までの利子などが非課税となる。 |
いずれも預金保険制度の対象で、元本保証があります。
※税法上の取扱いについては2023年10月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更の伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
貯蓄型保険
貯蓄型保険は、毎月の保険料が積み立てられ、解約時の解約返戻金や満期時の満期保険金としてお金を受け取れる生命保険です。
貯蓄型保険には、さまざまな種類があります。
- 終身保険:万一のとき死亡保険金を受け取れる保障が一生涯続く保険
- 養老保険:満期時に死亡保険金と同額の満期保険金を受け取れる保険
- 学資保険:契約者である親の万一に備えながら子どもの教育資金を貯められる保険
- 個人年金保険:老後資金を準備するための私的年金保険
貯蓄をしながら万一にも備えられる点が貯蓄型保険の魅力です。ただし、途中で解約すると、解約返戻金額は払い込んだ保険料を下回る可能性が高いので注意しましょう。
つみたてNISA
つみたてNISAは、2018年1月からはじまった少額投資非課税制度です。取扱いのある金融機関で専用口座を開設すると、年40万円まで、最長20年間の非課税での投資が可能です。最低積立金額や積立間隔は、金融機関ごとにルールが異なります。
2024年からは新NISA制度がはじまります。新NISAでは、つみたて投資枠として年間120万円、成長投資枠として年間240万円、合計すると年360万円まで投資可能です。非課税保有期間が無期限になるなど、さらに柔軟な資産運用に対応しています。
なお、現在のつみたてNISA口座は、20年間は非課税のまま保有できます。例えば、2023年に積み立てた場合は最長2042年まで非課税対象です。
つみたてNISAの投資対象は、一定の条件を満たした株式投資信託とETF(上場投資信託)のみです。安全性の高い商品に限られていますが、元本割れなどの投資リスクがあることを理解しておきましょう。
※税法上の取扱いについては2023年10月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更の伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
iDeCo(イデコ)
iDeCo(イデコ)は毎月の掛金と運用先を自分で決められる個人型確定拠出年金制度で、運用成績によって受け取る年金額が変わります。
掛金は月額5,000円からで原則として60歳まで資産を引き出せないため、老後資金を貯めたい人におすすめです。会社員や自営業者、専業主婦(夫)などの区分によって、掛金の上限は変わります。
iDeCo(イデコ)の特徴は、税制面の手厚い優遇です。
- 掛金の全額が所得控除される
- 運用中に得られた利益はすべて非課税となる
- 受取時の年金は、退職所得控除や公的年金等控除の対象になる
税金の負担を軽減しながら資産運用できるので、効率よくお金を貯められる可能性が高いでしょう。
2022年の制度改正で、自営業者、会社員、公務員、専業主婦(夫)など、20歳以上65歳未満のほとんどの人が加入できるようになりました。ただし、国民年金保険料を支払っていない人など、一部加入できない人もいます。
※税法上の取扱いについては2023年10月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更の伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
お金を貯めるときの注意点
お金の貯めるときには、それぞれの特徴にあわせて、預貯金と投資を上手に使い分けましょう。
普通預金や積立定期預金などの預貯金は、短期間で引き出せるため、近い将来必要なお金を貯めるのに適しています。
ただし、日本では低金利が続いているため、預貯金に頼りすぎると物価の上昇(インフレ)に対応できません。急激なインフレが起こると、預貯金の資産価値が相対的に下がる恐れもあります。
一方、つみたてNISAやiDeCo(イデコ)などの投資は、時間をかけた資産形成に向いています。運用次第でお金を増やせる可能性もあります。
しかし、投資には預貯金のような元本保証がないため、元本割れリスクが伴います。また、気軽に資産を引き出せない商品もあるため、計画的に利用しましょう。
お金を貯めるなら「明治安田生命じぶんの積立」もおすすめ!
毎月コツコツとお金を貯めたいなら、貯蓄型保険がおすすめです。
「明治安田生命じぶんの積立」なら月々5,000円から保険料の積立が可能です。毎月の保険料は指定口座から自動引き落しされるため、安定した貯蓄を実現できます。
保険料払込期間は5年で、いつ解約しても100%以上の受取率のため、安心して積み立てられます(保険期間は10年間)。また、一般生命保険料控除の対象なので、税金の負担軽減も期待できます。
※明治安田生命じぶんの積立をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
貯めたいのにお金が貯まらないと感じているなら、収支を把握してから、家計の見直しと貯蓄目標を持つことが大切です。また、貯蓄はコツコツと長く続けるほど成功させやすいため、ストレスにならない方法をみつけましょう。
お金を貯める方法には、預貯金や投資、保険などいろいろあります。それぞれ特徴が異なるので、目標や達成までの期間などにあわせた使い分けが大切です。
募Ⅱ2401933ダイマ推