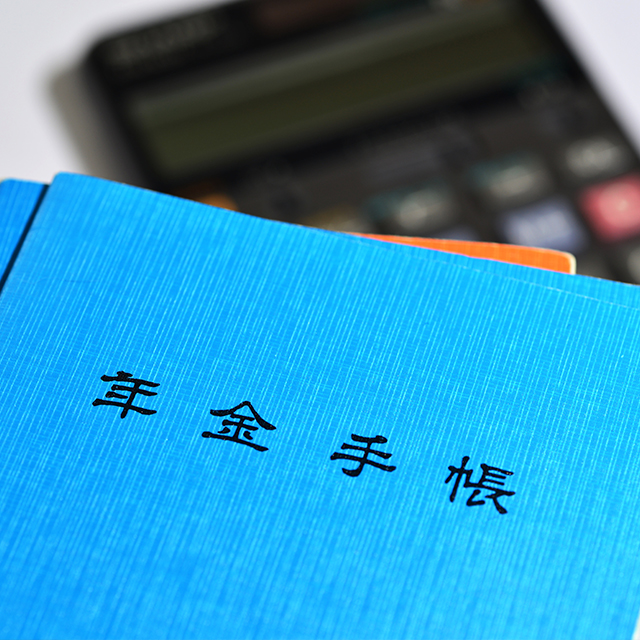育休手当(育児休業給付金)はいくらもらえる?
支給要件や期間、申請の流れも解説
育休手当とは、育児休業を取得したとき、子どもが原則として1歳になるまで受け取れる給付金のことで、正式には「育児休業給付金」といいます。
育休中は一般的に給与がなく、収入が大きく減るため、「育休手当はいつまでもらえる?」「いくらもらえる?」と気になっている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、育休手当の概要や要件、支給金額や支給期間を解説します。必要書類や申請の流れも解説するので、育休の取得を予定している人や検討している人はぜひ参考にしてください。
※本記事は、2024年1月現在の内容です。

育休手当(育児休業給付金)の概要
育休手当(育児休業給付金)とは、育児休業を取得した人が一定の要件を満たすときに受け取れる雇用保険の給付金です。
育休中は基本的に給与が出ないため、「世帯収入が大きく減ってしまう」「生活費が足りなくなるのでは」と不安な人もいるのではないでしょうか。
育休手当は、原則子どもが1歳になるまで、給与の約7割(181日目以降は5割)を受け取れます。育休手当は非課税であり、所得税(復興特別所得税を含む)や住民税がかかりません(※)。そのため、育休中の生活を守るための大切な収入源となります。
また、育休中の社会保険料は労使ともに免除され、育休期間中に給与が支払われていない場合は雇用保険料も発生しません。
なお、育休に性別の制限はなく、要件を満たせば男性・女性ともに取得でき、育休手当を受け取れます。
※住民税は前年の所得などによって計算されるため、育休中でも前年に所得があれば住民税の納税が必要です。
※制度に関する記載は2024年1月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
※税法上の取扱いについては2024年1月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更の伴い取扱いが変わる場合があります。
育休手当(育児休業給付金)をもらえる要件
育休手当(育児休業給付金)の受給要件は、以下の4つです。ただし、4つ目の要件は有期雇用契約の場合に限ります。
①原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した被保険者である(2回まで分割取得が可能)
②休業開始日前2年間に、給与支払基礎日数が11日以上(または給与の支払いの基礎となった時間数が80時間以上)該当する月が12ヵ月以上ある
③育児休業開始日から起算した1ヵ月ごとの就業日数が10日以下または就業時間数が80時間以下である
④養育する子が1歳6ヵ月に達する日までの間に、労働契約期間が満了することが明らかでない(有期雇用契約の場合)
育休手当(育児休業給付金)の支給期間はいつからいつまで?
育休手当がもらえるのは、原則として養育している子どもが1歳になった日の前日(1歳の誕生日の前々日)までです(※)。子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日まで受け取れます。
※民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされるため
ただし、一定の要件を満たした場合は、1歳6ヵ月または2歳になるまで育休手当の受給期間を延長できます。延長できる主なケースは、以下のとおりです(※)。
- 保育所など(無認可保育施設は除く)に申込みしているが入所できない
- 子どもを主に養育する配偶者が死亡した
- 子どもを主に養育する配偶者が病気やケガによって養育ができなくなった
- 離婚などで配偶者が子どもと同居しないことになった
- 産前産後休業期間である
また、「パパ・ママ育休プラス」を利用すれば、子どもが1歳2ヵ月になるまで育休を取得でき、要件を満たせば育休手当も受け取れます。以下で詳しく解説します。
※有期雇用契約の場合は、子どもが1歳に達する日の翌日時点で、子どもが1歳6ヵ月になるまでに労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。
パパ・ママ育休プラスとは
パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育休を取得する場合に一定の要件を満たすと、子どもが1歳2ヵ月になるまで育休を取得できる制度です。
パパとママが交代して取得する、同時に取得するなど、家庭の状況にあわせて柔軟に取得できます。
例えば、パパ・ママ育休プラスを利用してママが産後休業(8週間)後から育休を取得し、パパが6ヵ月間(子どもが1歳2ヵ月になるまで)育休を取得した場合、ふたりあわせて1歳2ヵ月まで給付率67%で育休手当を受け取れます。
ただし、パパ・ママ育休プラスを利用した場合も、それぞれが取得できる育休取得期間の上限は原則として1年間です。取得可能日数が増えるわけではないため、注意してください。
また、2022年10月には、「産後パパ育休」(出生時育児休業)もスタートしました。
産後パパ育休は、通常の育児休業とは別に、子どもが生まれてから8週間以内に4週間の休業を取得できる制度です。
生後8週間以内に4週間(28日)を限度に、2回に分けても取得できます。1歳までの育休とは別に取得できるため、分割すると合計4回に分割しての取得も可能です。
産後パパ育休を利用した場合も、要件を満たせば育休手当が受給できます。ただし、産後パパ育休で支給された日数は、育児休業給付の180日(支給率67%の上限日数)に通算されます。
育休手当(育児休業給付金)の支給金額
育休手当の支給金額は、以下のとおりです。
支給金額=休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日間)×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

「休業開始時賃金日額」は、育休開始前直近6ヵ月間に支払われた給与の総額を180で割った金額を指します。上限は15,430円、下限額は2,746円です(2024年7月31日までの金額)。支給日数が30日の場合、支給金額の上限はそれぞれ以下のとおりです。
| 区分 | 支給上限額 | 支給下限額 |
|---|---|---|
| 支給率67%・支給日数30日 | 310,143円 | 55,194円 |
| 支給率50%・支給日数30日 | 231,450円 | 41,190円 |
ただし、下限額は、育休中に給与が支払われなかった場合の金額です。給与が支払われた場合、その金額によっては下限額を下回ることがあります。
育休中に、休業開始時賃金月額の13%(181日目以降は30%)を超える給与が支払われた場合、支給金額は次の式で算出した金額です。
支給金額=休業開始時賃金日額×支給日数×80%-給与額
また、育休中に支払われた給与が休業開始時賃金月額の80%以上である場合、育休手当は支給されません。
育休手当(育児休業給付金)の支給金額の計算例
育休開始前の6ヵ月間に支払われた給与の総額が144万円だった場合を例に、受け取れる育休手当の支給金額を計算してみましょう。
休業開始時賃金日額は、144万円÷180日=8,000円となります。
育休期間中に給与が支払われなかった場合、支給月額は次のとおりです。
| 区分 | 支給月額 |
|---|---|
| 育休開始から180日間 | 8,000円×30日×67%=160,800円 |
| 育休開始から181日目以降 | 8,000円×30日×50%=120,000円 |
上記のケースで、支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)中に給与が15万円支払われた場合の支給月額も計算してみましょう。休業開始時賃金月額(8,000円×30日)の13%超~80%未満の給与が支払われているため、次のように計算できます。
支給月額=8,000円×30日×80%-150,000円=42,000円
育休手当(育児休業給付金)の申請方法・流れ
育休手当(育児休業給付金)の申請は、お勤め先を通して、在職中の事業所を管轄するハローワークで手続きします。
はじめて申請する際の受給確認・初回の支給申請手続きと、2回目以降の支給申請手続きに分けて、申請方法・流れを解説します。
受給資格確認申請・初回の支給申請手続き
育休手当を受給するには、お勤め先が受給資格確認の手続きを行なう必要があります。受給資格の確認申請と初回の支給申請は、同時の手続きが可能です。
必要書類は以下の4つです。
①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
③育児休業の開始・終了日、給与の金額と支払状況を証明できるもの
④母子手帳など育児の事実、出産予定日・出産日を確認できるもの(写し可)
申請の流れは以下のとおりです。
1.お勤め先に育休を申請する
2.お勤め先の指示に従って必要書類を用意する
3.お勤め先がハローワークに必要書類を提出する
4.受給資格がある場合は支給決定通知書が交付される
5.支給決定後約1週間で育休手当が振り込まれる
初回の支給申請は、育児休業開始日から起算して4ヵ月を経過する日の属する月の末日までに行ないます。支給まで一般的に日数がかかるため、なるべく早く手続きしましょう。
2回目以降の支給申請手続き
2回目以降の申請は、お勤め先を通じて原則として2ヵ月に1度行ないます。支給申請期間は、ハローワークから交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に記載されています。期間内に忘れず手続きしましょう。
必要書類は以下の二つです。
①育児休業給付金支給申請書
②支給対象期間中に支払われた給与の金額・支払状況、休業日数・就業日数を確認できる書類
なお、2回目申請用の「育児休業給付金支給申請書」は、受給資格確認後の支給決定通知書とあわせて交付されます。
子どもの将来のために計画的に備えるなら「明治安田生命つみたて学資」
育休中は収入が減少しますが、育休手当が受給できたり、児童手当の支給が開始されたりします。
子どもの将来に向けて計画的に備えておきたい人は、学資保険を検討しましょう。学資保険は、子どもの教育費に備えるための貯蓄型保険です。
原則として親が契約者となり保険料を払い込むことで、子どもが一定の年齢になったときに教育資金を受け取れます。
「明治安田生命つみたて学資」は、お子さまの進学にあわせて計画的に教育資金を準備できる学資保険です。費用がかさむ大学などの時期にあわせて年に1回、合計4回教育資金・満期保険金を受け取れます。
また、保険料の払込みは最も長くて15歳で終了するので、余裕を持って教育資金を準備できます。ご契約者さまが万一のときは以降の保険料の払込みが免除され、保障内容はそのまま継続されます。
お子さまの出生予定日の140日前からお申込みいただけるので、ぜひご検討ください。
※明治安田生命つみたて学資をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
育休手当は、育休を取得したときに受け取れる給付金です。子どもが原則として1歳になるまで、給与の約7割(181日目以降は5割)を受給できます。育児のために仕事を休み、その間の給与が支払われないときの生活を守るための大切な収入源です。
育休手当を受給するには、お勤め先を通じてハローワークに申請する必要があります。日数がかかるため、なるべく早めに手続きしましょう。
現在は、育児・介護休業法が改正され、産後パパ育休が創設されるなど、より柔軟に育休を取得できるようになってきています。育休中の収入や子どもの将来のお金についてしっかり話しあい、計画的に準備しましょう。
募Ⅱ2302743ダイマ推