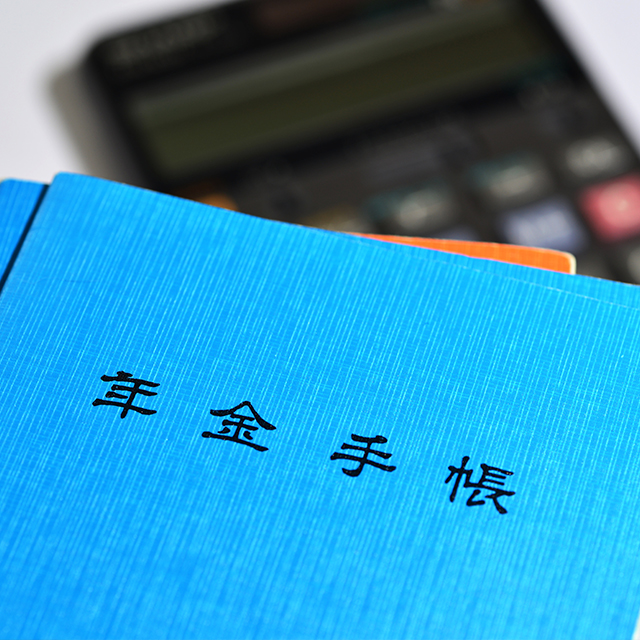子育て支援を子どもの年齢別に解説!
制度を活用して暮らしに役立てよう
子育て中は子どもの思わぬケガや病気、就学・進学にあたっての教育費など出費がかさみます。また、家計が急変して、子どもの生活や進路に影響を与えないかを考える人もいるでしょう。
国や各自治体では、さまざまな子育て支援制度を整備しています。子育て中の世帯にとって大きな助けになるため、上手に活用しましょう。
本記事では各種子育て支援制度を、子どもの年齢順に紹介します。子育て中の人はぜひ、参考にしてください。
※本記事は、2023年10月現在の内容です。

子どものいる人が利用できる子育て支援制度一覧
子育て中に利用できる主な支援制度を、子どもの年齢順に並べた一覧です。
- 出生時育児休業給付金・育児休業給付金:0~2歳
- 幼児教育・保育の無償化:0~5歳
- 子ども・子育て支援新制度:0~5歳
- 児童手当制度:0~15歳
- 児童扶養手当制度:0~18歳
- 自立支援医療制度(育成医療):0~18歳
- 子ども医療費助成制度
- 子育て支援パスポート事業
- 就学援助制度:小学生~中学生
- 家計急変支援制度:高校生
- 高校生等奨学給付金:高校生
- 高等教育の就学支援新制度:大学・短大・専門学校生
各制度内容を以下で解説します。
※各制度に関する記載は2023年10月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

出生時育児休業給付金・育児休業給付金:0~2歳
子どもが誕生し、養育する際の休暇を取ると、出生時育児休業給付金や育児休業給付金を受け取れます。
出生時育児休業給付金は産後パパ育休(出生時育児休業)を取得し、一定要件を満たすと給付金を受け取れます。
産後パパ育休は子どもの誕生から8週間以内、合計28日を限度として2回に分けて取得可能です。
育児休業給付金は1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得し、一定要件を満たすと給付金を受け取れる制度です。
子どもが1歳になる前日までの期間受け取れますが、要件を満たすと2歳になる前日まで受け取れる場合があります。2017年10月施行の育児・介護休業法改正によって、期間が延長されました。
幼児教育・保育の無償化:0~5歳
2019年10月から、幼稚園や保育園、認定こども園などを利用する3~5歳児クラスの子どもたちを対象に利用料(保育料)の無償化が全国でスタートしています。
また、地域型保育も無償化の対象です。
さらに、住民税非課税世帯では0~2歳児クラスの利用料も無償化しています。
子ども・子育て支援新制度:0~5歳
社会全体で「量」と「質」の両面から子育てを支える、子ども・子育て支援新制度が2015年4月からスタートしました。
子ども・子育て支援新制度での取り組みは、以下の2点です。
- 認定こども園の普及や地域型保育の事業の整備で支援の量を拡充
- 職員の配置・処遇の改善などで支援の質を向上
0~5歳の子どもを各施設・事業者へ預ける際は、保育認定が必要です。保育認定は子どもの年齢・家庭の状況にあわせて3つに分類されます。利用の際は、認定区分と所得に応じた保育料を支払い、区分ごとに利用できる施設が異なります。
また、以下の事柄も、子ども・子育て支援新制度の取組みです。
| 利用者支援 | 必要な支援を利用しやすくする情報提供や紹介を実施 |
|---|---|
| 放課後児童クラブ | 小学校の余裕教室や児童館などで、日中保護者がいない家庭の小学生が放課後を過ごす場所を整備 |
| 一時預かり | 急用や短期就労、リフレッシュ時などに子どもを預かる |
| 病児保育 | 病気や病後の子どもを預かる |
| ファミリー・サポート・センター | 支援を受けたい保護者と支援実施を希望する人の活動に関する連絡・調整 |
| 地域子育て支援拠点 | 地域の身近な場所で親子の交流や子育て相談できる場所を設置 |
| 子育て短期支援 | 一時的な事情で子どもを保育できないとき、宿泊や夜間に子どもを預かる |
| 乳児家庭全戸訪問 | 生後4ヵ月までの乳児がいる家庭を訪問して情報提供や養育環境を把握 |
| 養育支援訪問 | 養育支援が必要な家庭を訪問し指導や助言で適切な養育環境を確保 |
| 妊婦健康診査 | 妊婦の健康保持・増進を図るため健康診査や医学的検査を実施 |
安心して子どもを預けられる施設・事業者を増やすだけでなく、地域ニーズにあわせたさまざまな取組みを実施しています。
児童手当制度:0~15歳
児童手当制度では、子どもの誕生から中学校卒業までの期間を対象に、所定の金額を受け取れます。
| 子どもの年齢 | 子ども1人あたりの月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
児童手当は原則、日本国内に住む子どもが支給対象です。
なお、所得制限があるため、子どもを養育する人の所得が一定額以上の場合は減額、または手当自体を受け取れません。
ただし、所得制限の撤廃や受け取れる期間の延長が検討されています。今後の制度変更・拡充にも注目しましょう。
児童扶養手当制度:0~18歳
児童扶養手当制度は、離婚などでひとり親世帯となり、父親または母親と同一生計でない子どもを養育する家庭へ児童扶養手当が支給される制度です。
子どもが18歳になってから最初の3月31日を迎えるまでの期間受け取れますが、所得制限もあります。なお、養育する子どもが障害児の場合は、受け取れる期間が20歳未満までとなります。
収入ベースでの所得制限限度額が設定されており、全部支給は2人世帯で160万円、一部支給は2人世帯で365万円です。
支給される金額は以下のとおりです。一部支給に該当する場合は、所得に応じて受け取れる月額が変化します。
| 全部支給の場合 | 一部支給の場合 | |
|---|---|---|
| 月額 | 43,070円 | 10,160円~43,060円 |
| 子ども2人目の加算額 | 10,170円 | 5,090円~10,160円 |
| 子ども3人目以降の加算額 | 6,100円 | 3,050円~6,090円 |
ほかにも、自治体独自でひとり親家庭が対象の子育て支援を実施しているところもあります。
自立支援医療制度(育成医療):0~18歳
自立支援医療制度(育成医療)は、心身の障害を除去・軽減するための医療費負担を軽減する制度です。所得区分ごとに自己負担上限が決まっています。
| 所得区分 | 育成医療の自己負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得1:市町村民税非課税 (本人はまたは障害児の保護者の年収が80万円以下) |
2,500円 |
| 低所得2:市町村民税非課税 (低所得1を除く) |
5,000円 |
| 中間所得1:市町村民税が33,000円未満 (年収 約290~400万円未満) |
5,000円 |
| 中間所得2:市町村民税が33,000円以上235,000円未満 (年収 約400~833万円未満) |
10,000円 |
| 一定所得以上:市町村民税が235,000円以上 (年収 約833万円以上) |
対象外 |
制度の対象となる治療は、18歳未満の子どもが障害を除去・軽減する手術などで効果が確実に期待できる場合です。
子ども医療費助成制度
各自治体では、子どもの医療費を助成しています。
地域ごとに制度の名称や対象となる子どもの年齢、助成内容、所得制限の有無などに違いがあるため、詳細は住んでいる地域の自治体に確認しましょう。
また、地域差をなくして制度を全国で統一するべきとの意見も出ています。今後の動向にも注目しましょう。
子育て支援パスポート事業
子育て支援パスポート事業は、各自治体が実施する子育て世代支援事業です。地域企業や店舗が子育て世帯への割引・優待・応援サービスなどを提供しています。
子育て世帯への支援を手厚くし、子ども連れでの外出がしやすい、社会全体で子育て世帯を支える機運醸成を図っています。
なお、地域ごとにパスポートの形式や支援内容は異なるため、利用の際は内容を確認しましょう。
利用対象は、18歳未満の子どもがいる世帯、未就学児のいる世帯、子どもが3人以上の世帯など、地域によって異なります。また、住んでいる地域だけでなく、他地域でもサービスを受けられるよう、各都道府県が協力を強化しています。
就学援助制度:小学生~中学生
就学援助制度は、経済的理由で子どもの就学が困難な家庭を援助する制度です。小学校・中学校へ通うために必要な学用品費や給食費、修学旅行費などを支援します。
生活保護法が規定する要保護者、または教育委員会が要保護者に準ずる程度の困窮を認めた場合、補助が受けられます。
高等学校等就学支援金制度:高校生
高等学校等就学支援金制度は、高校などでかかる教育費負担を軽減する制度です。
所得などの要件を満たす世帯が受け取れ、高校は国公立私立を問いません。年収が約910万円未満の世帯が対象です。
家計急変支援制度:高校生
家計急変支援制度は、2023年4月から実施された、家計急変世帯の子どもが高校に通うための支援制度です。ケガや病気療養で勤務できない場合、自身に責のない理由で離職した場合などで、世帯年収が減少した家庭が受け取れます。
支給限度額は月額33,000円、公立高校等は月額9,900円です。また、都道府県ごとに高校の授業料軽減を実施している場合もあります。
高校生等奨学給付金:高校生
高校生等奨学給付金は、高校生などがいる低所得世帯を対象に、授業料以外の教育費負担を軽減する支援制度です。
授業料以外の教育費は、教科書や教材の費用、学用品費、修学旅行費などが該当します。また、都道府県ごとに制度詳細は異なります。
家計の急変で非課税世帯相当になった世帯も対象です。
高等教育の修学支援新制度:大学・短大・専門学校生
高等教育の修学支援新制度は、2020年4月から実施された支援制度です。
授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)と給付型奨学金の支給で、大学や専門学校に安心して学べるよう支援しています。給付型奨学金であるため返還は不要です。
支援対象の学校は、一定要件を満たす大学・短期大学・高等専門学校(4年・5年)・専門学校です。
対象者は世帯収入や資産の要件を満たし、進学先で学ぶ意欲がある学生ですが、世帯収入に応じて支給額は異なります。
各種奨学金制度:大学・短大・専門学・大学院生
奨学金制度とは、経済的な理由などで進学が難しい学生に学費の貸与や給付を行なう制度です。
奨学金制度で代表的な日本学生支援機構では、貸与型・給付型の各種奨学金制度を用意しています。奨学金ごとに、奨学金を受けられるかの家計基準があります。
また、日本学生支援機構以外にも大学生向けの奨学金を出している団体があるため、必要に応じて利用を検討しましょう。募集人数や指定大学、受け取れる金額などは団体ごとに異なります。
まとめ
子育て中の人は、子どもの年齢に応じたさまざまな子育て支援制度を利用できます。
各制度で受けられる支援内容を理解し、子育て中の費用負担を軽減させるために活用しましょう。
募Ⅱ2300648ダイマ推