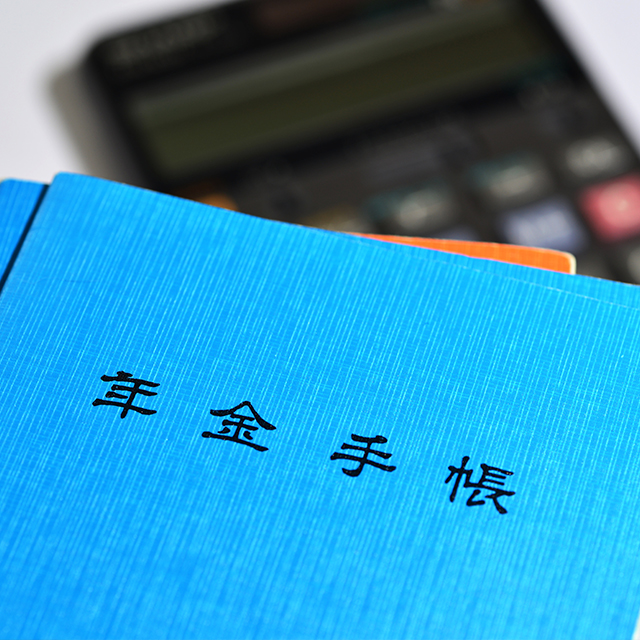学資保険をおすすめしない人の特徴は?
選ぶ際に確認すべきポイントも解説
学資保険は、子どもの教育資金を用意するための貯蓄型保険です。子どもが進学するタイミングにあわせて教育資金・満期保険金が受け取れ、計画的に教育資金を用意できます。
学資保険のなかには、死亡保障を有している商品もあり、子どもがいる家庭にとって学資保険は役に立つでしょう。
しかし、なかには学資保険をおすすめしない人もいます。子どもがいるからといって、すべての家庭に学資保険が必要とは限りません。
学資保険に興味がある人や加入を検討している人は、学資保険が必要かどうかを検討したうえで、加入すべきか判断しましょう。
本記事では、学資保険をおすすめしない人の特徴や、学資保険を選ぶ際に確認すべきポイントなどを解説します。
学資保険の加入を検討している人に役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてください。
※本記事は、2024年3月現在の内容です。

学資保険をおすすめしない人の特徴
学資保険をおすすめしない人の特徴は、以下のとおりです。
- すでに教育資金の用意ができている人
- 保険料の負担が厳しく、中途解約するリスクがある人
- 資産運用で教育資金を効率よく増やしたい人
- 貯めたお金を自由に引き出したい人
以下、それぞれ詳しく解説します。
すでに教育資金の用意ができている人
すでに教育資金の用意ができており、一定の目途がついている人であれば、学資保険を活用する必要性は低いでしょう。
学資保険の主な目的は、子どもの教育資金の用意なので、すでに預貯金や資産運用で教育資金が用意できていれば、学資保険に加入する必要はありません。
子どもの教育費は、幼稚園から大学まですべて公立の場合で約1,000万円、すべて私立の場合で約2,500万円程度が目安です(※)。なお、所得によっては児童手当や就学支援制度を受けられるため、すべて自己負担とならない場合もあります。
(※)出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」
(※)出典:日本政策金融公庫「令和3年度 教育費負担の実態調査結果」
教育費の目安に関しては以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
「子どものための預貯金はいくら用意すべき?教育費の目安と準備方法を解説」
※制度に関する記載は2024年3月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
保険料の負担が厳しく、中途解約するリスクがある人
学資保険の保険料負担が厳しく、保険金を受け取る前に中途解約するリスクがある人は、学資保険をおすすめしません。
学資保険を保険料払込期間中に解約すると、解約返戻金を受け取れますが、解約返戻金額は払い込んだ保険料総額を下回るケースが一般的です。
学資保険に加入する際には、保険料の払込満了まで解約しない前提で考え、最後まで保険料を払い込めるか、事前にしっかり検討する必要があります。
契約前に月々(毎年)の保険料をシミュレーションし、家計にとって大きな負担とならないかをご確認ください。
資産運用で教育資金を効率よく増やしたい人
資産運用で教育資金を効率よく貯めたい人や高いリターンを求めている人も、学資保険はおすすめできません。学資保険では、短期間で大きなリターンを得ることは難しいためです。
資産運用の知識があり、効率よく教育資金を用意したいと考える人は、学資保険より資産運用のほうが向いている可能性があります。
ただし、資産運用は元本割れのリスクが伴います。また、想定していた運用結果を得られる保証もないため、元本割れが不安な人は学資保険のほうが低リスクであるといえます。
貯めたお金を自由に引き出したい人
貯めたお金を自由に引き出したいと考えている人も、学資保険が向いていない可能性があります。
学資保険は、所定のタイミングで教育資金・満期保険金を受け取ることを前提とし、預貯金のように、必要な際にATMで簡単にお金を引き出せません。
また、途中で解約すると、受け取れる解約返戻金額は払い込んだ保険料総額を下回るケースが一般的です。
貯めたお金を自由に引き出したい人は、学資保険よりも預貯金で教育資金を用意するほうが向いています。
また、教育費だけでなく、急な出費が増えた際にも対応できる預貯金が用意できていない場合も、学資保険は不向きといえます。
学資保険がおすすめな人の特徴
一方、学資保険がおすすめな人の特徴は以下のとおりです。
- 現時点で十分な教育資金を用意できていない人
- 計画的に教育資金を用意したい人
- 保障を得ながら教育資金を用意したい人
以下で、それぞれ詳しく解説します。
現時点で十分な教育資金を用意できていない人
現時点で十分な教育資金を用意できていない人は、学資保険を検討してみましょう。
学資保険は、計画的に教育資金を用意できる点が特徴なので、これから教育資金を用意しなければならない人におすすめです。
教育資金・満期保険金を受け取れるタイミングは学資保険の商品ごとに異なりますが、一般的に学費がかさむ高校や大学進学時に受け取れる学資保険が多い傾向です。
コツコツ貯めつつ、必要なタイミングで教育資金・満期保険金を受け取りたい場合、学資保険が役立つでしょう。
計画的に教育資金を用意したい人
学資保険は計画的に教育資金を用意したい人に向いています。預貯金のように自由に引き出せないため、着実に教育資金を用意できます。
また、保険料が自動的に口座振替で引き落とされる学資保険なら、保険料を払い込む手間もかかりません。手間をかけずに教育資金を用意できるため、計画的な預貯金が苦手な人におすすめです。
保障を得ながら教育資金を用意したい人
契約者の万一の際に備えられる保障を得ながら、教育資金を用意したい人も学資保険が向いています。学資保険は、契約者の死亡や高度障害状態など、所定の要件に該当した際に保険料の払込みが免除される保険商品もあります。
保険料の払込みが免除されても、当初の契約内容に沿った教育資金や満期保険金を受け取れます。契約者が万一の際にも子どもの教育資金を用意できる点は、学資保険ならではの魅力です。
学資保険を選ぶ際に確認するべきポイント
学資保険への加入を検討する場合は、複数の保険商品を比較して選びましょう。具体的に、学資保険を選ぶ際に確認すべきポイントは以下のとおりです。
- 受取率を確認する
- 保険料を長期的に払い込めそうか確認する
- 保険金を受け取るタイミングを確認する
それぞれ詳しく解説します。
受取率を確認する
学資保険は、保険会社が販売している保険商品によって受取率が異なります。受取率とは、払い込んだ保険料総額に対して受け取れる保険金額の割合です。
例えば、払い込んだ保険料総額が100万円、受け取れる保険金額が105万円の場合、受取率は105%です。受取率が高いほど、払い込んだ保険料総額に対して受け取れる保険金額の割合が大きいことを意味します。
なお、受取率は保険商品やプランのほかにも、契約者や子どもの年齢、保険料の払込期間によっても異なります。また、保険料を一括で払い込んだり、短期間で払い込んだりすると受取率が高くなるケースもあります。
保険料を長期的に払い込めそうか確認する
月々(毎年)の保険料をシミュレーションし、長期的に払い込めそうか確認しましょう。学資保険を途中解約すると解約返戻金を受け取れますが、多くの場合払い込んだ保険料総額を下回ります。
学資保険は、契約から保険料払込満了までが10年や15年など長期になるケースが多いため、現在だけでなく将来も見据えたうえで、無理なく保険料を払い込めるか確認しましょう。
教育資金・満期保険金を受け取るタイミングを確認する
子どもの進学にあわせて、受け取りたいタイミングで教育資金・満期保険金を受け取れるか確認しましょう。保険金を受け取れるタイミングは、以下のように保険商品によって異なります。
- 中学進学・高校進学・大学等進学時にそれぞれ受け取る
- 高校進学時に受け取る
- 大学等進学時に受け取る
- 大学等進学時・大学等在学中に毎年受け取る
「いつ保険金を受け取りたいのか」によって、選択すべき学資保険は異なります。現在の貯蓄状況や将来の収支をシミュレーションしたうえで、最も適した学資保険を選びましょう。
学資保険以外で教育資金を用意する方法
教育資金を用意する方法は、学資保険だけではありません。以下に一例を紹介しますが、学資保険以外で教育資金を用意する方法はさまざまです。
- 児童手当
- 財形貯蓄
- 個人向け国債
- NISA
それぞれの特徴を解説します。

児童手当
児童手当とは、中学校を卒業するまで(15歳の誕生日後最初の3月31日)の児童を養育している人に支給される制度です。2024年3月現在、受給できる児童手当は以下のとおりです。
| 児童の年齢 | 児童手当(ひとりあたり月額)※ |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している人の所得が一定額以上の場合、特例給付として児童ひとり当たり月額5,000円が支給されます。なお、所得が一定額を超えると支給自体がありません。
※制度に関する記載は2024年3月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
児童手当をすべて貯めておくと、合計で約200万円(所得制限世帯でも約90万円)になります。
将来の教育資金として児童手当を活用したい場合は、児童手当専用の口座を用意して、着実に貯めるとよいでしょう。
財形貯蓄
財形貯蓄制度とは、事業主が従業員に代わって給与から天引きして計画的に貯蓄する制度です。財形貯蓄制度には、以下の3種類があります。
- 勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)
- 勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)
- 勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)
財形年金貯蓄は年金受け取り、財形住宅貯蓄は住宅取得の用途に限定されています。教育資金のために利用する場合は、一般財形貯蓄を活用しましょう。
財形貯蓄は給与から天引きされるため、着実に貯蓄できます。また、一般財形貯蓄は勤務先を通じて手続きを行なえば途中での引き出しも可能です。
個人向け国債
個人向け国債とは、個人が購入できるように政府が発行している国債です。最初に投資したお金(元本)が目減りすることなく戻ってきて、1万円から1万円単位で購入できます。個人向け国債には、以下の3種類があります。
| 種類 | 満期 | 金利タイプ |
|---|---|---|
| 固定3年 | 3年 | 固定金利 |
| 固定5年 | 5年 | 固定金利 |
| 変動10年 | 10年 | 変動金利 |
教育資金が必要になるタイミングにあわせて、最適な満期の商品は異なります。例えば、子どもが現在3歳で高校進学(12年後)のための教育資金を用意したい場合は、変動10年を選択するとよいでしょう。
NISA
NISA制度は、2024年に制度改正され新しくなりました。以下のように、一定の金額まで非課税で運用できます。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 | 1800万円(うち、成長投資枠は1,200万円) | |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
通常であれば、投資で得た分配金や譲渡益には20.315%の所得税(および復興特別所得税)・住民税がかかります(※)。しかし、NISAを利用すれば、一定の投資元本に対して得られた利益は非課税です。
以前は、5年または20年の非課税保有期間でしたが、制度改正で無期限化(恒久化)されたため、長期的な視野で投資に向き合えます。
ただし、NISAはリスクがある商品への投資が前提のため、預貯金とは違い元本保証ではありません。運用結果次第では払い込んだ金額を下回る恐れがあるため、注意しましょう。
(※)税務上の取扱いについては2024年3月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。
教育資金を学資保険で用意するなら「明治安田生命つみたて学資」がおすすめ
教育資金を用意する手段として、学資保険を検討している人は「明治安田生命つみたて学資」の活用がおすすめです。
「明治安田生命つみたて学資」は、教育資金が大きくかかる大学等への進学の時期に、教育資金3回と満期保険金1回の計4回にわたって教育資金・満期保険金を受け取れます。
保険料の払込みは10歳または15歳で終了するため、学費がかさむ時期には保険料の払込みが発生しない点も魅力です。出生予定日の140日前からお申込みが可能です。
さらに、契約者の万一の際は、保障はそのまま残しつつ、保険料の払込みが免除されます。死亡保障を備えつつ教育資金を用意できる点も、「明治安田生命つみたて学資」の特徴です。
加入時に保険料を一括払いした場合、教育資金・満期保険金の受取率は最大129.2%(※)となります。子どもの教育資金をしっかり備えたい人へおすすめです。
※受取率とは、払込保険料の累計額に対する満期までの受取総額の割合をいいます。また、受取率はご契約内容によって異なります。
※保険契約の型:Ⅰ型/ご契約者:25歳 男性/被保険者(お子さま):0歳/21歳満期/基準保険金額: 70万円/一括払込は10歳払込満了(新年掛)/保険料率:2025年11月1日現在
※明治安田生命つみたて学資をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
学資保険は、計画的に子どもの教育資金を用意できる貯蓄型保険です。子どもが進学するタイミングにあわせて、教育資金や満期保険金を受け取ることができ、契約者の万一の際にも備えられます。
しかし、すでに教育資金の用意ができている人や、保険料の負担が厳しく中途解約するリスクがある人など、学資保険をおすすめしない人もいます。
学資保険をおすすめしない人と、学資保険がおすすめな人の特徴を踏まえて、学資保険を検討すべきか判断しましょう。
募Ⅱ2500975ダイマ推