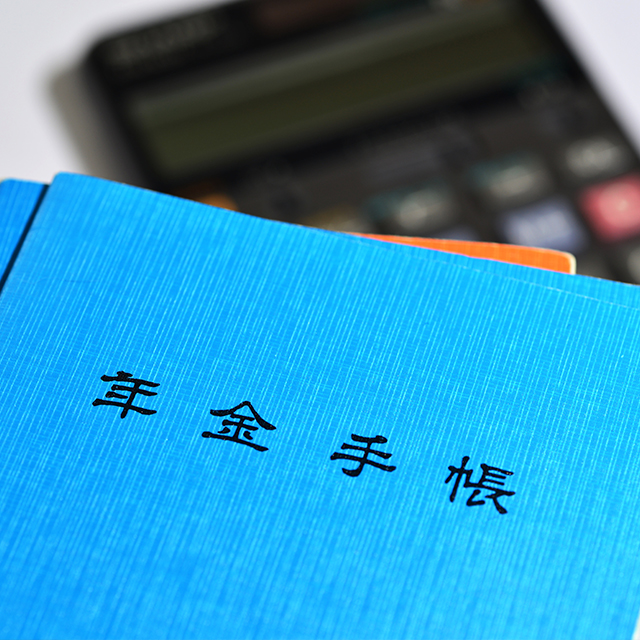児童手当は学資保険に利用す
るべき?教育資金を用意する
ための手段や注意点を解説
児童手当は、子どもが出生してから高校生年代までの間に受け取れる手当です。「児童手当は貯蓄するべき?」「児童手当で教育費をまかなえる?」と疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。子育て世帯は、児童手当をどのように使っているのでしょうか。
本記事では、児童手当の内容と注意点、使い道を解説します。また、教育費に備える手段の一つである「学資保険」についても説明します。
※税務上の取扱いについては2026年1月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。

児童手当とは
児童手当とは、高校生年代までの児童を養育している人が手当を受け取れる国の制度です。出生から18歳に達する日以後最初の3月31日まで受給できます。児童手当の支給額、支給時期について詳しくみていきましょう。
※制度に関する記載は2026年1月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は、養育する児童の年齢ごとに以下のように決められています。
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 (第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童および児童の兄妹等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
児童手当の支給時期
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2ヵ月分)が支給されます。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当が支給されます。
児童手当の使い道はみんなどうしてる?
内閣府の「児童手当等の使途に関する意識調査(平成30〜31年)」によると、児童手当の使い道(使用予定も含む)で最も多かったのは、「子どもの将来のための貯蓄・保険料」で57.9%、次いで「子どもの教育費等」の27.5%でした。
調査結果から、子育て世帯の多くは、普段の生活費や遊興費よりも子どもの将来にかかるお金や教育費に使っている・使いたいと考えていることが分かります。
出典:「児童手当等の使途に関する意識調査(平成30〜31年)」(内閣府)
大学の学費は早めから
備えておくことが大切
人生の三大資金の一つである教育費のなかでも、大学では多くの費用がかかるため、早くから備えておく必要があります。国公立大学・私立大学に4年間通った場合にかかる教育費の目安は、以下のとおりです。

| 国公立大学 | 私立大学(文系) | 私立大学(理系) | |
|---|---|---|---|
| 入学費用 | 672,000円 | 818,000円 | 888,000円 |
| 在学費用(4年間) | 4,140,000円 | 6,080,000円 | 7,328,000円 |
| 合計 | 4,812,000円 | 6,898,000円 | 8,216,000円 |
※入学費用には、受験費用、入学金、入学しなかった学校への納付金が含まれます。
※在学費用には、家庭教育費が含まれます。
出典:「令和3年度 教育費負担の実態調査結果」(日本政策金融公庫)
大学に通うと、生活費(交通費・住居費・光熱費・交際費など)やパソコン購入代など学費以外の費用がかかることも考えなければなりません。
大学でかかる教育費や生活費は、進路や自宅・自宅外通学により大きく変わってきますが、いずれにしても短期間で用意できる金額ではないため、計画的に用意しておくことが大切です。
児童手当を使わずにすべて貯蓄すれば、大学の教育費の一部をまかなえます。
教育資金に備えるなら
学資保険がおすすめ
学資保険なら、必要なタイミングにあわせて教育資金を用意できます。学資保険とは、子どもの教育費に備えるための貯蓄型保険です。
原則として親が契約者、子どもが被保険者として加入し、子どもの入学や進学にあわせて教育資金や満期保険金が受け取れます。
受け取れる教育資金や満期保険金の金額や受け取るタイミングは、商品やプランによりさまざまです。
学資保険には、主に以下のおすすめポイントがあります。
- 計画的に教育費を用意できる
- ご契約者が万一の場合、保険料の払込免除がある
- 生命保険料控除の対象になる
【学資保険のおすすめポイント1】
計画的に教育費を用意できる
学資保険は、契約時に決めた時期まで保険料を払い込むことで、子どもが小学校・中学校・高校に入学したときや大学入学・進学のタイミングでまとまった教育資金を受け取れる保険です。
毎月の保険料を口座からの自動引き落としで払い込むことができる場合も多く、着実に教育費を用意できます。
学資保険の場合は、契約の時点で受け取れる教育資金の金額が確定しているので安心です。また、解約などには手続きが必要となり、簡単には引き出せないため、将来のための教育費に手をつけてしまうリスクも抑えられます。
さらに、払い込んだ保険料よりも高い金額を受け取れる可能性があります。
【学資保険のおすすめポイント2】
ご契約者が万一の場合、保険料の払込免除がある
契約者である親の万一に備えた保障がついている点も、学資保険の特徴です。一般的に学資保険では、契約者である親が死亡・高度障害状態になった場合、それ以降の保険料払込みが免除されます。
払込みが免除されたあとも保障が続き、教育資金・満期保険金は予定どおり受け取れるため安心です。
【学資保険のおすすめポイント3】
生命保険料控除の対象になる
学資保険は、生命保険料控除の対象になります。生命保険料控除とは、払い込んだ保険料額に応じて、所得控除が受けられるものです。
生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があり、それぞれにつき所得税最高40,000円(※1)、住民税最高28,000円を所得から差し引けます。3つ合計で、所得税120,000円、住民税70,000円が上限です。
(2012年1月1日以後に締結した保険契約の場合。 2011年12月31日以前に締結した保険契約は取扱いが異なります。)
生命保険料控除が適用されれば、差し引いた控除額だけ課税所得金額が低くなるため、所得税・住民税の負担を抑えられます。
(※1)2026年の1年間所得税のみ、23歳未満扶養親族ありの場合は一般生命保険料控除の上限が6 万円になります。
なお、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計適用限度額(所得税)は、他の世帯と同様12万円で変更ありません。
教育資金を計画的に用意できる
「明治安田生命つみたて学資」
「明治安田生命つみたて学資」は、お子さまの進学にあわせて教育資金を着実に受け取れる学資保険です。大学などの時期に合計4回、教育資金・満期保険金が受け取れます。
保険料の払込みは長くても15歳までで終了し、費用がかさむ大学などの時期にあわせて教育資金を確実にお受け取りいただけます。ご契約時のお子さまの年齢が2歳以下の場合は、払込みを10歳までとすることも可能です。
また、ご契約者に万一のことがあると、保険料の払込みが免除されます。免除されたあとも、払込みがあったものとして保障が継続するので安心です。
「明治安田生命つみたて学資」は、お子さまの出生予定日の140日前からお申込みが可能です。お申込みの年齢が低いほど、長い積み立て期間を確保できるため、毎月の保険料の負担を抑えて教育資金に備えられます。
※当ページは、「ご案内ブックレット」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
児童手当は、出生から高校生年代までの子どもを養育している人が受給できる手当です。
教育費は、住宅資金、老後資金とあわせて人生の三大資金といわれます。とくに、大学は多くの費用がかかるため、早くからの備えが必要です。教育費に備えるなら、必要なタイミングで教育資金を用意できる学資保険もご検討ください。
募Ⅱ2501695 ダイマ推