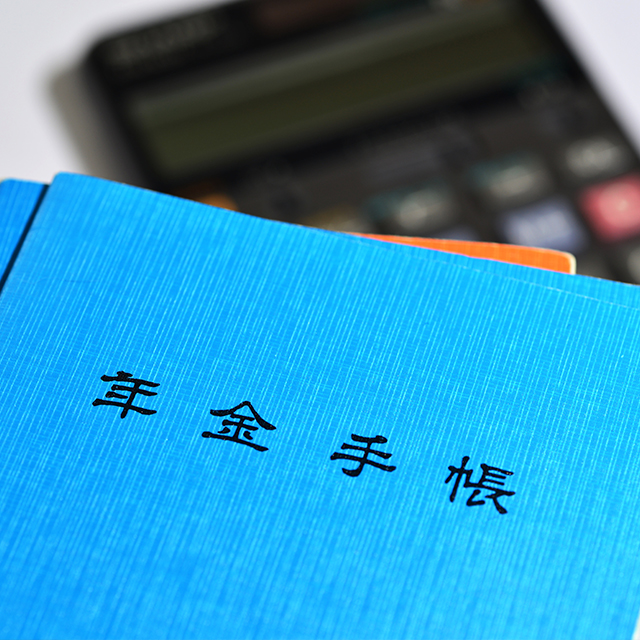子どものための預貯金はいくら用意すべき?
教育費の目安と準備方法を解説
子どもの成長を感じると嬉しいものですが、経済面で不安に感じている人もいるのではないでしょうか。
子どもにかかる教育費は大きな金額になりますが、「実際のところいくら必要なの?」「いくら預貯金すればいい?」とさまざまな疑問が生じます。
この記事では、子どもの教育費の目安を紹介し、いくら預貯金すべきなのか、どのような方法で準備できるのかを解説します。
子どもの将来に向けて計画的に準備したい人は、ぜひ参考にしてください。

子どもの教育費はいくらかかる?
子育てには、教育費や食費、日用品費、医療費、保育費、携帯電話料金などさまざまな費用がかかります。なかでも大きな割合を占めるのが教育費です。
子どもを1人育てるのに数千万円かかると言われますが、教育費がどのくらいかかるのかイメージできない人もいるでしょう。
そこで、幼稚園から大学までにかかる教育費の目安を紹介します。
幼稚園~大学までの教育費
文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」をもとに、幼稚園~高校までにかかる教育費の目安をまとめました。
| 区分 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 495,378円 | 926,727円 |
| 小学校 | 2,115,396円 | 10,001,694円 |
| 中学校 | 1,616,397円 | 4,309,059円 |
| 高校 | 1,538,913円 | 3,163,332円 |
| 合計 | 5,766,084円 | 18,400,812円 |
出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」をもとに作成
幼稚園~高校にかかる教育費を国公立と私立で比べてみると、大きな差があることが分かります。
また、日本政策金融公庫の「令和3年度 教育費負担の実態調査結果」によると、大学に4年間通ったときの教育費の目安は以下のとおりです。
| 国公立大学 | 私立大学(文系) | 私立大学(理系) | |
|---|---|---|---|
| 入学費用 | 672,000円 | 818,000円 | 888,000円 |
| 在学費用 | 4,140,000円 | 6,080,000円 | 7,328,000円 |
| 合計 | 4,812,000円 | 6,898,000円 | 8,216,000円 |
出典:日本政策金融公庫「令和3年度 教育費負担の実態調査結果」をもとに作成
上記をみると、私立大学(理系)は国公立大学の約1.7倍の費用がかかっています。
教育費は進路によって大きく異なる
上記の教育費をもとに、進路別の教育費の目安をまとめました。
| 区分 | すべて公立 | 高校まで公立 | 中学校まで公立 | 小学校まで公立 | すべて私立 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 495,378円 | 495,378円 | 495,378円 | 495,378円 | 926,727円 |
| 小学校 | 2,115,396円 | 2,115,396円 | 2,115,396円 | 2,115,396円 | 10,001,694円 |
| 中学校 | 1,616,397円 | 1,616,397円 | 1,616,397円 | 4,309,059円 | 4,309,059円 |
| 高校 | 1,538,913円 | 1,538,913円 | 3,163,332円 | 3,163,332円 | 3,163,332円 |
| 大学 | 4,812,000円 | 6,898,000円 (私立文系) |
6,898,000円 (私立文系) |
6,898,000円 (私立文系) |
6,898,000円 (私立文系) |
| 合計 | 10,578,084円 | 12,664,084円 | 14,288,503円 | 16,981,165円 | 25,298,812円 |
このように、教育費は子どもの進路によって大きく異なります。
幼稚園から大学までにかかる教育費は、すべて公立の場合で約1,000万円、すべて私立だと2,500万円以上になる計算です。また、自宅通学か下宿かによって生活費も大きく変わります。
子どものためにいくら預貯金するべき?
公立であれば、高校までは毎月の収入からやりくりする方法もありますが、大学は特に費用がかさみます。
国公立大学で約500万円、私立大学で約700~800万円程度かかるため、ある程度まとまった金額を用意しておかなくてはなりません。
例えば、大学入学までに入学費用と大学2年目までの教育費を預貯金する場合、必要な金額は約250~450万円です。
また、大学4年間の教育費を用意する場合は、約400万円(公立)を預貯金する必要があります。
また、子どもが中学校を卒業するまで支給される児童手当を預貯金するのも手段の一つです。
ここでは、預貯金する金額の目安として児童手当で受け取れる合計金額と20~40歳代の預貯金額を紹介します。
児童手当を預貯金すれば約200万円用意できる
児童手当とは、中学校卒業までの児童を養育している人に支給される手当です。支給額は、児童の年齢に応じて決まっています。
| 児童の年齢 | 支給額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上小学校終了前 | 10,000円 (第3子は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
出生後、中学生が終わるまでに受け取れる児童手当の金額を合計すると、約200万円です。児童手当は「15歳の誕生日を迎えたあとの最初の3月31日」まで支給されるため、誕生月によって総額に数万円の差が生じます。
なお、児童手当の支給額は月額で決まっていますが、毎月入金されるわけではありません。原則として、年3回(6・10・2月)に分けてそれぞれの前月分までの手当が支給されます。
20歳代の預貯金額は平均約339万円
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和4年)」によると、20歳代~40歳代の預貯金保有額は以下のとおりでした。
| 年代 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 20歳代 | 約339万円 | 約200万円 |
| 30歳代 | 約697万円 | 約390万円 |
| 40歳代 | 約1,132万円 | 約500万円 |
出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和4年)」
20歳代の場合、預貯金保有額は平均約339万円、中央値約200万円です。平均値は、大きく離れた数値に影響を受けやすいため、必ずしも実態を示しているとは言えません。参考程度に捉えるといいでしょう。
なお、中央値はデータを大きい順に並べたときに真ん中にくる値で、大きく離れた数値に影響されにくい数値です。
子どものための預貯金で注意すべきこと
親が「子どもの将来のために」とお金を準備する際に知らずにいると、税金がかかってしまう、要件を満たさず児童手当を受け取れないなどの事態が起きかねません。
子どものためのお金を用意する際は、以下の点に注意しましょう。
- 子ども預貯金用の口座は分ける
- 贈与税がかかる場合がある
- 児童手当制度には所得制限がある

子ども預貯金用の口座は分ける
子どもの預貯金用口座は、生活費や親の預貯金用の口座とは分けて開設しましょう。生活費を支払っている口座で子どもの預貯金をしていると、いくら貯まっているのかが分からず、計画的に教育費を準備できません。
子ども用の口座を分けて管理すれば、目標に対してどれだけ達成できているかが可視化でき、管理しやすくなります。
なお、親名義の口座、子ども名義の口座のどちらで管理してもよいですが、次で説明する贈与税には注意しましょう。
贈与税がかかる場合がある
貯めたお金を子どもにわたす際、贈与税がかかる場合があります。贈与税は、1年間に贈与された金額が110万円までであればかかりません。
親が子ども名義の口座を開設して管理している場合、子どもにわたすまでは贈与とみなされません。
しかし、子どもが大きくなり、口座を引き継いだタイミングで110万円を超えていれば、贈与税がかかってしまいます。
贈与税がかからないようにするには、子ども自身がキャッシュカードを管理するなどの対策が必要です。
※税法上の取扱いについては2023年6月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更の伴い取扱いが変わる場合があります。
児童手当制度には所得制限がある
児童手当を積み立てれば教育費の一部をまかなえますが、児童手当制度には所得制限が設けられています。
| 扶養家族等の人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 | |
| 0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
| 1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
| 2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
| 3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
| 4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
| 5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
保護者の所得が「所得制限限度額以上所得上限限度額未満」の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。また、「所得上限限度額以上」の場合、児童手当は支給されません。
所得制限の撤廃について議論などもなされていますが、制度が今後どのように変わるかは現時点では分かりません。
※制度に関する記載は2023年6月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
預貯金する以外にも教育費を準備する方法はある
子どもの教育費を用意する方法は、預貯金以外にもいくつかあります。
- 奨学金
- 教育ローン
- NISA
- 学資保険
奨学金
奨学金とは、経済的な理由で進学できない学生を援助するために、学費の給付や貸与を行なう制度です。日本学生支援機構や地方公共団体、大学などの機関が実施しています。
最も一般的な日本学生支援機構の奨学金は、「給付型(返済不要)」と「貸与型(返済必要)」の二種類です。また、貸与型には「第一種奨学金(無利子)」と有利子の「第二種奨学金(有利子)」があります。
奨学金は無利子または低金利なので、教育費を借りたいときにまず検討したい手段です。ただし、親の収入基準・学力基準を満たさなければ利用できない点や、申込みの時期が決まっている点には注意しましょう。
※制度に関する記載は2023年6月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
教育ローン
教育ローンは、教育費や在学にかかる費用を借入れできるローンです。大きく以下の二つに分けられます。
- 国の教育ローン(教育一般貸付)
- 民間金融機関の教育ローン
必要なタイミングで申込でき、学校や塾に納付する費用だけでなく在学に必要な住居にかかる敷金・礼金など、幅広い使途に充てられるのが特徴です。
国の教育ローンは民間金融機関に比べて金利が低い傾向にありますが、扶養している子どもの人数に応じて所得制限があります。
また民間金融機関の教育ローンは、一般的に所得制限はありませんが、年収の下限や勤続年数に基準が設けられているものもあるため、事前に確認しましょう。
また、教育ローンの金利はカードローンやクレジットカードのキャッシング機能と比べて低めですが、奨学金と比べると高い傾向があります。
NISA
NISAとは、一定額までなら投資で得られる配当金や売却益が非課税になる制度で、2014年からはじまりました。
現行の制度では、一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの3種類に分かれており、一般NISAとつみたてNISAの併用はできません。
2024年からは現行の制度よりも、抜本的拡充・恒久化された新NISA制度が導入される予定です。
NISAは長期の積立投資に適しており、得た利益は任意のタイミングで現金化することができます。そのため、NISAは子どもの教育費に備える方法としても活用できます。
ただし、元本が保証されていないため、運用結果によっては期待していた教育費を用意できないケースもある点には注意が必要です。
※制度に関する記載は2023年7月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
学資保険
学資保険は、子どもの教育費を準備するための貯蓄型保険です。原則親が契約者として毎月決められた保険料を払い込み、契約時に決めたタイミングで教育資金を受け取れます。
入学のたびに教育資金を受け取れるプラン、費用がかさみやすい大学の時期に毎年教育資金を受け取れるプランなど、受け取るタイミングはさまざまです。
学資保険の特徴は、いざというときの保障が得られる点です。親に万一のことがあった場合、以降の保険料の払込みが免除されます。
払込みが免除されたあとも保障はそのまま継続し、教育資金を受け取れます。
預貯金の場合、親に万一のことがあるとその時点で積み立てが止まってしまい、それ以上の金額を用意することはできません。
教育資金を計画的に準備するなら
「明治安田生命つみたて学資」
「明治安田生命つみたて学資」は、お子さまの成長にあわせて教育資金を受け取れる学資保険です。
保険料の払込みは長くても15歳で終了し、大学の時期などに合計4回、教育資金を受け取れます。そのため、費用がかさみやすい時期の負担軽減が可能です。
また、ご契約者に万一のことがあると保険料の払込みが免除されます。払込みが免除されたあとも保障は継続するため、いざというときに備えたい人にもご利用いただけます。
「明治安田生命つみたて学資」は、お子さまの出生予定日の140日前からお申込みが可能です。ぜひご検討ください。
※保険商品をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
子ども1人につき、幼稚園から大学まですべて公立で約1,000万円、すべて私立だと2,000万円以上の教育費が必要です。
子どものための預貯金は、早く始めるほど長い期間をかけて用意できるため、毎月の預貯金額が少なくて済みます。教育費の目安を知り、ご家庭の状況にあった方法で計画的に準備しましょう。
教育費を確実に準備したい人は、保障を得ながら必要なタイミングで教育資金を受け取れる学資保険もご検討ください。
募Ⅱ2300982ダイマ推