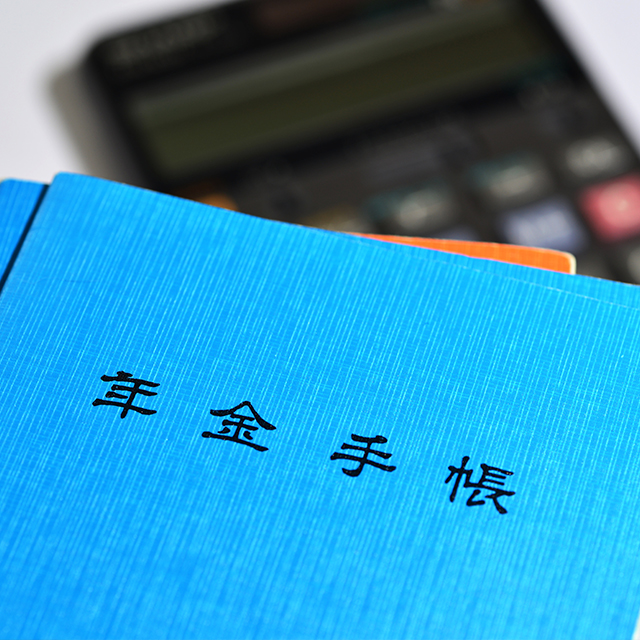老後の生活にお金はいくら必要?
生活費や年金受給額、老後資金の準備方法を解説
40代・50代になると、老後の生活が近い将来として現実味を帯びてきます。60代以降のライフプランニングを具体的に考えたい時期です。
公的年金が主な収入源となる老後の生活に向けて、いくら備えるべきか考える人も多いでしょう。老後資金に必要な金額は希望するライフスタイル次第で異なりますが、いずれにしても前もって準備する必要があります。
この記事では、老後の生活費や生活費以外に必要なお金、公的年金の受給額を解説します。ぜひ、老後資金に備える際の参考にしてください。

老後の生活費は1ヵ月にいくら必要?
老後の生活費は、月々いくらかかるのでしょうか。
総務省の家計調査では、1ヵ月あたりの支出の平均額を項目別にまとめています。2022年の平均結果から65歳以上の無職世帯のデータを参考に、老後に必要な生活費を解説していきます。
ただし、この記事で示す数値は2022年の調査でわかった平均値です。実際に必要な生活費は、住む地域やライフスタイルなど人それぞれ異なります。また、今後の物価変動などさまざまな要因によっても変動することが考えられます。目安の一つとしてとらえましょう。
65歳以上の一人暮らし世帯の生活費は毎月約14.3万円
総務省統計局の家計調査の2022年平均結果によると、65歳以上の単身無職世帯は月々の平均消費支出額が143,139円でした(※)。消費支出とは、生活に必要な商品やサービスの支出で、税金や社会保険料などは含みません。
| 項目 | 月平均額 | |
|---|---|---|
| 食料 | 37,485円 | |
| 住居(※1) | 12,746円 | |
| 光熱・水道 | 14,704円 | |
| 家具・家事用品 | 5,956円 | |
| 被服及び履き物 | 3,150円 | |
| 保健医療(※2) | 8,128円 | |
| 交通・通信 | 14,625円 | |
| 教育 | 0円 | |
| 教養娯楽 | 14,473円 | |
| その他の消費支出 | 諸雑費 | 13,595円 |
| 交際費 | 17,893円 | |
| 仕送り金 | 341円 | |
| 消費支出合計 | 143,139円 | |
※1 現住居,現住居以外の住宅及び宅地に関するもの並びにこれらに伴うサービスに対する支出
※2 入院費を含む
※出典:総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2022年(令和4年)平均結果の概要」をもとに作成
また、同調査によると、65歳以上の単身無職世帯の月々の税金や社会保険料の負担額は、平均12,356円です。
税金や社会保険料の負担、趣味や娯楽に使うお金を考えると、月に約15.5万円は必要でしょう。
※出典:総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2022年(令和4年)平均結果の概要」
65歳以上の夫婦二人世帯の生活費は毎月約23.6万円
総務省統計局の家計調査の2022年平均結果によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯は月々の平均消費支出額が236,696円でした(※)。
| 項目 | 月平均額 | |
|---|---|---|
| 食料 | 67,776円 | |
| 住居(※1) | 15,578円 | |
| 光熱・水道 | 22,611円 | |
| 家具・家事用品 | 10,371円 | |
| 被服及び履き物 | 5,003円 | |
| 保健医療(※2) | 15,681円 | |
| 交通・通信 | 28,878円 | |
| 教育 | 3円 | |
| 教養娯楽 | 21,365円 | |
| その他の消費支出 | 諸雑費 | 19,818円 |
| 交際費 | 22,711円 | |
| 仕送り金 | 1,334円 | |
| 消費支出合計 | 236,696円 | |
※1 現住居,現住居以外の住宅及び宅地に関するもの並びにこれらに伴うサービスに対する支出
※2 入院費を含む
※出典:総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2022年(令和4年)平均結果の概要」をもとに作成
また、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の税金や社会保険料の月々の負担額は、平均31,812円です。
税金や社会保険料の負担、趣味や娯楽に使うお金を考えると、月に約27万円は必要でしょう。
老後に必要なお金は生活費以外に何がある?
老後の生活費は一人暮らしで毎月約14.33万円、夫婦2人暮らしで毎月約23.6万円でした。
しかし、生活費以外のお金は含まれていません。生活費以外にも、老後の生活には次の費用を考えておく必要があります。
- 税金や社会保険料
- 自宅のリフォームや修繕費
- 手術や入院、通院などの医療費
- 介護や施設に入った場合の費用
- 葬儀やお墓の費用
税金や社会保険料
年金生活者になっても、税金や社会保険料の負担は発生します。
| 65歳以上の無職世帯 | 一人暮らし | 夫婦二人暮らし |
|---|---|---|
| 直接税 | 6,660円 | 12,854円 |
| 社会保険料 | 5,625円 | 18,945円 |
| 合計 | 12,356円 | 31,812円 |
※出典:総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2022年(令和4年)平均結果の概要」
表にまとめた金額は、家計調査の2022年の平均結果です。現在40代・50代の人が65歳以降となる10年後や20年後には、さらに負担金額が増加している可能性もあります。
住宅のリフォームや修繕費
住居が持ち家の場合、老後に住む場所を心配せずに済みますが、必要に応じてバリアフリー化や修繕をするケースもあるでしょう。
室内の段差解消や手すりを設置するほか、老朽化した箇所を修理または改装する場合の費用が必要です。あるいは、子ども世帯と二世帯で暮らすために、自宅をリフォームするケースも考えられます。
住宅リフォーム推進協議会の調査では、世帯主50代以上の家庭がリフォームした場合の費用は平均286.4万円でした(※)。
ただし、自宅のリフォームや修繕にかかる費用は、内容や規模、自宅の状態によって大きく異なります。部分的なリフォームなら数十万円程度で済むこともありますが、大がかりな改修をする場合は数百万円の費用がかかるでしょう。
※出典:住宅リフォーム推進協議会「2022年度 住宅リフォームに関する消費者(検討者・実施者)実態調査結果報告」
入院費
前述した月々に必要な生活費には入院費も含まれていますが、実際に入院するともっと多くの費用がかかります。
生命保険文化センターの調査結果によると、入院時の自己負担費用(※1)は平均19.8万円です(※2)。
また、入院日数の平均は17.7日ですが、60代は平均18.8日、70代は20.5日と高年齢になるほど入院日数が長くなる傾向にあります。入院日数が長くなれば、入院にかかる自己負担費用も高くなります。
生活費のほかに、入院が必要になったときのための費用も備えておくことが大切です。
※1 治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や 衣類、日用品などを含む。高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額
※2出典:生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」
介護や施設に入った場合の費用
老後は病気やケガだけでなく加齢による身体の衰えから、介護が必要になる場合もあります。
介護が必要になり、介護施設を利用すると別途、居住費や食費、日常生活費の負担が発生します。
2021年度の生命保険文化センターの調査結果によると、月々の介護費用は平均8.3万円、介護に要した一時的な費用の合計は平均74万円でした(※)。
介護保険サービスを利用した場合、利用者の負担金額は1割(一定以上の所得の場合は2割または3割)に抑えられていますが、要介護度別に限度額が定められています。
所得が低い人や1ヵ月の利用料が高額になった場合の負担軽減措置があるものの、介護が必要になった場合の備えも考えておく必要があるでしょう。
また、自宅での介護が難しい状況になった場合、介護老人福祉施設などへの入所を検討する場合もあるでしょう。入所費用や月々の費用は施設ごとに差が大きいため、老後のライフプランを立てるうえで考えておきたい事柄です。
出典:生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」
葬儀やお墓の費用
自身や配偶者に万一のことがあった場合、残された家族に負担をかけないよう葬儀費用やお墓を準備しておきたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
葬儀費用は地域や規模、内容によって大きく変わりますが、消費者契約法専門調査会の資料によると2017年の全国平均金額は195.7万円です(※)。家族中心の簡素な内容で済ませるなら、数十万円で葬儀を行なえる場合もありますが、いずれもまとまったお金が必要です。
また、お墓に関しては先祖代々のお墓か、お寺の共同墓に入るのか、あるいは個人のお墓を建てるのかなどで費用は異なります。
そのときになってから遺族が困らないよう、早い段階から家族と話しあっておくことが大切です。
公的年金の平均受給額はいくら?
2021年度の厚生年金の平均受給額は、併給する国民年金の老齢基礎年金とあわせて、月額143,965円でした。なお、国民年金の平均受給額は月額56,368円です(※1)。
厚生年金は加入期間と納めた金額が反映されるため、人によって受給額が大きく異なります。
また、国民年金は納付期間によって受給額が異なり、満額でもらえる場合の受給額は2021年度で月額65,075円でした(※2)。
一人暮らしの生活費約14.3万円・夫婦二人暮らしの生活費約23.6万円のみなら、公的年金の平均受給額でもまかなえる人もいるでしょう。しかし、税金や社会保険料の支払い、生活費以外の費用、老後の娯楽なども含めて考えると、十分な金額ではありません。
厚生年金と国民年金の平均受給額だけでは不足する部分を補う、老後資金を準備する必要があります。
※1出典:厚生労働省年金局「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
※2出典:日本年金機構「令和3年4月分からの年金額等について」
※年金制度に関する記載は2023年6月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
老後資金を準備する方法
公的年金だけでは、老後の生活に必要なお金が不足する可能性があると判明しました。不足に備えて、何らかの方法で老後資金を準備したいところです。
老後資金の準備方法には、預貯金や資産運用、貯蓄型保険への加入などが考えられますが、それぞれの特徴が異なります。準備方法は一つだけに限定せず、複数の方法をバランス良く組み合わせて備える方法がおすすめです。

退職金を老後資金にあてる
老後資金は退職金でまかなおうと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、勤め先ごとに退職金制度は異なり、誰もが同じ金額を受け取れるわけではありません。
多くの企業が退職金制度を設けていますが、なかには退職金制度がない企業も存在します。退職金制度がある企業でも、勤務年数や役職、人事評価などで受け取れる金額が変化し、制度内容もさまざまです。
退職金を老後の生活に使うなら、勤め先の制度内容を確認し、受け取れる見込額を把握しましょう。
なお、自営業の場合は退職金自体が存在しないため、退職金以外の方法で老後資金を準備する必要があります。
老後資金に備えて貯蓄する
早い段階から老後に必要な資金を考えて、貯蓄する方法もあります。会社員や自営業などの働き方にかかわらず、誰でも取り組める方法です。
老後資金を貯蓄する場合は普通預金より定期預金など、すぐに引き出せない方法がおすすめです。
NISAやiDeCoを活用して資産運用する
NISAやiDeCoを活用し、資産運用で老後資金を準備するのも選択肢です。
NISAは、枠内での運用であれば売却益や配当に課税されない制度です。iDeCoは自身で積み立てて運用した資産を65歳以降に受け取れる制度で、NISAと同じく税法上の優遇措置もあります。
運用結果が良ければ、多くの利益を期待できますが、投資である以上、損失リスクは避けられません。運用結果が悪いと資金不足に陥る可能性もあるため、投資する金融商品はよく考えて決めることが重要です。
※制度に関する記載は2023年6月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
貯蓄型の積立保険に加入する
貯蓄型保険とは、保険料を積み立てて満期保険金や解約返戻金を受け取れる貯蓄型の保険です。
貯蓄型の保険に加入し、老後資金に備えるのも選択肢の一つです。
払込期間や保険期間、受取率は保険商品ごとに異なりますが、老後資金の準備に使える保険もあります。ほかの準備方法とも比較し、加入を検討してみましょう。
※受取率とは、払込保険料の累計額に対する満期等までの受取総額の割合をいいます。
積立保険なら「明治安田生命じぶんの積立」
「明治安田生命じぶんの積立」は、月々5,000円から積み立てられる保険です。
健康状態にかかわらず加入でき、加入時の告知も必要ないため、健康に不安のある人や持病のある人も利用できます。
保険料の払込みは5年間で終わり(保険期間は10年間)、解約時の返戻率も満期保険金の受取率も100%以上です。
幅広い用途で利用できるため、40代・50代の人が今から老後資金を積み立てる場合も使えます。
※保険商品をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
老後に必要な生活費の金額は、一人暮らしで毎月約14.3万円、夫婦二人で毎月約23.6万円です。税金や社会保険料の支払いや住居のリフォーム、入院や介護の費用を加えると、公的年金だけでは不足することが予想されます。
不足を補うための老後資金を準備する方法には、退職金を使うほか預貯金や資産運用、積立保険への加入などが考えられます。必要な金額を考え、自分にあった方法で準備しましょう。
老後の備えとして必要な金額は、希望するライフスタイル次第で大きく異なります。早い段階から計画を立て、老後の生活に備えましょう。
募Ⅱ2300938ダイマ推