
自分は年金をいくらもらえる?
受給額の平均や計算方法、年金を増やす方法を解説
年金は、老後の生活を支える大切な存在です。将来もらえる年金の金額はいくらなのか、気になる人も多いでしょう。
将来もらえる年金額に不安があるなら、何らかの方法で備えなければなりません。
本記事では公的年金でいくらもらえるか、年金制度の基本をおさらいしつつ年金額の平均や計算方法を解説します。年金を増やす方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※本記事は、2023年10月現在の内容です。
※年金制度に関する記載は2023年10月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

公的年金制度の基本をおさらい
公的年金制度は社会保障制度の一つであり、老齢年金・遺族年金・障害年金があります。なかでも老齢年金は、原則として65歳以降に受給できる終身年金であるため、多くの人にとって老後の生活を支える存在です。
また、公的年金は国民年金(基礎年金)と厚生年金に分かれた2階建て構造です。
国民年金は20歳以上60歳未満が全員加入し、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に分かれています。
- 第1号被保険者:農業者や自営業者、学生、無職の人など
- 第2号被保険者:会社員や公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者
第2号被保険者に該当する会社員や公務員の人は、国民年金に加えて厚生年金にも加入します。厚生年金へ加入し、保険料を納付していた期間がある人は、将来国民年金と厚生年金の両方を受け取れます。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などをあわせた受給資格期間が10年以上あると、原則として65歳以降に受給できます。
老齢厚生年金は厚生年金への加入期間があれば、老齢基礎年金に上乗せして原則65歳以降に受け取れます。
年金受給額は平均でいくらもらえる?
将来もらえる年金額は加入期間や保険料納付済期間によって異なり、厚生年金は受け取っていた報酬の金額も影響します。
次の表は2021年度の国民年金・厚生年金で、平均年金額を5歳刻みでまとめた月額です。
| 平均老齢年金月額(2021年度末時点) | 国民年金 | 厚生年金 |
|---|---|---|
| 60~64歳(繰上げ受給) | 42,512円 | 77,274円 |
| 65~69歳 | 57,739円 | 143,613円 |
| 70~74歳 | 57,127円 | 144,357円 |
| 75~79歳 | 56,100円 | 148,293円 |
| 80~84歳 | 56,607円 | 157,500円 |
| 85~89歳 | 55,921円 | 161,541円 |
| 90歳以上 | 51,382円 | 160,460円 |
出典:厚生労働省年金局「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに作成
なお、60~64歳で年金をもらっている人は、受給開始を前倒しする「繰上げ受給」をしています。繰上げ受給では、繰り上げた月数に応じてもらえる年金額が減少します。
ほかの年齢と比べて少ない年金額になっている理由は、繰上げ受給の影響があるためです。
もらえる年金額の計算方法
年金がいくらもらえるかは、保険料を払い込んだ期間や納めた金額に応じて変化します。保険料を長く・多く納めていた人ほど、もらえる年金額は増加します。
また、厚生労働省の公的年金シミュレーターでは、加入期間や年収などからもらえる年金額の簡単な試算が可能です。自分はいくら年金をもらえるか気になる人は、活用するとよいでしょう。
以下では、国民年金と厚生年金に分けて、計算方法を解説します。
国民年金(老齢基礎年金)の計算方法
国民年金の場合、もらえる年金額の計算式は以下のとおりです。
老齢基礎年金の年金額=その年の老齢基礎年金の満額×保険料納付済月数÷480月
国民年金保険料を納付できていない期間があると、もらえる金額は減少します。
また、老齢基礎年金の満額は、賃金や物価の変動に応じて毎年改定が行なわれます。年度ごとに改定されるため、老齢基礎年金の満額は常に一定ではありません。
なお、2023年度の国民年金でもらえる金額は、満額で795,000円(月額66,250円)でした。
厚生年金(老齢厚生年金)の計算方法
厚生年金の場合、加入期間と納付した年金保険料の金額でもらえる年金額が変化します。給与を多く受け取っている人は、厚生年金保険料も多く負担しているためです。
また、A:2003年3月以前の加入期間と、B:2003年4月以降の加入期間とで、計算時に使用する係数が異なります。A・Bの合計で、老齢厚生年金の基礎となる報酬比例部分を計算します。
A=平均標準報酬月額(※1)×(7.125×1000)×2003年3月までの厚生年金加入月数
B=平均標準報酬額(※2)×(5.481×1000)×2003年4月以降の厚生年金加入月数
※1 平均標準報酬月額は、2003年3月以前の加入期間に関して、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を2003年3月以前の加入期間で割って算出した金額です。
※2 平均標準報酬額は、2003年4月以降の加入期間に関して、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、2003年4月以降の加入期間で割って算出した金額です。
もらえる年金を増やす7つの方法
将来もらえる年金額に不安を感じる人は、年金を増やす方法も検討しましょう。将来もらえる年金額を増やす主な方法は、以下のとおりです。
1. 年金を繰下げ受給する
2. 任意加入や追納で国民年金保険料を納める
3. 厚生年金に長く加入して保険料を多く払い込む
4. 付加年金で年金を上乗せする
5. 国民年金基金に加入する
6. 確定拠出年金(iDeCo)に加入する
7. 個人年金保険に加入する
以下では、7つの方法に関してそれぞれ詳しく解説します。
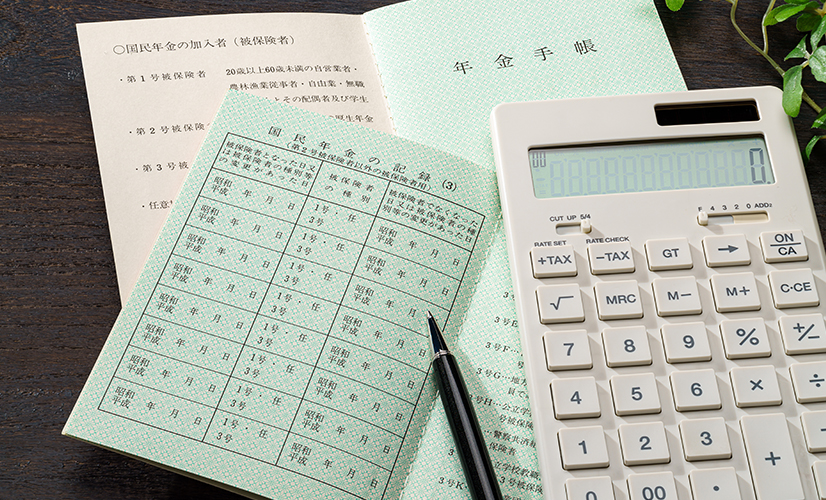
1.年金を繰下げ受給する
老齢年金は国民年金・厚生年金ともに受給開始を遅くする「繰下げ受給」をすれば年金額が増加します。
現在の制度では、66歳から75歳までの間で繰り下げ可能です。繰り下げるほど加算される金額は多くなり、増額率は生涯変わりません。
繰下げ受給による増額率は、以下の計算式で算出できます。
繰下げ受給による増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申請月の前月までの月数
年金の受給開始を75歳まで繰下げると120ヵ月の繰り下げで、年金額を84%まで増加できます。
ただし、繰下げ受給すると年金をもらえるまでの期間が長くなります。年金を受給開始するまでの間に必要な生活費などを、貯蓄や年金以外の収入でまかなえるのか考えておかなければなりません。
2.任意加入や追納で国民年金保険料を納める
国民年金は納付できなかった期間や加入していない期間があると、その分もらえる年金額が少なくなります。しかし、任意加入や追納でもらえる老齢基礎年金を増やすことができます。
任意加入制度では、60歳以降も国民年金保険料を納めると、納付月数を増やせます。納付できなかった期間や加入できていない期間がある人は、任意加入を検討しましょう。
免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けていた人は、その期間の保険料を追納すれば年金額を増やせます。ただし、追納が可能なのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限定されているため注意が必要です。
3.厚生年金に長く加入して保険料を多く払い込む
国民年金は年金額の満額が決まっていますが、厚生年金は加入期間と受け取っていた報酬でもらえる金額が変化します。
長く会社に勤め、厚生年金への加入期間が長ければ、老齢厚生年金でもらえる金額が増加します。定年退職後も雇用されて厚生年金への加入を続ければ、厚生年金で受け取れる年金額を増やせます。
また、昇進や昇給で報酬が多くなることでも、将来もらえる厚生年金も増加します。
4.付加年金で年金を上乗せする
定額の保険料とあわせて月額400円の付加保険料を収めると、老齢基礎年金に付加年金を上乗せができます。将来もらえる年金額に200円×付加保険料納付月数が上乗せされます。
ただし、付加年金は第1号被保険者・任意加入被保険者が対象です。また、後述する国民年金基金に加入している場合は、付加保険料の納付はできません。
5.国民年金基金に加入する
国民年金基金に加入すると、将来もらえる年金に上乗せできます。
第1号被保険者の自営業者やフリーランスの人は厚生年金に加入していないため、厚生年金をもらえません。しかし、国民年金基金へ加入すれば、もらえる年金を増やせます。
また、掛金は社会保険料控除の対象なので、税金の負担軽減が期待できます。
※税法上の取扱いについては2023年10月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更の伴い取扱いが変わる場合があります。
6.個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する
確定拠出年金(iDeCo)は、自分で掛金を拠出して運用することで、運用結果に応じた老齢給付金を60歳以降に受け取れる制度です。
iDeCoは20歳以上65歳未満ならば加入でき、以下3点の税法上の優遇を受けられる制度です。
- iDeCoの掛金は所得控除の対象になる
- 運用益は非課税で再投資できる
- 受取時は所得控除を受けられる
ただし、60歳以降に受け取れる金額は、運用結果に左右されます。結果が思わしくない場合、想定していた金額を受け取れない可能性もあるため注意が必要です。
※税法上の取扱いについては2023年10月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更の伴い取扱いが変わる場合があります。
7.個人年金保険に加入する
個人年金保険とは、公的年金へ上乗せして将来受け取る年金を準備するために加入する保険です。払い込んだ保険料を積み立てて、契約時に定めた年齢から年金を受け取れます。
年金を受け取れる期間や受取前に死亡した場合の保障などは、商品ごとに内容は異なります。加入の際は、商品の性質や契約内容を十分に確認しましょう。
「明治安田生命じぶんの積立」は老後資金の準備にも役立ちます
「明治安田生命じぶんの積立」は、月々5,000円から積み立てられる貯蓄型の保険です。
健康状態にかかわらず申込みが可能で、幅広い目的に備えられます。
また、いつ解約しても100%以上の返戻率のため、安心して積み立てられます。
老後資金に備える方法の一つとして、ぜひご検討ください。
※保険商品をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
65歳以降にもらえる公的年金には、国民年金と厚生年金があります。もらえる金額は加入状況や負担してきた年金保険料で異なります。
厚生労働省の公的年金シミュレーターでは、もらえる年金額の簡単なシミュレーションが可能です。いくらもらえるか気になる人は、参考にするとよいでしょう。
また、将来もらえる年金を増やす方法も存在します。受給額が不安な人は、年金を増やす方法を検討しましょう。
募Ⅱ2500739ダイマ推







































































