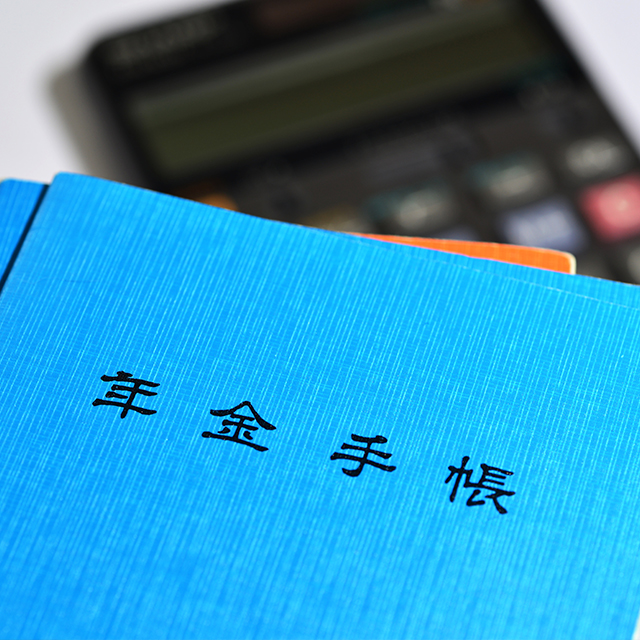児童手当はいつからいつまでもらえる?
申請方法や注意点とともに分かりやすく解説
児童手当は、子育て中にかかる費用を補ってくれる重要な存在です。受け取れる期間がいつからいつまでか、気になる人もいるのではないでしょうか。
本記事では、児童手当の基本概要や受け取れる期間を解説します。児童手当の申請期限や、児童手当の注意点も取り上げます。子育て中の人は、ぜひ参考にしてください。
※本記事は、2023年10月現在の内容です。
※児童手当制度に関する記載は2023年10月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。

児童手当とは
児童手当とは、児童を養育する人が受け取れる手当です。
家庭などでの生活安定や未来の担い手となる子どもが、健やかに成長できるよう作られた制度で、1972(昭和47)年から実施されています。
児童手当の対象となる子どもの年齢は、制度改正によって時代とともに変化してきました。
児童手当はいつからいつまで受け取れる?
現在の制度では、養育する子どもが0歳から15歳までの期間、児童手当を受け取れます。厳密には子どもが中学校を卒業するまで(15歳の誕生日を迎えたあと、最初の3月31日を迎えるまで)が対象期間です。
児童手当がもらえる時期は原則、毎年6月・10月・2月の年3回に分かれています。6月は2〜5月分、10月は6〜9月分、2月は10〜1月分と、前月分までを受け取れます。
児童手当を受け取るために必要な条件は、以下のとおりです。
- 養育している子どもが日本国内に在住
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育
- 養育者の所得が所得上限限度額未満
条件を満たせない場合は児童手当を受け取れません。ただし、留学目的で子どもが海外に住んでいて、一定要件を満たす場合は受け取り可能です。
また、両親が離婚協議をしていて別居の場合、児童手当は養育する子どもと一緒に暮らしている人が優先的に受け取れます。
状況次第では、子どもの両親以外が児童手当を受け取るケースもあるでしょう。例えば、子どもが両親と死別して未成年後見人に養育されている場合や、施設または里親のところなどで養育されている場合です。
その場合、子どもを養育する未成年後見人や子どもが入所する施設の設置者、里親などが養育者として児童手当を受け取ります。
児童手当の支給額と所得制限
児童手当の支給額は、養育している子どもの年齢によって異なります。
また、児童手当には所得制限が設けられているため、一定以上の所得を得ている人は児童手当を受け取れません。
以下で児童手当の支給額と所得制限を詳しく解説します。
児童手当の支給額
児童手当で受け取れる金額は、以下のとおりです。
| 支給対象の年齢 | 児童手当の金額(1人あたりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
支給額は支給対象となる子どもの年齢で決まるため、住んでいる自治体が変わっても金額は変わりません。
児童手当に設けられている所得制限
児童手当は、受給者の扶養親族等の数に応じて所得制限が設けられています。所得制限には、所得制限限度額と所得上限限度額があります。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (収入の目安) |
所得上限限度額 (収入の目安) |
|---|---|---|
| 0人 (例:前年末に子どもが産まれていない場合) |
662万円(833.3万円) | 858万円(1,071万円) |
| 1人 (例:子ども1人の場合) |
660万円(875.6万円) | 896万円(1,124万円) |
| 2人 (例:子ども1人と年収103万円以下の配偶者の場合) |
698万円(917.8万円) | 934万円(1,162万円) |
| 3人 (例:子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合) |
736万円(960万円) | 972万円(1,200万円) |
| 4人 (例:子ども3人と年収103万円以下の配偶者の場合) |
774万円(1,002万円) | 1,010万円(1,238万円) |
| 5人 (例:子ども4人と年収103万円以下の配偶者の場合) |
812万円(1,040万円) | 1,048万円(1,276万円) |
子どもを養育する人の所得が所得制限限度額未満なら、年齢別に定められた金額を受け取れます。しかし、所得が所得制限限度額以上の場合は、子どもの年齢別に定められた金額を受け取ることはできません。
所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満ならば、特例により子ども1人あたり一律5,000円(月額)を受け取れます。2022年10月支給分(6~9月)からは法改正により、所得上限限度額以上の場合は一律5,000円の特例給付も受け取れなくなりました。
ただし、受給者が施設の設置者や里親の場合は、所得制限を適用せずに児童手当を受け取れます。
児童手当の申請はいつまでにすればいい?
子どもが産まれた、またはほかの地域から転入した場合、現住所の市区町村で児童手当の申請を15日以内に行ないましょう。
申請が遅れた分だけ受け取れる月数が少なくなるため、児童手当の申請は速やかに行なう必要があります。申請方法は以下でくわしく解説します。
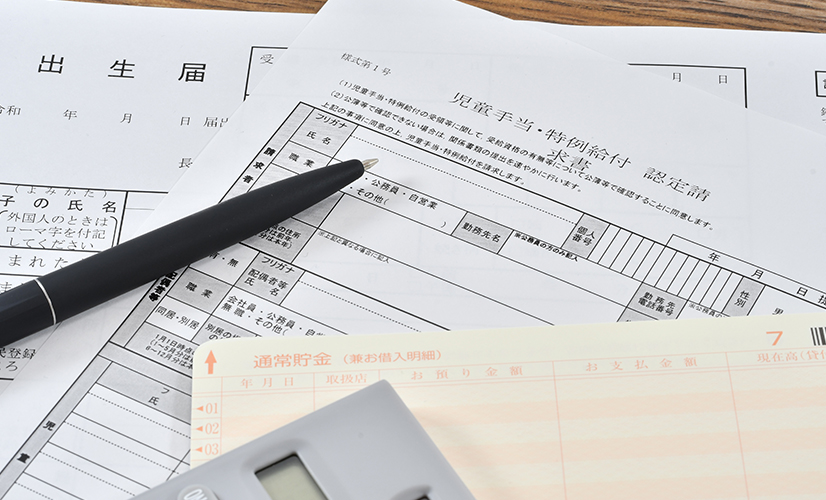
児童手当をはじめて申請をする場合
子どもが誕生し、児童手当をはじめて申請する場合は、出生日の翌日から15日以内に認定請求を行ないましょう。認定請求では、受給者が居住する市区町村へ認定請求書を提出します。
認定請求の際は、認定請求書のほかに以下の書類が必要です。
- 窓口で手続きする人の本人確認書類
- 申請者名義の金融機関の通帳など
- 申請者と配偶者のマイナンバーが確認できる資料
- 申請者の健康保険証の写し(被扶養者や公務員の場合)
また、子どもの出生届を里帰り出産した先で提出すると、児童手当の受け取りに別途手続きを要します。出生届と児童手当の申請は、同じ市区町村で行ないましょう。
児童手当を引き続き受け取る場合
児童手当を継続して受け取るには、毎年6月30日までに現況届の提出が必要な場合があります。
原則として2022年6月分以降からは現況届の提出は不要になりましたが、以下のケースにあてはまる人は提出が必要です。
- 住民基本台帳で住所を把握できない法人の未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力などで住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 施設などの受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった人
現況届の提出時には、以下の添付書類を準備しましょう。
- 健康保険証の写し(請求者が会社員などの場合)
- 前住所地の市区町村長が発行する前年分の児童手当用所得証明書(その年の1月1日に現住所で住民登録がなかった場合)
現況届の提出を求められているのに提出しないでいると、6月分以降の児童手当を受け取れません。児童手当の受け取りに必要な手続きは、出生時の認定請求だけではない点に注意しましょう。
児童手当に関する注意点
児童手当に関する主な注意点は以下のとおりです。
- 海外で暮らす子どもは基本的に支給対象外
- 申請タイミングによって減額される場合がある
- 受給者が公務員の場合は勤務先で申請する
- 里帰り出産の場合は出生届を出す市区町村に注意する
それぞれ詳しく解説します。
海外で暮らす子どもは基本的には支給対象外
児童手当の支給対象は日本国内で暮らす子どものため、海外で暮らす子どもは支給対象外です。ただし、留学目的で海外に暮らしていて、要件を満たす場合は児童手当を受け取れます。
海外で暮らしていても例外的に児童手当の支給対象となるには、以下の要件3つをすべて満たす必要があります。
1.日本国内に住まなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超える期間住所があった
2.教育を受ける目的で海外に住み、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していない
3.日本国内に住まなくなった日から3年以内
また、短期間の留学で日本へ帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、「1」の要件を満たしていなくても、児童手当を受け取れる場合があります。
申請タイミングによって減額される場合がある
児童手当の受け取りは原則、申請月の翌月分からですが、「15日特例」があります。
異動日(子どもの出生日や転入した日)が月末近くの場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内なら申請月分から児童手当を受け取れる特例です。
例えば6月30日が異動日だった場合、7月1日から7月15日までの15日以内に申請すれば、翌月の8月分からではなく7月分から受け取れます。
しかし、この場合、特例期間を過ぎた7月16日以降の申請だと7月分を受け取れず、児童手当が1ヵ月分受給できないことになります。
受給者が公務員の場合は勤務先で申請する
受給者が公務員の場合は勤務先が居住地と離れていても、居住地ではなく勤務先で児童手当を申請します。
退職等で公務員でなくなった場合は、公務員でなくなった日の翌日から数えて15日以内に、居住する市区町村で申請が必要です。
里帰り出産の場合は出生届を出す市区町村に注意する
里帰り出産の場合、出生届は里帰り先ではなく、受給者が住む地域で提出しましょう。
里帰り出産した地域でも、出生届の提出自体は可能です。しかし、児童手当は受給者が住む地域の市区町村でなければ申請できません。
出生届を受給者が住む地域以外で提出すると、児童手当の申請に別途手続きを要し、受け取りが遅れる原因となります。
手続きを効率よく進めて児童手当を受け取るために、出生届は受給者が住む市区町村で提出するとよいでしょう。
教育費の備えに「明治安田生命つみたて学資」がおすすめ
「明治安田生命つみたて学資」は、お子さまの成長にあわせて教育資金を受け取れる保険です。充実した受取率(※)で、確実にお子さまの教育資金を準備できます。
保険料の払込期間はお子さまが15歳までなので、教育費がかさみやすい高校までに保険料の払込みが終了します。
また、ご契約者が万一の際は保険料の払込みが免除され、保障は継続するので安心です。
※受取率とは、払込保険料の累計額に対する満期までの受取総額の割合をいいます。
※保険商品をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。
まとめ
児童手当は、養育する子どもが中学生まで(15歳の誕生日を迎えたあと、最初の3月31日を迎えるまで)の期間、養育者が受け取れます。ただし、所得制限があるため、一定以上の所得のある人は受け取れません。
はじめて児童手当を申請する場合は、子どもの出生日の翌日から15日以内に児童手当の認定請求を行なう必要があります。
また、海外で暮らす子どもは原則、支給対象から外れ、受給者が公務員の場合は勤務先で申請するなどの注意点も存在します。注意点も理解したうえで、児童手当を受け取りましょう。
募Ⅱ2302175ダイマ推