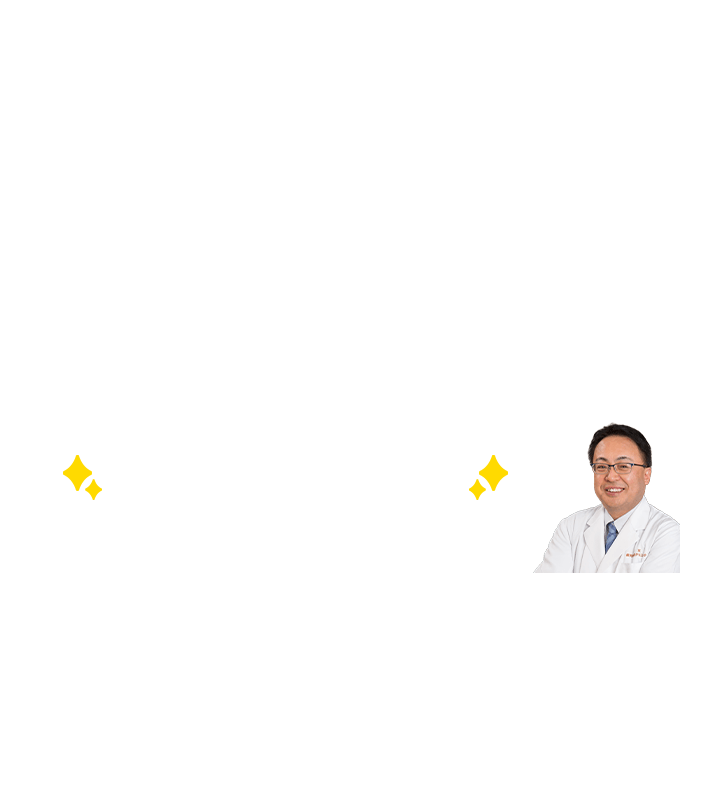
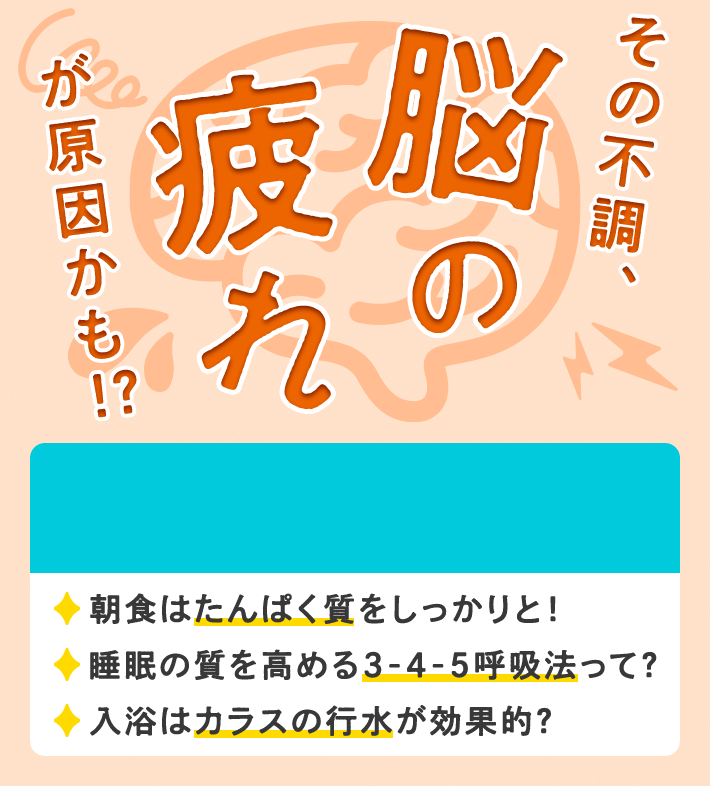
※本記事は、2025年3月時点の内容です
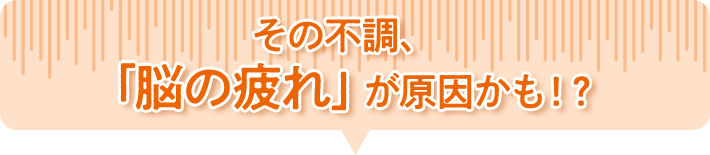
疲労回復の名医に聞く!正しい疲れリセット法
「体がなんとなくだるい」「集中力が続かない」「寝ても疲れが取れない」
――こうした運動や勉強、仕事などで生じる「体の疲れ」。こんなちょっとした不調は、実は「脳の疲れ」によるものかもしれません。今回は、脳の疲れが引き起こすさまざまな不調とその原因、さらに疲れの取り方について、疲労に詳しい医師の梶本修身先生に伺いました。
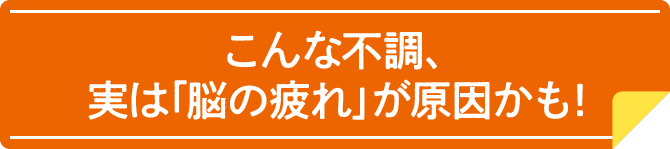
疲労の正体は「脳の疲れ」?
そもそも、「疲労」とは何でしょうか。例えば、運動したあとのだるさを、「体の疲れ」としてとらえる人も多いでしょう。しかしその正体は、実は「脳の疲れ」。運動後の疲労感は、筋肉ではなく脳の自律神経の疲弊が原因です。運動すると脳も体も酸素を必要とし、体温が上昇します。自律神経は、脳へ酸素を送り、さらに脳の温度上昇を抑えるために全身に指令を出します。そのため、運動負荷が高いほど指令は複雑化し、自律神経は疲弊していきます。これ以上負荷をかけないように、自律神経は脳に「疲労」を感じさせ、活動を止めようとします。これを受けて、私たちは「疲れた」と感じるのです。
このメカニズムは、運動したときに限ったものではありません。睡眠不足や長時間のデスクワーク、ストレス、さらには猛暑のなかで過ごしたときに感じる「疲労」も、同じように脳が感じているものです。つまり、すべての疲労は「脳の疲れ」からくるものであり、自律神経からのSOS信号といえるでしょう。そのため、ストレスや睡眠不足が続いて脳がしっかりと休息できないと、疲れが取れずにさまざまな不調へとつながってしまいます。疲労を解消するには、十分な睡眠を取って脳を休ませる必要があるのです。
- ※ 出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 疲労回復の話』(梶本修身・著/日本文芸社)
- ※ 何らかの病気が原因で疲労感を生じる場合もあります。睡眠が十分に取れていて、日中の活動に著しい支障をきたすほどではないものの、全身のだるさなど不調が続いている場合は医師に相談しましょう。
あなたは大丈夫?
こんな症状は「脳の疲れ」のサインです
毎日感じているちょっとした不調こそ、脳が疲れているサインです。以下に挙げた項目に当てはまる数が多いほど、脳の疲れがたまっている可能性が高くなります。
- 起床から4時間くらいたつと眠気やだるさを感じる
- 寝床につくと5分以内に眠っていることが多い
- 眠りが浅かったり、いびきをかいたりすることが多い
- ちょっとしたことですぐイライラする
- 仕事や勉強など作業に集中できず、すぐに飽きてしまう
- 親しい友人との会食でも面倒に感じる
脳の疲れは万病のモト!?
「疲労」という脳のSOS信号を無視して活動を続けていると、何が起きるのでしょうか。まずあくびや眠気、だるさなどが現れ、注意力や判断力が低下します。そうした状態を放っておくと自律神経が乱れ、めまいや立ちくらみ、動悸、息切れ、頭痛、肩こり、耳鳴り、不眠などさまざまな不調を招きます。さらに免疫力が低下して、風邪など感染症にかかりやすくなったり、肥満や高血圧、糖尿病など生活習慣病のリスクを高めたりすることにもつながります。最終的には心筋梗塞や脳卒中、がんなどにつながる可能性もあります。こういったリスクを回避するためにも、日ごろから脳の疲労を見逃さす、すばやく対処することが必要です。

「やりがい」や「楽しさ」で
隠されてしまう疲労こそ危険です
「脳の疲れ」のなかでも特に気を付けたいのが、「隠れ疲労」です。例えば、趣味のゲームや編み物など、楽しい作業は疲れを感じにくく、長時間続けてしまうこともあります。しかし、そんなときこそ注意が必要。楽しいからといって、脳が疲れないわけではありません。疲れを感じないのは、意欲や達成感が脳の疲れを隠してしまうからです。本当は疲れているはずなのに、疲労感が隠れてしまう「隠れ疲労」は、自覚がないまま疲労が蓄積していくため、とても危険です。さまざまな不調を引き起こすだけでなく、免疫機能が低下して病気にかかりやすくなります。
「隠れ疲労」に陥りやすいのはこんな人
隠れ疲労は、真面目な人ほど陥りやすいといわれます。集中力が高いことは、仕事上は有益なことですが、その分、脳と身体を酷使しているということ。評価されてやりがいや達成感を感じ、疲れを無視して作業を続けてしまうことは、過労死の危険につながりかねません。作業に集中するのは1時間〜1時間30分を目安として、深刻な疲れに陥らないように注意しましょう。
当てはまる人は要注意!
-
責任感が強い人
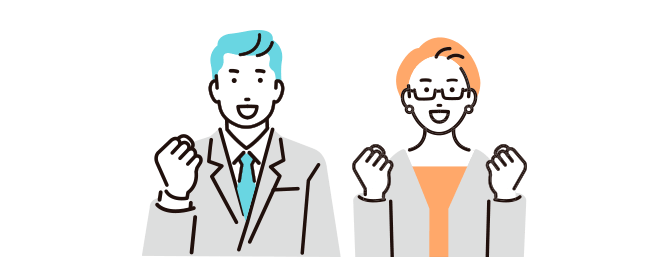
達成感ややりがいは、疲れのアラートを隠してしまいます。自覚のないまま脳が休めず、疲労が蓄積していくことに。
-
作業に没頭しがちな人

特に2時間以上作業を続けがちな人は注意!たとえデスクワークでも、脳を酷使していることに変わりはありません。
-
サービス精神が旺盛な人

ほめられたり、喜んでもらえたりすれば、疲れが吹き飛ぶという考えは、注意が必要。脳は休めなければ、疲れ続けていくだけです。
脳の疲れをため込んでしまうと、
深刻な病気に陥ることも。
日々の体調管理に加えて保険を活用し、
もしものときに備えませんか。
忙しい毎日に追われて脳の疲れを蓄積させてしまうと、身体にさまざまな不調をきたし、深刻な病気を引き起こすこともあります。ライフスタイルにあわせて保障をカスタマイズでき、健康増進をサポートする仕組みも備えた明治安田の商品で、もしものときに備えませんか?
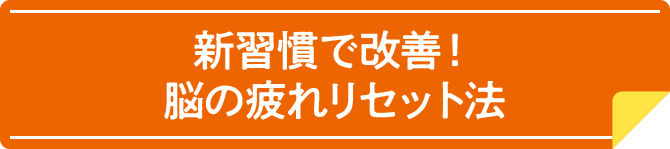
脳の疲れを回復させるには、自律神経をいたわることが何より大切。しかし、温泉やサウナ、いわゆる「スタミナ食」など、一般的に知られている疲労回復法のなかには、むしろ疲労をため込んでしまう要因につながるものもあります。ここでは最新の研究結果に基づいた、簡単で効果的な脳の疲れの回復法を紹介します。
睡眠の新習慣
真っ暗にした寝室で快適な室温を保ち、
厚めの掛け布団を使う
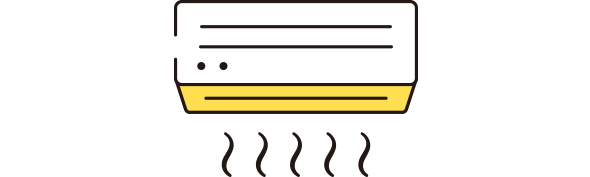
質のよい睡眠をとるには、寝室を真っ暗にすることが不可欠です。寝るときは、カーテンをしっかり閉め、照明は豆電球程度の明るさのものでも消しましょう。明かりだけでなく、温度も大切なポイント。脳にとって理想的な寝室の室温は、夏は23~25℃、冬は20~23℃。布団内の温度は、1年を通して33℃程度を保つのがよいといわれています。エアコンを利用して脳にとって最適な室温を保ち、1年中厚めの掛け布団を使うのがおすすめです。
横向き寝の姿勢でいびきを防ぐ

いびきは、睡眠の質を落とす大きな原因の一つです。いびきをかいていると、気道が狭くなって酸素不足になるため、心拍数や血圧を上げて脳に酸素を送るために、自律神経が指令を出し続けなければならなくなります。その結果、睡眠中も脳が十分に休むことができなくなってしまいます。いびきをかきにくくするには、横向きに寝るのがおすすめ。右側を下にすると、食べた物の消化を助け、自律神経にかかる負担を減らしてくれます。抱き枕を使うと、横向き寝の姿勢をとりやすくなります。
寝る前に「3-4-5呼吸法」で
脳の温度を下げる

睡眠の質を上げるためにおすすめなのが、「3-4-5呼吸法」です。まず3秒間かけて鼻から息を吸い、4秒間息を止めたら、5秒間かけてゆっくり口から息を吐き切ります。寝る前に3~4回繰り返しましょう。鼻の穴から喉へと続く空気のとおり道である鼻腔は、脳の自律神経を司る視床下部などの近くに位置します。そのため、鼻から空気を吸い込むことで自律神経の中枢を冷やし、日中の活動で熱を持った状態の脳をクールダウンすることができます。
食事の新習慣
朝食はたんぱく質を
しっかり摂って体をポカポカに

栄養バランスのよい食事を摂ることは、疲労回復の第一歩。特に朝食は、たんぱく質を欠かさずに。たんぱく質には、体内で熱をつくりだす働きがあります。そのため、朝食にたんぱく質をしっかり摂ることで、体が温まり、日中を活動的に過ごせるようになります。鮭や納豆、豆腐、卵料理などを取り入れた和定食にすれば、動物性たんぱく質と植物性たんぱく質をバランスよく摂ることができます。
疲労回復成分「イミダペプチド」を積極的に摂る
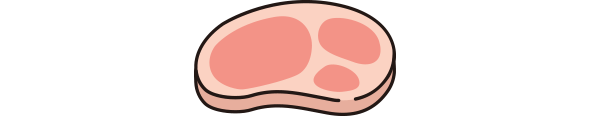
自律神経を整え、疲労回復を早めてくれる成分が「イミダペプチド」です。過度な運動や作業などが続くと、脳内で活性酸素が過剰に発生し、自律神経の細胞を酸化させて疲労を引き起こします。イミダペプチドは、そうした活性酸素をピンポイントで攻撃し、疲労を軽減してくれるのです。イミダペプチドが最も豊富に含まれているのが鶏胸肉。カツオやマグロ、豚肉などにも多く含まれています。推奨される1日の摂取量は200mg。鶏胸肉(皮なし)なら50~100g程度を食べることで、効率的に摂取できます。
※ 出典:『眠れなくなるほど面白い 図解 疲労回復の話』(梶本修身・著/日本文芸社)
疲れているときほど「スタミナ食」は避ける

疲労回復を目的として、うなぎや焼き肉、ニンニクをたっぷり使った料理など、いわゆる「スタミナ食」を摂っていませんか?実はこれらの料理は、脂肪分が多くカロリーも高いので、消化に時間がかかります。そのため、スタミナ食を摂ると胃腸への負担が増え、自律神経を乱してしまうことになるのです。
リラックスの新習慣
意識してこまめに休憩をとる

脳の疲れをためないためには、定期的な休養が必要です。たとえ疲れていないと感じても、「1時間作業をしたら、5分間休憩する」など、時間を決めて休むようにしましょう。特に長時間同じ姿勢でいると血液循環が悪くなり、自律神経の活動性が高まって脳に疲労がたまりやすくなります。休憩中は立ち上がって歩いたり、軽いストレッチをしたりして体をほぐしましょう。また、血液循環を悪化させないためには、水分補給も忘れずに。
1日1回、自然のゆらぎを感じる
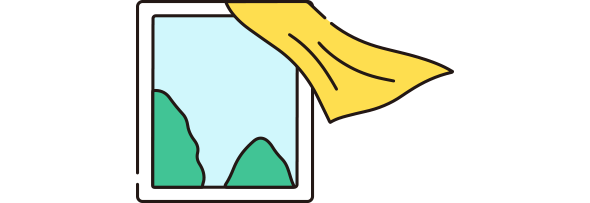
疲労回復のためには、自然の「ゆらぎ」を五感で感じるのが効果的です。ゆらぎとは、そよ風や木漏れ日、小川のせせらぎなど自然界に発生する不規則な規則性を持つ現象のこと。実は人間にも脳波や心拍数、呼吸などのゆらぎが存在します。人間の持つそのリズムと自然のゆらぎがシンクロすることで、快適さを感じてリラックスできるのです。自然界のゆらぎを感じるのにおすすめなのが森林浴。公園や遊歩道など緑の多い場所なら、森林浴と同じような効果が期待できるので、1日10分程度でも外に出て樹木の香りを嗅いだり、鳥のさえずりに耳を傾けたりしましょう。外に出るのが難しい場合でも、窓を開けて風を入れたり、サーキュレーターで空気を循環させたりすれば、ゆらぎを生み出すことができます。
入浴はぬるめのお湯で「カラスの行水」
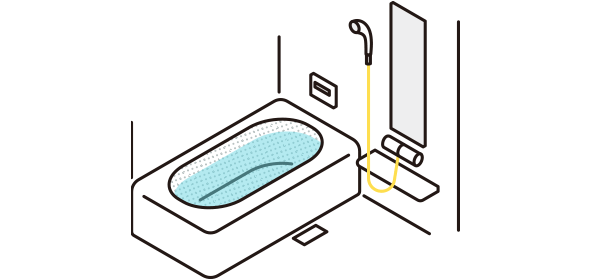
疲れを取る目的でサウナや熱いお湯のお風呂に入るのは、実は逆効果です。なぜなら、体温や脈拍、血圧が上昇することで、脳の温度を調整しようとする自律神経に負荷をかけてしまうから。結果、かえって疲れを招くことにつながります。脳の疲れを回復させる理想の入浴法は、短時間で入浴をすませる、いわゆる「カラスの行水」です。38~40℃程度のぬるめの温度で、心臓より下の湯量にして、5分程度半身浴するのがおすすめ。夏場や疲れているときは、無理にお風呂につからず、シャワーだけですませるのでも構いません。
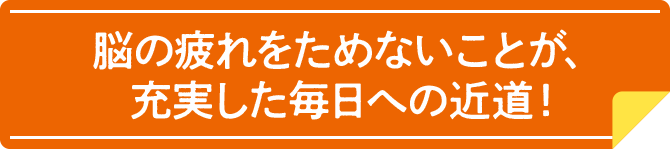
脳の疲れを回復させるには、毎日の生活習慣を見直すことが大切です。いつもの習慣をちょっとだけ変え、ご紹介した脳の疲れを回復させる新習慣を実践して、自律神経のバランスを整えましょう。何より大切なのが、脳が発している疲れのサインを見逃さないようにして、休むことです。脳の疲れを上手にリセットして、より充実した毎日をめざしましょう。

監修
梶本修身
監修梶本修身
医師・医学博士。東京疲労・睡眠クリニック院長。大阪大学大学院医学系研究科修了。2003年から産学官連携「疲労定量化及び抗疲労食薬開発プロジェクト」統括責任者。大阪市立大学大学院医学研究科疲労医学講座特任教授などを歴任。TVやラジオなど多数出演。著書に『すべての疲労は脳が原因』(集英社新書)、『眠れなくなるほど面白い 図解 疲労回復の話』(日本文芸社)など。
- ※本記事は、2025年3月時点の内容です。
- ※本記事は、当社が梶本修身様に監修を依頼して掲載しています。
- ※本記事は、監修者の知見や経験を踏まえて執筆しています。
脳の疲れをため込んでしまうと、
深刻な病気に陥ることも。
日々の体調管理に加えて保険を活用し、
もしものときに備えませんか。
忙しい毎日に追われて脳の疲れを蓄積させてしまうと、身体にさまざまな不調をきたし、深刻な病気を引き起こすこともあります。ライフスタイルにあわせて保障をカスタマイズでき、健康増進をサポートする仕組みも備えた明治安田の商品で、もしものときに備えませんか?
![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/life/life46/tsumitate_logo-01_sp.png)




![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/common/recommend/product_bnr_beststyle_02.png)



