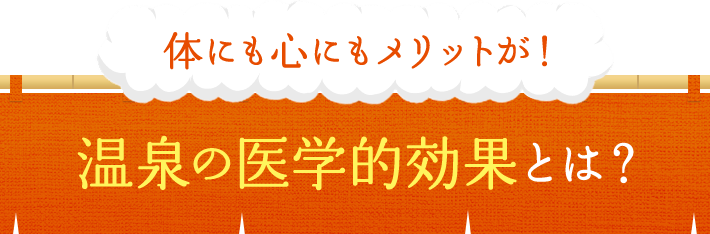
温泉が健康にもたらす代表的な医学的効果には、次のようなものがあります。
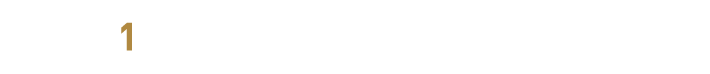
温かいお湯に浸かると、血管が拡張して血流が良くなります。それによって、全身に栄養が行きわたりやすくなり、老廃物の回収が進みやすくなります。また、温めることで筋肉や関節がほぐれて柔らかくなります。さらに神経の過敏性を抑えることができ、痛みが和らぎます。このような効果を「温熱作用」といいます。
温熱作用は普段の入浴でも得られますが、温泉には体を温める成分が溶け込んでいるため、より強い温熱作用が得られます。
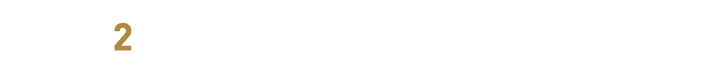
お風呂に入ると、浮力の効果で体重が軽く感じられます。首まで浸かった場合、水中での体重は普段の約10分の1に感じられます。私たちは常に重力を感じていますが、入浴中は重力から解放されます。そのため関節や筋肉の緊張が緩んで、リラックスすることができるのです。
湯量の少ない半身浴では、浮力も少なくなってリラックス効果も半減。また、シャワーで済ませている場合は浮力の効果を得られません。お湯が豊富に湧き出る広々とした温泉で、首までしっかり浸かれば浮力の効果を堪能できます(息苦しく感じるときは無理せず半身浴にしましょう)。
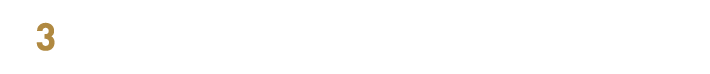
温泉に入っていなくても、温泉地に来ただけで、心も体もリフレッシュすると感じた経験はありませんか?これは、「転地効果」によるものです。転地効果とは、日常とは異なる自然豊かな環境に身を置くことで、心身に良い影響をもたらす効果のこと。温泉地に足を運ぶと、転地効果によってストレスが和らいで自律神経のバランスが整うのです。
転地効果は自宅のお風呂では得られません。非日常的な場所に移動・滞在して、美しい景色を眺めたり、雄大な自然を味わったりすることも温泉の醍醐味なのです。
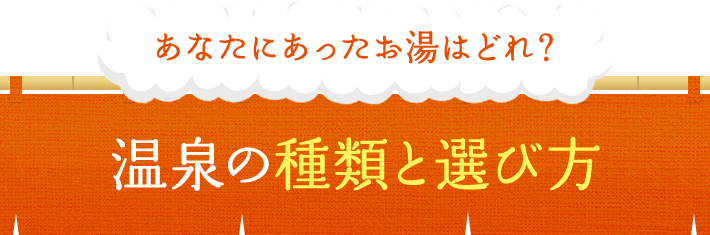
温泉は泉質によって異なる特徴があり、期待できる効果もさまざまです。泉質ごとに効果があるとされる症状や体調の悩みのことを「適応症」といい、それを知ることで自分にあった温泉を選びやすくなります。
健康増進や不調の軽減・改善、美容に役立つおすすめの泉質やその特徴、泉質別適応症、代表的な温泉地をご紹介します。
- 本記事に記載された効果(適応症)は、「浴用」に関して各温泉地の温泉分析書等の情報による見解に基づくものであり、実際の効果には個人差があります。
- 一つの温泉地に複数の泉質がある場合もあります。実際に訪れる際は、各施設の泉質情報をご確認ください。
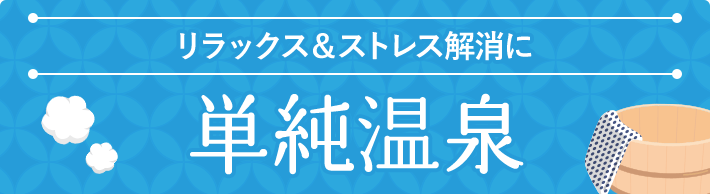
溶存成分(ガス成分を除く)※が1,000mg/kg未満、源泉の水温が25℃以上の温泉。肌触りが柔らかくて刺激が少ないのが特徴で、リラックスでき、疲労やストレスを和らげてくれるとされています。
温泉のなかに溶け込んでいる物質
【泉質別適応症】
自律神経不安定症、不眠症、うつ状態
代表的な温泉地
栃木県・鬼怒川温泉、岐阜県・下呂温泉、愛媛県・道後温泉

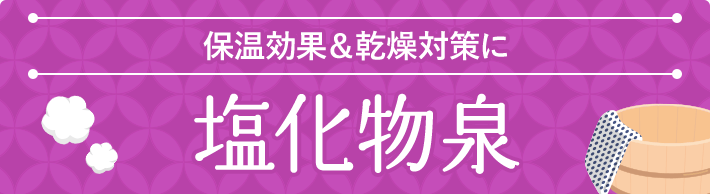
塩分が豊富に含まれている温泉。皮膚の表面に塩の膜ができることで、高い保温効果をもたらすとされています。
【泉質別適応症】
きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症
代表的な温泉地
宮城県・秋保(あきう)温泉、石川県・片山津温泉、鹿児島県・指宿(いぶすき)温泉など

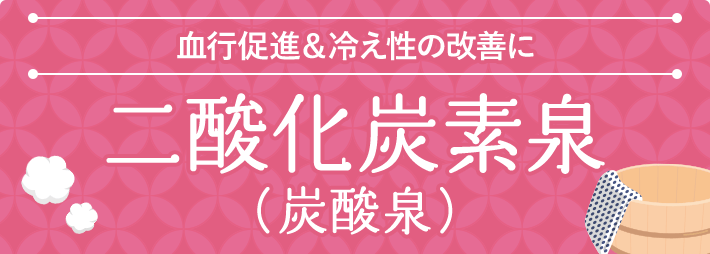
炭酸ガスが溶け込んでいる温泉。お湯に溶け込んだ炭酸ガスが皮膚から吸収されることで、血管が拡張され血流を促進するとされています。
【泉質別適応症】
きりきず、末梢循環障害、冷え性、自律神経不安定症
代表的な温泉地
長野県・唐沢鉱泉、大分県・長湯温泉など

温泉と安心の保障で健康を守る、
健やかな毎日をはじめてみませんか?
心と体を整えてくれる温泉。ゆったりとした時間に、健康の大切さを改めて感じる方も多いのではないでしょうか。健康的な毎日を過ごすためには、今の健康づくりに加えて、将来への“備え”も欠かせません。明治安田では、日々の健康管理から、いざというときの保障までサポートする保険をご用意しています。温泉と保険で、今とこれからの健康を守る。そんな健やかな毎日をはじめてみませんか。
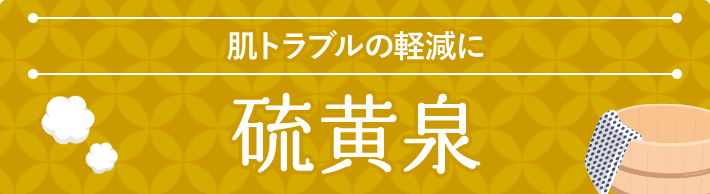
硫黄や硫化水素が含まれている温泉。タマゴの腐敗臭に似た特有の匂いが特徴です。殺菌力が強く、皮膚の表面の細菌などを取り除くとされています。アトピー性皮膚炎や慢性湿疹などの皮膚疾患に対しても、症状の緩和に効果があるといわれています。
【泉質別適応症】
アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、慢性湿疹、表皮化膿症
硫黄泉には硫黄型と硫化水素型があり、硫化水素型には末梢循環障害が追加されます。
代表的な温泉地
北海道・登別温泉、山形県・蔵王温泉、群馬県・万座温泉など

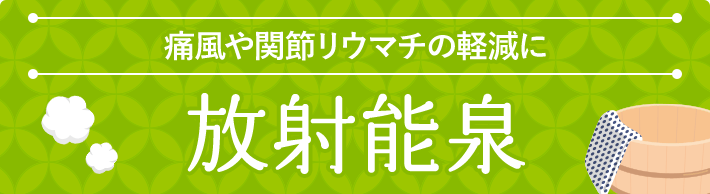
微量の放射能を含む温泉で、「ラドン温泉」や「ラジウム温泉」とも呼ばれます。微量の放射線は、人体に良い影響を与えることが一部で報告されています。炎症による痛みに対して作用があるとされ、痛風や関節リウマチなどの症状が軽減されることがあるといわれています。
【泉質別適応症】
高尿酸血症(痛風)、関節リウマチ、強直性脊椎炎など
代表的な温泉地
山梨県・増富温泉、鳥取県・三朝(みささ)温泉、広島県・鞆の浦(とものうら)温泉

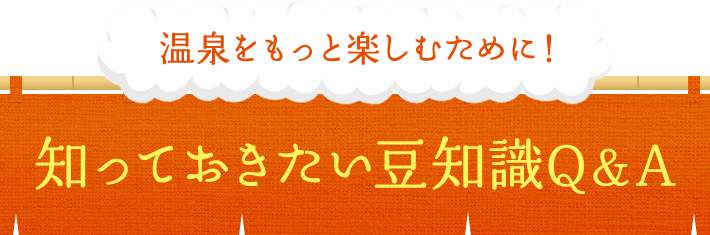
温泉の効果を最大限に活かしながら、安全に楽しむためには正しい知識が大切です。そこで、温泉に入る前に知っておきたい疑問にお答えします。
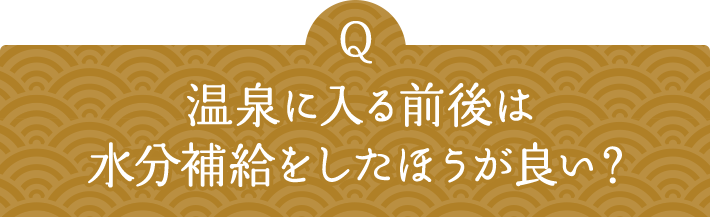

コップ1~2杯の水分をとりましょう。

入浴で失われる水分は800mL程度といわれています。脱水症状を防ぐには、温泉に入る前にコップ1~2杯の水分をとりましょう。温泉に入ったあとも、水分補給を忘れずに。水分補給は水でも構いませんが、牛乳や麦茶、スポーツドリンクをとると脱水症状を防ぎやすくなります。入浴後、血流を保ち、体を冷やさないようにするには、常温の飲み物がおすすめです。入浴後の飲酒は、水分補給にはなりません。
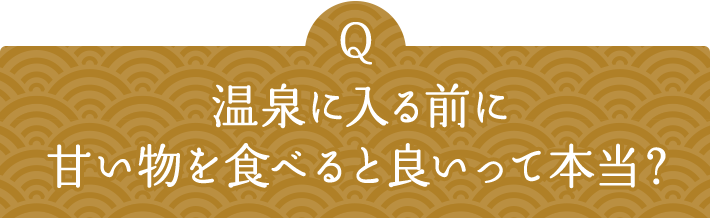

低血糖予防には甘い物が有効です。

空腹状態で温泉に入ると、人によっては低血糖を起こしてふらつきや手足の震え、冷や汗などを招く可能性があります。温泉に入る前に軽く甘い物を食べておくと、低血糖を防げます。温泉付きの旅館やホテルの客室には、お茶と一緒に「お着き菓子」と呼ばれるお茶菓子が用意されていることがありますが、それらを食べるのも良いでしょう。
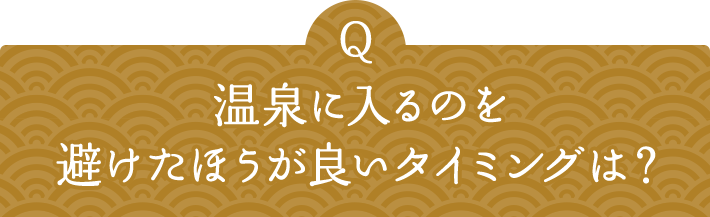

食事前後の30分間や運動直後、飲酒後は避けましょう。

食事前後30分間は温泉に入るのを避けてください。温泉に入ると血管が広がって血流が良くなりますが、血液は皮膚などの身体表面へ多く分配されるため、内臓への血流が相対的に減ってしまいます。その結果、食事の前後に胃腸など消化器官への血流が減り、消化不良を招くおそれがあります。また、運動直後も同様に、筋肉などへの血流を促す必要があるため、すぐに温泉に入るのは避けましょう。さらに、転倒などの危険があるため、飲酒後も温泉に入ってはいけません。
出典:環境省『あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは』(平成26年8月)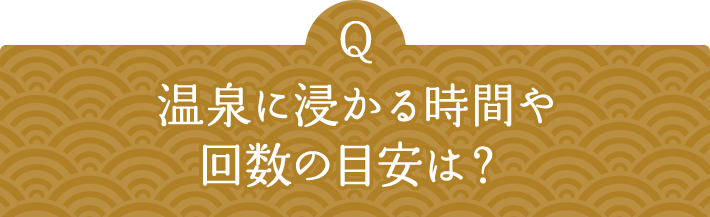

汗がにじんできたら出どき、1日2~3回程度の入浴が目安。

温泉は湯温が高めの場合が多いので、長湯をすると湯あたりを招きます。額や顔に汗がにじんできたら湯船から出ましょう。体への負担を避けながら温泉を楽しむには、こまめにお湯から出ることが大切です。少し長めに浸かりたい場合は、半身浴にするのがおすすめです。
温泉地に来ると、つい欲張ってたくさん温泉に入りたくなるかもしれません。しかし、それでは疲れを癒やすどころか、疲労を蓄積させてしまいます。温泉に入るのは、1日2~3回程度にしましょう。
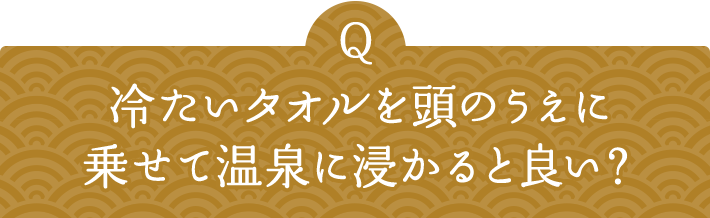

冷たいタオルは脳の温度を下げ、のぼせを防止するのに効果的です。

体を温めながらも頭だけは適度に冷やして脳内の温度が上がらないようにすると良いとされています。屋内の温泉に浸かるときは、冷水で濡らしたタオルを頭に乗せるのがおすすめです。そうすることで、脳の温度を下げ、のぼせ防止にも効果的です。
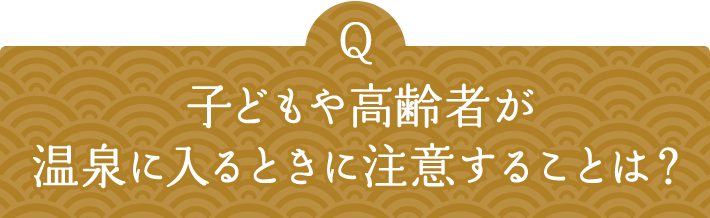

溺水や転倒、ヒートショックなどに注意しましょう。

子どもはたとえ浅い場所でも溺れる危険があります。特に小学校低学年以下は注意が必要です。必ず大人が一緒に入り、子どもから目を離さないようにしてください。また、子どもは体温の調節機能が十分に発達していません。大人よりも熱さに弱いため、温泉に入る際は脱水症状に注意してください。子どもが温泉から出たいと言っていたり、顔や額に汗がにじんでいたり、肌が赤くなっていたら速やかに上がりましょう。
高齢者の場合、転倒や意識障害などの入浴事故に注意が必要です。また、急激な温度差が引き起こすヒートショックのリスクもあります。特に冬の露天風呂は避けるほうが安心です。さらに高齢者では熱さを感じにくくなって、熱すぎるお湯に長く浸かってしまうことも。温泉に表示されている温度計を確認して、ぬるめのお湯から入るようにしましょう。
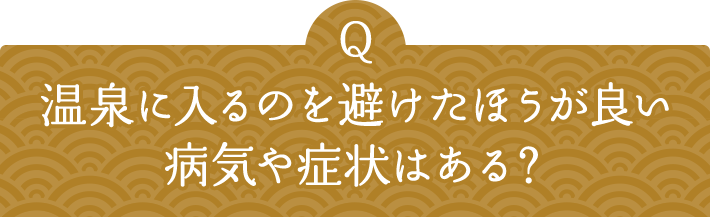

禁忌症にあたる場合や体調がすぐれないときは入浴を控えましょう。
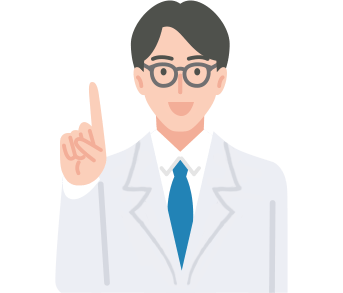
さまざまな健康効果をもたらしてくれる温泉。しかし、「禁忌症」といって、1回の温泉への入浴でも有害で危険性がある病気や症状があります。次に紹介する禁忌症にあたる場合は、温泉に入るのは避けてください。ただし、禁忌症にあたる場合でも、専門的知識を持つ医師の指導で温泉に入るのが可能なこともあります。
体調や持病に不安がある場合は、事前に医師に相談されることをおすすめします。
温泉の一般的禁忌症(浴用)
- 病気の活動期(特に熱のあるとき)
- 活動性の結核、進行した悪性腫瘍または高度の貧血など身体衰弱の著しい場合
- 少し動くと息苦しくなるような重い心臓または肺の病気
- むくみのあるような重い腎臓の病気
- 消化管出血、あるいは目に見える出血があるとき
- 慢性の病気の急性増悪期
泉質別禁忌症(浴用)
泉質が酸性泉、硫黄泉の場合・・・皮膚または粘膜の過敏な人、高齢者の皮膚乾燥症
出典:環境省「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」及び「鉱泉分析法指針(平成26年改訂)」について(平成26年7月1日)、環境省『あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは』(平成26年8月)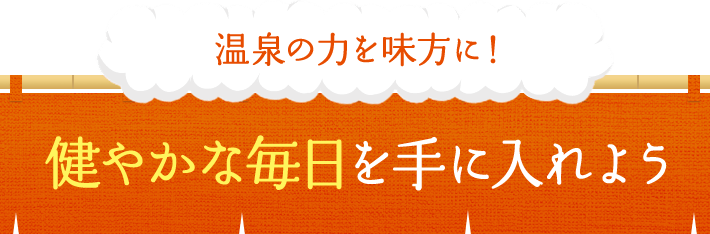
温泉は単にリラックスできるだけでなく、健康増進の助けにもなってくれます。環境省では「新・湯治」を推進しています。これは、温泉に入ることに加えて、温泉地周辺の自然や歴史、文化、食なども楽しむことで、心身ともに健康になるという過ごし方です。温泉地を訪れたら、工芸品づくりに参加したり、名物を味わったりなどさまざまな体験をしてみましょう。健康づくりに温泉を活用して、いきいきと過ごせる毎日をめざしたいですね。

監修
早坂信哉
監修早坂信哉
温泉療法専門医、博士(医学)。東京都市大学人間科学部教授。地域医療の経験から25年以上にわたって4万人以上の入浴を調査してきた温泉・お風呂に関する医学的研究の第一人者。テレビやラジオ、新聞、雑誌、講演など多方面で活躍中。著書に『最高の入浴法』(大和書房)、『おうち時間を快適に過ごす 入浴は究極の疲労回復術』(山と溪谷社)など。
- ※本記事は、2025年4月時点の内容です。
- ※本記事は、当社が早坂信哉様に監修を依頼して掲載しています。
- ※本記事は、監修者の知識や経験を踏まえて執筆しています。
温泉と安心の保障で健康を守る、
健やかな毎日をはじめてみませんか?
温泉でリラックスして楽しみながら自身の健康を考える一方で、もしもの病気やケガに備えることも大切です。明治安田では、もしものリスクだけでなく、普段の健康管理もサポートする保険をご用意しています。温泉と一緒に保険をうまく活用して、健康的な毎日を築いていきませんか。
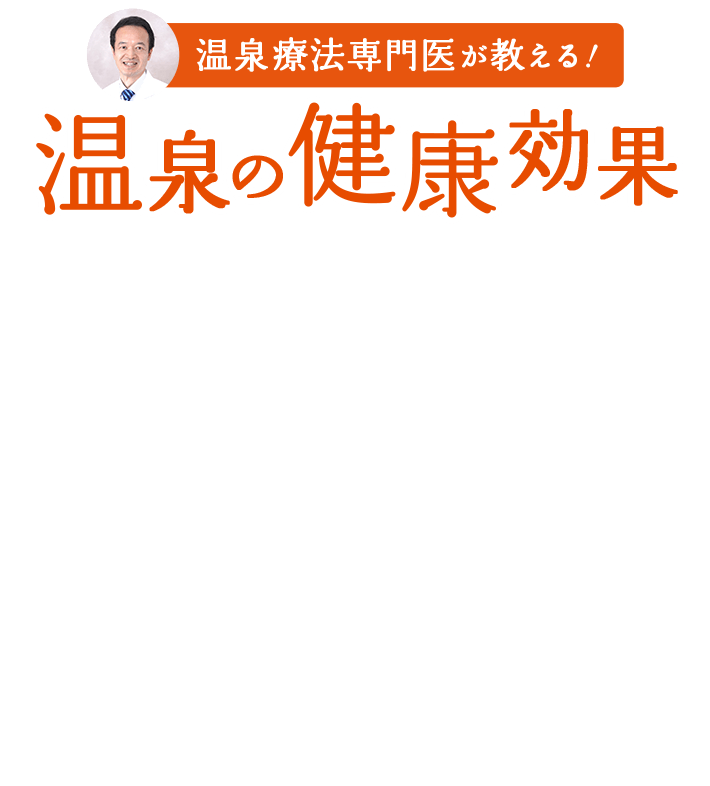
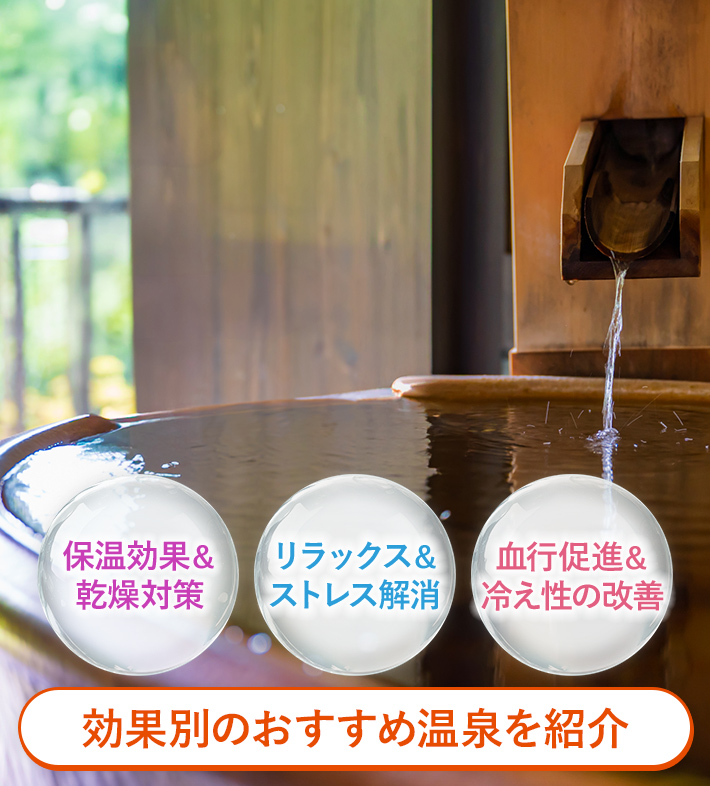
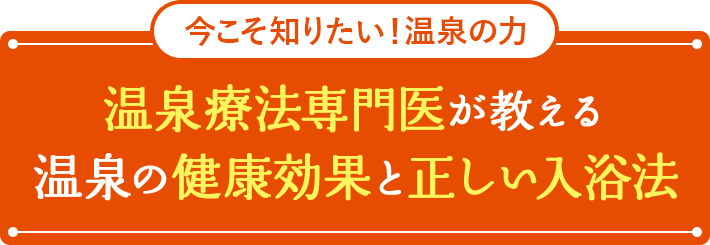
![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/health/health25/pickup_logo_best_sp.png)




![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/common/recommend/product_bnr_beststyle_02.png)



