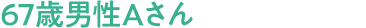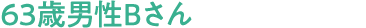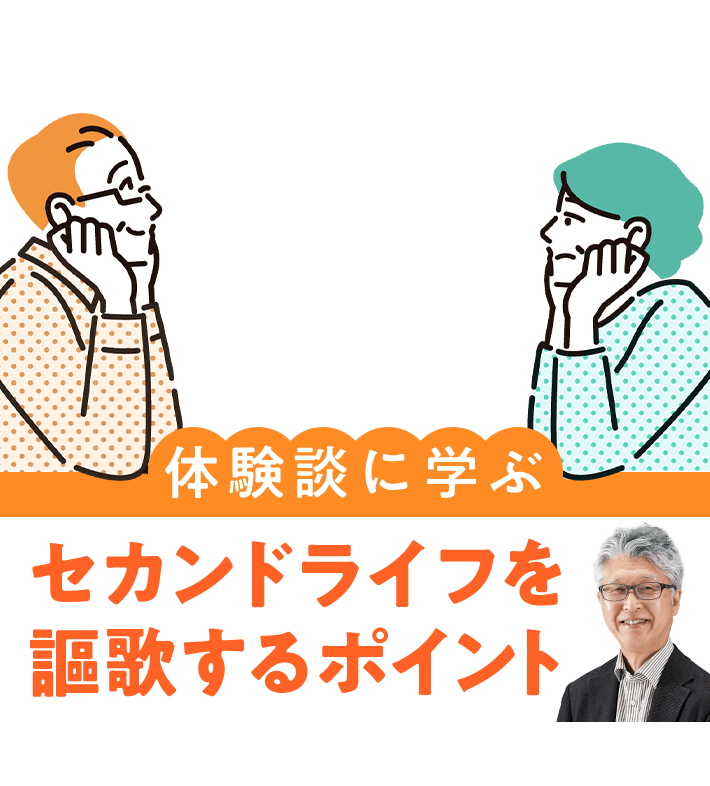

※本記事は、2024年12月時点の内容です

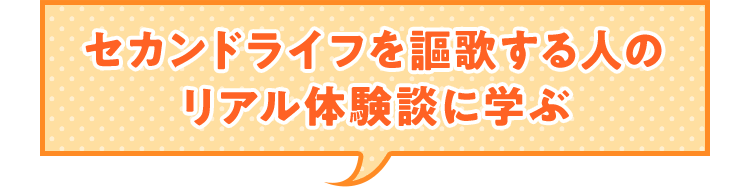
「定年後、どんなふうに過ごそう……」。
50代・60代は、そんなセカンドライフについて考えはじめる時期です。
特に準備せずに漠然と定年を迎えるのと、事前に準備をしたうえで定年を迎えるのとでは、セカンドライフの充実度は大きく変わってきます。
楽しいセカンドライフを送るために今準備しておくべきことは何か、セカンドキャリアコンサルタントの髙橋伸典さんに伺いました。
1
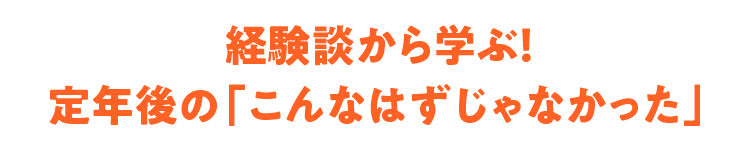
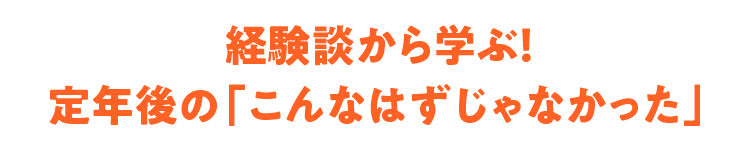
定年後のセカンドライフには、「想定」と「現実」とのギャップがつきもの。
例えば今の時代、60歳定年後も多くの人は「働く」という選択をしますが※1、期待通りの給料が得られなかったり、仕事内容に満足できなかったり、また職場に限らず新しく属した環境に上手くなじめなかったり。それに向けてある程度の心構えをしていたとしても、「こんなはずじゃなかった!」という事態は起こりえます。
具体的にはどのような「ギャップ」が発生するのでしょうか。ここでは、セカンドライフにおいて「想定」と「現実」でギャップが生まれたという、3人のリアルなエピソードをご紹介します。
- ※1 厚生労働省 令和5年「高年齢者雇用状況等報告」調査より。60歳定年企業において令和4年6月1日から令和5年5月31日に定年に到達した者(404,967人)のうち、継続雇用された者は87.4%。
- ※ 紹介するエピソードは、実際のエピソードをもとに加筆修正しています。
![[事例1]](../assets/imgs/life/life42/learn_case-01_sp.png)


新卒で入社以来同じ外資系企業で働き続け、早期退職の募集にエントリーして57歳で退職したAさん。
退職後にキャリアコンサルタントの資格を取得して再就職に挑んだものの、受け皿はかなり少なく愕然。起業へと目標をシフトするが、収益につなげるのが難しく断念。再度就職活動をし、なんとか中小企業に再就職が決まるが、成果を上げても社長になかなか認められず、人間関係で苦悩する日々。仲のいい友人に相談すると「自分勝手で偉そうな部分が出てしまっているのでは?」という指摘を受ける。そこで自分勝手な仕事の進め方をしていたことにハッと気付き、社長に素直に謝罪。
以後はうまく社長とコミュニケーションを築くことができた。

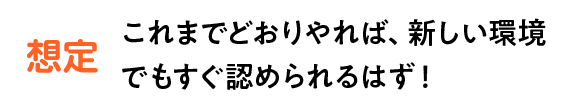

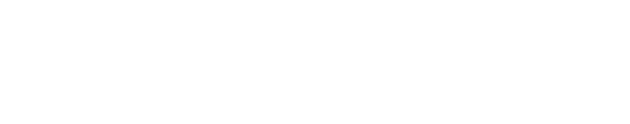
50代・60代ともなると管理職として人を指導する立場でいたことで、いつのまにか「上から目線」で周りを見てしまっていることも少なくありません。しかし、新しい場所にいくと、それは通用しません。新しい環境にあわせて「自分の気持ちも柔軟に変化させる」ことが大切です。「マインドチェンジ」することでいろいろな歯車がうまくまわり、仕事や趣味が充実していきます。
![[事例2]](../assets/imgs/life/life42/learn_case-02_sp.png)
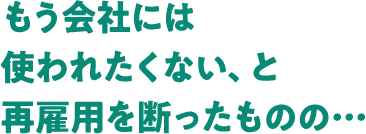

金融関係の企業に長く勤めたが、ライン管理職でなく、定年まで実務マネジャーとして活躍し、60歳で退職したBさん。
専門職は、もうやり切った。「もう会社には使われたくない」と再雇用の提案を断り、退職を選択。その後人事のセミナー講師になろうとするも仕事の依頼はなかった。どれだけ専門性があっても定年後はすぐに仕事は見つからないもの。「地道に専門領域を深めることと人脈を広げることが必要だ」と、これまでの専門職関係の勉強会に参加。そこで知りあった人から仕事を紹介してもらったことがきっかけで、現在は個人事業主として専門性を活かした仕事をこなしている。

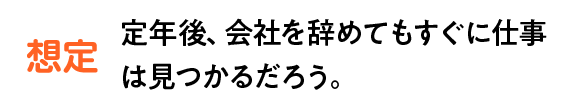
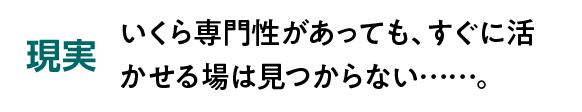
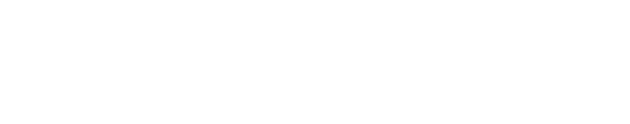
何か専門的に得意な分野があることは、定年後の武器になります。「専門性をきわめること」で、定年後においても長く仕事に携わることができます。ただしその専門性を活かすには、人に知ってもらうことが必要です。関連の勉強会に参加するなど、ネットワークを広げることが役立ちます。そのなかで人からの紹介を通じて、仕事は広がっていきます。
![[事例3]](../assets/imgs/life/life42/learn_case-03_sp.png)


市役所に長く勤め、60歳で定年退職。その後再任用されたCさん。
再任用後の待遇面は悪くなく、働く環境としては満足していた。ところが、この環境も65歳で終了。その後を考えると次第に不安になってきた。「65歳を過ぎたらどのように毎日を過ごそう……」。内向的な性格のCさんは、コミュニティに所属するのが苦手で今まで避けていた。しかし、「このままではいけない」と一念発起。自分の居場所をつくろうと、いろいろな集まりに積極的に参加。そのなかでも会社の忘年会の出し物で感動したウクレレに興味を持ち、ウクレレ教室に行ってみることに。体験してみると性格にもマッチしていることがわかり、60歳で通いはじめた。65歳で再任用満了後もウクレレ教室が企画するイベントに定期的に参加し、充実したセカンドライフを過ごしている。

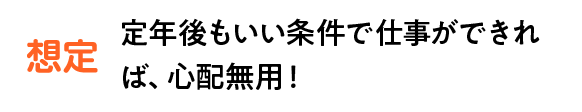
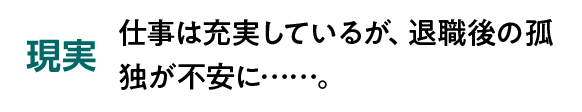
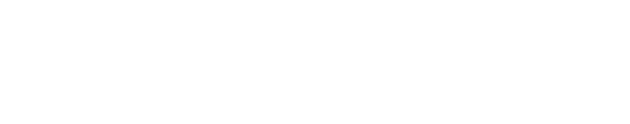
「自分が幸せと感じることは何だろう」と真剣に考え、それを実践できる、仕事以外での「もう一つの居場所」を見つけましょう。どんなことに幸せを感じられるかは、人それぞれ。だからこそ自分にあった場所を見つける準備を、早くからしておきましょう。「定年後に探せばいいや」と思っていても、いざとなると自分にあうものに全然出会えず「ときすでに遅し」という場合も多くあります。
楽しいセカンドライフを送るためには
お金や健康への備えも必要不可欠!
定年後を楽しく生き生きと過ごすためには、自分も家族も安心できるような「備え」が大切です。また、楽しく過ごすためには、資金も重要。充実したセカンドライフを送るために、資産の増加が期待できる外貨建保険や、もしものときの医療保険を活用しましょう。
明治安田のおすすめの保険
2
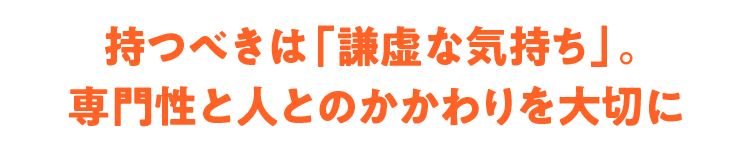
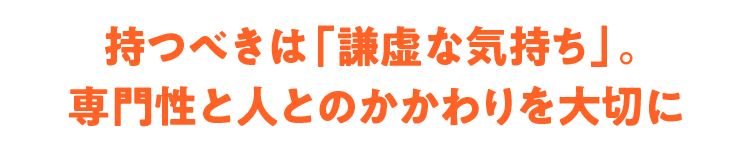
これらの3人の事例をはじめ、さまざまなセカンドライフを過ごす人の声をもとに、セカンドライフを充実させるポイントを3つピックアップしました。

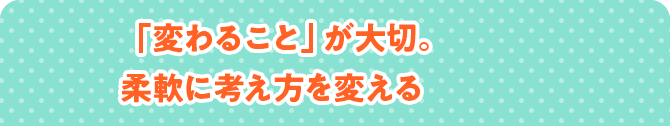
今の50代・60代は同じ会社で長く働いてきた人が多く、新しい環境においても、これまでの感覚で立ち振る舞ってしまいがち。新しい環境で再スタートする際は「謙虚な気持ち」を持つことが大切です。

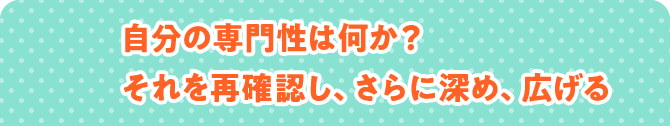
現役時代から専門分野の実務をたくさん経験しておくことが、定年後の自分の強みとなります。専門分野の勉強会などに参加することで、つながりを増やすチャンスも。

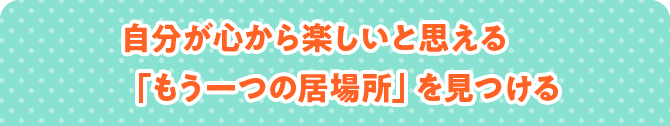
仕事とは別に打ち込めることがあると、生き生きと暮らせます。ただ、どんなことが自分にあうのかを探すには少し時間がかかる場合も。早くからいろいろ体験をしてみて、趣味探しをすることが大切です。
3
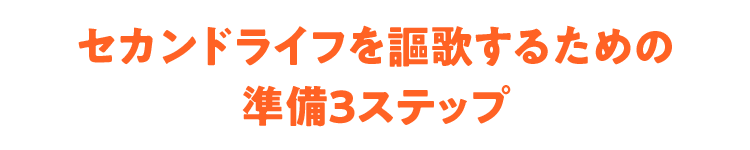
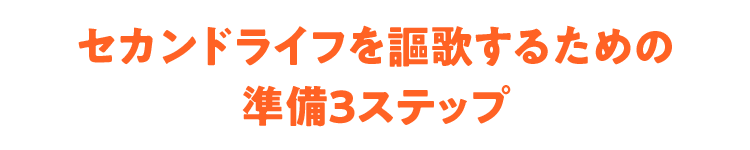
定年後を楽しく過ごすには、まずは「どんなセカンドライフを送りたいか」を具体的にイメージすることからはじめましょう。セカンドライフを充実させるためには、仕事や趣味に対しての備えが必要不可欠。そうすることで、「シニアのリスク3K」と言われている「金」「健康」「孤独」のうちで最も厄介だと言われている「孤独」にも打ち勝つことができるかもしれません。ただし一気に準備するのは大変なので、一つずつできることから。そのための3ステップをご紹介します。
ステップ1



まずは、セカンドライフについての情報収集を徹底して行ないましょう。セカンドライフについて書かれている本や、発信している人などをリサーチ。とにかくいろいろな情報を見て、自分にあうかどうか取捨選択するのがファーストステップです。
見ていくうちに、自分がどんな過ごし方に共感を持てるかが具体的にわかってきます。
ステップ2



いくつもの情報を見聞きしていくうちに、自分の描く理想のセカンドライフに合致するものを見つけられるはずです。そうしたら、それをさらに深掘りしていきましょう。今の時代は、SNSを通じて発信者ともつながることができます。それをうまく利用しましょう。例えば興味を持ったYouTubeチャンネルのオンラインサロンがあったら登録してみたり、著者が開催するセミナーに実際に足を運んでみたり。情報を発信する人とさらにかかわることで、違う側面の気付きが得られるでしょう。スキマ時間にこのようなアンテナをはることで、セカンドライフへのイメージをより具体的に構築できるでしょう。
ステップ3
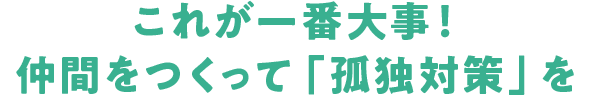
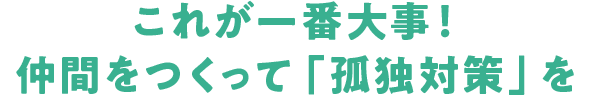
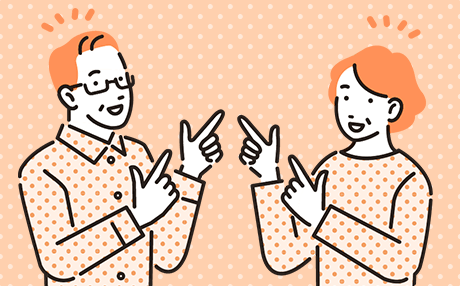
コミュニティに参加することで、定期的に開催されている勉強会などの情報も入ってくるようになります。この「定期的に」というのが大切。定期開催される会に参加することで、だんだんと横のつながりができてきます。同世代で同じ感覚を持つ仲間がいることは、財産です。仲間をつくり「孤独対策」をすることは、セカンドライフを充実させるうえで、最も重要といっても過言ではありません。
4
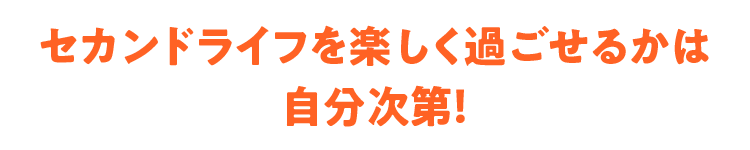
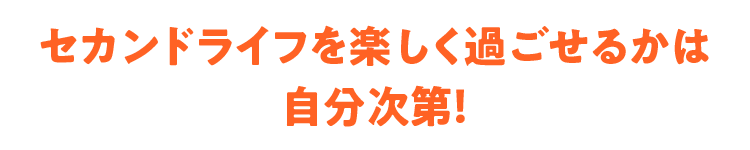

監修
髙橋伸典
監修髙橋伸典
1957年兵庫県生まれ。セカンドキャリアコンサルタント。自身の経験をもとにセカンドキャリアを支援する業務に着手。各自治体、企業などのセミナーにてセカンドキャリアの具体的アドバイスを行ない、5,000人を超える受講者の行動変容につなげた実績を持つ。現在は「東京定年男女の会」を主宰。著書に『退職後の不安を取り除く 定年1年目の教科書』日本能率協会マネジメントセンター、『定年後 自分らしく働く 41の方法』三笠書房(知的生きかた文庫)などがある。
- ※本記事は、2024年12月時点の内容です。
- ※本記事は、当社が髙橋伸典様に監修を依頼して掲載しています。
- ※本記事は、監修者の知識や経験を踏まえて執筆しています。
楽しいセカンドライフを送るためには
お金や健康への備えも必要不可欠!
定年後を楽しく生き生きと過ごすためには、自分も家族も安心できるような「備え」が大切です。また、楽しく過ごすためには、資金も重要。充実したセカンドライフを送るために、資産の増加が期待できる外貨建保険や、もしものときの医療保険を活用しましょう。
明治安田のおすすめの保険
募Ⅱ2402675ダイマ推
この記事を見た方におすすめの保険商品
-
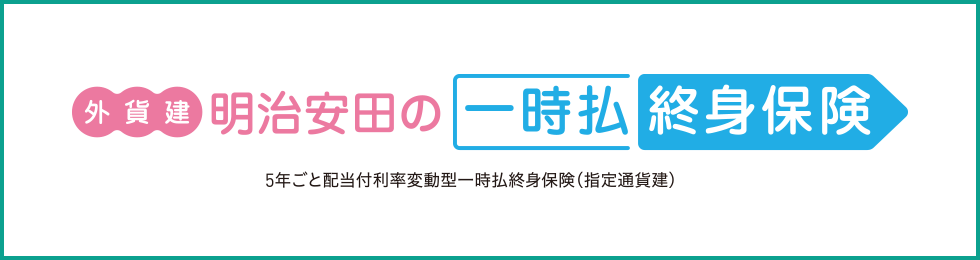
充実の死亡保障を一生涯にわたってご準備いただける米ドル建ての一時払終身保険です。※1※2※
- ※保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)兼コンセプトパンフレット」を必ずご確認ください
- ※この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください
-
- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります
- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の保険金額や返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります
- ・市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる市場価格調整を適用するため、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります
-

一生涯にわたる保障と将来の資金準備を兼ね備えた米ドル建ての終身保険です。※2※3※4※
- ※保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)兼コンセプトパンフレット」を必ずご確認ください
-
※この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください
- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「保険契約関係費用」「解約控除」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります
- ・為替レートの変動により、積立金額が毎回の保険料(円)をご契約時の当社所定の為替レートで試算した金額を下回ったり、お受け取りになる円換算後の保険金額や解約返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を下回り、損失が生じるおそれもあります
- ※この保険は、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約返戻金額を低く設定しています。そのため、この期間内に解約された場合の返戻金額は積立金額を下回ります。特に、この期間内に解約返戻金を円でお受け取りいただく場合の金額は、為替レートの変動により、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を大きく下回り、損失が生じるおそれがあります
-

入院中の治療費だけでなく、治療費以外にかかる費用にも対応できる一時金給付型の終身医療保険です。※5※
- ※保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください
-
※1 この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください
- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります
- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の保険金額や返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります
- ・市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる市場価格調整を適用するため、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります
- ※2 保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)兼コンセプトパンフレット」を必ずご確認ください
-
※3 この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください
- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「保険契約関係費用」「解約控除」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります
- ・為替レートの変動により、積立金額が毎回の保険料(円)をご契約時の当社所定の為替レートで試算した金額を下回ったり、お受け取りになる円換算後の保険金額や解約返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を下回り、損失が生じるおそれもあります
- ※4 この保険は、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約返戻金額を低く設定しています。そのため、この期間内に解約された場合の返戻金額は積立金額を下回ります。特に、この期間内に解約返戻金を円でお受け取りいただく場合の金額は、為替レートの変動により、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を大きく下回り、損失が生じるおそれがあります
- ※5 保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください