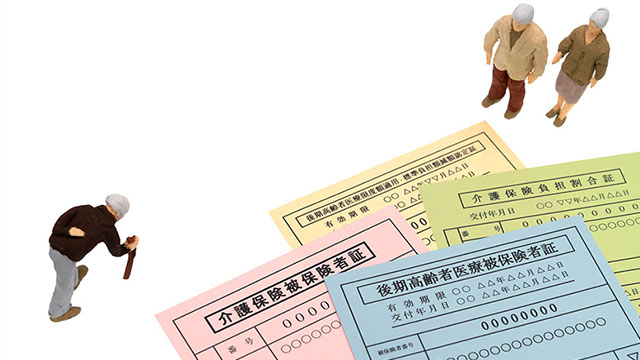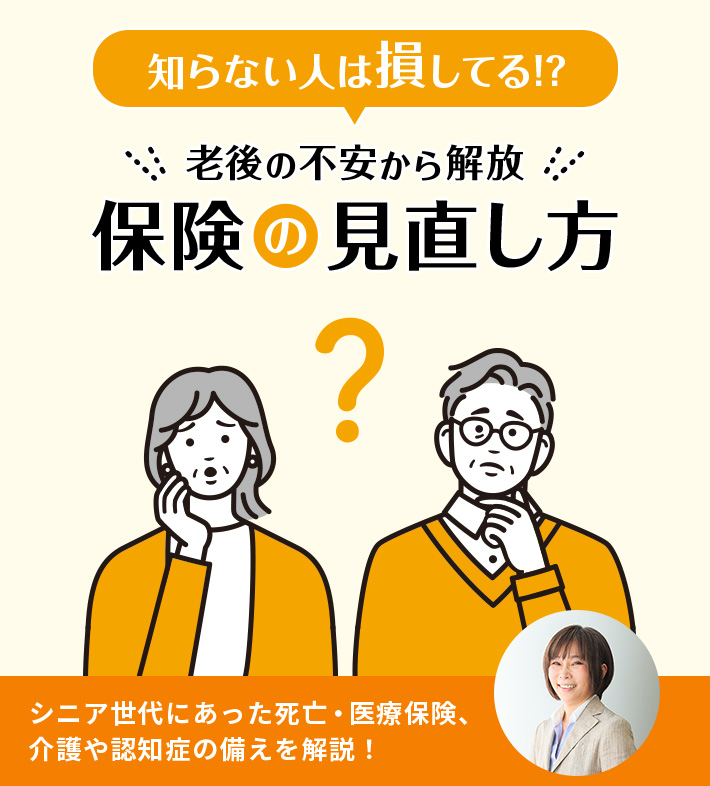
- ※本記事は、2023年6月時点の内容です

夫が定年退職を迎えた佐藤さんご夫婦。
現役時代とは違い、退職金や年金で生活することになり、環境が変わるため、生命保険も見直しが必要かもと感じています。
本記事では、佐藤さん夫婦が、退職後の生命保険の見直しについて、ファイナンシャルプランナーに相談。
見直し方のポイントや注意すべき点をお金のプロに教えてもらいました。
登場人物紹介
-
相談者

佐藤浩さん(65)・久美子さん(60)夫婦
3人の子どもも独立して現在は一戸建てに夫婦二人暮らし。
浩さんが定年退職を迎え、年金生活のなかで介護保険など老後に特化した生命保険について知りたいと考えている。 -
相談に乗ってくれる
ファイナンシャルプランナー
井戸美枝さん
保険の見直しのポイントを解説してくれるファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。
シニア世代ならではのアドバイスが得意。
シニア世代も生命保険の見直しが
必要ってホント?
定年後の生活費を確保しつつ、医療費もしっかり備えていかなくてはいけません。長生きに向けた対策をすることが、幸せな老後につながりますよ。
まずは、加入している生命保険を見直して、今の自分たちの状況にあっているかを確認しましょう。
まずは加入している生命保険の
棚卸しをしてみましょう
- 保障内容は退職後の生活設計にあって
いるか - 死亡保障が過度に手厚い商品に加入して
いないか - 医療介護の保障は万全か
- 保障期間はいつまで必要か
- 保険料は無理なく払える金額か
死亡保険の見直しは
保障内容の検討から
会社員が亡くなり、遺族の条件があえば遺族厚生年金がもらえます。
さらに、18歳未満の子どもがいる場合は遺族基礎年金があります。年金額は、亡くなった人の職業や年収などで異なります。
また、子どもが独立して子どもの生活費や教育費がかからなくなった場合は、多額な死亡保障は不要になります。死亡の保障額を下げるなど、保障型の定期保険なら解約するのも手です。
貯蓄とのバランスを考えながら検討しましょう。
コロナ禍を機に家族葬がメインになってきていますし、合同のお墓や樹木葬などを行なう人も増え、葬式やお墓にお金をかけるという価値観が変わりつつあります。
小規模葬儀なら50~100万円程度、お墓も供養の仕方によって費用を抑えられます。
家族や子どもと相談したうえで、必要な金額を割り出してみることです。
誰のためにいくら残したいのか、
今一度考えましょう
- 葬式の形やお墓はどうするのかを考えつつ、
葬祭費を計算しよう - 死亡保障額は、死亡後の葬儀費用等に困ら
ない程度でOK
医療保険の見直しはリスクを考え、
手厚めに
特に75歳以降は後期高齢者医療制度への加入により、公的保障が変わるため、一定の収入がある方以外は、1割負担で済みます。どの世代にもいえることですが、公的保障で足りない分を民間の生命保険で賄うのが基本的な考え方です。
例えば、入院の際、知らない人と同室になるのは、思った以上にストレスがかかることもあります。個室にすることも見据え、差額のベッド代を民間の保険でカバーできるようにしておくと安心ですね。
質の高い入院生活や療養生活をおくりたいなら、その分お金がかかります。
病気の状態にもよりますが、70代以降は体に負担がかかる先進医療の治療を避け、緩和ケアを重視するケースも多いもの。
最期をどこで迎えたいのか、家族とも話し合っておくことが大切です。
最期をどう過ごしたいか、
考えましょう
- どこでどんな医療を受けたいか。
家で過ごしたいのか(在宅治療)、
病院や施設を望むか - 差額ベッド代は準備しておいたほうが安心
- 70代以降は、緩和ケアを重視するケースも
多い
介護や認知症など、シニア世代
ならではの備えにも注目!
自分たちも将来、子どもには迷惑をかけたくないと思っていますが、だいたいどれくらいかかるものなのでしょうか?
介護期間は、平均5年1ヵ月なので、公的介護保険制度の介護保険サービスを利用した際の負担する費用の総額は、約580万円にもおよびます。
ですが、介護は人によって状況が異なるため、なかなか一律でいえないのが難しいところです。
※1・・・(公財)生命保険文化センター「2021(令和3)年度生命保険に関する全国実態調査(速報版)」より
貯蓄で介護費用を貯める手もありますが、ほかの出来事に使ってしまう可能性もありますよね。
いざというときに困らないためにも、民間の介護保険に入って、しっかり備えておくことをおすすめします。
そうしたときのために、介護費用の備えのひとつとして、生命保険に加入しておくのも有効な方法ですよ。
「指定代理請求人」とは、認知症などで意思表示が難しい被保険者の代わりに保険金を請求できる人のことで、配偶者や直系の血族などが該当します。
認知症保険のなかには、保険金を「指定代理請求人」の口座に振り込むよう調整できるものもありますよ。
認知症の場合、介護サービスによって費用もさまざま。なかには認知症に特化した生命保険もあるので、気になる方は検討してみましょう。
残したい資産が多い人は、保険を利用すると良いでしょう。
また、最近では、生前贈与で対策を考える方もたくさんいますので、そのために活用できる生命保険もあります。
高齢になってから加入できます。
そのほか、「贈与契約書」の作成など、煩わしい手続きを省略できる商品もあるので、贈与の手間を減らすことができる点においても、相続対策に保険に加入しておくことをおすすめします。
この記事を見た方におすすめの保険商品
-
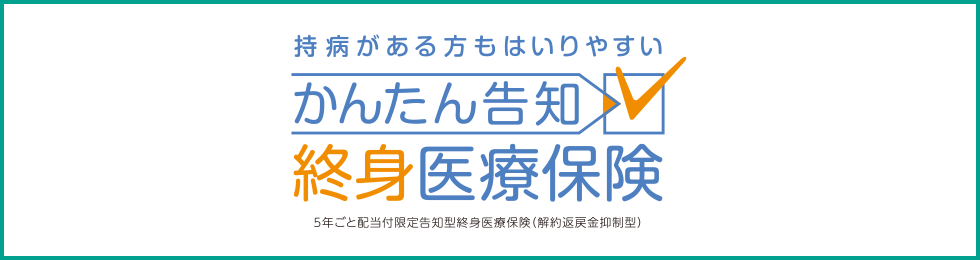
持病がある方もはいりやすい、かんたんな告知で一生涯の保障をご準備いただける一時金給付タイプの医療保険です。
- ※ 保険商品をご検討いただく際は、「保険設計書(契約概要)」または「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください
-

所定の要介護状態に該当したときの一時金・終身年金や万一の保障を一生涯にわたりご準備いただける保険です。
- ※ 保険商品をご検討いただく際は、「保険設計書(契約概要)」または「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください
-

軽度認知障害(MCI)と認知症への備えを一生涯にわたりご準備いただける保険です。※1
- ※ 保険商品をご検討いただく際は、「保険設計書(契約概要)」または「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください
- ※「いまから認知症保険 MCIプラス」は、「軽度認知障害終身保障特約」を付加した場合の「いまから認知症保険」をいいます
-
![市場価格調整機能なし 贈与がかんたん 外貨建 一時払終身保険 5年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[A] Ⅱ型](/dtf/lfm/assets/imgs/common/recommend/product_bnr_dolzouyo.jpg)
お客さまの大切な資産を"かんたん・計画的"に生前贈与できる米ドル建ての一時払終身保険です。※2
- ※ 保険商品をご検討いただく際は、「保険設計書(契約概要)」または「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください
- ※この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください
- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります
- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の死亡保険金・生存給付金・解約返戻金などの合計額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります。また、生存給付金の円換算額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を上回り、贈与税額が大きくなる場合があります
- ※ 保険商品をご検討いただく際は、「保険設計書(契約概要)」または「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください
- ※1 「いまから認知症保険 MCIプラス」は、「軽度認知障害終身保障特約」を付加した場合の「いまから認知症保険」をいいます
-
※2 この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください
- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります
- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の死亡保険金・生存給付金・解約返戻金などの合計額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります。また、生存給付金の円換算額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を上回り、贈与税額が大きくなる場合があります
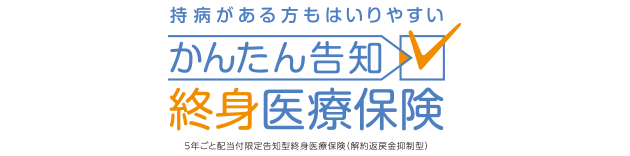
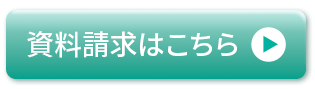
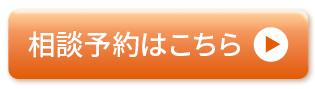


![市場価格調整機能なし 贈与がかんたん 外貨建 一時払終身保険 5年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[A] Ⅱ型](../assets/imgs/life/life16/hoken_bnr_05_sp.png)