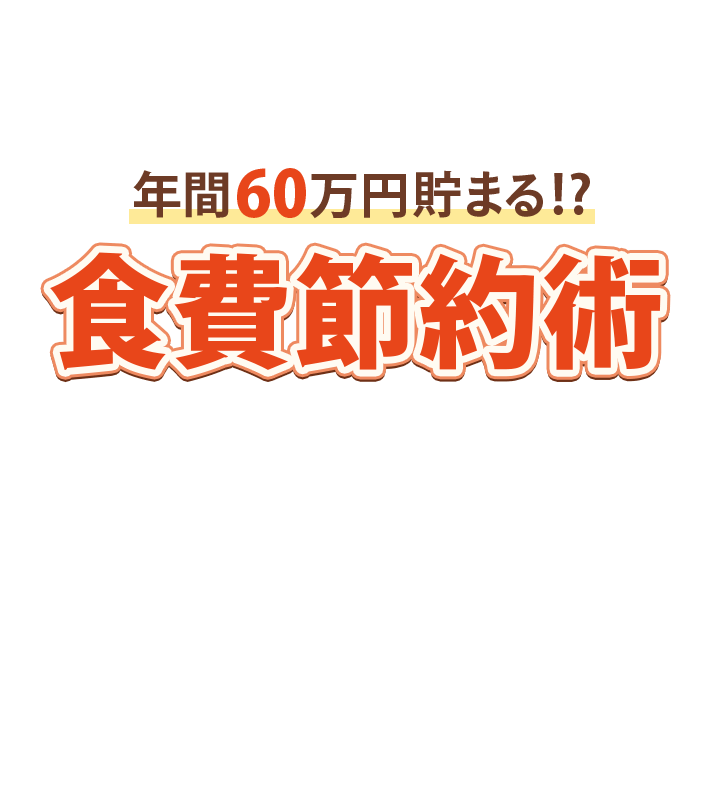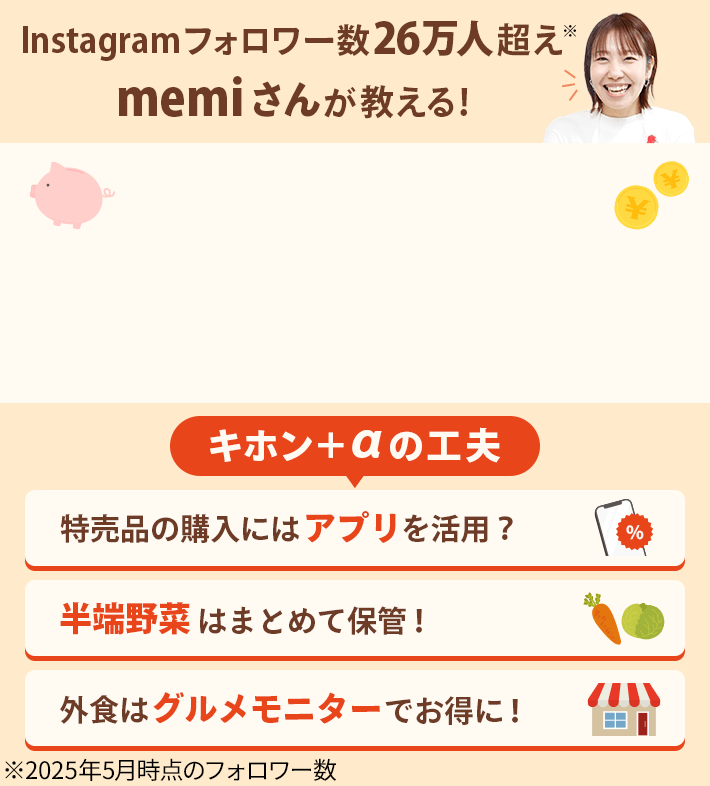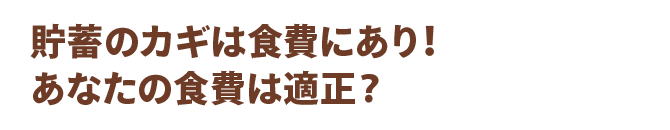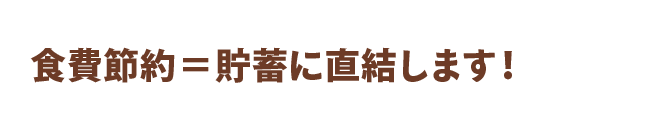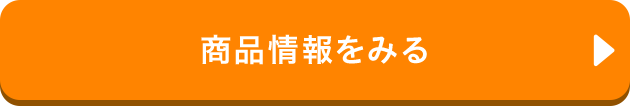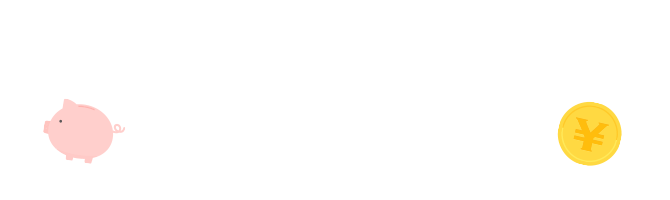
貯蓄を増やすには、日々の食費を見直すことが効果的です。なぜなら、食費は毎日欠かすことのできない支出だからです。食費の節約を習慣化すれば、無理なく継続的に貯蓄ができるようになります。さらに、思い立ったらすぐに実践できるのも、食費節約の大きなメリットです。ただし、食事は健康に生きるために必要不可欠。無理な節約では長続きしません。まずは、今の食費が家計でどのくらいの割合を占めているのか、「エンゲル係数」でチェックしましょう。

エンゲル係数とは、家計の消費支出に占める食費の割合のことです。消費支出とは、住居費や光熱費などの生活費を指しています。エンゲル係数は、生活費において食費にお金をかけすぎていないかをチェックする目安になります。
●エンゲル係数の計算方法は以下のとおりです。
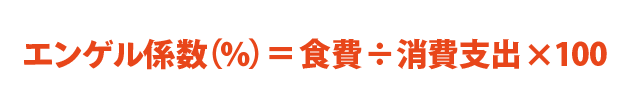
一般的にエンゲル係数の適正値は15~20%といわれてきましたが、近年、物価の上昇などによって、エンゲル係数の平均値が上昇しています。実際、総務省統計局「2024年家計調査(家計収支編)」によると、ふたり以上の世帯の食費は1ヵ月あたり平均85,040円、エンゲル係数は28.3%。単身世帯の食費は1ヵ月あたり平均43,941円で、エンゲル係数は25.9%。どちらも支出の約3割が食費にあてられていることに。家族構成や収入、何にお金をかけるかによって各家庭のエンゲル係数の数値は異なってきます。特に、外食やテイクアウトをよく利用する人はエンゲル係数が高くなりがちです。まずは自分と同じ家族構成の平均値と比較して、自分の家庭の食費を見直し、節約をめざしていきましょう。
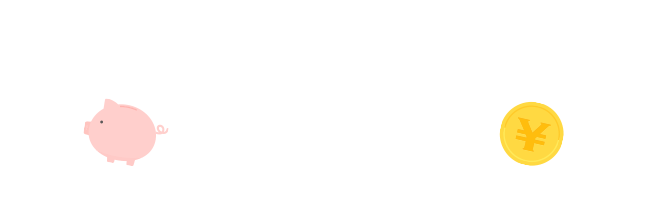
一般的に知られる食費節約術にちょっとした工夫をプラスすれば、さらに効率よく食費を節約できます。誰にでもすぐに実践できて、意外と知られていないけど効果がある「+α」の節約ワザをご紹介します。
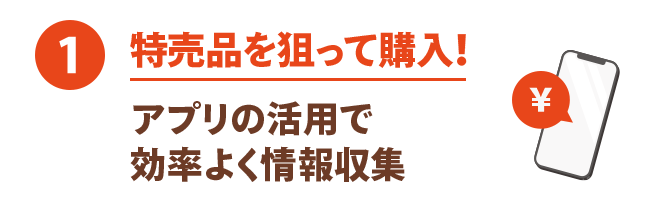
節約の基本は「安く買うこと」。特売品などを積極的に選びたいところです。しかし、スーパーごとに特売状況が異なり、どこが一番安いか把握するのは大変ですよね。そんなときに「+α」で活用したいのが、スーパーやドラッグストアなどのチラシをチェックできる「Shufoo!(シュフー)」などのチラシアプリ。買い物前に複数のスーパーを見比べたり、特売品や安い食材を探したりと、効率的にリサーチができます。
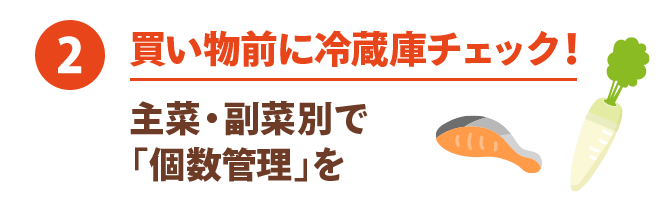
無駄遣いを減らすためには、買い物前に冷蔵庫の中身を確認して足りない食材を把握するのを習慣にすることが大切です。そこで、「+α」でおすすめしたいのが、「主菜」と「副菜」というカテゴリで食材を管理する方法です。主菜になる肉や魚は何個あるか、副菜として使える野菜は何個あるかをチェックして、それぞれに必要な個数をメモ。あとは、決めた個数に沿ってカテゴリごとに安い順で食材を選びます。個数を決めることで衝動買いを防げるとともに、カテゴリごとに必要数を管理するので「今日はじゃがいもが高いから、お値打ちになっているにんじんを買おう」と、柔軟に判断しながら、安さ優先で買い物ができるようになります。
食費節約プラス貯蓄型保険で、
将来への資産形成をより効率的に!
買い物の仕方や献立の立て方などを工夫することで、楽しく食費を節約!毎日欠かすことのできない支出である「食費の節約」を習慣化すれば、「無理なく継続的に」貯蓄ができるようになります。食費の節約と貯蓄型保険をうまく組み合わせて活用することで、将来の目標としている資産形成に、より一歩近づくことができます。
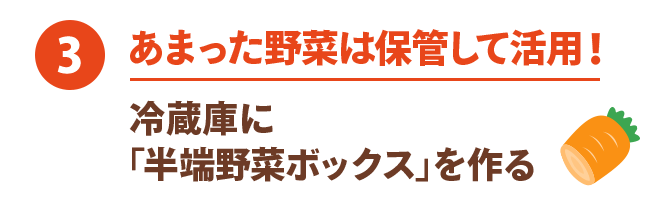
野菜を使いきれずに、あまらせてしまうことがありますよね。半端になった野菜もすぐ廃棄せず、冷蔵庫に保管して賢く活用しましょう。そこで「+α」の工夫です。冷蔵庫に「半端野菜ボックス」を作り、使いかけ野菜をまとめて保管しましょう。こうすることであまっている野菜をひと目で把握できるようになり、無駄なく使いきれます。たまった半端野菜は、カレーや鍋、炒飯などの具材にすることで、一食分の食費が浮きます。

安価で、かつさまざまな料理に活用できる「ひき肉」。そんなひき肉は、フードプロセッサーなどを使って自家製ミンチを作ると、お店で買うより安上がりになります。さらに、小分けにして冷凍しておけば、使い勝手もアップ。加えて、ひき肉をもっと上手に節約する「+α」の方法としておすすめなのが、ほかの食材を混ぜて「かさ増し」すること。例えば、ひき肉で肉団子を作る際、豆腐やお麩、刻んだもやしなど混ぜてかさ増しすると、節約につながるだけでなく、食感も豊かになります。
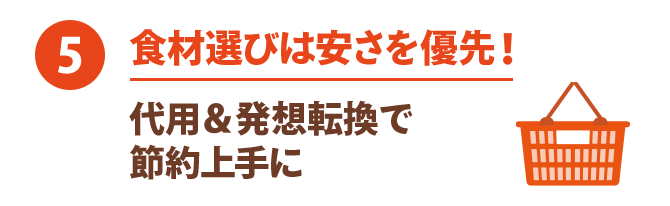
使いたい食材が高くて買えない……。そんなときは、食感や味が似た野菜を代わりに使ってみましょう。高いたけのこの代わりにじゃがいもを使ってチンジャオロースを作る、葉物野菜が高かったので日持ちのよい根菜でサラダを作るなど、柔軟に食材を使うようにすることで、節約しながら料理ができます。さらに「+α」の節約術として、特売の食材をきっかけに、新しい料理にチャレンジしてみるのもおすすめです。例えば、「チンゲン菜は使い方がわからない」と敬遠されがちですが、レシピサイトで検索すれば、意外と多くの活用法が見つかります。一度試してみておいしかったら、そのまま料理のレパートリーに加えていきましょう。
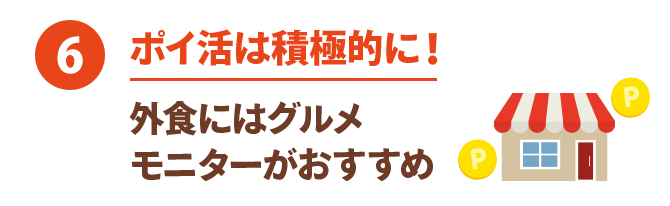
日々の買い物やサービス利用でポイントを貯め、そのポイントを活用する「ポイ活(ポイント活動)」。すでに実践している人も多いかもしれません。ポイ活の対象となるサービスはたくさんありますが、一歩先をゆく「+α」のポイ活としておすすめしたいのがグルメモニターサービスの活用。気になるお店に応募して当選すれば、食事をしてアンケートに答えるだけで、利用金額の何割かがポイントで還元されます。場合によっては全額返ってくることも。外食をお得に楽しむことができます。

疲れているときはつい外食や惣菜に頼りたくなりますが、そういった無駄遣いを減らせるのが「作り置き」。時間があるときに下ごしらえや副菜の作り置きをしておくことで、忙しい日もひと手間省けて、自炊が楽になります。
さらに、簡単な時短レシピを冷蔵庫に貼っておけば、疲れて献立を考えたくない日も迷わず調理できます。調味料とあまった食材を入れて火を付けるだけの鍋レシピや、あまった具材を調味料と混ぜて焼くだけのホットプレートレシピなど、いくつか自分なりの時短レシピを持っておきましょう。キッチンや冷蔵庫を清潔に保つことも、やる気をアップさせるポイントです。
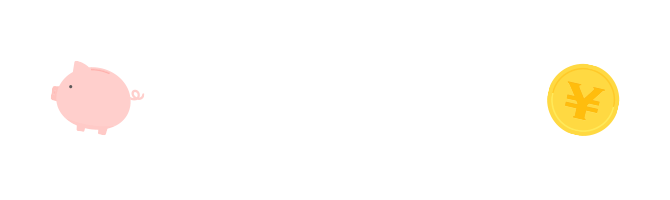
日々の食費を見直すことは支出を見直すことに直結し、貯蓄への近道になります。とはいえ、頑張りすぎても長続きしません。アイデア次第で楽しみを見つけやすいのが、食費の節約。目標のために楽しみながら実践することで、節約を習慣化できます。楽しみながら長く続けられる方法で、毎日無理なく食費を節約して、お金を貯める仕組みを作っていきましょう。

監修
memi
監修memi
夫と小学校3年生の息子と暮らす三人家族で、生活費を「1週間1万円」でおさえるという節約生活を提唱しているインスタグラマー。フォロワーは26万人を超える(2025年5月時点)。三人家族の節約ごはん&節約生活を投稿している。著書『節約ワンプレートごはん』は、シリーズ累計6万部を達成。
- ※本記事は、2025年3月時点の内容です。
- ※本記事は、当社がmemi様に取材を依頼して掲載しています。
- ※本記事は、監修者の知識や経験を踏まえて執筆しています。
食費節約プラス貯蓄型保険で、
将来への資産形成をより効率的に!
買い物の仕方や献立の立て方などを工夫することで、楽しく食費を節約!毎日欠かすことのできない支出である「食費の節約」を習慣化すれば、「無理なく継続的に」貯蓄ができるようになります。食費の節約と貯蓄型保険をうまく組み合わせて活用することで、将来の目標としている資産形成に、より一歩近づくことができます。