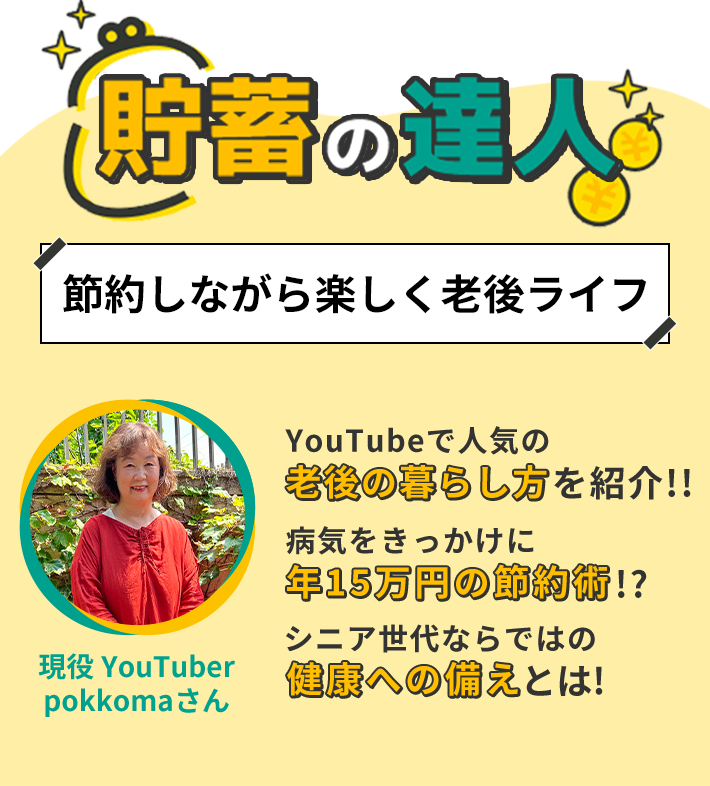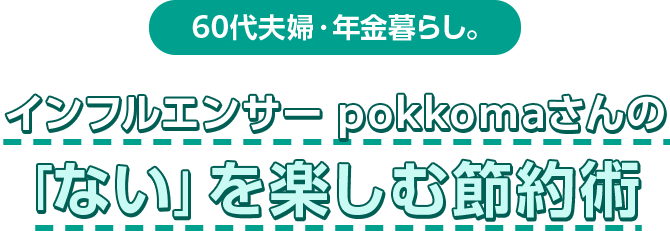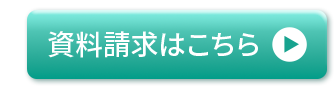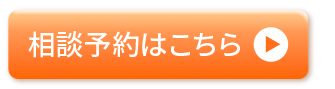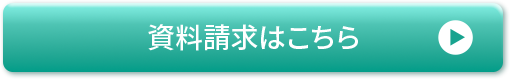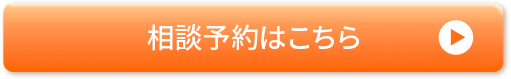60歳で引退するまでは、どんなことをされていたのでしょうか?
pokkomaさん:
設計事務所で働いていました。小さな会社だったので、人事から総務まで担当する、いわゆる「何でも屋」です。子どもが3人いますが、ふたり目までは子育てに専念し、その後は30年間以上、いろんな職場で働いてきました。もともと70歳以降も働くつもりだったのですが、60歳で体調を崩してしまい引退しました。
シニア世代の日常を発信したYouTubeが人気です。はじめたきっかけは?
pokkomaさん:
家で療養生活をしているときに、趣味のパンづくりについて調べていたら、大好きな沖縄の石垣島でのパンづくりをYouTubeで発信されている方の動画に出会いました。「こんな素敵な世界があるんだ!」と興味がわき、私もやってみたいなと。デジタルには苦手意識がありましたが、無料セミナーで学びました。

YouTubeでは、散歩でふと見つけた農家で買い物をしている様子を配信
当時は、老後の生活をYouTubeで発信しているシニア世代がほとんどいない状態。数少ない動画も、年金の堅苦しい内容や老後の厳しいお金事情など、シリアスなものしかなかったので、あえてそのままの日常を発信するスタイルにしたんです。珍しさからYouTubeに取り上げられ、一気に登録者が増えました。
はじめた当初は登録者数や収益を意識していましたが、今は全く気にせず、マイペースで楽しんでいます。暮らしの記録や料理のレシピなどを映像で残すことで、自分がこの世にいなくなった後も子どもや孫たちに思い出を残せるかなと思っています。
現在は、主に年金で生活していらっしゃるのでしょうか?
pokkomaさん:
65歳になったので、年金を貰う手続きをしました。現在は、夫が休職中のため、夫の年金と私の年金で生活しています。そこまで余裕があるわけではありませんが、工夫しながら日々の暮らしを楽しんでいますね。
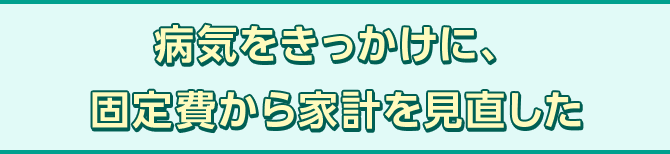
節約をはじめたきっかけを教えてください。
pokkomaさん:
60歳で体調を崩して仕事を引退したのを機に、お金の使い方を見直しました。子どもたちはすでに独立していたので、コンパクトな家に住み替えて、暮らしをミニマムに。2台あった車のうち、1台は処分し、残りの1台は、普通自動車から軽自動車に乗り替えました。サイズダウンすることで、車両保険や車検、ガソリンなどのすべてのコストが下がり、年間で15万円ほどの節約になりましたね。
軽自動車への乗り換えは、節約効果が大きいですね。その後は、何から見直していったのでしょうか?
pokkomaさん:
まずは、自分にかけるお金を見直しました。仕事をしていたころは、月に1〜2回ほど美容室に行き、1回15,000円ほどかかっていました。給料が入ってきたら、そのまま行きつけのブランドでお洋服を買うなど、今思うと、かなり散財していましたね。
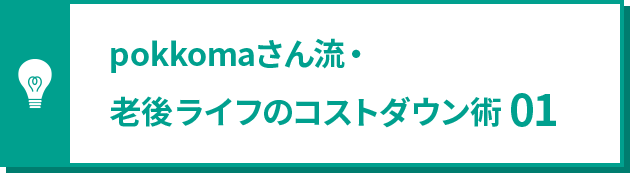
軽自動車に乗り換えることで、
家計のスリム化を実現
2台車がありましたが、1台は処分。残りの1台は、普通自動車から軽自動車に乗り替えました。
サイズダウンにより、車両保険や車検、ガソリンなどのすべてのコストの削減に成功!
- 自動車税
- 年額58,000円→年額10,800円
年額47,200円ダウン - 駐車場代
- 月額10,000円→月額8,300円
年額20,400円ダウン - 保険料
- 年額12万円→同程度の補償で年額63,000円
年額約57,000円ダウン
そのほか燃費がよくなり、ガソリン代もダウン
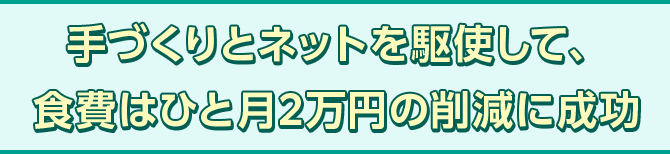
例えば、どのような工夫をされているのでしょう?
pokkomaさん:
食材で足りないものが出るたびにスーパーに行っていたら、余計なモノを買ったりして、出費が増えてしまいますよね。例えば、調味料。マヨネーズがなくても、卵とお酢を混ぜるだけで自家製マヨネーズが完成。それまで、出番の少ない調味料は、賞味期限切れで捨ててしまうことが多かったのですが、家にあるもので代用することで、「このレシピには、この調味料でなければ」という概念が無くなり、節約につながりました。
今は便利な時代で、インターネットで検索すれば、どんなことでも出てくるので、わからないことはインターネットに頼りますね。

「ないから買う」ではなく、発想を変えて、今あるものでアレンジするのですね。シニア世代になると、「デジタルは苦手」とインターネットを敬遠しがちな傾向があります。
pokkomaさん:
慣れてしまえば簡単ですし、代用品で上手くつくれたときは、「やった!」という新しい発見をしたようなプチ感動を味わえます。以前は、家電を買うときも、店にあるなかで商品を購入していましたが、今は、インターネットで必ず価格を比較するように。選択範囲が広がりますし、必要なものだけをじっくり購入でき、ムダ遣いがなくなります。インターネットを通じていろんなことにアンテナを張ることで、知らなかった情報を得ることができ、脳の活性化にもなると思っています。
ほかには、どんな節約をされていますか?
pokkomaさん:
アプリで生産者から旬の食材を直接購入しています。少しキズのあるものを安く購入できる事で、節約はもちろん、食品廃棄を少しでも減らす事ができればいいなと。もともと道の駅が好きでよく行きますが、それよりもさらに安いんですよ。
アプリを活用して、産地直送の食材を直接購入するのはユニークですね。生産者の顔が見えるので安心感もあります。
pokkomaさん:
生産者の方と直接やりとりをする事で、食べ方を教えてもらうなど何気ない交流も楽しみのひとつです。近所に散歩がてら、農家の方から直接野菜を購入することもあります。食は生活の楽しみでもあるので、あまり削ろうとは考えていませんが、冷蔵庫のものを駆使してアレンジし、買い物の回数も多くて週3日程度に減らしたところ、月97,000円かかっていた食費が月2万円ダウン。年間で24万円も減らせました。
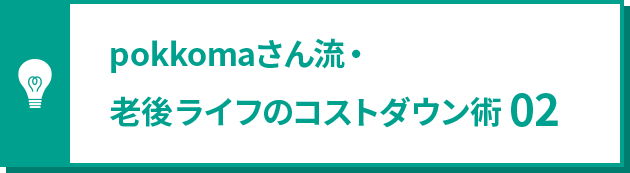
アプリで生産者から直接購入・
足りない調味料は家にあるもので代用!
アプリで生産者から直接購入すると、道の駅より安く済みます。
また、足りない調味料を家にあるもので代用することで買い物の回数を抑えました。
- 食費
- 月額97,000円→月額77,000円
年額24万円ダウン

- 「ないから買う」ではなく、今あるもので
アレンジ - 「デジタルは苦手」と敬遠せずに、インターネットに頼る
バブルを経験している世代は、贅沢を知っている分、節約にネガティブなイメージを持つ人も少なくありません。意識を切り替えるのは難しくなかったですか?
pokkomaさん:
実は、意外とそうでもなかったんです。母の影響で「お金がないなら、ないなりの暮らしを楽しむ」という感覚が身についていたおかげかもしれません。母は、豪快にお金を使う一方で、生活が厳しいときは、500円玉をフィルムケースに入れて貯蓄するなど、ポジティブに暮らしを楽しむ人でした。
お金がないことをネガティブに捉えず、今の暮らしをどう楽しむかに目を向ける。ちょっとした工夫で、心豊かに暮らせます。すべては物事の捉え方しだい。人生楽しんだもの勝ちだと思っています。また、節約するだけでなく浮いたお金は趣味を楽しむ費用にあてていますよ。
「引き締める」だけでなく、「かけどころ」もつくることで、メリハリを意識されているのですね。
pokkomaさん:
夫と一緒に楽しめるものにはお金をかけようと思っています。最近は、体に負担の少ない観劇やコンサートに行くのが趣味なんです。この間は、ミュージカルを観て、感動して帰ってきました。2人分のチケットで28,000円かかりましたが、この先何回行けるかもわからないし、自分たちへのご褒美だと思って楽しんでいます。本当に見たいものを選んで、できれば年に2回くらいは行きたいですね。
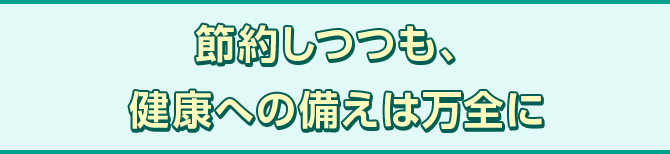
人生100年時代。これからの人生を備えとして、実践していることはありますか?
pokkomaさん:
やはり一番不安なのが、健康ですね。私自身、60歳のときに体調を崩して仕事をやめていますし、今年に入って夫が入院し、現在も通院しながら療養しているので、どうしても医療費がかさみます。一方で収入は減りますよね。ですから、現状にあわせて、保険を見直しました。それまでは保障額500万円の死亡保険に入っていたのですが、3人の子どもたちはすでに結婚して家庭を持っているので、お葬式代くらいを残しておけばという感覚で、保障額を200万円に下げました。医療保険は、負担を抑えつつ、夫が通院を続ける今のライフスタイルにあった見直しを意識しました。
健康への不安が増す年代なので、節約をしつつも、保険でしっかりリスクに備えたいと思っています。出費するところと節約するところを使い分けてメリハリのある家計を意識しながら、ポジティブに暮らしていきたいですね。

- 好奇心と柔軟さで「ないならないなり」
の暮らしを楽しむ - メリハリが大事。引き締めるだけでなく、
楽しむお金もキープ!

Profile
pokkoma
Profilepokkoma
66歳、マンションに夫とふたりで暮らす。YouTubeチャンネル「pokkoma life」を運営。料理や掃除などのなにげない日常を投稿し、つつましくも前向きな暮らしぶりがシニア世代に人気。著書に『60歳を過ぎてから見つけるちいさな暮らしの幸せのヒント』(Gakken刊)
- ※本記事は、2023年7月時点の内容です。
- ※当コラムは当社が、pokkoma様に取材を依頼して掲載しています。
無理をしない緩やかなペースで、自分らしい節約ライフを楽しむpokkomaさん。
「こうではなくては」と、これまでの価値観ややり方に固執せず、新しい挑戦を楽しみながら、暮らしに取り入れていくしなやかさは見習いたいもの
です。
pokkomaさん流の暮らしをヒントに、家計を見直し節約に取り組んでみてはいかがでしょうか。
募Ⅱ2302027ダイマ推