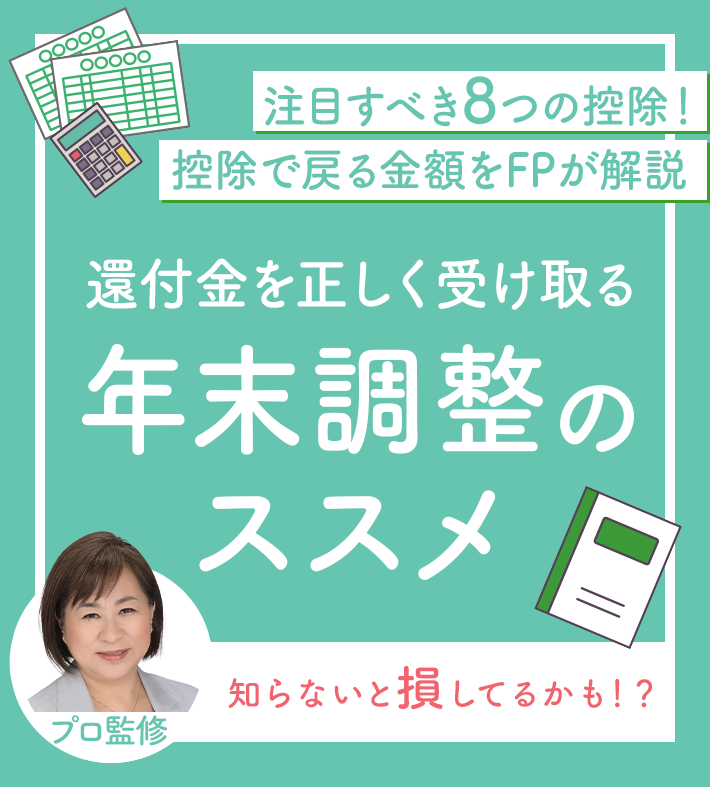
- ※本記事は、2023年7月現在の内容です
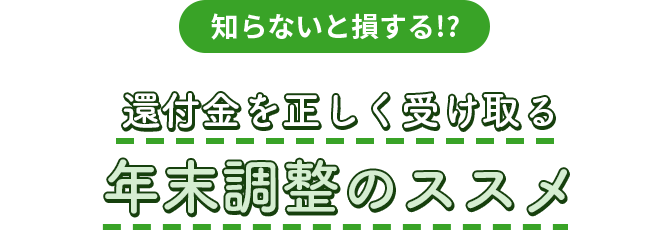
12月が近づくと、気になるのが恒例行事の年末調整。書類の準備等もありやや面倒に感じますよね。でも年末調整は、税金を支払いすぎていた場合に、それらを正しく戻してもらうための大切な作業。損をすることのない年末調整を行なうためのポイントと、具体的な家族構成をもとにした控除額の例を紹介します。
- ※所得税には復興特別所得税(東日本大震災からの復興に用いられる税金。所得税の2.1%)も付加されますが、コラム内では省略しています。
- ※控除とは、「一定の金額を差し引く」という意味。税金について使われる場合、課税対象となる所得金額や納付すべき税金の額から一定の金額を引く制度を指します。
- ※税務上の取り扱いについては2023年7月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取り扱いが変わる場合があります。個別の取り扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
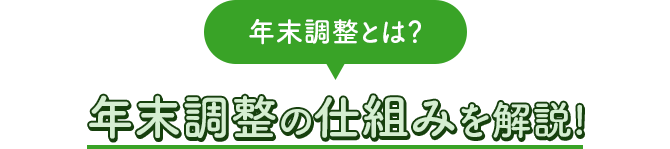
会社から給与をもらっている人は、毎月の給与等から所得税が天引き(源泉徴収)されているかと思います。会社では源泉徴収した税金を、社員の代わりに納税する仕組みになっています。
この天引きされている税額はあくまでも概算で、国税庁の「源泉徴収税額表」に基づいて求められています。
最終的な納税額は、1年間(1月~12月)に支給された給与・賞与から各種控除などを引いて確定します。ここで、実際の納税額と天引きされた税額は必ずしも一致せず、過不足が発生することがあり、この過不足を精算するための手続きが年末調整です。そして、年末調整の結果戻る税金を「還付金」といいます。
年末調整を行なう必要があるのは、あくまでも会社に所属している人のみであり、フリーランスなど会社に所属していない人は、納税者本人が税額を確定する、確定申告を行なう必要があります。
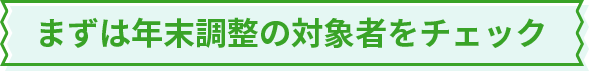
年末調整の対象者となるのは、主に次のような方です。
- 会社などに1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職し年末まで勤務している人
ここには、パート・アルバイトなども含まれます。ただし、給与が2,000万円を超える人など、例外となる人も。給与が2,000万円を超える人は自分で確定申告を行なう必要があります。
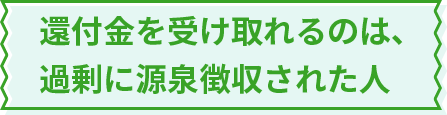
年末調整を行なうことで還付金を受け取れる人は、源泉徴収されていた税額よりも、年末調整後の正しい納税額の方が少なかった人であり、生命保険や地震保険に加入している、住宅ローン控除を受けているなど、後述する控除が多い人ほど戻る可能性が高くなります(源泉徴収税の範囲で)。会社に出していた「扶養控除等申告書」より、扶養親族の数が増えた場合なども還付額が増えます。
逆に、源泉徴収されていた税額よりも、年末調整後の正しい納税額の方が多かった場合は、不足分が調整されます。扶養家族が減った場合などが想定されます。
発生した過不足の調整(還付や支払い)は、12月もしくは1月の給与で行なわれます。また、年末調整により確定した所得税額は、「源泉徴収票」として1月末までに配布されるので、必ず目を通し、保管しておきましょう。
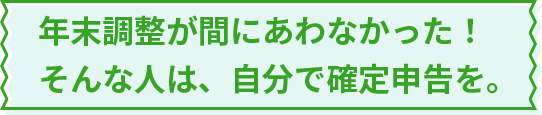
年末調整の手続きや控除証明の書類の提出が間にあわなかった…という場合は、自分で確定申告を行なうことになります。
また、医療費控除や住宅ローン控除の初年度分など、確定申告でなければ処理できない控除もあります。そういった場合も、年末調整を行なったうえで、さらに確定申告が必要です。
確定申告の申告期間は、翌年の2月16日から3月15日まで。国税庁サイトのe-Taxを利用して、PCやスマートフォンで行なうこともできます。
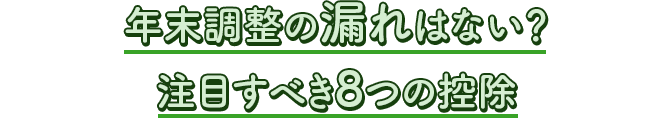
では、年末調整で押さえておくべき控除にはどのようなものがあるでしょうか?
ここでは主要な8つの控除を紹介します。控除とは所得税の計算の際に、所得から差し引いたり、なかには算出した所得税額から差し引くことができるものです。
もうすでに知っている!という人も、今一度見直してみましょう。もしかしたら、忘れていた控除がまだあるかもしれません。
-

まずは必ずチェック!扶養控除
生計を一にする16歳以上の親族のうち、合計所得金額が48万円(給与収入103万円)以下の場合、控除を受けることができます。年齢は12月31日現在で判断します。
<控除額>
- 一般の控除対象扶養親族(16歳以上)
- 38万円
- 特定扶養親族(19~23歳未満)
- 63万円
- 老人扶養親族(70歳以上)
- 48万円(同居老親等:
58万円)
(参照:国税庁サイト)
-

所得額に応じて額が決まる基礎控除
「基礎控除」は、合計所得金額が2,500万円以下である場合に、所得額に応じて最大48万円が控除されます。勤務先に「基礎控除申告書」を提出する必要があります。
<控除額>
合計所得金額 基礎控除額 2,400万円以下 48万円 2,400万円超
2,450万円以下32万円 2,450万円超
2,500万円以下16万円 2,500万円超 - (参照:国税庁サイト)
-

本人と配偶者の所得次第で配偶者控除・配偶者特別控除
本人の合計所得金額1,000万円以下で、同一生計で合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合に受けられるのが配偶者控除です。合計所得金額が48万円超133万円以下の場合には配偶者特別控除が適用に。
<控除額>配偶者控除
納税者本人の
合計所得金額控除額 一般の控除
対象配偶者老人控除対象
配偶者
(70歳以上)900万円以下 38万円 48万円 900万円超
950万円以下26万円 32万円 950万円超
1,000万円以下13万円 16万円 <控除額>配偶者特別控除
控除を受ける納税者本人の
合計所得金額900万円
以下900万円超
950万円
以下950万円超
1,000万円
以下配偶者の合計所得金額 48万円超
95万円以下38万円 26万円 13万円 95万円超
100万円以下36万円 24万円 12万円 100万円超
105万円以下31万円 21万円 11万円 105万円超
110万円以下26万円 18万円 9万円 110万円超
115万円以下21万円 14万円 7万円 115万円超
120万円以下16万円 11万円 6万円 120万円超
125万円以下11万円 8万円 4万円 125万円超
130万円以下6万円 4万円 2万円 130万円超
133万円以下3万円 2万円 1万円 (参照:国税庁サイト)
-

年間支払った全額が社会保険料控除
給与から引かれている厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料は、年末調整時に社会保険料控除として精算されます。年間に支払った社会保険料の全額が控除の対象。源泉所得税を算出する際にすでに加味されています。
同一生計の配偶者・子などの社会保険料を支払った場合も、控除の対象です。<控除額>
- 社会保険料控除
- 全額
-

iDeCo掛金は小規模企業共済等掛金控除
会社員でもiDeCoは加入可能です。この掛金は年末調整で小規模企業共済等掛金控除として申告が必要です。全額が控除対象です。
<控除額>
- 小規模企業共済等掛金控除
- 全額
-

最高5万円の地震保険料控除
地震保険料の控除額と旧長期損害保険料の控除額をあわせて最高5万円の控除が受けられます(旧長期損害保険料のみは最高15,000円)。地震保険料控除証明書が必要です。
<控除額>
- 地震保険料控除
- 最高5万円(旧長期損害保険料のみは最高15,000円)
-

「住宅ローン控除」で知られる住宅借入金等特別控除
会社員の場合、住宅借入金等特別控除を受けるには、初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は、年末調整で「住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。控除額は、借入年度や借入額、物件タイプ、経過年数等で異なります。所得税額を計算し終えてから差し引く税額控除です。
-

保険加入で最高12万円の生命保険料控除
生命保険や介護医療保険、個人年金保険に加入して保険料を支払うと、控除を受けられます。控除額は保険の種類や保険料、加入時期によって変わり、保険料控除証明書が必要です。保険の種類により控除の枠は異なるため、確認するようにしましょう。
<控除額>
保険等の
種類旧契約
(平成23年まで)新契約
(平成24年以降)新旧両方が
ある場合一般生命保険料 最高5万円 最高4万円 最高4万円 個人年金保険料 最高5万円 最高4万円 最高4万円 介護医療保険料 - 最高4万円 - 合計 最高12万円 (参照:国税庁サイト)
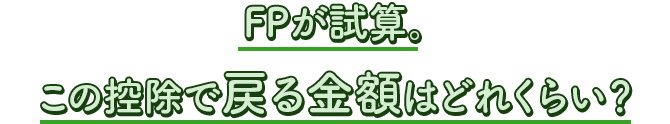
あくまでも試算の範囲にとどまりますが、還付を受けられるケースを、FPのアドバイスとあわせていくつかご紹介します。試算は、特定の控除により戻るであろう金額を、税率から算出した見込み額です。所得とほかの控除との関係で、試算例のように還付を受けられないケースもありますのでご注意下さい。
- ※復興特別所得税(東日本大震災からの復興に用いられる税金。所得税の2.1%)はコラム内では省略しています。
- ※社会保険料は、40歳未満14.7%、40歳以上15%で概算。
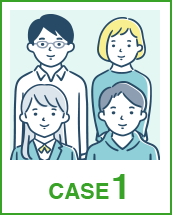
今年16歳になった子どもがいるが、扶養控除の届出を忘れていた
(試算例)

- 本人
- 44歳、年収790万円
- 配偶者
- 42歳、年収200万円、子ども2人(16歳・14歳)
- 年末調整時のそのほかの控除
- 基礎控除48万円、社会保険料控除118.5万円、生命保険料控除8万円
会社に出した扶養控除等申告書に子の扶養の記載忘れていた!
今年16歳になった第1子は扶養控除38万円
年末調整をすることで、子の扶養控除により
76,000円の所得税の還付が見込まれます。
毎年、会社に提出する扶養控除等申告書を書く際には、年末時点の年齢であることに注意。16~23歳未満の子どもだけでなく、70歳以上の親を扶養する場合も扶養控除の記載を忘れずに。
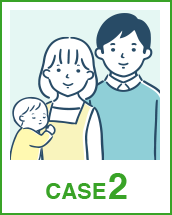
妻が仕事をやめ配偶者控除の対象になった
(試算例)
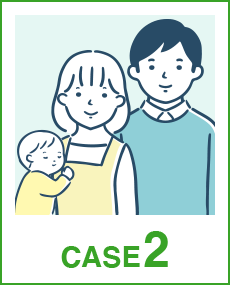
- 本人
- 35歳、年収600万円
- 配偶者
- 33歳、年収0円、子ども1人(1歳)
- 年末調整時のそのほかの控除
- 基礎控除48万円、社会保険料控除88.2万円、生命保険料控除8万円
妻が育休後に職場復帰予定だったが、体調を崩して離職。
会社に出した扶養控除等申告書と異なる内容となり、配偶者控除38万円を受けられることに。
年末調整をすることで、配偶者控除により38,000円の所得税の還付が見込まれます。
会社に提出してある扶養控除等申告書に変更がでた場合は、会社に扶養控除等の(異動)申告書を出すことで、給与から天引きされる税額が小さくて済み、年末調整での精算額も小さくなります。配偶者が仕事をやめ、年収が扶養の範囲になると確定した際には、忘れずに手続きをしましょう。
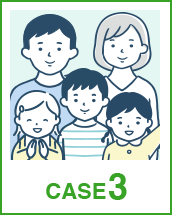
生命保険に加入しているため、生命保険料控除証明書を提出
(試算例)
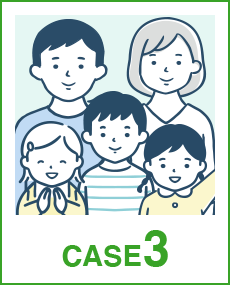
- 本人
- 32歳、年収450万円
- 配偶者
- 28歳、年収100万円、子ども3人(6歳・4歳・2歳)
- 年末調整時のそのほかの控除
- 基礎控除48万円、社会保険料控除66.15万円、配偶者控除38万円
生命保険料控除12万円
年末調整をすることで、生命保険料控除により、6,000円の還付が見込まれます。
10~12月ごろに届く生命保険料控除証明書をなくさないようにしましょう。保険会社のサイトからダウンロードし、年末調整の書類を提出する際にデータで添付できる場合もあります。
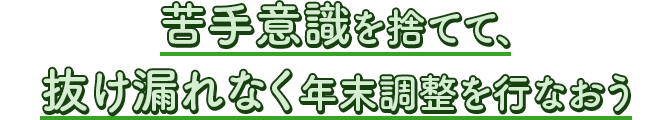
年末調整について、苦手意識を持っている人は多いはず。しかし、年末調整を行なうことで、不足する税金を納めるケースもありますが、多くは支払い過ぎた所得税が還付されます。会社から手続きの依頼が来たら「待ってました!」という気持ちで臨んではいかがでしょう。
自分が納めている所得税はいくらで、どんな控除を受けているのか。納税額が多い場合は、ほかにも受けられる控除はないのか。年末調整は、それらを見直す良いチャンス!知識を身に付けることで還付金を正しく受け取り、上手に税金と付きあっていきましょう。

執筆
豊田眞弓
執筆豊田眞弓
ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー、相続診断士。FPラウンジ代表。個人相談のほか、講演や研修講師、マネーコラムの寄稿などを行なう。6ヵ月かけて家計を見直す「家計ブートキャンプ」も好評。大学・短大で非常勤講師も務める。「50代・家計見直し術」(実務教育出版)など著書多数。
- ※本記事は、2023年7月時点の内容です。
- ※本記事は、当社が豊田眞弓様に執筆を依頼し、掲載しています。
ニーズにあわせた保険を
ご案内いたします
明治安田では、病気・ケガ・就業不能・万一への備えとして、ライフステージの変化に対応した「最適な保障」をご提供する保険や貯蓄型の保険など各種ご用意をしております。
保険の種類や保険料、保障内容、控除の仕組みなど、もし何かご不明な点やお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。控除に関するお悩みやそのほかの内容についても、詳しくお話しできます。
年末調整で控除を活用しつつ、しっかりと将来設計を行ないましょう。
継続的な資金形成のために、
おすすめの積立保険

受取率はいつでも100%以上
いつでも、お払い込みいただいた保険料と同額以上の金額をお受け取りいただけます。
生命保険料控除の対象
明治安田生命じぶんの積立は生命保険なので、生命保険料控除の対象となります。
募Ⅱ2401641ダイマ推

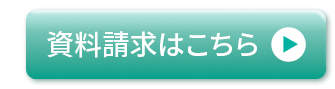
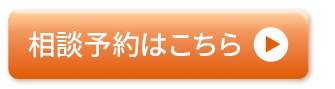

![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/money/money24/tsumitate_logo-4_sp.png)


![万一を支える、健康を応援する ベストスタイル 健康キャッシュバック [5年ごと配当付組立総合保障保険]](../assets/imgs/common/recommend/product_bnr_beststyle_02.png)


