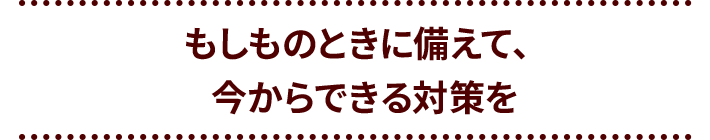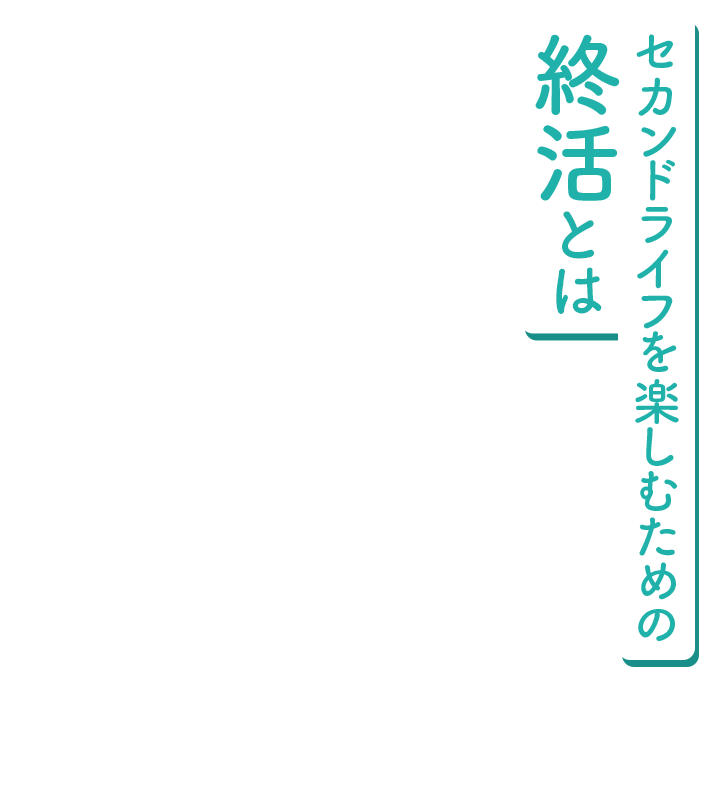

※本記事は、2024年2月時点の内容です
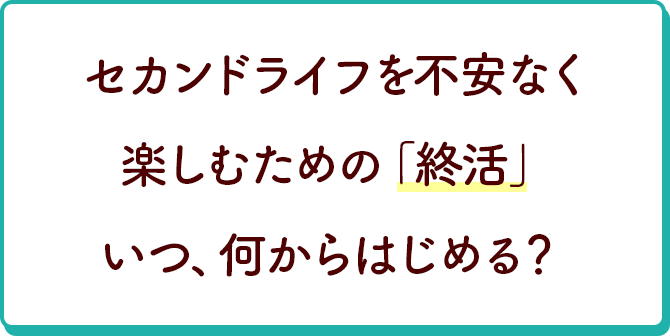
人生100年時代といわれる現在では、「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。ですが、「実際にどんなことをすればいいかわからない」、そんな声も多く聞かれます。そこで今回は、終活アドバイザーとしても活躍するファイナンシャルプランナーの山田静江さんにお話を伺って、終活の目的や意義、ポイントについてご紹介します。
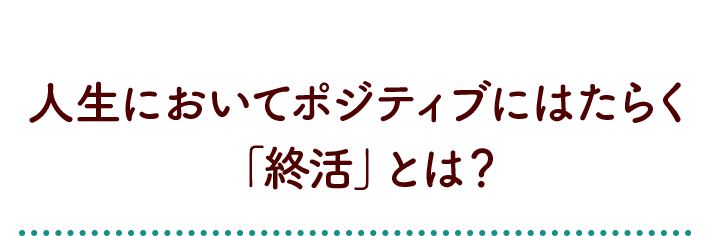
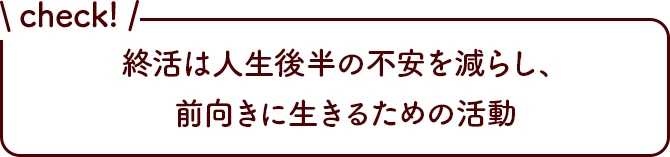
終活とは、充実したセカンドライフを送る方法を考えるとともに、遺された家族の負担を減らすことを目的に行なう活動です。
90歳代はもちろん、100歳を迎える高齢者も珍しくなくなり、後半期の人生は思いのほか長くなっています。多くの人が定年を迎える60歳を人生の後半の開始期とすると、その後の平均余命※は男性で23.59年、女性に至っては28.84年にもおよびます。一般的に、65歳以上の高齢期になると、病気を患う可能性が高く、体力や判断能力も徐々に衰え、日常生活を送るのに周囲のサポートが必要になってきます。さらに認知症を発症して判断能力が低下した場合は、意思表示もままならなくなる可能性も。その場合、誰に何を頼むのか、介護費用や生活費はどうするのか、あらかじめ準備しておく必要があります。また、生前に支えてくれた人のために、死亡後の手続きや相続の備えも必要です。
体力も判断能力もあるうちに、自分の希望を叶えるための計画を立てて、周囲が困らないよう準備を整えることが、終活の最終目的。
終活は、自分の死と向き合うという点でネガティブな印象を持たれがちですが、後半期の人生を不安なく前向きに生きるための計画であり、むしろポジティブな活動といえます。
※ 出典:厚生労働省『令和4年簡易生命表』(主な年齢の平均余命)
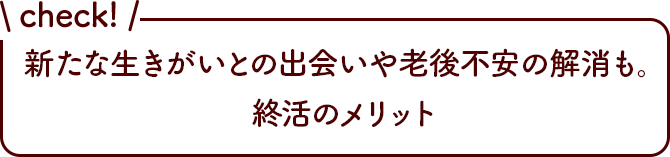
終活を行なうメリットは、個々の置かれた状況で異なりますが、一般的には次のようなメリットが考えられます。
- セカンドライフを前向きに送ることができる
- これまでの病歴、資産の全体像、人間関係など、自分を取り巻く情報を整理することで、検討すべき課題が明確になります。老後資金はどれくらい必要か、認知症やそのほかの病気になったらどうすべきかなど、漠然とした老後不安を解消する手立てを講じることができます。
また、やり残したことは何か、どのような暮らしを望んでいたかなど、心のなかも整理できるので、新たな生きがいや目標を見つけ、後半期の人生を前向きに送ることができます。 - 周囲の人の負担を軽くできる
- 葬儀や埋葬の手配、知人への連絡、役所への届け出、遺品整理や相続など、遺族にはやるべきことがたくさんあります。財産情報、友人・知人の連絡先、葬儀の希望など、終活で整理した情報をエンディングノートなどに記しておくことで、生前も死後も周囲の人の負担を軽減できます。
- 相続トラブルを回避できる
- 財産を誰にどのように遺すか検討し、相続の希望が決まったら遺言書に記すことで遺族間のトラブルを防ぐことにもつながります。
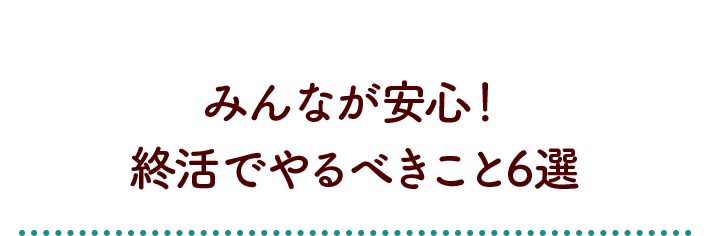
ここからは、実際に終活でやるべきことを6つに絞って紹介します。

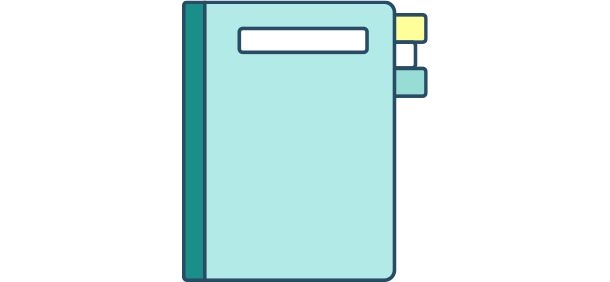
終活で最も大切なのが人間関係の情報を整理することです。なぜなら、人生の晩年など、心身の自由が利かなくなったときには、周囲の人の力に頼らざるを得ない状況に陥る可能性があるからです。まずは、次のことからはじめてみましょう。
- 親族については家系図を書いて
自分との関係性を明確にしておく - 連絡先のリストを作る
入院の手配や身元保証人、認知症になったときの介護や財産管理、亡くなった後の葬儀や埋葬の手続きなど、いざというときは誰に頼るのかを決めて当人にも確認しておきましょう。引き受けてくれる親族がいない場合は、信頼できる友人・知人や専門家に依頼し、契約を交わす必要があります。認知症になったときの財産管理については、家族や親族であっても事前の契約が必要になるので注意が必要です。また、親しい友人や知人の連絡先リストを作っておくと、何かあったときの連絡がスムーズにできます。


家族が亡くなると、遺族がやらなくてはならないことの一つに遺品整理があります。いまのうちに不要な物や遺族が処分に困るような物を整理しておけば、遺族の負担を減らせます。整理のポイントは以下です。
- 愛着のある物は視界に入る場所に出して
おき、邪魔だと感じるようなら処分する - 人に譲ろうと考えている物品は
生きている間に譲っておく - IDやパスワード専用の一覧表を作成し、
信頼できる人に託しておく※
愛着のある捨てられない物でも必要ないと感じるようなら処分するのも一つの方法。人に譲りたい物があれば、親子など近しい間柄を除いては、生前に譲っておくことをおすすめします。遺品となると、故人の思いを受け止めきれないと感じる人も少なからずいるので、あらかじめ相手に確認しておくと良いでしょう。
また、パソコンやスマートフォンには個人情報にかかわるデジタル情報も数多く残されています。後から処分しやすいよう、IDやパスワードを一覧表にしたり、不要な物は削除したりして、いまのうちに整理を。自身が亡くなった後、指定した人がデータにアクセスできるように設定するシステムを搭載したスマートフォンなどもあるので、そういった物を利用するのもおすすめです。
- ※ 情報流出等のリスクもあるため、個人情報の取り扱いにはご注意ください

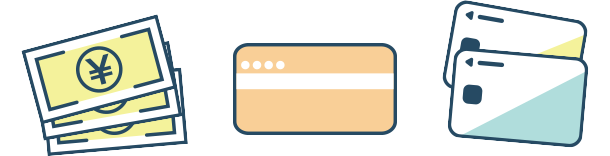
不動産、預貯金や株式、保険など、財産の種類ごとに何がどれだけあるのか把握しておきましょう。財産の種類ごとの整理ポイントの例は次のとおりです。
-

- 家や土地などの不動産資産は、登記簿謄本を取得して、所在地や名義を確認しておきます。過去に相続で取得した不動産などは、名義変更をし損ねていたり、共有名義になっていたりするケースもあるため、あらかじめ名義変更の手続きをしておきましょう。
-

(預貯金・株式・投資信託・債券など) - 預貯金や株式などの金融商品が複数の金融機関に分散している場合は、使っていない口座は解約するなどして、管理しやすいよういくつかの口座にまとめておくと良いでしょう。株式や投資信託を保有している場合は、売却して預貯金口座に入金しておくことも大切です。
-

(生命保険・個人年金など) - 保険証券を見て、契約内容や受取人などを確認し、自分の希望と異なる場合は見直しの手続きを行ないましょう。保険証券が見当たらない場合は再発行の手続きを行なうか、年に一度送られてくる契約内容のお知らせを保管するなどして、いつでも保障内容を確認できるようにしておくと見直ししやすくなります。
-

- クレジットカードの口座から引き落としされる契約がある場合、名義人が亡くなった後も契約を解約しない限りは請求が続きます。複数のカードを利用している場合、遺族はクレジットカードの履歴を一つずつ確認して解約の手続きをしなければなりません。そうした負担を少しでも軽くするために、使っていないカードや契約は解約して整理しておきましょう。また、毎月の利用明細を印刷して取っておくと、支払先の確認がしやすくなります。
不動産の登記簿謄本や保険証券など、財産にかかわる書類はまとめておくと、いざというときに探す手間が省けます。このとき、どこにどれだけの財産があるのか書き出すことも忘れずに。市販のエンディングノートを使えば、終活に必要な情報を項目ごとに書き込めるので、活用してみるのも良いでしょう。
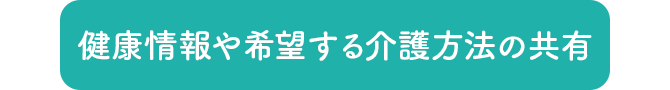

病気やケガによる入院や、高齢者施設へ入居する際には、持病やこれまでの病歴、服薬している薬の種類などの医療情報の提供を求められます。そのため、以下のことを事前に行なっておくと良いでしょう。
- かかりつけ医や
かかりつけ薬局を決めておく - 持病や病歴、服薬などの健康情報の
記録を周囲の人に伝えておく - 介護の希望を伝えておく
一般的に病気のリスクが高まる70歳を過ぎたら、かかりつけ医を決めておくことが得策です。また、自分自身で伝えられないケースも想定して、持病や病歴、服薬などの健康情報の記録はあらかじめ周囲の人に伝えておきます。さらに、認知症を発症するなどして介護が必要になった場合に備えて、自宅介護か施設へ入居するのか、入居する場合はどのような施設を望むのかなど、介護の希望についても伝えておきましょう。
75歳を過ぎて後期高齢者になると一般的に病気のリスクが一気に高まり、健康情報が必要になる機会も増える可能性があります。診療や入院時に必要な健康情報は早めに用意することをおすすめします。
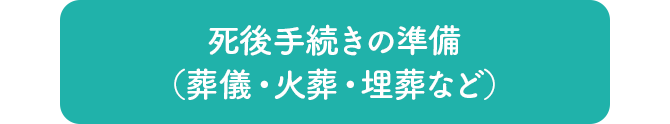
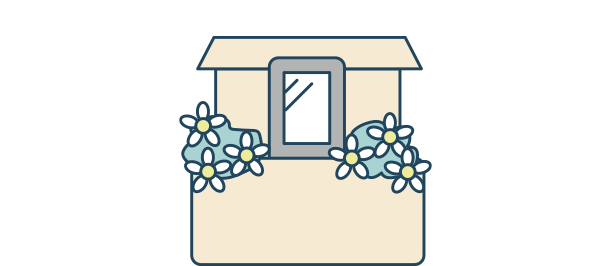
最近では生前に葬儀やお墓の準備をされる方も多く、葬儀は近親者のみの家族葬でお墓は夫婦墓にするなど、「準備は整えてある」という方も少なくないでしょう。しかし、見落とされがちなのが遺体の搬送や安置、火葬から埋葬までの手配など、臨終から葬儀、葬儀からお墓までをつなぐ手続きの準備です。例えば、火葬するには死亡届の提出が必要ですが、死亡届を出せるのは、親族や同居人、後見人等に限られます。頼れる親族がいない場合は頼れる第三者と「任意後見契約」※1と「死後事務委任契約」※2を結んで、手続きを依頼しておくことができます。
- ※1 本人に十分な判断能力があるうちに、信頼できる人(任意後見人)に財産管理などを行なってもらうことを依頼する契約
- ※2 自身の死後に行なう葬儀や遺品整理などの事務手続きを生前に第三者に委任する契約


葬儀や埋葬などの死亡後の手続きを除くすべての項目において、忘れてはならないのが認知症への対策です。
認知症と診断され、意思決定ができないと金融機関に判断されると、資産を保護するために預貯金の引き出しや保険金・給付金などの請求ができなくなります。このような事態の対処として、家庭裁判所が認めた後見人が本人に代わって財産管理を行なう「成年後見制度」がありますが、本人が認知症になる前に本人が決めた人に財産管理を頼める任意後見契約を結んでおくと良いでしょう。
銀行や証券、保険などの取引については、自分で決められるうちに代理人を指定できる代理人制度を利用することもできます。また、高齢化社会のニーズに応えて、介護や認知症など老後のリスクに備える保険商品も多くあるので、老後資金の準備として活用しましょう。
やるべきことが多い終活。作業をスムーズに進めるには、「①自分にかかわる情報を備忘録として書き出す」「②書き出した情報を整理して、課題を洗い出す」「③課題解決のため法的手続きや契約を行なう」と、ステップを分けて行なうことがポイントです。最初は慣れない作業に戸惑うこともあるかもしれませんが、それを念頭に、できるところからはじめてみましょう。
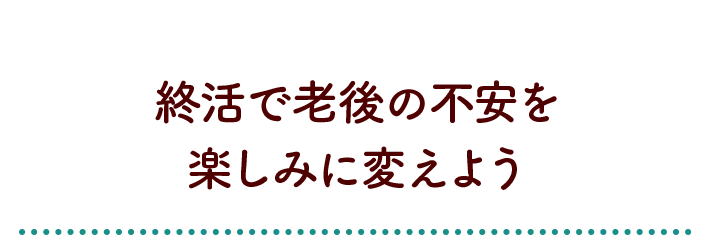
終活のすべてを完了させるにはそれなりの時間が必要ですので、できるだけ早く取りかかることをおすすめします。終活をはじめるのに適齢期はありませんが、遅くとも、体力、気力、判断能力が衰えはじめるとされる75歳までを目途に、ライフステージの変化を機にご自身で決めるのが良いでしょう。例えば、健康に不安を感じたとき、定年を迎えたとき、親の介護や死に接したとき、加えて、親に終活をすすめるためにまずは自分が先にはじめてみるというのも良いタイミングです。また、元気なうちに旅行を楽しむ費用を捻出するなど、楽しみを目標にはじめるのも良い機会になります。終活を行なうことで老後の不安を楽しみに変えていきましょう。

監修
山田静江
監修山田静江
東海銀行(現、三菱東京UFJ銀行)に勤務後、会計事務所および独立FP会社勤務を経て
2001年にファイナンシャルプランナーとして独立。セミナー講師や執筆・監修、相談、FP関連業務の企画等を行なっているほか、NPO法人ら・し・さ副理事長として、エンディングノートの普及活動や、終活アドバイザー協会の運営に注力している。
- ※本記事は、2024年2月時点の内容です。
- ※本記事は、当社が山田静江様に監修を依頼して掲載しています。
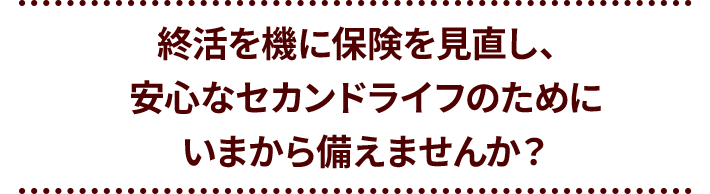
医療や葬儀など、老後は経済的負担もかかってきます。そのため、終活を行なうにあたり、老後資産の計画をしっかり立てておくことも大切です。明治安田は資産運用をして老後の資金対策としておすすめの商品や、認知症のリスクに備えられる商品をご用意しています。また、保険は死亡保険金の非課税枠を利用できるなど、相続対策としても有効です。終活とともに保険を賢く利用して備え、安心できるセカンドライフを送りましょう。
募Ⅱ2402493ダイマ推
この記事を見た方におすすめの保険商品
-
![贈与がかんたん外貨建一時払終身保険 市場価格調整機能なし 5年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[A][Ⅱ型]](../assets/imgs/common/recommend/product_bnr_dolzouyo.jpg)
お客さまの大切な資産を“かんたん・計画的”に生前贈与できる米ドル建ての一時払終身保険です。※1※2※
- ※保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください
- ※この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください
- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります
- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の死亡保険金・生存給付金・解約返戻金などの合計額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります。また、生存給付金の円換算額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を上回り、贈与税額が大きくなる場合があります
-

軽度認知障害(MCI)と認知症への備えを一生涯にわたりご準備いただける保険です。※1※3※
- ※保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください
- ※「いまから認知症保険 MCIプラス」は、「軽度認知障害終身保障特約」を付加した場合の「いまから認知症保険」をいいます
- ※1 保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください
- ※2 この生命保険は米ドル建ての商品のため、以下の点にご留意ください
- ・お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります
- ・為替レートの変動により、お受け取りになる円換算後の死亡保険金・生存給付金・解約返戻金などの合計額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を下回るおそれがあります。さらに、ご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれもあります。また、生存給付金の円換算額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した金額を上回り、贈与税額が大きくなる場合があります
- ※3 「いまから認知症保険 MCIプラス」は、「軽度認知障害終身保障特約」を付加した場合の「いまから認知症保険」をいいます
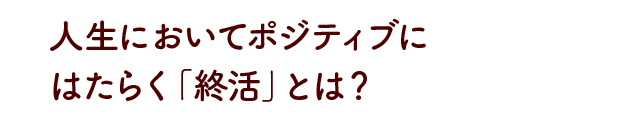
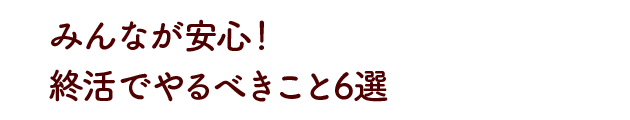
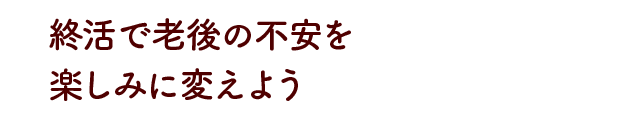
![贈与がかんたん外貨建一時払終身保険 市場価格調整機能なし 5年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[A][Ⅱ型]](../assets/imgs/life/life29/tsumitate_logo-02_sp.png)