
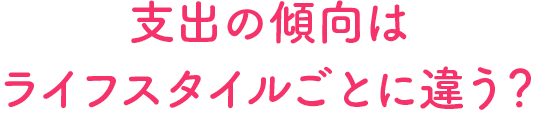

単身世帯の1ヵ月の平均生活費
| 項目 | 平均(円) | |
|---|---|---|
| 住居※ | 36,380 | |
| 食費 | 35,014 | |
| 水道 光熱費 |
電気代 | 4,782 |
| ガス代 | 2,861 | |
| 上下水道代 ・その他光熱費 |
1,515 | |
| 家具・家事用品代 | 3,664 | |
| 被服および履物代 | 7,977 | |
| 保健医療費 | 5,531 | |
| 交通費 | 7,546 | |
| 自動車等関係費 | 7,026 | |
| 通信費 | 6,183 | |
| 教育費・教養娯楽費 | 22,488 | |
| その他 | 諸雑費 (こづかい・ 仕送り金含む) |
12,146 |
| 交際費 | 7,805 | |
| 消費支出 | 160,919 | |
※出典:総務省統計局『家計調査年報(家計収支編)』(34歳未満の単身・勤労者世帯)2022年(令和4年)
※住居費は、現住居が持家で家賃の支払いのない世帯も含んだ平均の金額となるため、賃貸の場合はさらに高い費用となる可能性があります。
総務省統計局の『家計調査報年報(家計収支編)』によると単身世帯の1ヵ月の平均生活費は160,919円。食費の割合がやや高めで、月平均は35,014円となっています。どうしても外食が多くなりがちなため、負担のない範囲で自炊に切り替えるだけでも大きな節約効果が期待できます。
また、ひとり暮らしの場合、家具や家電といった大きな買い物は、サブスクリプションやレンタルのサービスを活用することで出費を大幅に減らすことができます。ひとり暮らしは、水道光熱費や家賃などの固定費の支出が家計の大半を占めるため、それ以外の部分をどこまでカットできるかが勝負。なるべく無理なく、長続きする節約を心がけましょう。

米だけを炊く
「半分自炊」で食費と時間を節約
食費の節約には、自炊の習慣をつけることが最も効果的ですが、ひとり分の食材は割高になるため、かえってコストが高くつく場合も。料理が得意な人であれば、安い食材を購入し、おかずを多めに作って冷凍保存する手もありますが、普段料理をしない人にとっては、時間と手間がかかり負担が大きいでしょう。そこで、お米だけは炊いて冷凍庫にストックしておき、おかずだけを買う「半分自炊」がおすすめです。
会社にお弁当を持参する場合も、ご飯と飲み物だけを持っていけば、すべて外食で済ませるよりも出費を抑えることができます。

家具や家電は所有せず、
サブスクリプションや
レンタルを活用
新生活がはじまるときや、買い替えのタイミングなど、家具や家電の購入には、大きな出費が伴います。貯蓄が少ない人や、あまりお金を使いたくないときにおすすめなのが、家具や家電のサブスクリプションやレンタルサービスを活用して費用を抑える方法。なかには、月額500円程度から最新家電やおしゃれな家具がレンタルできたり、修理や交換などが無料になったりするところも。家具や家電を「所有しない」ことで、引っ越しの費用も安く済みます。
ただし、選ぶ商品や利用期間によっては、結果的に購入するよりも高くなる場合があるため、しっかりと見極めたうえで利用しましょう。
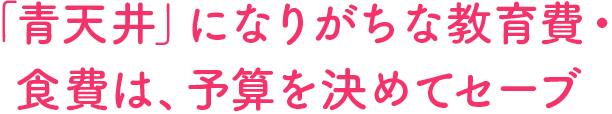
子育て世帯の1ヵ月の平均生活費
| 項目 | 平均(円) | |
|---|---|---|
| 住居※ | 17,043 | |
| 食費 | 87,103 | |
| 水道 光熱費 |
電気代 | 13,414 |
| ガス代 | 5,226 | |
| 上下水道代 ・その他光熱費 |
7,022 | |
| 家具・家事用品代 | 13,920 | |
| 被服および履物代 | 13,109 | |
| 保健医療費 | 13,441 | |
| 交通費 | 5,902 | |
| 自動車等関係費 | 30,194 | |
| 通信費 | 15,075 | |
| 教育費・教養娯楽費 | 63,152 | |
| その他 | 諸雑費 (こづかい・ 仕送り金含む) |
37,990 |
| 交際費 | 11,247 | |
| 消費支出 | 333,839 | |
※出典:総務省統計局『家計調査年報(家計収支編)』(4人世帯・勤労者世帯)2022年(令和4年)
※住居費は、現住居が持家で家賃の支払いのない世帯も含んだ平均の金額となるため、賃貸の場合はさらに高い費用となる可能性があります。
子育て世帯にとって、教育費はやはり頭を悩ませる問題。2022年の総務省統計局『家計調査年報(家計収支編)』によると、4人世帯の生活費は、333,839円。そのうち、教育費は30,253円です。教養娯楽費とあわせると、月6万円ほどのお金を教育費にあてていることがわかります。
そのほか、育ち盛りの子どもへの食費もかなり家計を圧迫するのではないでしょうか。
上表によれば、4人世帯の場合月々87,103円の出費。決して小さな額ではありません。もちろん、子どもにお金がかかり、思うように貯蓄ができないことが多い時期ですが、目標を立て、少しずつ貯蓄を継続していくことが大切です。

買い物の予算は
週単位・日数単位で細かく設定
子どもと一緒にスーパーに行くと、ついつい突発的な出費が増えてしまい、食費の予算が守りづらいもの。計画倒れを防ぐには、月単位で予算を立てるのではなく、週単位や日数単位で使えるお金を細かく把握し、その範囲内で買い物をするように心がけることが大切です。
また、買った食材を「使いきる」のも、大事なポイントです。環境省の試算によると、一般的な4人家族の家庭から出る食品ロスは、年間およそ6万円。つまり、月5,000円も無駄にしているということになるんです。「消費期限切れで結局捨てる羽目に……」ということがなるべく起こらないよう、定期的に冷蔵庫の残り物で料理をするなど、美味しく食べきる工夫をしましょう。

「盛り付け」「かさまし」術
を駆使する
唐揚げなどのメインとなるおかずを大皿にのせて食卓に出すと、あっという間になくなってしまいませんか?そんな悩みを解消するには、「視覚効果」を利用することがおすすめ。複数のおかずを小分けに盛り付けることで、ボリュームのある豪華な食卓に見せるウラ技です。子どものおやつも同様です。グミやクッキー、チョコレートなど、いろんなお菓子をちょっとずつワンプレートに並べて視覚的に楽しませることで、お菓子を袋ごとわたすよりも少ない量で満足感を与えることができます。お菓子の食べ過ぎも防げますし、一石二鳥ですね。
また、豆腐やもやし、ちくわ、鶏むね肉、麩などの食材を料理に混ぜ込み、量自体をかさましすることも、節約効果を高める方法としておすすめです。

日用品は
「ふるさと納税」の返礼品で補う
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体(市区町村)に寄付ができる制度。寄付金のうち2,000円を超える部分は所得税の還付、住民税の控除の対象(所得等に応じた上限あり)となり、さらに地域の特産品などの返礼品がもらえる仕組みです。ふるさと納税と聞くと、カニや牛肉などの豪華食材をイメージする人が多いかもしれませんが、実際には、トイレットペーパーや洗剤、野菜の詰めあわせや豚肉の切り落としなど、日常的に使えるものもたくさんあります。こうした返礼品を活用し、家計の節約につなげるのも賢い方法です。
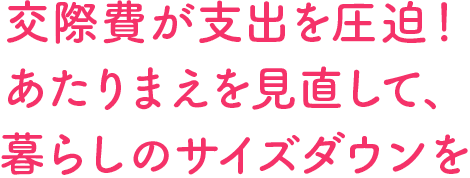
老後世帯の1ヵ月の平均生活費
| 項目 | 平均(円) | |
|---|---|---|
| 住居※ | 16,687 | |
| 食費 | 72,805 | |
| 水道 光熱費 |
電気代 | 12,494 |
| ガス代 | 5,167 | |
| 上下水道代 ・その他光熱費 |
6,870 | |
| 家具・家事用品代 | 11,070 | |
| 被服および履物代 | 5,798 | |
| 保健医療費 | 16,280 | |
| 交通費 | 2,552 | |
| 自動車等関係費 | 17,327 | |
| 通信費 | 10,152 | |
| 教育費・教養娯楽費 | 22,572 | |
| その他 | 諸雑費 (こづかい・ 仕送り金含む) |
29,352 |
| 交際費 | 20,376 | |
| 消費支出 | 249,501 | |
※出典:総務省統計局『家計調査報告書』(65歳以上の二人以上世帯)2022年(令和4年)
※住居費は、現住居が持家で家賃の支払いのない世帯も含んだ平均の金額となるため、賃貸の場合はさらに高い費用となる可能性があります。
『家計調査報告書』を見ると、65歳以上のふたり以上世帯の家計で目立つのは、意外にも交際費。そのほか、保健医療費についても先述の4人以上世帯の平均が月々13,000円程度であるのに対し、65歳以上のふたり以上世帯は月々約16,000円ですから、ほかの世帯と比べて家計のなかで比較的大きな支出となっていることがわかるでしょう。
また、定年後はライフスタイルが変わるため、これまであたりまえだと思っていた支出を見直すタイミング。加入している保険は今の暮らしにあっているか、車は本当に必要なのか。必要か不要かを検討しながら、暮らしをサイズダウンしていきましょう。

必要がないと感じた付き合いは、
思いきってやめる
「おすそ分け」「お返し」の文化で育った老後世代は、お歳暮やお中元のほか、旅行に行くたびに知人へのお土産を買いこんだり、お返しのやりとりを繰り返したりなど、ほかの世代と比べて「贈り物」にお金をかけがちな傾向があります。それ自体は決して悪いことではありませんが、負担に感じている人も少なくはありません。
もしそのような「交際費」が家計を圧迫していると感じるようであれば、「この付き合いは本当に必要か」を吟味し、必要のないものは思いきってやめることも場合によっては必要でしょう。

車は必要なときだけ、
カーシェアリングを活用
車は所有しているだけで、駐車場代、車検や自動車税、保険料など、さまざまな維持費がかかりますよね。暮らしをサイズダウンしたい定年後の家庭にとって、車にかかる費用は大きな負担になります。
ライフスタイルや住環境にもよりますが、カーシェアのステーションが近くにあるなら、思いきって車を手放してカーシェアリングを活用することで、大きな節約効果がのぞめます。車は15分単位で借りられるところが多いため、買い物や病院への行き来など、短時間だけ車を使いたい場面でも、無駄なく利用することが可能です。
また、65歳以上の人が運転免許証を自主的に返納した場合、公共交通機関利用時の運賃割引や、タクシー券の交付などが享受できるため、それらの制度を活用するのも良いでしょう。

今の暮らしにあった
保険を選ぶ・見直す
ライフスタイルが変わるときは、保険を見直すタイミングです。特に定年後はこれまでと暮らしが大きく変わるため、加入している保険の内容について確認する必要があります。その保険は、今の自分たちのニーズに本当にあっているのか、複数の保険に加入している場合は、保障内容が被っていないかなどをチェック。
過剰なものは削ったり、変更したりなどして、家計に負担がかからないようにしましょう。

最後に、家計の支出で大きな割合を占める「水道光熱費」の削減方法についてもご紹介します。ポイントは、「窓」と「給湯」の対策を徹底すること。
これらの二つを重点的に引き締めるだけで、水道光熱費のコストを効率的に下げることが可能です。

窓からの「外気」を防いで
冷暖房の効率アップ
エアコンは、家のなかで最も消費電力の大きい家電の一つです。そんなエアコンをできるだけ効率良く利用するには、窓から入ってくる「外気」をしっかりと遮断することがカギとなります。
プチプチのエアークッションや断熱シートを窓に貼って断熱性を高めたり、窓とサッシの隙間をテープで埋める、カーテンを遮熱カーテンに変えるなどの工夫をしたりすることで、外気を防ぎましょう。

お湯は水の3倍の値段!
入浴時は特に節水を
家庭内で使われているエネルギーの約3割を占めるのが「給湯」。同じ水量でも、給湯器から出てくるお湯と水道の水を比較すると3倍のコストがかかります。つまり、お湯を使う場面で節約を意識することで、水道光熱費をグッと引き締めることが可能です。
特に最もお湯を使う場面である入浴時は、節約のポイント。シャワーを16分間使うと、一般的な浴槽にお湯を張るのと同じだといわれています。そのため、複数人で暮らしている場合などは、浴槽にお湯を張ったほうが結果的にコストを抑えられる可能性が高いでしょう。
体を洗うときも、できるだけ浴槽のお湯を使うことで、水道光熱費を抑えることができます。

今回紹介した節約術は、少しの工夫で大きな効果が見込めるものばかり。明日からの暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。

監修
和田由貴
監修和田由貴
消費生活アドバイザー、家電製品アドバイザー、 食生活アドバイザーなど、幅広く暮らしや家事の専門家として多方面で活動。また、環境カウンセラーや 省エネ・脱炭素エキスパートでもあり、2007年には環境大臣により「容器包装廃棄物排出抑制推進員(3R推進マイスター)」に委嘱されるなど、環境問題にも精通する。私生活ではふたりの子を持つ母で現役の節約主婦でもあり、日常生活に密着したアドバイスを得意とする。
「節約は、無理をしないで楽しく!」がモットーで、耐える節約ではなく快適と節約を両立したスマートで賢い節約生活を提唱している。
- ※本記事は、2023年11月時点の内容です。
- ※本記事は、当社が和田由貴様に監修を依頼して掲載しています。
新年度の今がはじめどき!
節約とあわせて、
貯蓄型保険もはじめてみませんか
新年度は、気持ち的にも資産形成について考えはじめる良いタイミング。
節約によってお金をしっかりと貯めることで、将来的に豊かな生活を実現することができます。あわせて、今あるお金を賢く運用して積極的に増やすことで、より満足度の高い生活を送ることが可能です。
募Ⅱ2302759ダイマ推
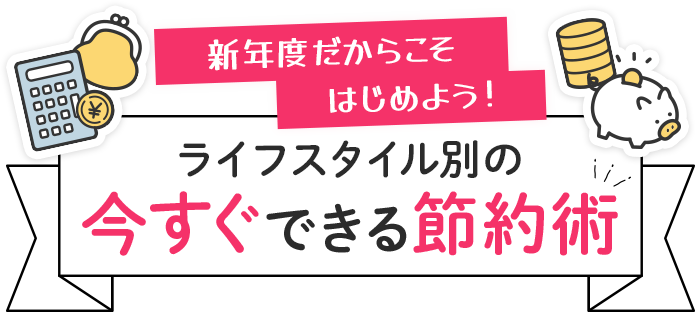

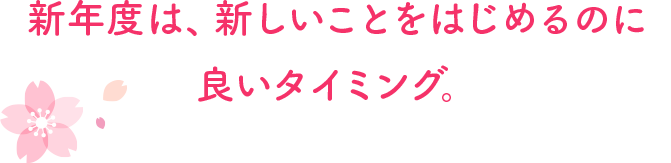
![[単身世帯]](../assets/imgs/life/life25/content_ttl_icon-02_sp.png)

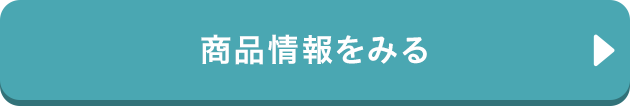

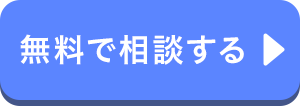
![[子育て世帯]](../assets/imgs/life/life25/content_ttl_icon-03_sp.png)
![[老後世帯]](../assets/imgs/life/life25/content_ttl_icon-04_sp.png)
![[番外編]](../assets/imgs/life/life25/content_ttl_icon-05_sp.png)






