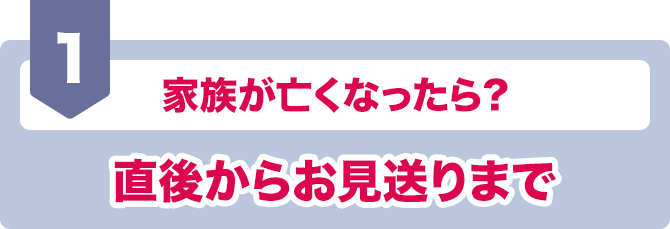
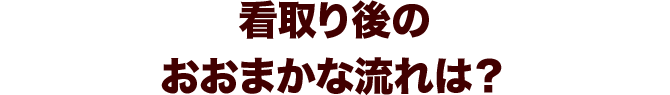
- ご遺体のエンゼルケア(死後に行なう処置)を行ない、搬送・安置
- 納棺後、通夜・葬儀
- 火葬
- 納骨
大切な身内を失って深い悲しみに包まれる当日から、残された家族は多くのことに対応しなければいけません。
まず、病院で亡くなった場合は、医師から「死亡診断書」を受け取ります。
一方、ご自宅で息を引き取った場合は、亡くなり方によって対応が異なります。自宅療養や自宅介護を受けていた場合はまずかかりつけ医に連絡し、療養中の疾患によるものと診断されると死亡診断書が発行されます。かかりつけ医がいない場合は、事件性がないかを確認するため、警察を呼ばなければいけません。警察が遺体の検案と身元確認などを行ない、事件性がなければ死亡診断書に代わる「死体検案書」が発行されます。
それから近親者への訃報の連絡、ご遺体の搬送先を決めること、死亡届や火葬許可申請書の提出など、やるべきことは多岐にわたります。
葬儀会社は病院からの紹介もありますが、希望の予算や葬儀の形をあらかじめイメージし、調べておくと良いでしょう。
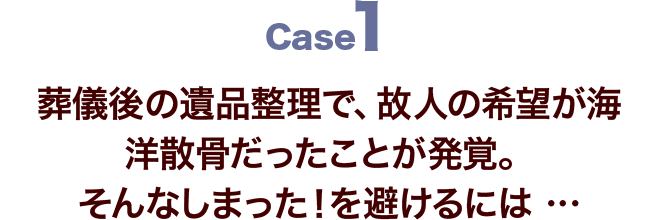
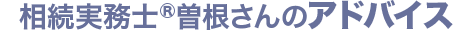
家族が元気なうちに、希望の葬儀やお墓(海洋散骨や樹木葬なども含め)のスタイルを話しておきましょう。

亡くなる瞬間は、誰にもわかりません。家族が元気なうちに、どんな葬儀やお墓(海洋散骨や樹木葬なども含め)が希望かなど、話しておくことも大切です。ご本人が生前に購入したお墓は、非課税財産となるので、相続税の負担軽減にもなります。
何より最期のセレモニーが決まっていれば、残された家族は戸惑うことなくお見送りの準備をはじめられるでしょう。
今は、さまざまな形で見送ることができる時代です。一般的なお葬式でも、香典返しに二次元コードを付け、そこから故人の生前の写真が見られるようにした、という方もいらっしゃいました。残された人々が、ホッとなごみ、前向きになれるアイデアを家族で考えてみるのも良いでしょう。
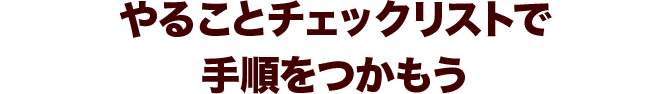
身内が亡くなってから、すべき手続きは多様です。それぞれに期日があるので、優先順位を決めて、終わった項目ごとにチェックを入れていきましょう。
- 訃報連絡
- 死亡診断書または死体検案書の受け取り
- ご遺体搬送の手配
- 葬儀会社の手配と打ち合わせ
- 死亡届・火葬許可申請書の提出
- 葬儀の準備
- 健康保険の資格喪失届(社会保険)
補足メモ
死亡診断書・死亡届はこの後の手続きにも必要。複数枚のコピーを取っておきましょう。葬儀代の領収書は、葬祭費の支給申請手続きに必要なので大切に保管を。
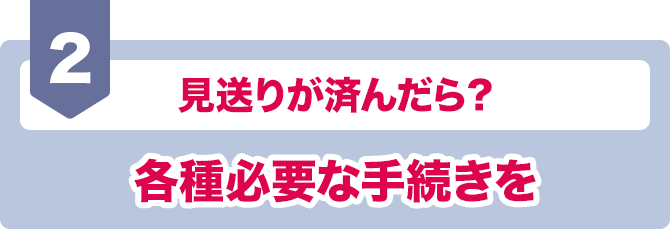
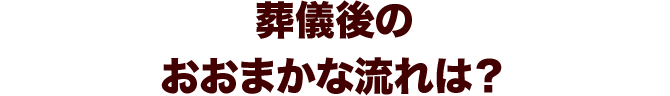
- 役所等への各種届け出・返却
- ライフラインなどの解約手続き
- お金に関する各所への精算・請求
葬儀によるお見送りが済んだら、速やかに必要な手続きや届け出をはじめましょう。多くの手続きが必要となりますが、大きく分けると3種類あります。
まず一つ目は「返却・届け出」。国民健康保険の資格喪失届や世帯主変更届、年金の受給停止手続きや電気・ガス・水道、電話などの解約(または名義変更)です。
二つ目は「精算」。健康保険料と介護保険料の過払い分の還付(または不足分払込み)と住民税残額請求の支払いです。
三つ目は「請求」。生命保険の受取手続きや、団体信用生命保険の手続き、高額療養費・高額介護合算療養費の請求などのほかに、葬祭費(埋葬料)の請求や未支給年金の請求など、申請すればもらえるお金があるので忘れずに確認しましょう。
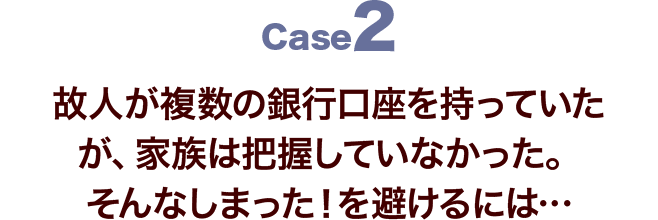
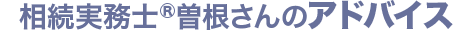
あらかじめ、家族で新制度「貯蓄口座管理制度」を共有しておきましょう。

手続きには、それぞれ期限が設けられているので、手順にそって粛々(しゅくしゅく)と進めましょう。
「誰が」「いつ」「何の」手続きを行なうのかを、身内で分担し、はっきりしておくと良いですね。単独で進めてしまうと、「何かあるのでは?」と、誤解を生む原因になることがあります。代表者ひとりが行なう場合も、ほかの相続人がいる場合は手続きの進捗状況を共有しておきましょう。
さて、多くの手続きのなかでもわかりにくいのが、銀行口座です。名義人が亡くなったら、遺族は銀行に死亡を知らせて、口座の凍結と残高証明書の発行をしてもらいます。同時にクレジットカードなどの解約手続きも行ないます。特に今、ご高齢の方のなかには、一つの銀行に預貯金をまとめず、複数の銀行に一定額を分散させている方もいらっしゃいます。ご本人すらどこに口座を持っていたか忘れているということも。マイナンバー情報を金融機関に提供することで、すべての預貯金口座とマイナンバーを紐づけることができる「貯蓄口座管理制度」がスタートしたので、どこの口座にどれだけの資産があるのかも含め、元気なうちに家族で共有しておきましょう。
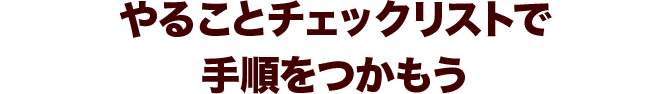

- 国民健康保険の資格喪失届・保険証返却と世帯主変更届
- 介護保険資格喪失届・保険証返却
- 年金の受給停止手続き
- 電気・ガス・水道・電話などの解約・名義変更
- 運転免許証・パスポートなど公的証明書、クレジットカードなどの返却・処分
- 住民税精算の届け出書提出

- 健康保険料と介護保険料の過払い分の還付または不足分払込み
- 住民税残額請求の支払い

- 高額療養費・高額介護合算療養費の請求
- 健康保険に葬祭費(埋葬料)を請求
- 未支給年金の請求
- 遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の請求
- 生命保険の受取手続き
- 団体信用生命保険の手続き
補足メモ
銀行口座は、遺族が死亡を知らせると凍結されます。故人が口座から料金を自動引き落としで契約しているサービスがある場合は、未払いにならないよう注意しましょう。
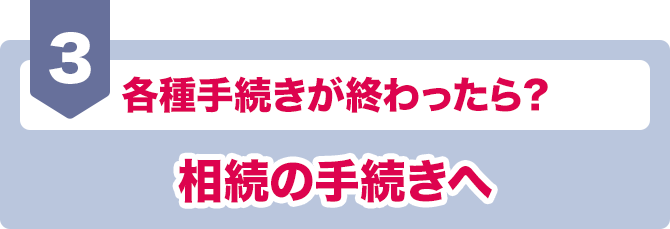
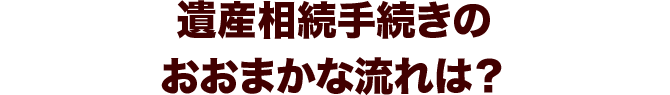
- 相続人の確定・戸籍関係書類収集
- 遺言書の確認
- 相続財産の調査
- 準確定申告
- 遺産分割協議
- 相続税の申告・納付
- 名義変更
「相続」は、人生の節目のなかで向き合う大きな出来事の一つです。財産の多少にかかわらず、亡くなった人の財産は相続人全員が手続きをします。スムーズに進めるために、負債などのマイナスの遺産も含めて、相続財産の調査をしっかり行なっていきましょう。
相続人と相続財産が特定できたら、遺言書がある場合はその内容に従って相続手続きを進めます。
遺言書がない場合は、民法が定めた「法定相続分」を目安に、相続人全員で話し合って遺産分割協議を行ない、合意を得て手続きします。
相続したものによって、それぞれ手続きの内容と期限は異なりますので確認しましょう。相続する財産が、一定金額を超える場合は、亡くなった日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告と納付も必要です。
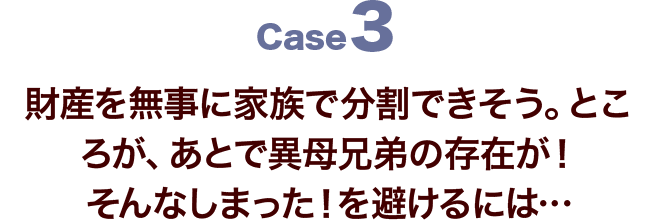
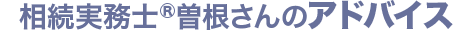
最初にやるべきことは、故人の戸籍謄本の確認です。

相続をはじめるには、まず相続人の確認が必要です。故人の戸籍謄本を確認したら、異父兄弟・姉妹(異母兄弟・姉妹)の存在が発覚し、思いがけない相続人が見つかった、ということもあります。
同時に遺言書の有無の確認をします。遺言書には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。遺言書が法務局に預けられていれば問題ありませんが、遺言書が自宅や金庫などから見つかった場合、家庭裁判所にて検認を受けます。検認を終えても日付の書き忘れや印鑑の押し忘れ、また「○○に相続を託す」というあいまいな表現のために無効になってしまうことも。遺言書の内容をしっかりと確認したうえで、進めていきましょう。
次に相続財産の確認と評価が必要です。不動産の場合は、固定資産税の納付書をもとに評価をします。銀行の預金は通帳や残高証明書で確認します。株式は証券会社で残高証明書を発行してもらいます。
最近は、故人のパソコンのなかを調べたら、ビットコインが見つかったということも。ご本人しかわからないIDやパスワードなどは、あらかじめ書き残しておいてもらうなど、生前からルールを決めておくと良いでしょう。
相続財産がわかり、特に遺言書などがない場合は、「遺産分割協議」を行ないます。この協議は、相続人全員で話し合い、全員の同意で決定することが原則です。それぞれが自己主張を繰り広げないよう、公平な分け方を決められるリーダーを立てると良いでしょう。
協議がまとまらなければ、期限までにいったん法定割合で相続税の申告と納税をし、協議がまとまった段階で、改めて正式な分割割合で申告し直します。
どうしてもまとまらない場合、家庭裁判所に調停を頼むことができますが、調停では財産の分け方は決めてくれても、個々の感情まではすくってくれません。それぞれ別の弁護士を立てれば、相続人同士は話ができなくなります。亡くなった人への感謝と、相続人同士の思いやりでちょっとずつ譲り合い、自分たちで協議をまとめられるようにしましょう。
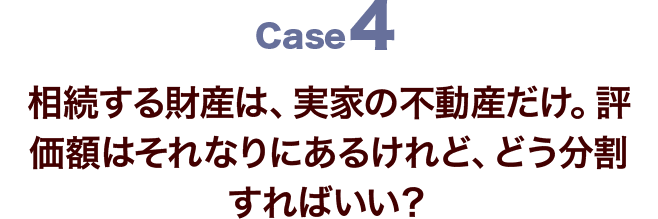
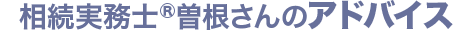
生命保険を活用することで、遺産相続をスムーズに進められます。

相続でよくある問題の一つに、実家の不動産の評価額は高いけれど、財産はそれだけという場合です。遺留分といって、遺言書があっても法定割合の半分の遺留分が侵害されていれば財産を請求できる権利があります。遺留分請求をされたら、その相手に対しては現金で支払わなければなりません。現金がなければ、実家の不動産を相続した人が売却することになりかねません。不動産のように簡単に分割するのが難しい遺産がある場合、相続人の間で不公平感が少なくなるよう、親はある程度の貯蓄をつくっておくのが理想です。生命保険を活用することで、まとまった貯蓄資産を準備したり、簡単に生前贈与することができます。生命保険の死亡保険金には非課税枠がありますので、使い切れば相続税の負担の軽減にもなりますし、遺族が相続でもめない対策にもなります。
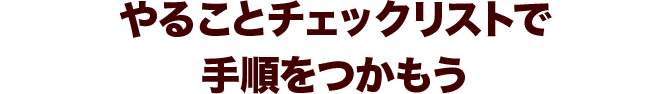
- 被相続人(故人)の戸籍謄本の取得
- 相続人の戸籍謄本・住民票の写し・印鑑証明書の取得
- 遺言書の確認
- 相続財産の調査
- 準確定申告
- 遺産分割協議
- 相続税の申告・納付
- 預貯金・株式・不動産・自動車の相続手続き
- 遺品整理・処分
補足メモ
故人に確定申告の必要があれば、1月1日から死亡日までの所得を計算し、法定相続人が代理で申告する「準確定申告」が必要です。また、「戸籍法の改正」で故人の戸籍謄本も、相続人が暮らしている自治体の役所でそろえられるようになりました。
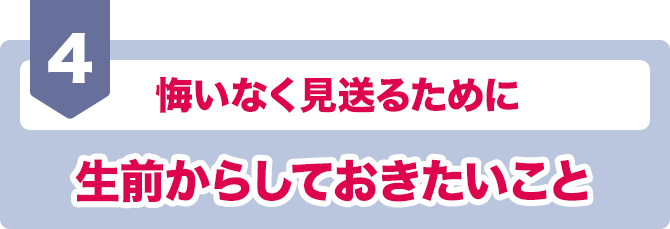

大切な身内を悔いなく見送るには、どのようなセレモニーが良いか、どんなお墓が良いかなど、あらかじめ本人の希望を知っておくことも大切です。元気なうちから家族の思いに耳を傾け、コミュニケーションを深めておけば、いざというときに希望をかなえることができ、落ち着いて見送る手続きを進められるでしょう。
財産もほぼ確定し、子どもたちの様子もわかる70代は、相続や遺言書の準備をはじめるタイミングです。人生100年時代。家族で話をしながら、さまざまな整理を80歳までに済ませておけば、あとの20年をのんびり過ごしてもらうことができます。
親子で一緒に思い出をつくり、人生を振り返ること。財産を整理しておくこと。いざというときのことを考えて準備しておくこと。終活は本人だけのものでなく、家族がこの先を前向きに生きるためのテーマです。
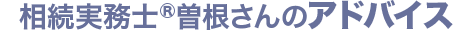

忘れてはいけないのは、旅立ちを目の前にした差し迫ったときより、その前の、ともに過ごせる時間のほうがずっと長いということ。「悔いなくやりきった」という思いで大切な身内を見送るには、何より元気なうちに密なコミュニケーションをとっておくことです。病気が発覚し、入院・手術となってからでは、遺言書の話はもちろん、「相続」というワードも出せないこともあります。
親子でこれからやりたいことをリストアップし、ともに思い出をつくりましょう。エンディングノートも親子で書き進めれば、親がどんな人生を歩んできたかを知るチャンスにもなりますし、絆が深まります。私は父が入院したときに、励みになり思い出にもなるようにと、父の本をつくって自費出版しました。親子でできることは探せば色々あります。
遠方に住んでいても、病院や施設まかせにしないで連絡を取り合い、「今どうしてる?」「これからしたいことはある?」とまず親のことを聞いてあげる。
財産の話をするときは、「あくまで主役はお父さん、お母さん。長生きしてもらうためにサポートしたいし、兄弟・姉妹でもめないように教えておいてね」と伝えましょう。
大事にしたいのは誰かひとりが先走ることなく、子どもたち、兄弟・姉妹全員がそれぞれ親とコミュニケーションをとり、親の希望や情報を引き出し、みなで情報共有しておくこと。そうすれば、より多くのことがかなえられるし、家族でもめることもありません。

監修
曽根恵子
監修曽根恵子
株式会社夢相続代表取締役。相続実務士Ⓡ。公認 不動産コンサルティングマスター。相続対策専門士。出版社勤務を経て、不動産コンサルティング会社にて相続サポートを多く経験したことをきっかけに、相続コーディネート業務を開始。相続対策の提案や実務の窓口となる相続の専門家、相続実務士Ⓡの創始者として、1万5,000件以上の相談に対応し、「家族の絆と財産を守るほほえみ相続」をサポートしている。TVやラジオなどメディアへの出演のほか、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本』(扶桑社)をはじめ、監修書や著書も多数。
- ※本記事は、2024年5月時点の内容です。
- ※本記事は、当社が曽根恵子様に監修を依頼して掲載しています。
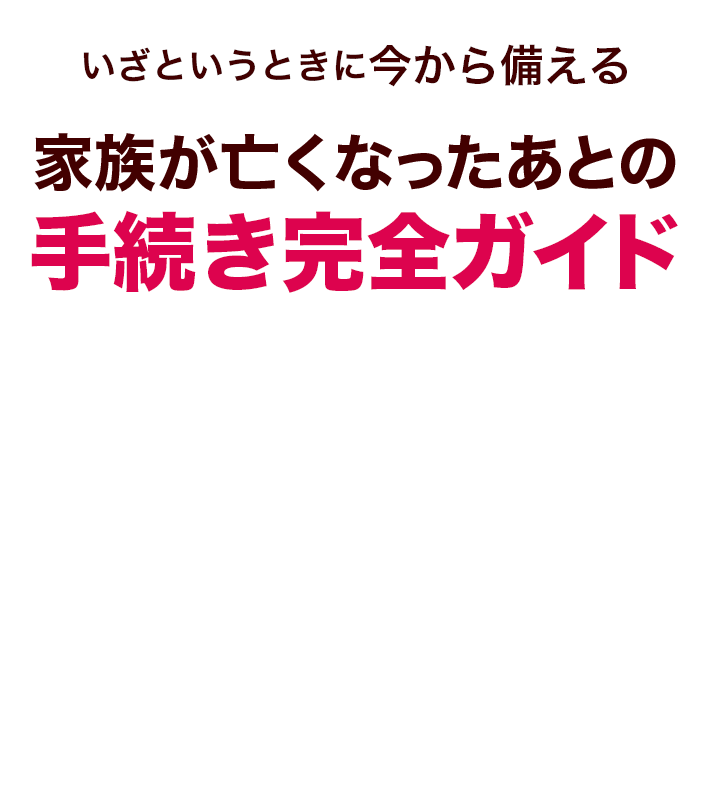
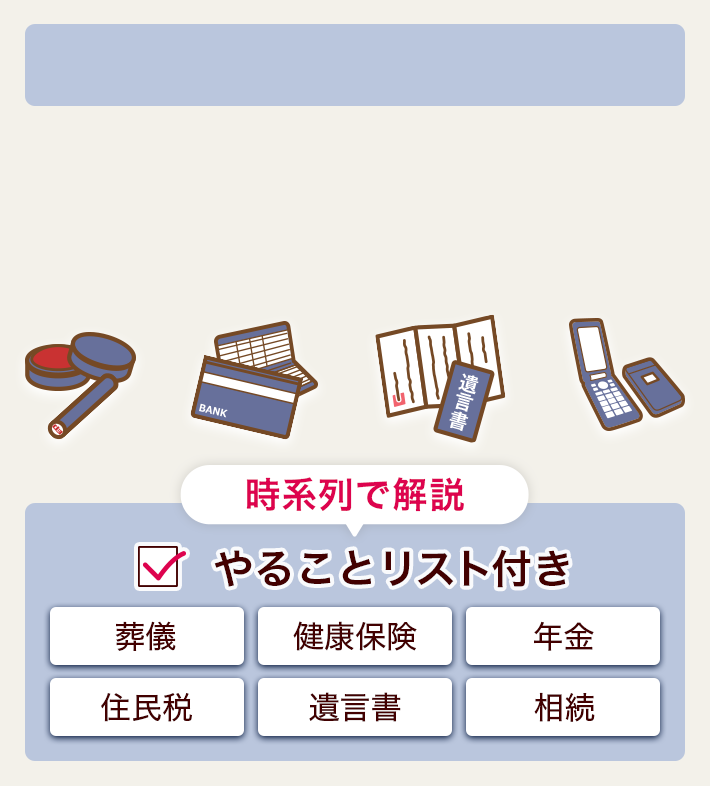

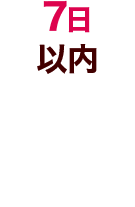
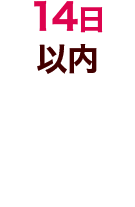
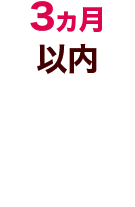

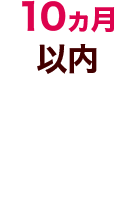





![贈与がかんたん 外貨建一時払終身保険 市場価格調整機能なし 5年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[A] II型](../assets/imgs/life/life33/tsumitate_logo-02_sp.png)



![贈与がかんたん 外貨建一時払終身保険 市場価格調整機能なし 5年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[A] II型](../assets/imgs/common/recommend/product_bnr_dolzouyo.jpg)


