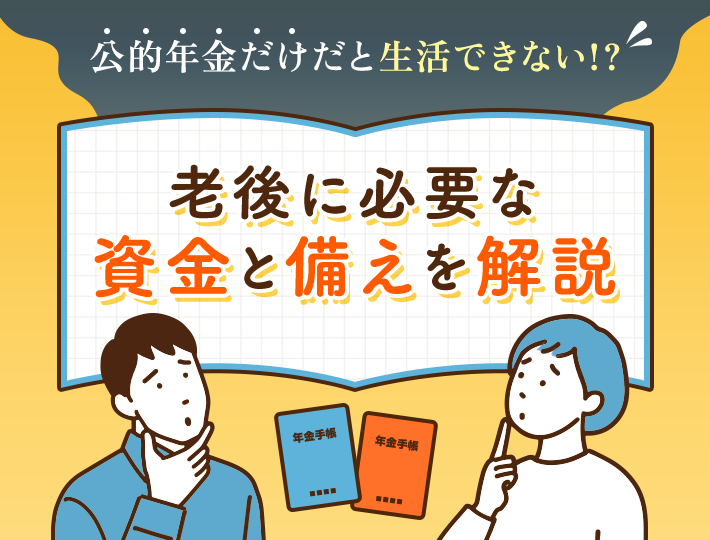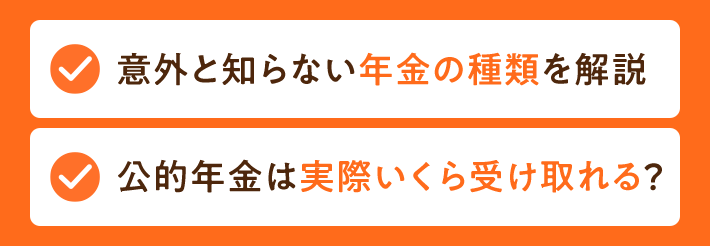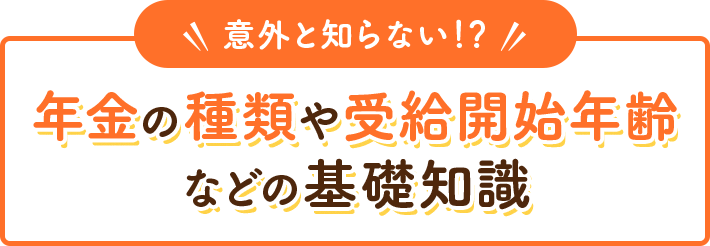

現行の公的年金制度では、多くの方が国民年金と厚生年金の2つに加入しています。国民年金は基礎年金とも呼ばれていますが、この年金は国民全員に加入義務があるものです。一方、厚生年金は主に企業に就業している方が加入する年金です。そのため、フリーランスや自営業者の方など、人によっては国民年金のみに加入している場合もあります。厚生年金の保険料は毎月の給与から天引きされ、企業が同額を負担したうえでみなさんの代わりに国に納めていて、その金額には国民年金の保険料も含まれています。
また、年金は受給開始後、2ヵ月に1回偶数月に、日本年金機構から銀行口座等に振り込まれます。

公的年金の支給開始年齢は65歳とされています。ただし、60歳から受け取れる繰り上げ受給、75歳※まで受け取り時期を遅らせる繰り下げ受給があるため、実際の受給開始年齢は人によって違います。
※1952(昭和27)年4月1日以前生まれの方は、繰り下げできる年齢は最大で70歳となります。

繰り上げ受給とは、簡単に言うと本来の支給開始年齢である65歳よりも早く年金を受け取れる制度のことです。反対に、繰り下げ受給は、年金の受け取りを65歳以降に遅らせることができる制度です。
繰り上げ受給は、受給開始年齢を最大で60歳まで5歳繰り上げることができます。65歳よりも前に年金を受け取りたい方にはメリットのある制度ですが、年金額が1ヵ月あたり0.4%減額されてしまいます。また、一度申請し受給が開始すると、途中でストップしたり変更したりすることはできません。また、万一障害を負ってしまった場合に受け取れる障害年金も、繰り上げ受給で65歳より前に年金を受け取っている方は受給できなくなってしまいます。
繰り下げ受給は、受給開始年齢を最大で75歳まで10歳繰り下げることができます。メリットとしては、年金額が1ヵ月あたり0.7%増加するという点が挙げられます。また、事前申請制ではないので、75歳まで年金を繰り下げるつもりであっても事情が変われば、ご自身の状況にあわせて何歳からでも受け取ることができます。例えば、65歳以上も働けそうであればできる限り働き続けて収入を確保して、働くのが厳しいと感じたら受給を開始する、ということが可能です。
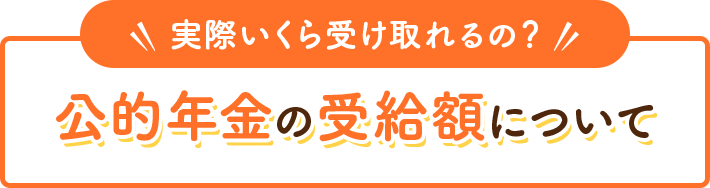
まずは国民年金の受給額について教えてください。

まず、全員が加入義務のある国民年金は、40年間加入すると満額を受け取ることができます。その満額の金額は、物価に連動して国が毎年見直しをして決定されます。ただし、大きく変化することは稀で、おおよそ年額80万円※と思っていただいて大丈夫です。つまり、月額約66,000円※ですね。
※厚生労働省『年金制度基礎資料集』(2023年10月発行)

企業に属して働いている方が加入している厚生年金の受給額は、厚生年金加入期間中の平均年収と勤続年数によって変わってきます。つまり、国民年金と違って人によって受給できる金額が異なる、ということです。(公務員の方も厚生年金に加入していますから同様の仕組みとして読み進めてください。)
具体的な受給額は下記の計算式で計算されます。
「厚生年金加入期間中の平均年収×5.481÷1000×勤続年数」※
参考として、大学卒業後に38年間(23歳~60歳)保険料を支払ったケースを想定し、退職時点の年収別に年金受給額をシミュレーションしてみると、このようになります。
| 年収別の厚生年金受給額シミュレーション | |
|---|---|
| 平均年収400万円 | 約6.9万円/月 |
| 平均年収500万円 | 約8.7万円/月 |
| 平均年収600万円 | 約10.4万円/月 |
| 平均年収700万円 | 約12.1万円/月 |
| 平均年収800万円 | 約13.9万円/月 |
このように厚生年金は、現在の収入が将来受け取れる年金の額と連動していることがわかりますね。
※厚生労働省『年金制度基礎資料集』(2023年10月発行)

自分自身の年金受給額を誰でも比較的簡単に知ることができる方法としては、「ねんきん定期便」と「ねんきんネット」が挙げられます。
計算式が出ているとはいえ、特に厚生年金の受給金額を計算する際に必要な「厚生年金加入期間中の平均年収」についてご自身で正確に把握するのは難しいですよね。
ねんきん定期便は、毎年誕生月の当月もしくは前月に加入者の自宅にはがきもしくは封書で送られてくるものです。こちらには、年金の加入期間や加入履歴、年金の見込額などが記載されています。
また、50歳未満の方と50歳以上の方ではフォーマットが異なり、50歳未満の方にはこれまでの加入実績に応じた年金額が、50歳以上の方には60歳まで引き続き年金に加入した場合の見込額が記載されています。
基本的には国民年金と厚生年金の直近一年分の納付状況が記載されていますが、35歳・45歳・59歳の節目年齢と呼ばれる年には、これまでのすべての期間の納付履歴が記載されています。
一方、ねんきんネットは、ねんきん定期便に記載されている情報がいつでも好きなタイミングで確認できるオンラインのサービスです。こちらでは、常にこれまでのすべての加入履歴や年金の見込額が記載されています。
毎年送られてくるねんきん定期便で受給額を含めた自身の年金情報を確認するのはもちろんですが、ねんきんネットを活用して自主的に確認する習慣が付けられるとより良いと思います。

やはりみなさんが一番気になるのは、年金の見込額だと思います。もちろん、見込額の確認も大切なのですが、この見込額は国民年金と厚生年金の加入履歴に基づいて計算されています。そのため、加入履歴などの記録が間違っていないかどうかを確認することも大切です。
特に、過去に転職や休職のご経験がある方は、その期間の加入状況が正しく反映されているかどうか、しっかりとチェックしましょう。
また、結婚やそのほかの理由で氏名が変更になった方も、記録が正しく引き継がれているかどうか、年金手帳が誤って2冊ないかどうかなども確認しましょう。
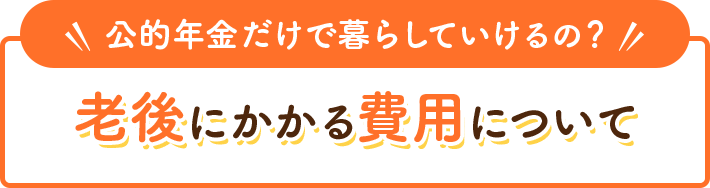
実際、老後は公的年金のみで暮らしていけるのでしょうか?

確かに多くの方々が気になる部分だと思います。年金がどのくらい頼りになるのか検討する際に欠かせないのが、「所得代替率」の考え方。「所得代替率」とは、現役世代の男性の平均の手取り収入に対して、公的年金を標準的に受給しはじめる65歳時点の高齢夫婦ふたりの「モデル世帯」が、受け取ることができる年金額の割合を示したものです。
「モデル世帯」は、夫が平均的な収入の会社員、妻が専業主婦で、夫が40年間厚生年金の保険料を納めた場合を想定しています。国は、現役世代の半分を上回る収入があれば、老後も一定程度の生活水準を維持できるとして、将来にわたって50%以上の所得代替率を確保するようにしています。これが年金の健全性を測る際の物差しです。
現在の所得代替率は、60%程度です。ただ、平均手取り収入額の60%程度の金額で生活できるかどうかは、その人が老後にどのような生活レベルを求めているかにもよるでしょう。
さらに、すべての方が上記「モデル世帯」と同じ働き方をしている訳ではありません。年金受給額は、それぞれの年金加入履歴により異なるので、年金受給額についてはご自身で確認することを意識しましょう。
例えば、世帯別の3つのパターンを例に年金受給額を予測してみると下記のようになります。
| 単身世帯 平均年収500万円 (国民年金・厚生年金あり) |
二人世帯 平均年収650万円 妻は専業主婦(厚生年金なし) |
二人世帯 【夫】平均年収 500万円 【妻】平均年収 400万円 (ともに国民年金・厚生年金あり) |
|
|---|---|---|---|
| 国民年金 | 6.6万円 | 13.2万円 | 13.2万円 |
| 厚生年金 | 8.7万円 | 11.2万円 | 15.6万円 |
| 合計(月) | 15.3万円 | 24.5万円 | 28.9万円 |
※3パターンとも大学卒業後に38年間(23歳〜60歳)、保険料を支払った場合とする
(参考)
- ・令和5年時点での国民年金の満額は795,000円※1
- ・厚生年金の算出方法
「厚生年金加入期間中の平均年収×
5.481÷1000×勤続年数」※2
- ※1 厚生労働省『2023年度版 年金制度のポイント ―くらしの中に、年金がある安心。―』
- ※2 厚生労働省『年金制度基礎資料集』(2023年10月発行)
単身世帯だと月々15万円、二人世帯だと24〜29万円程度の収入となりますが、家賃や光熱費などの固定費を差し引くと、人によってはかなり余裕のない暮らしとなってしまう可能性があります。
このように、みなさんが老後費用について考える際には、自分自身が年金受給年齢になったときの生活水準を予測して、支出額と受給額の差を計算する必要があります。老後の生活水準は、働いているときの生活水準が基準となることが多いため、今現在の生活水準も見直す必要が出てくるかもしれませんね。

老後の備えをスタートするのに「早すぎる」ことはありません。すべての方に「今すぐに行動を開始しましょう」とお伝えしたいです。
まずは、ねんきん定期便やねんきんネットを活用して、自身の年金にまつわる状況を把握しましょう。ほかにも、年金事務所に行くことでも確認できます。
現状を把握したら先ほどお伝えしたようにシミュレーションをしましょう。現在の資産状況と照らしあわせて、老後にお金が足りるのかどうか、足りないのであればいくら足りなくなりそうなのかを把握しましょう。
その後、資産形成を含めて今からでもできることを考えるようにします。
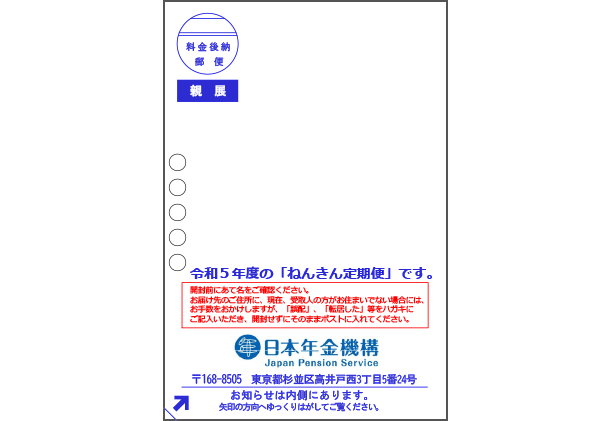
※参照:令和5年度「ねんきん定期便」50歳未満の方

「貯蓄から投資へ」というスローガンのもと、国が国民に資産形成を積極的に促していますよね。ただ、闇雲に資産形成に取り組もうとするのではなく、先ほどもお伝えしたようにまずは自身の年金状況の把握からはじめることが大切です。そのうえで、それぞれに必要な資産形成をするようにしましょう。
公的年金は、おおまかに言うと国民年金と厚生年金の2階建て構造です。この2階建ての年金だけで老後資金をカバーする自信のない人は、自分で3階部分を形成していく必要があります。それが老後に向けた資産形成のことです。
資産形成の方法には、年金保険やiDeCo、NISAなど、さまざまな方法があります。それぞれの特徴を知ったうえで、自分にあったものを選ぶことが大切です。

まずは、年金についての正しい知識を身に付けましょう。ねんきんネットなど専門のサイトから情報を得るのも良いですし、ファイナンシャルプランナーをはじめとする、いつでも相談できる専門家を身近に置いておくことも選択肢の一つとして挙げられるでしょう。
また、結婚して家族がいる方は、ご自身の資産や年金見込額、老後のお金のことなどについて、真剣に話しあうようにしましょう。お金の話は話題にしにくいことかもしれませんが、お互いの大切な未来のためにも早めに話しあうことをおすすめします。

「ある程度」頼りにする、という意識でいるのが良いと思います。公的年金や健康保険などの社会保障制度の目的は、制度の改善こそあれ、いまだ「防貧」の意味合いが強いです。あくまでも最低限の暮らしを維持するために支えあう仕組みなのだと理解しておきましょう。最低限の保険として捉えて、自身の状況にあわせて資産形成などの準備をしておくことが大切です。
また、何よりも長く働ける身体でいることが第一です。健康で働き続けられなければ資産形成も難しくなってしまうので、身体を大切にしながら将来についてもしっかりと考えましょう。

監修
山中伸枝
監修山中伸枝
心とお財布を幸せにする専門家、ファイナンシャルプランナー(CFP®)。
1993年米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業後メーカーに勤務。これからは一人ひとりが、自らの知識と信念で自分の人生を切り開いていく時代と痛感し、お金のアドバイザーであるファイナンシャルプランナー(FP)として2002年に独立。年金と資産運用、特に確定拠出年金やNISAの講演、ライフプラン相談を多数手掛ける。金融庁サイト 有識者コラム連載で執筆を行なうほか、著書に『50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話』(東洋経済新報社)、『ど素人が始めるiDeCo(個人型確定拠出年金)の本』(翔泳社)など。
- ※本記事は、2023年11月時点の内容です。
- ※本記事は、当社が山中様に監修を依頼して掲載しています。
- ※公的年金制度に関する記載は2023年11月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
募Ⅱ2400940ダイマ推