くらま
節約系YouTubeチャンネル『倹者の流儀』を運営。ファイナンシャルプランナー資格保有。生活費は月に5万円、一日一食、家具は段ボールで手づくりなど、徹底的な節約・倹約生活を送り、社会人1年目にひとり暮らしをしながら250万円以上を貯金。現在も会社員とYouTuberを兼業し、節約に役立つコンテンツを動画やブログで発信している。


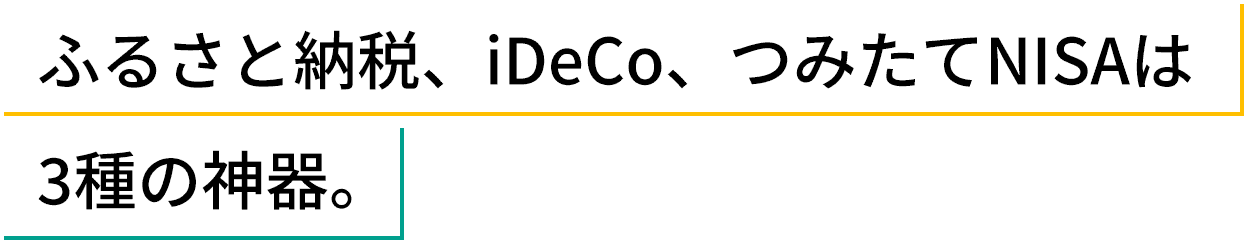
みなさん、やったら得する、やらないと損する。そんな制度がこの世にはたくさんあるのをご存じでしょうか?今回はファイナンシャルプランナーの資格を有し、節約系YouTubeチャンネルの『倹者の流儀』の運営者としても活躍するくらま氏監修のもと、名前は聞いたことあるけれど、手はつけられていない!という方が多い制度をくらまさんの視点で解説してもらいました!
節約系YouTuberとして知られるくらまさんは、会社の家賃補助を利用して、固定費を削減。ポイントを駆使して、買い物や支払いを行なう。そして、家具はダンボールで自作。外食は禁止で自炊がメイン。さらには、上司にもらったお茶や水を持ち帰りそれを自宅で飲む……と、とにかく節約に余念がありません。
こういった積み重ねによってお金は貯められるものですが、コツコツ頑張る節約よりも大きな利益が見込める制度を利用するのもお金を貯めるうえでは必要不可欠!
そこで今回は、くらまさんも太鼓判を押す、お得かつ今すぐでも取り入れるべき制度や仕組みを3つご紹介していきます。※2022年10月時点の税制・制度に基づいた記事になり、今後制度が変更される可能性もあります。
 贅沢できて、税金の控除も
贅沢できて、税金の控除も
くらまさんも積極的に使っている制度で、ぜひともみんなにもしてほしい!と、太鼓判を押すのがふるさと納税。ふるさと納税とは、全国の応援したい地域に寄附ができる仕組みで、寄附金の使い道は選ぶことが可能。地域に貢献しながら、寄附の返礼品として地域の特産物を手に入れられるうえに税金の控除が受けられる魅力的な制度です。
例えば、年収500万円ある独身者で子なしの場合、実質負担2,000円で約6万円の控除※1が受けられるうえに返礼品がもらえるという制度なのです。ちなみに返礼品の還元率は3割が上限のため、選び方次第で18,000円分の価値のある返礼品を手に入れられてしまうのです。
※1……寄附金の控除額は、「所得税からの控除」「住民税基本分からの控除」「住民税特例分からの控除」の3つの控除の合計金額となります。
これだけでもかなりお得でやらねば損!な制度なのは理解に十分。ですがこの制度の魅力は、自分でどこに納税をして、何を手に入れるかをチョイスできる点にあります。例えば、海産物が有名な地域にふるさと納税を行なって、おいしい海産物を手に入れるも良し。お酒が好きなら、酒類の名産地に納税してお酒を手に入れるも良し。工芸品が有名な地域に納税すれば、素敵な器などを手に入れることも可能なのです。
「これほど贅沢に特化した制度はないですから」と、くらまさん。その言葉のとおり普段の節約生活では、買えない贅沢品や嗜好品をねらってふるさと納税しているそうです。
ちなみに、ふるさと納税はさまざまなサイトから行なえますが、例えば自分のクレジットカードやポイントサービスと連動しているものを利用すれば、さらにポイントが加算されるためよりお得にふるさと納税できるとのこと!ぜひ、挑戦してみてくださいね。
 掛金、運用益、給付時に
掛金、運用益、給付時に
続いて紹介するのが、くらまさんが老後の資金を貯めるならコレと、声を大にして推奨するiDeCo(個人型確定拠出年金)です。iDeCoは、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度。掛金を自ら拠出し、自ら運用方法を選んで運用します。そして、掛金とその運用益との合計額を60歳以降に給付金として受け取ることができる制度です。つまり、節税しながら老後の資金を作れる仕組みなんです。
年金もあるし、貯金していればまあ大丈夫でしょう。と、高をくくっている方も少なくないでしょうが、ゆとりある老後に必要とされている金額※2はおよそ2,000万円。年金と利率の低い貯蓄では、本当に安心な老後を迎えられるとは言えません。
会社員の場合年額27.6万円(月額23,000円)を上限(個人事業主の場合は月額6.8万円、年81.6万円が上限)として、掛金を拠出することができます。例えば、年収500万円で企業年金なし、他控除なしの人が30歳でスタートして65歳で受け取りをする場合、毎年上限金額の掛金を拠出すると、一年あたり所得税と住民税をあわせて5万5千円ほど、節税できます。そして、何より大きいのが65歳になって受け取るときのメリット。利回り3%で運用※3した場合でも、およそ145万円が非課税対象になるうえに、積み立て元本が966万円に対して運用益がおよそ725万円。一時金で受け取れば、退職所得控除※4が適用されるためおよそ1,691万円を受け取ることが可能なのです。
ちなみに、これを5%で運用できれば、さらなる資産増加も望めるのです。ちなみにくらまさん曰く、iDeCoはとても守られた財産で、極端な話、もし自己破産で差し押さえになったとしても、iDeCoで積み立てた資産は没収されない資産であるとのこと。
「ただし、このお金を引き出せるのは60歳になってから。まずは、自分の生活を保証するだけの貯金を急いで貯めて、なるべく早く運用を始めてみましょう!」とのこと。少しでも生活に余裕のある方は始めない手はない制度なので、まずはプロに相談してみましょう!
※2……出典:金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」(金融庁)
(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603/01.pdf)
※3……出展:「資産運用シミュレーション」(金融庁)より算出
(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/moneyplan_sim/index.html)
注:あくまで想定であり、3%の利回りを保証するものではありません。
※4……一時金を受け取る前年以前に退職金を受け取った場合、退職所得控除の上限が合算で計算されます。退職金と一時金の双方で退職所得控除を受けるには、取得の前年より4年以上経過が必要条件となります。すなわち、iDeCoの一時金をもらった5年後に退職金を取得すれば、双方に退職所得控除が適応されます。
 少額から始められる
少額から始められる
最後に、紹介する制度が「つみたてNISA」です。「つみたてNISA」は少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度で、毎年40万円(投資できる総額は最大800万円=年間40万円×20年)を上限として一定の基準を満たした投資信託に積立投資することができます。投資を開始した年から、最長20年間の間に得た分配金と売却益(譲渡益)がまるっと非課税となる、優れた制度なのです。ちなみに、通常口座で運用する場合は分配金と売却益に20.315%課税されてしまいます(一部のケースでは加算されない場合もアリ)。
投資と聞くと、これまたかなりハードルが高いと思ってしまいがちですが、つみたてNISAには誰でも気軽に始められる理由が3つあります。一つ目は、長期運用を見据えて積立でコツコツトライできるということ。そして、二つ目は、大金を使うリスクを負わずに資産形成ができるということ。そして三つ目がつみたてNISAで採用される投資信託は、国が定めた低コストかつ、長期・積立・分散に適した基準をすべて満たした商品のみという点。
つまり、長期的な資産形成に適した制度ということなのです。
ちなみに、40万円×20年=800万円をつみたてNISAに投資して、利回り3%で運用できた場合、運用益がおよそ292万円。非課税による軽減効果は59万円。積み立て総額はおよそ1,092万円となります。これを5%に変えて運用できれば、さらなる資産増加も望めるのです。
「投資や株式がわからない人でもトライしやすい制度」と、くらまさんも推奨しているつみたてNISA。少しでも興味がわいたら、こちらもプロにご相談してみるのをオススメします!
というわけで、今回の【みんなが得する制度はコレだ】では、くらまさん監修のもと、知識がなくともトライしやすい制度3選!をお届けいたしました。ふるさと納税に加えて、最近耳にする機会が増えてきた「iDeCo」と「つみたてNISA」。いずれも簡単に始められて、節税ができる。そして返礼品がもらえたり、低いリスクで投資に挑戦できる。そして、老後の資金も貯められる。ぜひ、これを機に始めてみてはいかがでしょうか。それでは、次回の【みんなが得する制度はコレだ】もお楽しみに!
※「iDeCo」と「つみたてNISA」は国が推奨する制度であり、一般の投資や積立と比べてリスクは低いとされています。ですが、損失が発生するリスクもあります。

くらま
節約系YouTubeチャンネル『倹者の流儀』を運営。ファイナンシャルプランナー資格保有。生活費は月に5万円、一日一食、家具は段ボールで手づくりなど、徹底的な節約・倹約生活を送り、社会人1年目にひとり暮らしをしながら250万円以上を貯金。現在も会社員とYouTuberを兼業し、節約に役立つコンテンツを動画やブログで発信している。
募Ⅱ2201345営企