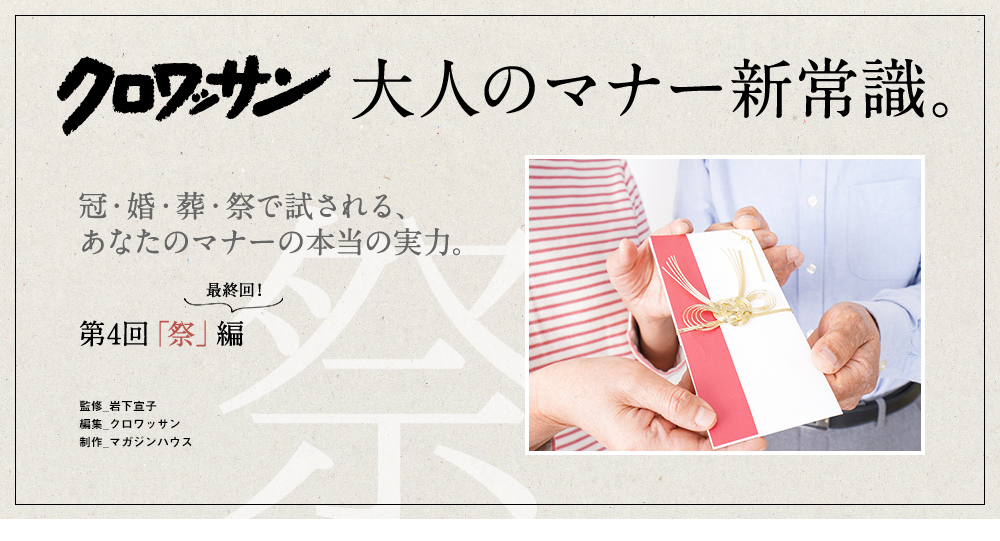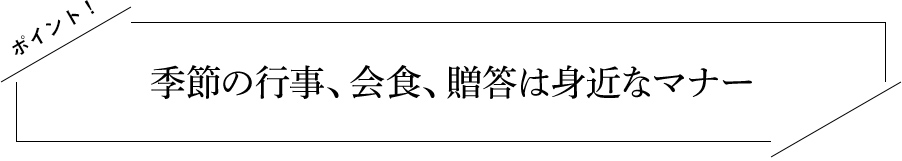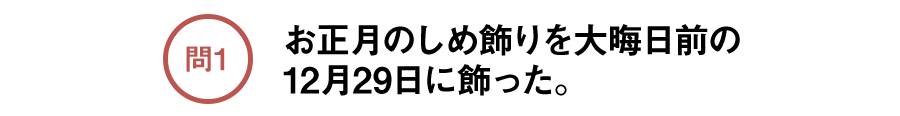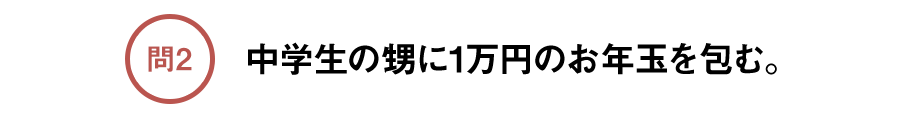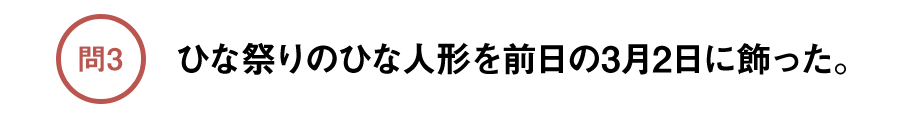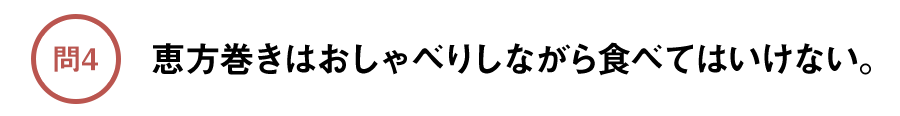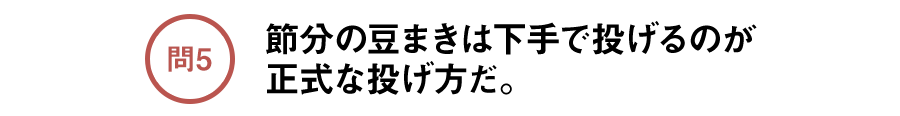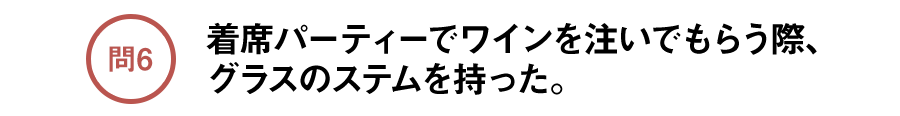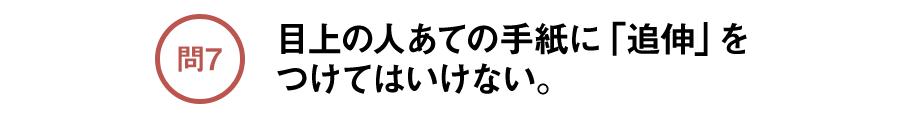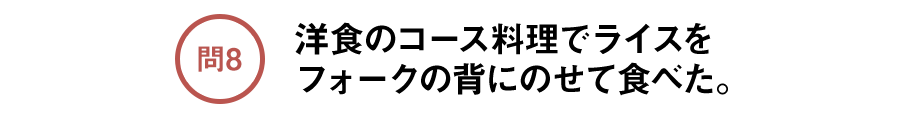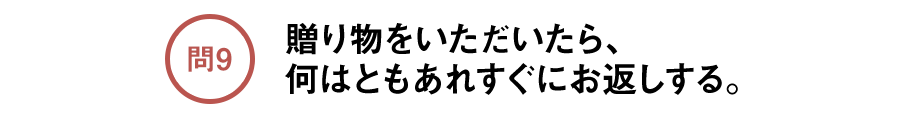マナーを知っていようといまいと、人生の儀式はおかまいなしにやってくる。そんな「いざ」に備える、大人の心得。マガジンハウス発行の『クロワッサン』が監修する「大人のマナー新常識。」の特別配信4回目。
冠・婚・葬・祭の儀式や行事の知っておくべきルールをマナーデザイナー岩下宣子さんがクイズ形式で指南してくれます。最終回となる今回は「祭」編。お正月やひな祭りなど身近な年間行事にも、心得るべきマナーはたくさん。
気軽に楽しみながら大人のマナーを学んでみましょう。難問揃いなので、6~7割正解すれば、優秀です!

お正月飾りは、12月28日までに飾る(つまり、クリスマスの飾りは27日までに片付け終わらなければいけない!)。「31日の大晦日は『一夜飾り』といって縁起が悪く、29日も二重苦ということでよくないとされています。この日についたお餅は『苦餅』といわれるので、餅つきもしません」
「お年玉の目安は、1ヶ月のおこづかい程度と考えればいいでしょう」。そうすると、中学生で1万円は多すぎる印象。「また、親戚なら親同士であらかじめ話し合って、小学生の間はいくら、中学生は何千円というふうに身内での相場を決めておくと、お互いに気が楽です」
ひな人形は、女の子の成長と幸福を願って、桃の節句に飾るもの。「お正月飾りと同じで、一夜飾りは縁起が悪いのでよくありません。2月の初旬から中旬、遅くとも1週間前には飾るようにしましょう」。ひな祭りの後は、いつまでも飾っておかずに、早めに人形をしまったほうがいいとされる。

節分に恵方巻きを食べるのは、もともと関西地方の風習。最近になって全国に広まった。その年の恵方=神様のいる縁起のいい方角を向いて、ひとり1本の太巻きを食べるというもの。太巻きを切り分けてはいけない。「食べている最中に話すとご利益がなくなってしまうといわれています」
「鬼は外」と、追い出さなければならないからといって上手で思い切り投げてはだめ。下手でやさしく投げるのが正しい。「神社のお賽銭をイメージしてみてください。神様にお供えするお金はやさしく投げ入れますよね。節分の豆も同じで、もともとは供えるという意味合いも兼ねていたのです」。鬼は深夜にくるとされるので、豆まきは夜に行なう。窓や扉を開けて家の奥から順番にまき、玄関が最後。豆まきの後は、無病息災を願って年齢に一つ足した数の豆を食べる。
ビールや日本酒を注いでもらうときは杯を持ち上げるのに対し、ワインの場合はテーブルにグラスを置いた状態で注いでもらうのが正しいマナー。「ステム(脚)に手を添える程度ならいいかもしれませんが、持ち上げようとする所作に見えてしまうのは、やめたほうがいいでしょう」

追伸とは、本来なら書き直さなければならないところを横着して追記したということ。「上司などへの手紙に追伸をつけたら、『面倒だから書き直しをしませんでした』というメッセージになってしまいます」。目上の人にあてた場合に限らず、正式な手紙には追伸をつけずに書き直しを。
洋食のコースでライスが出てくるのは日本だけ。フォークの背にのせるのも日本独自の習慣といえそう。「ナイフを使ってのせてもいいですが、フォークだけで普通にすくうほうがマナーに適っています。背にのせるのは落とさずきれいに食べるのが難しく、見ているほうもハラハラしてしまいます」
「贈った側からすると、あまりにもすぐにお返しが届いたら、贈りものをしたことでかえって気を遣わせてしまったのではないかと心配になります。内祝いなどは、いただいてから3週間以内を目安にお返しをするのがいいと思います」。タイミングが遅すぎても、早すぎてもよくないのでご注意。
初出 『クロワッサン』 No.1007・2019年10月10日発売

マナーデザイナー
岩下宣子さん
現代礼法研究所主宰。NPO法人マナー教育サポート協会理事長。『一生使える! 大人のマナー大全』(PHP研究所)など監修、著書多数。「マナーは本来、自分ではなく相手に恥をかかせないための思いやりです。意味を理解したうえでルールを知っておけば、気持ちに余裕が生まれ、相手に思いを寄せることができるはずです」
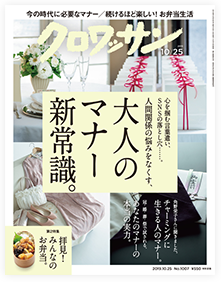
Information
大人だから一通りの礼儀作法はわきまえている。
けれど、年を重ねるほどに身に染みるのは、教科書どおりのマナーやマニュアルだけでは人間関係はうまくまわっていかないということ。
たぶん、大事なのは思いやりの心と柔軟な精神。自分も相手も、ともに機嫌よく過ごしたいなら、これまでの決まりごとにとらわれず、マナーや常識もバージョンアップさせていこう。
無用な軋轢のない、快適な関係を築くための、新しい考え方のヒントを集めました。
クロワッサン No. 1007
大人のマナー新常識。
・定価:550円 (税込)
・発売:2019.10.10
・ジャンル:実用
https://croissant-online.jp/ ![]()